9月7日のdevkin meetup Vol.6に運営側として参加・登壇しました。
告知ページ
前日のkintone Café 名古屋 Vol.19の熱気も鮮やかな朝は、ホステルわさび名古屋駅前から始まりました。

朝は近所の米野駅を訪れて、行き交う列車を眺めました。それからマザック工作機械ギャラリーに移動し、工作機械の世界をじっくりと堪能しました。
そして隣のヤマザキマザック美術館へ。ここは前日に石際さんに教わった場所です。ロココ調の絵画の素晴らしさに感銘を受け、心の鏡を磨いてきました。
その勢いで、ユウゼン総本店であんかけスパゲッティをいただき、名古屋腹をキメてから会場の中日ビルへ。

サイボウズ名古屋オフィスに来るのは、1年3カ月前のkNN(kintone Night Nagoya)以来でしょうか。入口で、devkin meetupを提唱した久米さんと合流し、そのまま名古屋オフィスへ。設営等もコジロウさんがほとんど行ってくださったので、運営としては特にやることもなく。

今回、私は運営側での参加です。ただし、今回は準備にあまり関わっていません。司会進行、受付も皆さんにお任せしました。私がやるべきは、部活動の報告を部長として登壇をするくらい。
私の仕事が色々と忙しくなっているため、準備に携わる時間も取れなくなっています。ただ、私としてはこのdevkin meetupには引き続き関わりたいと思っています。なぜなら、kintone技術者界隈を盛り上げたい思いがあるためです。
kintoneのユーザーコミュニティが盛り上がるのはとてもよいことですし、サイボウズオフィシャルパートナーの方々がビジネスコミュニティで活動するのも素晴らしいこと。その二つと並んで技術者がkintoneをカスタマイズし、次の可能性を模索するコミュニティの盛り上がりも大切です。
devkin meetupは、kintone技術者コミュニティの一角として、盛り上げていきたいと思いますし、その盛り上がりに貢献したいと思います。

今回、devkin meetup Vol.6には面白い趣向がありました。
ブラザー販売の山本さんが持ってきたハンディサイズのシールプリンターからその場でワッペンシールを印刷してもらったのです。来場者のみなさんのXのアイコンやデータを事前にkintoneレコードに登録しておいていただき、それを受付でシールとして印刷してもらえたのです。私ももちろん、シールを左胸に貼ってdevkin meetupに臨みました。

さて、司会進行を担ってくださった石際さんによる開会のあいさつとともに、自己紹介タイムです。
ここでまた趣向が。前日のkintone Café 名古屋 Vol.19の自己紹介に使われたカタルタを使い、ランダムに表示された助詞または接続詞を使って自分を紹介する遊びです。kintone Café 名古屋 Vol.19ではkintone上で抽選と表示を再現していたのですが、さすがにdevkin meetupではkintoneが用意されていません。そこで直前に石際さんがClaudeと対話して間に合わせました。さすがです。
さて、カタルタの趣向を使って、皆さんが自己紹介を行った後は、いよいよ本編。



まずはサイボウズさんからのユカタンさんより「サイボウズinfo 連携コネクタ編」と題して、リリースされたばかりの連携コネクタについてのご紹介!
これは私も楽しみにしていました。私はIFTTTやzapier、makeなど様々な連携ブリッジサービス(iPaaS)を使っています。BizteXさんも以前、パートナーとして契約させてもらっています。そのBizteXのkintone内に組み込まれたOEM版が、この連携コネクタということです。
設定のデモはうまくいかなかったようですが、私は連携自体は上にあげたさまざまなサービスで実践済みです。
デモよりも知りたかったのは、連携コネクタとBizteXの違いです。どういう制約があるのか。BizteXと連携コネクタは同一サブドメイン内で共存が可能なのか。すでにBizteXを使っている場合は契約上どうなるのか。
知りたいことは多々ありましたので、質問タイムの中でも2点ほど質問させてもらいました。事前に質問を募っておられたDiscordで質問した内容の延長です。
この連携コネクタはこれからさまざまな場で使うことが増えるでしょう。楽しみです。

さて、続いては、部活動の紹介タイムです。藤村さんから!
– chrome拡張部
– マネタイズ部
– 気になるライブラリ研究部
– ER図作成ツール開発部
– gas部
– hack出ちゃう?部
– gameni部
などなど。



私はこの中の「ER図作成ツール開発部」の部長として、「A5:SQL Mk-2」の作者である松原さんと行った開発の経緯をお話ししました。
前回の大阪のdevkin meetupでの登壇から、久米さんを介して松原さんとつながり、長いDMを送って協力要請を行った発端から、部員の皆さんと議論してkintoneの特性をどうER図に落とし込むかを考え、松原さんにβ版として実装していただいた流れを。
kintoneの特性をどうER図に落とし込むかを部員の皆さんと議論した下りは、登壇のスライドでは触れていません。が、また機会があればお話ししたいと思います。
私のスライドの中では、今回の部活で実現したA5:SQL Mk-2ついて、松村さんが記事を書いてくださっていたので、松村さんにも登壇してもらい、少し背景を話してもらいました。突然の振りに対応していただき、松村さん、ありがとうございました。



他の部活からもそれぞれの部長が部活動の報告を行っていただきました。まだ活動がこれからの部も、徐々に進めている部もあります。こういう取り組みはぜひ進めていきたいと思っています。
「伽藍とバザール」に書かれたオープンソースソフトウェアの開発方式は著名です。その開発思想のエッセンスのわずかでも、kintoneコミュニティーの中に実践できれば、より多くの技術者がkintoneエコシステムに関わってもらえるはず。
私も企業を経営しています。その立場としては、この理想と経営の両立がそう簡単にはいかないこともわかっています。しかしながら、今のあらゆるソフトウェアの仕組みは、オープンソースコミュニティーが作ってきたソースを活用して作り上げられています。ある企業が技術やノウハウを独占したまま、他の企業にそれを開示しないやり方では、インターネットやノーコードツールはここまで発展しなかったでしょう。
devkin meetupがそういうコミュニティに貢献できればと思っています。私も余裕が出てきたら、他の部活にも顔を出したいと思います。
さて、続いてはLTコーナー。皆さん、それぞれにLTを披露してくださいました。

まずは受付でラベルプリンターで出力してくださったブラザー販売の山本さんから。
なるほど、kintoneとはこのような構成で出力できるのか、ということがとても理解できました。これだと実装もできそうですね。また、実機さえ持っていれば、いろんなイベントで活用できそうです。自分が運営するイベントも、お客様の運営するイベントも。こちらは早めに試してみたいと思います。

続いては、上海から来てくださった松村さん。
昨日のkintone Caféに続いて参加してくださっています。その松村さんからはPower Automateとの連携です。
お客様によっては、MicrosoftのAzureをクラウド基盤として採用されています。それなのにkintoneとは全然つながっていないことが多いのです。Power Automateとの連携は私もまだ実装の機会がありません。なのでとても参考になりました。
ここは、やがて実装の必要が出てくるはず。タイトルの写真を撮り忘れたのがもったいない。
続いての中村さんも前日に続いてです。
広島から来てくださって、その場でLTに名乗りを上げ、その場でスライドを作って発表するバイタリティーが素晴らしい。
中村さんは、Postmanを用いた権限設定の連携という、とても実用的なネタを披露してくださいました。
私もPostmanはよく使います。特にアプリ設定作業ではかなりの省力化を発揮してくれます。権限設定に使うことはあまりありませんが、これを使えば様々な活用ができそうです。私も早速、とある案件で権限の一括設定でこれを提案しました。
これまた写真を撮り忘れてしまいました。

続いてはヒラドさんから。
kintone界隈でも存在感と知名度がうなぎのぼりのヒラドさん。実はそのすべての始まりが、前回の大阪で開かれたdevkin meetup Vol.4 in 大阪である事は、私たちにとっても誇りです。より一層のヒラドさんの飛躍を期待したいと思います。
ヒラドさんからは、今回kintone Hackの本選に進んだHackの裏側を少し教えてもらいました。私は8月のkintone Café HYOGO Vol.7でヒラドさんの登壇を聴いていたので、Hackの背景は知っていました。
が、今回はその時に話した内容とは少し目線が変わっていて、興味深かったです。もちろんその内容はここでは書けません。
この後のCybozu Days 2025の会場で、ヒラドさんの登壇を楽しみにしたいと思います。
前回のdevkin meetup Vol.4の記事にも書きましたが、ヒラドさんのような方が世に羽ばたく姿を見るのは嬉しいこと。その土壌となるコミュニティーとしてのdevkin meetupの存在意義を感じます。

続いては森田さんからです。レコード間差分を比較するプラグインを披露してくださいました。この変更履歴の把握は私も様々な案件で求められます。krewDataを用いて実装した経験もあります。こうしたデータ調査系の仕事って必ず案件の中で発生しますが、正直に言って建設的ではありません。だからこそ、システムを使って楽にしてしまう。これこそは技術者として成すべき作業でしょう。私もこの作業はもう少し追求しようと思います。

続いては、サイボウズのさりぽろさんから、「kintone JavaScript APIを紹介します!」です。このところのkintoneのバージョンアップで、画面制御系のAPIリリースが相次いでいるのは素晴らしいことです。
もともと、kintoneの画面系の制御については、DOMいじりと言われる非推奨の実装に手を染めざるを得ないことがしばしばありました。そうしたDOMいじりのあれこれは、このところのJavaScript APIの充実によって少しずつ減るはずです。
私にとっては、こうしたAPIが実装される事は、今後予定されているkintoneのデザイン刷新においてその部分の切り替えの考慮が不要になることを意味します。kintoneのデザイン刷新は、これからのkintoneに係る技術者にとって共通の課題であるはずです。JavaScript APIの充実によって、その部分のデザイン刷新の調査や対応のリスクが軽減することを歓迎します。

続いては、徳島から来られた本橋さんによる「ちょっとした不便をDIYで解決! AI片手に日曜コーディング」。
ここで紹介されたサムネ盛丸とCoverTweakはすぐに使えそうです。私のkintone実装の上でのウィークポイントは、kintoneのデザイン面に無頓着であること。kintoneのデザインはもうお客様にほとんどお任せしてしまい、あまりこちらで関知しないスタイルを続けています。
今後、こうしたツールを使って、少しでもお客様のkintoneを彩るお手伝いをしなければならないと思っています。この私の弱点を補完するツールとして重宝したいと思います。

最後のLTは、司会進行の大役を担ってくださった石際さんから。「kintone開発環境 Claudeといっしょ!」というタイトルです。
kintone開発フレームワークであるErakisの開発者でもある石際さん。自社でkintone開発を行う上での事例なども見せてもらいました。私もdrawioは頻繁に使っており、kintoneとの連携に関しては、様々に試行錯誤を繰り返しています。AIを用いた試行も行っており、こうした事例は本当に参考になります。
またそもそもの開発フローも、こうしたフレームワークを使わなければならない事は骨の髄から理解しています。が、なかなか時間が取れず、決定版となる方向に行けていないのが実情です。今の私の大きな問題だと認識しています。AIを用いたコーディングの壁打ちとしてならば、以前から成果は上げています。が、AIエージェント的に一連の開発プロセスをAIに任せる流れには、まだ実装として実現できていません。ここを早く実現しなければならないと思っております。

最後は、久米さんからdevkin meetupの創始者として、締めの挨拶をいただきました。それをもって無事に閉会となりました。そういえば皆さんで集合写真を撮っていなかったですね。

そして会場近くの「ワイマーケットのクラフト食堂 ナゴロバ」で懇親会。ワイマーケットさんが作る豊富な種類のクラフトビールの中から3種類が飲み放題ということで、たくさんいただきました。まだ残暑の厳しい日々、心と喉を潤しつつ、皆さんとの会話に花を咲かせました。技術イベントならではの、技術上の話題なども交わせたのがよかったです。残念ながら私は最終の新幹線の都合があり、二次会には参加できませんでした。が、懇親会で皆さんと様々な会話ができたことで、二日間にわたる名古屋の良い余韻を残しつつ、名古屋を去ることができました。

ビールに酔い、のぞみに座れず、通路で立ったまま寝た私。新横浜についた際、切符をなくしてしまい、駅員さんとやり取りをする羽目になりました。その切符は東京まで旅をし、旅先で保護された結果、私も無事に無賃乗車の疑いが晴れ、帰宅できました。まあ、あまりよく覚えていないのですが。
いずれにしても、お会いした皆さん本当にありがとうございました。


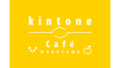
コメント