
長年にわたって読んだ本のレビューを書いてきた。だが、本書、つまり暗夜行路のレビューでしばらく途絶えてしまっていた。
理由は、私の忙しさがピークを迎えつつあるからだ。さらに、本書に対してのレビューを書く気がどうにも起きなかったからでもある。
今の私の忙しさは、私の望む人生のあり方と少し違っている。
その一方で、今の私が世の中に受け入れられ、私のようなものでも仕事を通して世の中に貢献できている手応えも得ている。
今の私の生き方は、仕事に追われ、仕事に急かされている。そうした経営者の生き方を強いられたわけではなく、自分で選び取った道だから、後悔はない。ただし、本書の主人公である時任謙作のような自由気ままな生き方とは対極に来てしまった。
かつて、そのような生活を望んでいた私だったが、今の私はそこからは程遠い。
謙作の生き方はいわゆる高等遊民と言えよう。親の遺産だけで気ままに暮らし、小説を書いて過ごす。締め切りに妨げられず、タスクにも追われず、ましてや、どこかに通勤する雑事からは無縁。何物にも縛られない日常を送っている。
それは私が若い頃に望んでいた暮らし方でもある。
今の私は、忙しさへの手応えもある程度得ている。その忙しさとは、上役に急かされるものではなく、自分の意思によるものだからなおさらである。
だから、謙作のような生き方に対する羨ましさを、今の私はそれほど感じない。
その一方で、謙作のような長閑な人生に憧れる自分もいる。
そうした矛盾した感情が、苛立ちとして本書のレビューを書く気を失わせていた。
私は、今の大多数の勤め人の暮らしが人間にとって理想の暮らしとは思っていない。
そのため、謙作に対して苛立つ理由は、大多数の勤め人のような生き方とは逆の生き方をしているからではない。
自由な暮らしは結構だ。ただし、目的もなく、ずるずると日々を送ることの方に苛立つ。
もっとも、23から25歳にかけての私も、人から見たら謙作並みの生活を送っていたと非難されることだろう。だが、当時の私は何かになりたくて、かつ、勤め人の暮らしからはそれが得られないと思い、家にこもって本ばかり読んでいた。
本書は、日本文学史上においても名作とされている。
ところが、そういう人生を辿ってきた今の私には、本書を一読しただけではその価値が響いてこなかった。
どうすれば、本書の真価がわかるのだろうか。
本書の真価が分からないのは、私の忙しさと余裕のなさから来ているに違いない。それが苛立ちになっているのだろうか。
苛立ちを感じる理由は、私が仕事に追われ、雑事にまみれた毎日を送る中で俗人になってしまった証しなのだろうか。もしそうなら、かつての私は、今の私を負け犬と呼ぶのかもしれない。
本書は、主人公の時任謙作が、両親の愛を知らずに育った身の上からか、半ば投げやりに家庭を持とうとする。その企てが破れては、気の向くままに放浪する。吉原の遊里に遊び、自分を見つめ直すためとの名目で尾道に行く。そして、また東京に戻る。
謙作の悩みに同情の余地がないわけではない。親の愛を知らず、それでいて遺産が残された境遇は、苦労や屈託、挫折を謙作に経験させなかった。謙作の悩める日々は、謙作のせいでもあるし、境遇のせいでもある。
ただ、本書で書かれる謙作の愛子やお栄への求婚は、どう考えても愛から生まれたものではない。自分の思うままに任せぬ放浪の人生を繋ぎ止める碇として、彼女たちを利用しているようにしか見えない。
その心理はかつての私のように自由気ままな生き方を最善としていた私でさえ共感できない。それが私の中に苛立ちを生んでいるのだろうか。
本書を上梓した当時の著者は、既に文壇において確固たる地位を築いていた。日々の生活にあくせくする必要もなく、時任謙作のように自由気ままな毎日も過ごせただろう。実際、著者は各地を頻繁に転居している。
私のように毎日仕事で追われている者にとっては、著者の毎日は望んでも手に入れられない憧れだ。だが、憧れだけでレビューを否定的に書いても仕方がない。それは妬みや嫉みにすぎない。
さらに冷静になって、考察を深めてみる。
例えば、今の私自身を客観的に見るとどうなるだろう。
私自身、毎日あちこちに移動している。商談や登壇を挟みながら方々に旅をしている。毎日同じ場所に通勤することはなく、大半の社会人の暮らしとは明らかに違う。また、私自身のそうした毎日を、一日一度FacebookなどのSNSでアップしている。
おそらく私のそうした毎日を見た方によっては、境遇の違いに苛立ちを感じるのではないだろうか。私が時任謙作や、その背後に透けて見える著者の境遇に羨ましさと苛立ちを感じたように。
そこまで考えが及ぶと、本書を非難することは不当なのではないかという気持ちになる。
そもそも私の今の境遇も、世の中の人によっては恵まれているのかもしれないのだから。
人の生き方は人それぞれ。自分が望むように生きられていれば、たとえ小説の中の登場人物であろうと苛立ちを感じる謂れはない。
そのように考えることで、私の苛立ちは少し鎮まった。
本書の価値とは、立場や時間によって、人の考えが変わってしまうことを示す点にあるのかもしれない。
自我の同一性とは、私たちが生きるためには欠かせない概念だ。これが崩れてしまうと、自分が自分でなくなってしまう。
若い頃の自分と今の自分は、どれだけ年月が経っていようと同一人物である。その確信があるからこそ、私たちは生きていける。
だが、人は成長する。同一人物であっても、考えは年齢につれて変化する。変化しない者は成長しない者である。
若い頃の私は時任謙作の生き方に共感していたが、今は違う。否定的な苛立つ感情を抱いている。
だが、本書を読み、レビューのための考察を経ることで、さらに私自身が考えを深めていかねばならない。
後編では、そのあたりの考えをもう少し進めてみたいと思う。
2020/12/19-2020/12/23

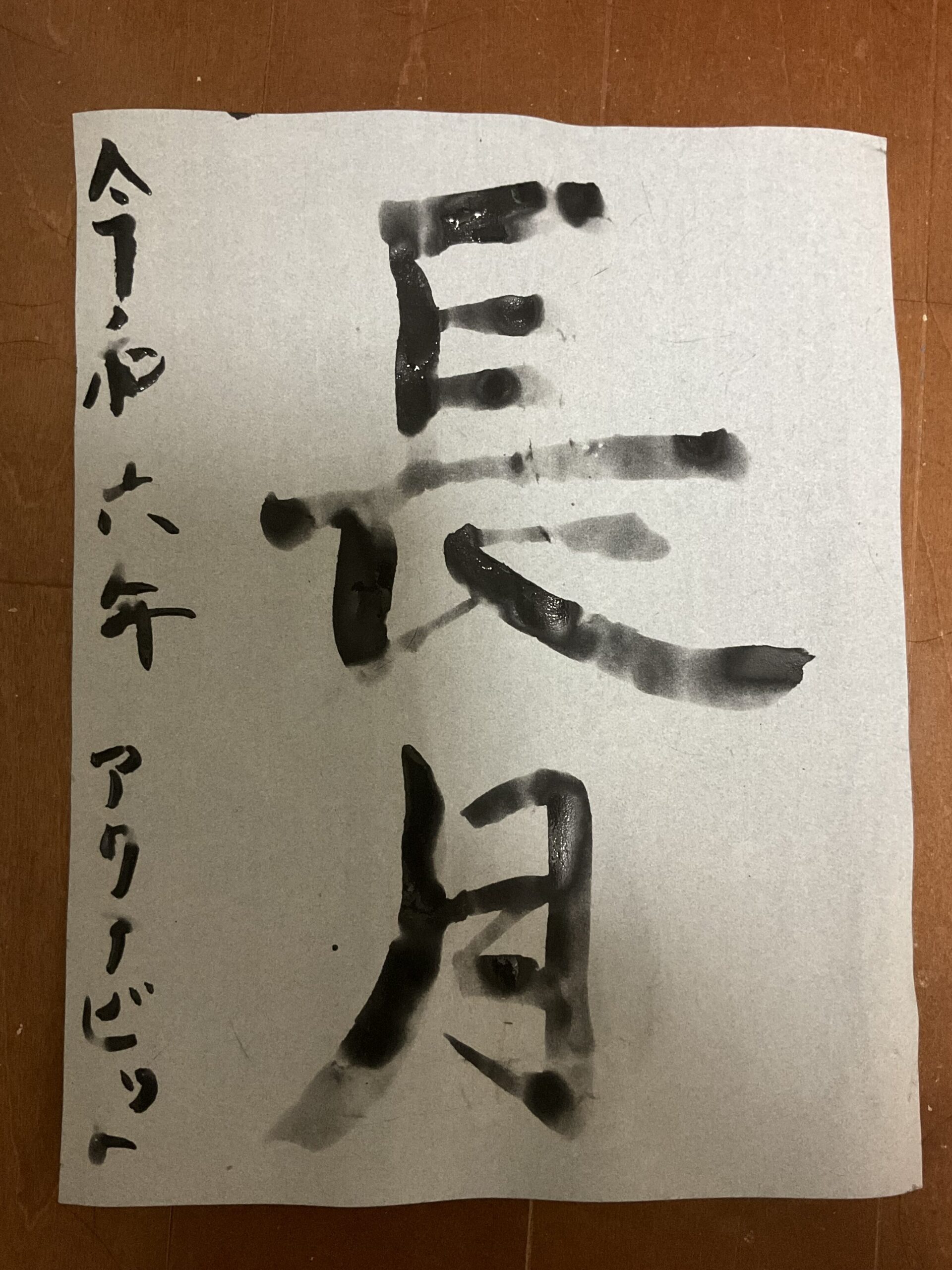

コメント