
私は劇場で舞台や映画を観る前にあまりパンフレットを読まない。だが、本作は珍しいことに見る前にパンフレットを読んでいた。なぜなら妻と長女が先に観ていて、パンフレットを購入していたからだ。だから軽くストーリーの概要だけは知った上でスクリーンの前に臨んだ。家族四人で観たのだが、妻と長女は二回目の鑑賞となる。妻子にとっては何度も観たいというほど、本作に惚れ込んでいるようだ。
妻子の言う通り、確かに本作は素晴らしい。何がいいって、とにかく曲がいい。本作にはとてもキャッチーで耳に残る楽曲が多い。ミュージカルが好きな妻子にとってはミュージカル映画の王道を行く本作はたまらないと思う。私もミュージカルの舞台や映画はよく見るのだが、本作に流れる曲の水準の高さは他の名作と呼ばれるミュージカル舞台や映画に比べても引けを取らないと思う。かなりお勧めだ。妻が最初の鑑賞でサウンドトラックを買った気持ちもわかる。
妻から事前に聞いていたのは、本作が多彩な切り口から楽しめること。だが、その切り口が何なのかは観るまでは分からなかった。そして観終わった今は分かる。それは例えば家族の愛だったり、ハンディキャップを持って生まれた方への真の意味の配慮だったり、挑戦する人生への賛歌だったり、19世紀には厳然とあった差別の現実だったり、夫と妻の間の視点の違いだったり、身分を超えた愛だったり、演劇史からみたサーカスの役割だったり、米国のエンターテイナーの実力の高さだったり、あまりCGを感じさせない本作の撮影技術だったり、いつのまにか日本のテレビから消えた障がい者だったり、本作の場面展開の鮮やかさだったり、事実を脚色する脚本の効果だったり、SING/シングのシナリオと本作のシナリオが似ていることだったり、YouTubeで流れるメイキングシーンを観たくなるほどの本作の魅力だったり、さまざまだ。
そのすべての切り口から、本作は語れると思う。なぜなら本作は、限られた尺の中で視点のヴァリエーションを持たせることに成功しているからだ。メリハリを持たせているといってもよい。本作の尺は105分とそれほど長くない。そんな短い時間の中であっても構成と映像に工夫を凝らし、これだけたくさんの切り口で語れるような物語を仕上げている。その演出手法は見事だ。
本作はどちらかといえば物語の展開を楽しむ類の作品ではない。19世紀のアメリカで異彩を放ったP・T・バーナムの生涯をモチーフとしているが、彼の生涯は詳細に語らず、端折るところは大胆に端折っている。特に、バーナムと妻のチャリティの出会いから子を持つまでの流れを「A Million Dreams」の曲に合わせて一気に描いているシーンがそうだ。曲の一番を子役の二人に歌わせ、そのあと、ヒュー・ジャックマンがふんする青年バーナムとミシェル・ウィリアムズの演ずるチャリティの声が二番を引き継ぐことで、観客は視覚と聴覚で二人の成長を知る。しかも、この流れの中で挟まれるシーンは、チャリティが身分の違うバーナムに一生をかけて添い遂げようとする意志の強さと、バーナムの上流階級を見返したいとの反骨の心を観客に伝えている。
本作には上に挙げたシーンのように、登場人物の視点や心の揺れを画面の動きだけで表す演出が目立つ。それによって映像の中に多種多様な物語をイメージとして詰め込んでいるのだ。だからこそ、上に挙げたようなさまざまな切り口を本作の中に描写できるのだろう。
私は先に挙げた切り口のうち、三つほどが特に印象に残った。それを書いてみたい。
まずは、障がい者の取り上げ方だ。かつてドリフターズがやっていた「8時だョ!全員集合」では何度か小人のレスラーがでていた。ところが、最近はそういった障がいのある方を笑うような番組は全く見かけなくなった。障がいのある方を笑うなどもってのほか、というわけだ。だが、もともとエンターテインメントとは、本作でもバーナムが語っていたように猥雑で日常には出会えない出来事を楽しめるイベントだったのではないか。障がいのあった方でも、喝采と拍手でたたえられるような場。観客が彼らを笑うのではなく、彼らが観客を笑わせる。それこそがエンターテインメントの存在意義ではないかと思うのだ。だからこそ、彼らが一団となって自分が自分であることを高らかに歌い上げる「This is me」がこれだけの感動を呼ぶのだ。
本作には大勢のフリークスと呼ばれる人々が登場する。体の一部に障がいをもち、普段は日陰に追いやられていた方々だ。本作に登場する障がい者のうち、犬男やヒゲ女、入れ墨男などは、特殊メイクだろう。だが、当時人気を博した親指トム将軍を演ずる方と巨人を演ずる方は、実際に小人症と巨人症を患いつつ俳優として糧を得ている方だと思われる。かつて「ウィロー」という、小人の俳優がたくさん出演する映画を劇場で観た。今の日本に、こういうハンディキャップを持った方々の活躍する場があり、エンターテインメントとして成立っていることを私は寡聞にして知らない。スポンサーに配慮しての、リスクを考えてのことなのかどうかも知らない。もしそうだとすれば、もし日本の一般的な娯楽であるテレビに昔日の勢いが失われているとすれば、そういう見せ物的な要素が今のテレビから失われたからではないだろうか。
もちろん、障がい者もさまざまな人がいる。人によっては表に出たくないと思う人もいるだろう。だが逆に、人前に出て自分を表現し、賞賛を受けたいと思う障がい者だっているはず。障がい者だからといって十把一絡げにあつかうのはどうだろう。本作にも、彼らのようなフリークスたちが、バーナムサーカスに入って初めて本当の家族を得たというセリフがある。とすれば、そういう場をもっと作っても良いと思うのだ。エンターテインメントとはお高くとまった娯楽であっても良いが、同時に猥雑で珍しいものという側面もなくてはならないはず。アンダーグラウンドで後ろ暗い要素は全て排除され、インターネットに逃げてしまった。それが今のテレビがオワコン扱いを受ける原因だと思う。本作は、今の我が国のエンターテインメントに足りないものを思い出させてくれる。
続いては、バーナムがパートナーのフィリップをバーでスカウトするシーンだ。「The Other Side」のナンバーに乗って二人が丁々発止のやりとりを繰り広げる。本作には記憶に残るシーンが数多くあるが、このシーンもその一つ。ミュージカルの楽しさがこれでもかと堪能できる。カクテルバーのフレアショーを思わせるようにグラスとボトルが飛び交う。今の地位を捨てて冒険しようぜと誘うバーナムと、上流階級に属する劇作家の地位を盾に拒むフィリップ。スリリングなグラスのやりとりに対応して、「The Other Side」の歌詞は男の人生観の対決そのものだ。もちろん人によって価値観はさまざま。どう受け取るかも自由だ。私の場合は言うまでもなくバーナムのリスクをとる生き方を選ぶ。バーナムが今もなお名を残す成功者であり、彼の後ろには何百人もの失敗者がいることは承知の上で。それは本作が多面的な視点で楽しむことができるのと同じだ。全ては人生観の問題に帰着する。でも、それを差し置いてもこのバーで二人が掛け合いを演ずるシーンは心が躍る。すてきな場面だと思う。
あと一つは、結婚とは夫婦の感じ方の違いであることだ。バーナムは先に書いたとおり、成功に前のめりになる人物だ。リスクをとらない人生などつまらないと豪語し、フィリップを自らの生き方に巻き込む。だが、奥さんのチャリティはバーナムとは少し違う。彼女にとって成功はどうでもいいのだ。彼女は夫のバーナムが夢を追う姿に惹かれるのだから。そのため、バーナムが成功に浮かれ、夢を忘れた姿は見たくない。フリークスの仲間や家族を置いたまま、欧州から招いたジェニー・リンドとの興行に出かけるバーナムには夢を忘れて成功に溺れる姿しか感じない。そして、リンドとバーナムにスキャンダルの報道がでるに及んでチャリティは家を出てしまう。チャリティにとってみれば成功とはあくまでも結果に過ぎない。結果ではなく、経過。理想を見る男と現実を見る女の違いと言っても良いかもしれない。
つまり、本作はただ無責任にバーナムのような投機的な生き方をよしとする作品ではない。それとは逆のチャリティの価値観を置くことでバランスをとっている。それに応えるかのようにバーナムは最後までジェニー・リンドからの誘惑に揺るがず、妻子に操を立て続ける。彼が娘たちと妻を慈しむ心のなんと尊いことか。本作、そして主演のバーナムに魅力があるとすれば、この点だろう。山師の側面と家族に誠実な側面の釣り合いがとれていること。自らペテン師と大書されたシルクハットをかぶる姿も彼からうさん臭さを払拭している。
不具のフリークスたちをたくさん抱えてはいても、根本的に彼の側の人物で悪く書かれる人は登場しない。外見は中身の醜さに比例しないからだ。むしろ、つまらぬ差別意識で垣根を築こうとする上流階級の心の狭さこそが本作においては醜さの表れなのだ。本作は、一見するといびつな人物が多数登場するキワモノだ。だが、実は本作はあらゆるところでバランスをとっているのだ。それこそが本作を支える本質なのだと思う。
バーナムとチャリティは、身分の差を乗り越えて結ばれる。もう一組、身分の差を乗り越えて結ばれるカップルがいる。フィリップとアンだ。見た目や身分の壁を取っ払おうとする本作の試みがより強調されるのが、ザック・エフロンが演ずるフィリップとサーカスの空中ブランコ乗りアンにふんするゼンデイヤが夜の舞台で掛け合うシーンだ。演目に使うロープを使って二人が演ずるダイナミックな掛け合いは「Rewrite The Stars」のメロディに合わせ、サーカスを扱う本作にふさわしい見せ場を作る。ここも本作で見逃せないシーンの一つ。バーナムがとうとう義父と分かり合えなかったように、フィリップもアンとの恋を成就させるため両親と縁を切ってしまう。このシーンは、私が妻と結婚した頃のさまざまなことを思い出させる。立場は逆の。それもあって本作は私を魅了する。
本作はとにかく歌がよいと冒頭に書いた。それらの歌は、歌い手の姿が映えていればなおさら輝く。挿入歌が良い映画はたくさんある。だが、それらはあくまでも映像の後ろに流れる曲にすぎない。本作は演者がこれらの曲を歌いながら演ずる。曲はBGMではなく、作品そのものなのだ。全ての歌い手が輝いている。(ジェニー・リンドがステージで歌うシーンはさすがに吹き替えだったが。ミッション・インポッシブルであれだけのアクションをこなしていた彼女がこれだけ歌ったとすれば、それこそ感嘆する)。特にタイトルソングと上に書いた「This is me」はフリークスが勢ぞろいして見事なダンスを見せながら歌われるのだからたまらない。
欧米はミュージカルが芸術として欠かせない。我が国も宝塚や劇団四季、その他の劇団が頑張っているとはいえ、まだまだ主流にはなっていない。それは、テレビであまりミュージカルが流れてこないためもあると思う。たぶん、ミュージカルの魅力に気付いていない日本人はまだまだ多いはず。
今の私はジャニーズ事務所に何も含むところはない。秋元康さんにも。なので、ジャニーズ事務所や秋元康さんに逆にお願いしたいのだが、所属のアイドルの皆さんにはミュージカルで遜色なく歌い踊り演じられるぐらいのレベルになってほしいと思う。そうすれば、本作のようなレベルの作品が日本から生まれることだって夢ではなくなるのだから。
それこそ、何度でも本作をリピートしてみて欲しいと思う。
‘2018/03/10 イオンシネマ新百合ヶ丘


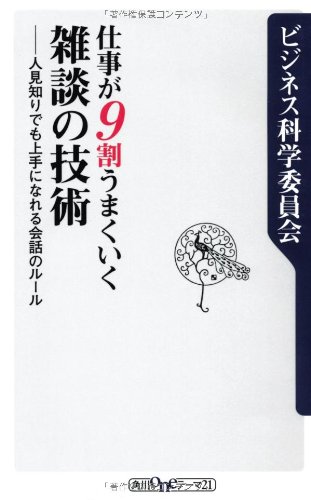
コメント