2025/8/25にkintone Café HYOGO Vol.7に参加してきました。これはそのブログです。
なんとなくkintone Café HYOGOをやることは聞いてはいたし、何か六甲かどこかでやるみたいなこともちらっと聞いていました。
ですが、私はそもそも行くつもりがありませんでした。
なぜなら、その前々日にMOVEDさんのビジネス共創拠点Cataloのオープニングイベントに呼ばれていたからです。金曜日にそのイベントに出るという事は土日のどちらか仕事をしなければ。
そんなわけで当初は全く参加する予定はなかったのです。Cataloのオープニングイベントの懇親会に出た翌朝、主催の稲澤さんからのメッセージに気づくまでは。
これには伏線があります。7月にkintone Café 神奈川を松田町で主催した際、参加してくださった大野さん(今回のHYOGOにも参戦)から懇親会の席で、何か六甲山に参戦する的なことをおっしゃっていたんです。そこで私も調子良く「いいなあ行こうかなあ」的なことを言ってたんです。
その記憶もあり、今回のお誘いがあったので、これは断るわけにはいかないなと思いました。
メッセージをもらった後も結構悩んで、各所に連絡も取り、実家にも連絡を取り、作業スケジュール等、やらねばならない案件が実装できるかなども含めて、参加を決断し、表明しました。それが前日の朝10時ごろ。
ただし、私が参加を表明したのはそんな一面だけの理由ではありません。
まず、北陸新幹線を全線完乗するチャンスが来たことも理由の一つです。糸魚川から兵庫に向かうには北陸新幹線に乗らねばなりません。
私自身、両親ともにルーツは福井です。子どもの頃は毎夏に必ず福井に行くのが恒例行事でした。ところが時間が取れず、もう20年ほど行ってません。せめて車窓からでもいいから、福井の景色を見たい、と思いました。
また、実家である以上、交通費だけの負担で済み、宿泊費はいりません。8月の頭に万博に家族で参加した際に両親とは会ったばかりですが、また顔を見せてあげられそう。
まだあります。稲澤さんへのご恩を返す良い機会と感じました。また、その数週間前も稲澤さんとSNS上で会話した際、また会いましょうと会話もしていました。また、稲澤さんとの語りで経営のヒントがもらえるかもとの思惑もありました。
最後に、これも外せない理由ですが、六甲山でやるこのkintone Café のロケーションが魅力的だったこと。私は25歳までの年月の大半を西宮の実家で過ごしました。
家の窓からは、特に地震で全壊するまでの私の部屋からは六甲山が見えていました。そんな六甲山でkintone Caféをやるとなれば参加したい、という誘惑には抗えませんでした。
そんなわけで、開催前日の朝10時に参加を表明した後、2時間ほど糸魚川を自転車で走り回り、汗だくになった後、地元のホビーというお店で岩のりラーメンを食べ、お土産を買って糸魚川を出ました。
北陸新幹線で糸魚川から敦賀。敦賀から普通に乗り換え、近江塩津から網干行きの新快速に乗り換え、甲子園の実家に行きました。

さて、当日。朝7時半前には出かける準備をしました。弟に甲子園口まで車で送ってもらい、そこから六甲道へ。六甲道からは神戸市営バスに乗って六甲ケーブル下駅へ。このルートで移動するのはほとんど初めてかも。
西宮に住んでいたころも、帰省した際も、六甲山上に行く手段はほぼ車です。電車・バス・ケーブルカーで行くことはありません。今回も、六甲ケーブル下駅からケーブルカーに乗るのは多分生涯でも二回目のはず。
おかげさまで集合時間よりも前に着いたのですが、私より前に何人かおられます。はるばる神奈川から大野さんも来てます。
私はトランクも持ってきたので、トランクを駅のロッカーに何とか詰め込み、皆さんとの再会を楽しみました。
私がkintone Café HYOGOに参加するのは2回目です。Vol.2だったかの城崎の時に泊まりがけで参加しました。
その時に来ていた方々もちらほらお見かけしたので、さほどアウェイ感はありません。


ところがその道中は、今までのkintone Caféにないアウェイな道中でした。
アウェイ感があるというか、新鮮というか。
ところが、一日経つとアウェイがホームになっていくから不思議です。
まず、ケーブルカーで皆さんと共に登る道中が一体感を高めてくれます。
さらに、ケーブルカーが上の駅についた後も、山道を目的であるROKKONOMADOまで歩きます。そのいでたちはほぼハイキング。



kintone Caféにハイキングを加えるという発想はなかったですね。私も今までお寺でkintone Caféを開催したり、餃子を焼き上げて食してからkintone Caféとか、全市区町村を塗りつぶすとか、いろんな趣向を試してきましたが、kintone Caféの前のハイキングは新しい。
その効果は、まず、参加者の一体感を高めると同時にアイスブレイクになります。さらには歩くことで脳内が活性化され、新鮮な気分でカフェに臨めます。これは良いと思いました。
しかもなんということか。この日の天候は小雨混じりの絶好の気候。神戸の街がくっきりと見えなかったのは残念でしたが、このところの酷暑に参り気味だったので、この気候はかえって私にはありがたかったです。


さて、会場に着いたら早速設営です。会費も払って。各座席につき。
ROKKONOMADはもちろん私も初めて訪れました。いわゆる山の上で合宿や作業などができるコワーキングスペース的な機能を持っています。
で、今回のようなイベント利用の場合、15名から。つまり15名が最低催行人数だったわけで、私が参加表明をしたことで、最後の15人目のピースになったらしい。まずはよかった。

さて、まずは宗政さんからの司会進行で始まりました。またこの司会進行がゆるくて良い。思わずほっこりします。
さらにはkintoneハッピートーク。これも良いですね。kintone Café HYOGOは、随所に稲澤さんの伴走支援の経験が取り入れられており、私も参考にします。
私が相方になったのは大野さん。お互い最近のkintoneを入れてよかった、楽しかった、幸せになったという出来事を語り合いました。
そして続いてはLTタイム。画面に出たのは、kintone上でぐるぐる回る三分割のグラフ。止まると該当者が出るという面白い仕組みです。
そして私はこれを見て、ほっと力が抜けました。あ、LTせんでもええんや、という。
なぜならば、前日の朝に参加表明してしばらく経った後、ちょうど新快速に乗っている時間に「あ、そういえばLTやらなくてもいいのかな」と。入れ忘れていたコンパスへの参加表明を登録した際、LT枠が一つ空いていたので、そこにポチっとしました。
夜になって稲澤さんから連絡があり、LTするよりも、基本的には参加者として楽しんでほしい。ひょっとしたらいきなり振るかもしらんけど、と。
それも、もっともと思ったので、私は別案件の実装に力を注いでいました。
無茶振りされた時のために表紙と自己紹介を用意したスライドは作っておき、振られたときに何を話そうかなぁと頭の中での考えだけ複数用意しておき、ケーブルカーで登山しました。
ところが、表は三分割。あれ?三人のLTで三分割なら、私の出番はないのか。じゃあいいやと思ったんです。

そんな力の抜けた感じで、まずは抽選でトップバッターに選ばれた大野さんのLTを拝聴しました。
大野さんのLTで印象に残ったのは、話者がその場、そのタイミング、話しながら自分で考える、皆さんからの反応。それらによっていうことが変わっていく化学反応です。大野さんも話しながら自分自身でも気づきながら、話し直されたのかな、という印象を受けました。
というのも、先日の松田町でのkintone Café 神奈川での登壇にかなり近い内容でお話しされていたからです。ただ、その時に聞いた内容と今回の内容では、私自身の聞いた印象も変わっています。
そもそもタイトルがその時と変わっていました。「市民開発」と銘打たれており、この言葉に本当にしっくり馴染んでいない私がいるため、その違和感の源を知りたいと、私自身も興味を持って聞くことができました。
そもそも、皆さんkintone hive Tokyoには来られていない方がほとんど。私のように大野さんの登壇をkintone hiveでも聞き、kintone Café 神奈川でも聞き、六甲山でも聞きという方がいないはずです。
「キンとも」なる新しい言葉の提案も含め、皆さんが大野さんのやり方や取り組みに共感されていてよかったです。

続いては、工場長こと藤崎さんのLTを拝見しました。
工場長は最近よくkintone界隈ではお名前を見かけますが、実は私はお会いするのは今日が初めて。しかもお互いが西宮にご縁があるとのことで、私も会いたいと思ってました。
しかも聞いてみると、六甲山縦走を何回もされてるという剛の者。二人が住んでいた西宮は、まさにその縦走道によって南北が分断されている市なんです。
ウルトラクイズを模した、六甲山縦走の知識を問うモノ。私、縦走はろくにやったことがありません。せいぜい蓬莱峡でバーベキューや飯盒炊爨を楽しんだり、その道を車で走ったり、芦屋から歩いて六甲山に登る位しかしていません。
私はすぐに気づきました。URLにeverysiteの文字が含まれている。つまりこれはエブリサイトで作ったクイズや。俄然、興味が増します。
ちなみに私、知識が全然なかったので、縦走に関するクイズは9問中、2問しか合いませんでした。
このクイズ自体もなかなか興味深く、須磨から宝塚までを歩き倒す縦走の沿道には私のご縁のある地が多数あります。東京に出て25年を超えた今だからこそ、体が動く今のうちに縦走は経験しておきたいと思いましたし、故郷の山をきちんと歩きたいという意味でも興味深いものでした。
クイズ自体とても面白かったのですが、皆さん運営も含めてポカーンとしています。これ、kintoneと全然関係ないやん、です。そこで急遽工場長さんのエブリサイトの作り方講座が。この流れって演出じゃないん?と私は思いましたが、どうもガチだった様子。
そして、エブリサイトの作り方自体もとても興味深いものでした。なるほど。
前年のCybozu Daysでもアールスリーの金春さんが説明セッションを開いていたのですが、私自身がブース対応で聞けず、代わりにうちのメンバーに行って聴いてもらい、報告をもらっていただけでした。
なので、エブリサイトの管理画面を見るのはほぼ今回が初めて。そういった意味でも興味深かったです。

さて、そこで一度休憩に入ります。今回は一日フルでkintone Caféなので、昼食付。皆さんでソーシャルルームと名付けられた食堂に行き、思い思いに語りながら、親睦を深めます。

出していただいたカレーがとてもおいしかった。
最近の私は、なるべくラーメンを食べずにカレーを食べるようにしています。そうした意味でもとてもタイミングが良かった。
今回のkintone Café HYOGOは、関西の各地からにとどまらず、名古屋、神奈川、東京と参加地域も豊か。kintone Caféの喜びです。





食べ終わった後は、泣き虫天気が急にニコニコ晴れに変わり、良い天気になったので、皆で庭を散策。また、集合写真もこの時に撮りました。
そしてまた部屋に戻り、午後の部開始です。
午後の部ですが、実は私午後の休憩の前に稲澤さんから耳打ちされました。後でむちゃ振りしていい?と。
つまり、出番がないと思い込んでいた私のLTの枠が急遽復活したのです。やばいと、慌てて朝のケーブルカーの写真や六甲の写真などをスライドに入れ、さらに頭の中で考えていたアイディアをスライドに書き留めました。

そんなわけで、午後のLT一発目のヒラドさんのスライドや投稿の詳細はあまり頭に入らず。
でも、実はこのネタで、ヒラドさんは前々日のkintone hackに挑戦し、見事本戦に進みました。すばらしい。ちなみに私はこのkintone hackの予選は、ちょうどCataloのオープニングパーティーの真っ最中だったので聞いていません。
なので、ヒラドさんの内容をじっくり楽しむのはCybozu Daysの本編に取っておきます。

さて、続いては私です。
先にハードルは下げておかねばなりません。急遽スライドを作りましたと言い訳に走りました。
急拵えのスライドなので、スライドの完成度は低い。その中でどこまで笑いをとり、注目を集められるか。
私としては兵庫に戻ってきたことを打ち出したい。そして外から見た兵庫の誇るべきところを語りたい。
兵庫から上京して25年以上経った今だからこそ、兵庫のことはますます好きです。また、兵庫が誇る多彩な特色も、ある程度ならすぐに答えられます。
そこで、そうしたデータをkintoneでデータとして貯められないか、という提案でした。それらを考えていたので、サクッとテキストでスライドに反映しました。この尖ったkintone Café HYOGOのこれからに私の提案が活かされれば本望。
そんな小品でした。
やっぱり、こういう場ではただ聞くだけでなく、語りたいわけです。
そして、東京くんだりから来た輩がなんか楽しそうに話しとるわ、kintoneってなんやろ?って思ってもらえればそれでよし。そういう場でもっとたくさん話せれば、自分も皆も満足。そうありたいですね。
まあ、こういう振りに対応してこそナンボなんです。共遊開発も。
なので、こういう振りはこれからも歓迎です。

さて、続いては最後の登壇者。自動的に石際さん。
よくkintone Caféでもお会いする石際さんですが、登壇を拝見するたびにアクロバティックな内容に度肝を抜かれています。福笑いやら、ファミコンの再現やら、お化けやら、そして先日の和歌山ではなんと粘菌アルゴリズムの再現ですよ。石際さんの発想と技術力にはいつも脱帽しています。
今回は、テッキーな内容ではなく、石際さんにしてはおとなしめの内容。
でも、私だってそうです。石際さんも忙しいし、会社も立ち上げたばかり。毎回アクロバティックな内容の登壇ばかりだと脳を捻挫してしまいます。
ただ、今回の石際さんの登壇がまた考えさせられる内容でした。
「『好き』を言語化する技術」をモチーフに語ってくださいました。
システム開発、要件定義、伴走支援、共遊開発、研修講師。実はこれからのシステム構築にあたって、言語化はもっとも修得すべき技術だと思っています。いわゆるコミュニケーション能力ですね。
ただし、kintone Caféは、システム構築だけに限らずkintoneを中心とした推し活としてのコミュニティーです。kintoneが好きだけにとどまらず、それをどうすれば発信し、共感してもらうかの場でもあります。
それぞれの推す気持ちをどう広げていくかは、参加された方すべてにとって共通の課題ではないでしょうか。皆さんが今後どうやって推し活を展開するか。
本も購入して読もうと思います。

さて、続いては、グループワークです。
サイボウズさんが運営するコミュニティサイト「キンコミ」で質問のあった15の質問の中から、先ほどと同じ抽選の仕組みで三つのグループに分かれ、やり方を皆で相談しました。

一つ目は、日付計算の件。年度末の日付を計算するのにコードを使わずどうすればいいか?
二つ目は、日報を入れない人に対して、どうすれば入れてもらえるようにできるか。
それぞれ皆さんでいろんな考えを描きました。こういう時に100人の答えが出てくるのが筋の良さです。私はやはり1回目も2回目もオーソドックスで王道のやり方で提案しました。
JavaScriptやプラグインに頼らないやり方って、こういう時じゃないと意識できないので、kintone Caféは本当に助かります。
私たちも、こういう相談に対して、うちのメンバーの中でもきちんと答えられるようにしないとダメだなと思っています。JavaScriptで解決することが必ずしも最善じゃない場合もあるので。
皆さんとは本当に良い時間を過ごしました。あるチームは日報の入力を促すため、ニコニコ動画を遥かに凌駕した弾幕を流しまくるkintone界隈でもなかなか見ないカスタマイズを披露してくれました。
そういう風に皆さんと一日を過ごすことが貴重です。
なぜ企業は合宿をするのか。それは平日の業務の多忙の中ではそういうことがなかなかできないからです。こうやって密度の濃い時間を過ごしたことで、業務によって分散した意識が集中でき、その分、理解も進みます。
kintoneも同じ。皆さんkintoneに携わって日々の業務をこなしていらっしゃいますが、忙しすぎてなかなか新たな視点や考えを受け取ることができないのです。
私も一緒です。本当に余裕が取れない。経営も大変。標準化したくても時間が取れない。マニュアル作りたくても時間が取れない。指示もできてない。
こういう機会に参加することで、新たな視点や考え方を得て、アウェイだったのがホームになる。
私も日々案件に追われ、新しい考えを得にくくなっていることを自覚する。
まさにそれこそがkintone Caféのようなコミュニティの力だと思います。
私も油断すると遅れます。いらだちます。危機感に苛まれます。焦ります。
気楽な個人事業主から経営者へ。自分なら案件も取れるし、自分一人で生計を立てるだけなら統制も要りません。kintoneの良さを内部で普及させたり、kintoneの気構えや考えを浸透させる必要もありません。
だからこそ、こういう場にうちのメンバーを連れてきたい。いろんな考えを得てもらい、今のやり方以外にも選択肢があることを知ってほしい。
そのためには、こういう場に、私と一緒じゃなくてもいいので参加して、いろんな方の意見を得てほしい。

最後に皆さんと下山した後、六甲道の駅前の居酒屋で。またここでも親睦を深めました。楽しくアウェイ感を拭い去り、ホームに浸る自分を感じました。
故郷はいいなあ。
最後は稲澤さんに新神戸まで送ってもらい、車中でさまざまな話を。
これで色々な物事が完結しました。来た甲斐がありました。
今回ご縁のあった皆さん、本当にありがとうございました。


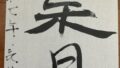
コメント