 3週間前に参加したkintone Café 和歌山に続いて、今回の山口でもとても実りのある体験ができました。
3週間前に参加したkintone Café 和歌山に続いて、今回の山口でもとても実りのある体験ができました。技術者としてのこれからを考えさせられたほどのインパクトを私に与えた一日となりました。
また、インパクトだけではありません。行政利用や過疎地への展開など、今の私にとって関心の深いテーマが、登壇された方々から話されたこともあり、印象深いkintone Caféだったと思います。
実際、私も様々な業種・業態のkintoneに関わっています。今回の皆さんの登壇内容のあちこちで自分ごととして思い当たる節があり、参加していて当事者である気持ちを強く感じました。
昨年にも参加したkintone Café 山口。
今回も参加したのは、主催の吉富さんからお声がけいただいたことも大きな理由ですが、他にも二つの理由があります。
今回も参加したのは、主催の吉富さんからお声がけいただいたことも大きな理由ですが、他にも二つの理由があります。
一つ目は、昨年のkintone Café 山口の懇親会で教えられた「伴走支援という言葉を使うべきではない」の答え合わせをするためです。
そこで示唆されたアドバイスをもとに、共遊開発という言葉を編み出しました。それから一年たち、自分と会社の取り組みを振り返る機会にしたいと思いました。
そこで示唆されたアドバイスをもとに、共遊開発という言葉を編み出しました。それから一年たち、自分と会社の取り組みを振り返る機会にしたいと思いました。
二つ目は、山口とIoTの関係です。
昨年の参加記事には書きませんでしたが、私は実は山口の方々とは、IoTの分野でかつてご縁があったのです。2016年頃から2018年頃にかけてです。
IoT分科会という名のコミュニティーがあり、集まる方のほとんどは山口出身で東京在住のIT関係の方々でした。ひょんなご縁から、山口に全くご縁がない私であるにもかかわらず、山口県出身のIT業界の方々と様々なご縁をいただいていました。
特にその当時の私はIoTに関する知識がほとんどなく、せっかくの機会をkintoneに生かすことがあまりできませんでした。もったいないことをしたと思います。
昨年の参加記事には書きませんでしたが、私は実は山口の方々とは、IoTの分野でかつてご縁があったのです。2016年頃から2018年頃にかけてです。
IoT分科会という名のコミュニティーがあり、集まる方のほとんどは山口出身で東京在住のIT関係の方々でした。ひょんなご縁から、山口に全くご縁がない私であるにもかかわらず、山口県出身のIT業界の方々と様々なご縁をいただいていました。
特にその当時の私はIoTに関する知識がほとんどなく、せっかくの機会をkintoneに生かすことがあまりできませんでした。もったいないことをしたと思います。
あれから約8年が経ち、今はITやIoTで様々な案件を受けるようになりました。当時は全くIoTに対する知見がないままに参加していたので、今の私だったらどうだろうかと自分への答え合わせをしたかったのです。
kintone関係で自分の中で解像度が上がった今だからこそ、山口の方々に対して何かできることがあるかもしれない、IoTを用いてまた何かできないか。そう思って、今回も参加しました。
kintone関係で自分の中で解像度が上がった今だからこそ、山口の方々に対して何かできることがあるかもしれない、IoTを用いてまた何かできないか。そう思って、今回も参加しました。
今回は、昨年と同じくメグリバ。新山口駅に隣接しています。
ただ、昨年はメグリバの大きなイベントと重なった関係で、部屋の中のコミュニティースペースでの開催でした。しかし今年は外のオープンスペースでの開催となりました。
ただ、昨年はメグリバの大きなイベントと重なった関係で、部屋の中のコミュニティースペースでの開催でした。しかし今年は外のオープンスペースでの開催となりました。

 さて、そうしている間に人数も集まってきました。
さて、そうしている間に人数も集まってきました。そして、司会の吉富さん、藤井さん、中野さんからそれぞれ挨拶があり、開会です。
 まずはサイボウズ社の川谷さんから、kintoneについてのご紹介がありました。
まずはサイボウズ社の川谷さんから、kintoneについてのご紹介がありました。kintoneの使い方や活用例などをお話ししてくださり、ありがたい限りです。AI連携など最新のkintone情報をメーカーとして説明し、事前の知識を参加者に伝えてくださるので、後に登壇する方がkintoneの説明を繰り返す必要がなくなります。
特に業務改善を芋づる式に例える考えは、皆さんにぜひ知っていただきたい概念です。最近、さまざまな場所で支援を行う際に思うのが、まず組織から外に出てコミュニティーに参加することの大切さです。外に出て初めて、考え方も取り組み方も芋づる式に得られることを実感しているからです。
 続いては、島根の益田から来られた檜谷さんによる「山口市における地域コミュニティによる活用事例」です。
続いては、島根の益田から来られた檜谷さんによる「山口市における地域コミュニティによる活用事例」です。私はかつてチーム応援ライセンスの開始記念セミナーに登壇したことがあります。その後もさまざまなNPO系のイベントに顔を出し、登壇もしました。今でも主な業務内容ではないとはいえ、kintoneのNPO活用に関心は持ち続けています。
檜谷さんとはそうした場においてリアルでもすれ違ったことがありますし、オンラインの場でも何回かご一緒したことがありますが、じっくり語り合うのは今回が初めてでした。とても楽しみにしていましたし、実際、檜谷さんの話の内容は過疎地におけるkintoneの活用事例としてとても参考になるものでした。
檜谷さんとはそうした場においてリアルでもすれ違ったことがありますし、オンラインの場でも何回かご一緒したことがありますが、じっくり語り合うのは今回が初めてでした。とても楽しみにしていましたし、実際、檜谷さんの話の内容は過疎地におけるkintoneの活用事例としてとても参考になるものでした。
どう取り組んでも、都会に住む私たちにとって、過疎地の課題を本当に理解することは困難だと思っています。実際、懇親会でも檜谷さんからそのことを指摘されました。
ただ、都会だ田舎だと言ってる間に、都会でも同じ課題がすぐに喫緊になることは人口動態からも明らかです。今の私たちが都会だからといってその問題を軽く考えていると、手遅れになるかもしれません。
今のうちに過疎地や田舎での取り組みには、きちんと目を向けておくべきです。また、そうした地で活動するNPOの活動こそ、私たちがもっと注目しておかなければならないのです。
kintoneは手軽さにおいても、比較的低予算で始められる点においても、地方や過疎地や田舎でこそ威力を発揮します。
檜谷さんはそうした現場に住み、課題意識も持ち、深く考えておられます。
kintoneの実装においても工夫が見られ、とても参考になりました。
今のうちに過疎地や田舎での取り組みには、きちんと目を向けておくべきです。また、そうした地で活動するNPOの活動こそ、私たちがもっと注目しておかなければならないのです。
kintoneは手軽さにおいても、比較的低予算で始められる点においても、地方や過疎地や田舎でこそ威力を発揮します。
檜谷さんはそうした現場に住み、課題意識も持ち、深く考えておられます。
kintoneの実装においても工夫が見られ、とても参考になりました。
 前回のkintone Café 山口でもご一緒した藤井さんによる、山口県庁としてのkintone導入事例です。
前回のkintone Café 山口でもご一緒した藤井さんによる、山口県庁としてのkintone導入事例です。前回も一参加者として懇親会の最後までご一緒してくださった藤井さん。今回はスタッフとして関わりを深めて参加してくださいました。 もともとはITエンジニアとしてSESの現場で働いていた藤井さん。おそらくは、私と似たような経歴をお持ちのはずです。それが見事に山口県庁に転職し、県庁でkintone導入や浸透に向けて色々と苦労しておられるようです。
私も今、自治体には導入を進めています。藤井さんのおっしゃるような苦労はよく理解できます。
また、そうした苦労がわかるだけに、私も研修講師で改善の意識改革を訴えるべき時に、藤井さんの語ってくれた内容は生かしていきたいと思いました。
藤井さんの登壇内容は、私にとっての自分ごととして拝聴することができました。
上に書いたIoT分科会の中で山口県庁の方とはご縁がありました。そのため、より一層、自分ごととして再び山口に関わり、応援したくなりました。
また、そうした苦労がわかるだけに、私も研修講師で改善の意識改革を訴えるべき時に、藤井さんの語ってくれた内容は生かしていきたいと思いました。
藤井さんの登壇内容は、私にとっての自分ごととして拝聴することができました。
上に書いたIoT分科会の中で山口県庁の方とはご縁がありました。そのため、より一層、自分ごととして再び山口に関わり、応援したくなりました。
長州はかつて明治維新を成し遂げ、近代日本の発展に大きな貢献を果たしました。令和の今、松下村塾のような存在が山口から生まれ、わが国を再び羽ばたかせるかもしれません。
山口県庁がこれからkintone導入において活発になることを願ってやみません。また、今回のkintone Caféの内容から考えると、その可能性は高そうです。
楽しみです。
山口県庁がこれからkintone導入において活発になることを願ってやみません。また、今回のkintone Caféの内容から考えると、その可能性は高そうです。
楽しみです。
 休憩の後は筒井さん。
休憩の後は筒井さん。この筒井さんこそが、冒頭に挙げた「技術者としてのこれからを考えさせられた」体験をもたらしてくれた張本人です。
非技術者でありながら、AIを使えばここまでのことができてしまう実例。
私もその事はもう今までにnoteで何回も書いてきています。うちのメンバーに危機感を持ってもらうためです。私自身もその危機感を抱いていたつもりでした。
ただ、それが生きた見本として目の前で筒井さんの登壇を拝見して、実例として見せられるとやはり驚きます。
本当にそうした方がいた事実と、私が伝えてきた事は間違っていなかったという安堵。それとともに押し寄せてきたのは技術者としての危機感です。
私もその事はもう今までにnoteで何回も書いてきています。うちのメンバーに危機感を持ってもらうためです。私自身もその危機感を抱いていたつもりでした。
ただ、それが生きた見本として目の前で筒井さんの登壇を拝見して、実例として見せられるとやはり驚きます。
本当にそうした方がいた事実と、私が伝えてきた事は間違っていなかったという安堵。それとともに押し寄せてきたのは技術者としての危機感です。
筒井さんのような熱意のある方がこれからどんどん増え、技術者の力を借りずに自力で業務改善を成し遂げてしまう未来がもう実現されていること。そして、第二第三の筒井さんのような方々がこれからも控えているであろうこと。
その時、技術者に与えられた案件の総量は増えるのか、それとも減っていくのか。
その時、技術者に与えられた案件の総量は増えるのか、それとも減っていくのか。
私はあと5年はkintone界隈の案件の総量は増えると見ています。
ですが、それ以降はこうした筒井さんのような方が増えていくことで、減っていくのではないかと一抹の不安を抱えています。
今でもAIに頼めばコーディングなどもしてくれます。きっちりとプロンプトに指示内容を書けば、かなりの確度で正確なコードが返ってきます。
そのコードの実装方法やシステム構成も的確に質問すれば、的確な答えが返ってきます。
筒井さんは通勤車内でAIと音声で対話し、そこで解像度を高めたプロンプトやコードを考え、会社に着いた後、実装に専念します。そうすることで、今まで非技術者が難しいと諦めていた実装が実現できてしまう。
まさに脅威であり、かつ、これからのわが国はこういう頼もしい存在が支えていってくれると安心できます。
筒井さんとは夜の懇親会でも語り合いましたが、その経歴からもさまざまなことを考えさせられました。例えば学校教育の効力とは何かや、コミュニケーション能力の必要性など。 今までもnoteでは何回か取り上げていますが、引き続き筒井さんや筒井さんのような方については題材にさせてもらいたいと思っています。
ですが、それ以降はこうした筒井さんのような方が増えていくことで、減っていくのではないかと一抹の不安を抱えています。
今でもAIに頼めばコーディングなどもしてくれます。きっちりとプロンプトに指示内容を書けば、かなりの確度で正確なコードが返ってきます。
そのコードの実装方法やシステム構成も的確に質問すれば、的確な答えが返ってきます。
筒井さんは通勤車内でAIと音声で対話し、そこで解像度を高めたプロンプトやコードを考え、会社に着いた後、実装に専念します。そうすることで、今まで非技術者が難しいと諦めていた実装が実現できてしまう。
まさに脅威であり、かつ、これからのわが国はこういう頼もしい存在が支えていってくれると安心できます。
筒井さんとは夜の懇親会でも語り合いましたが、その経歴からもさまざまなことを考えさせられました。例えば学校教育の効力とは何かや、コミュニケーション能力の必要性など。 今までもnoteでは何回か取り上げていますが、引き続き筒井さんや筒井さんのような方については題材にさせてもらいたいと思っています。
筒井さんの登壇は、一つのストーリーとして見事です。
私たちの共感も得られ、内容のクォリティも含め、ぜひkintone hiveに登壇してほしいと思える内容でした。
ぜひ中四国代表として登壇してくださることを待っています。
私たちの共感も得られ、内容のクォリティも含め、ぜひkintone hiveに登壇してほしいと思える内容でした。
ぜひ中四国代表として登壇してくださることを待っています。
 ここからはLTタイム。
ここからはLTタイム。まずは原田さんから。
子ども向けにプログラム教室を開いていらっしゃる原田さん。その中でkintoneについて思っていただいていることを率直に語ってくださいました。まさにおっしゃる通りです。こうした方がkintoneに対して向き合ってくださり、こうした場で登壇してくださることが、これからのkintoneエコシステムには必要です。また、日本の生産性を上げるためにも必要です。
原田さんのように子ども向けに啓蒙活動をしてくださる方が、kintoneをはじめとしたノーコードツールを広め、業務改善の風土や基盤を子どもに対して教えてくれることが、これからの日本を変えるはずです。
ぜひ応援したいと思いました。
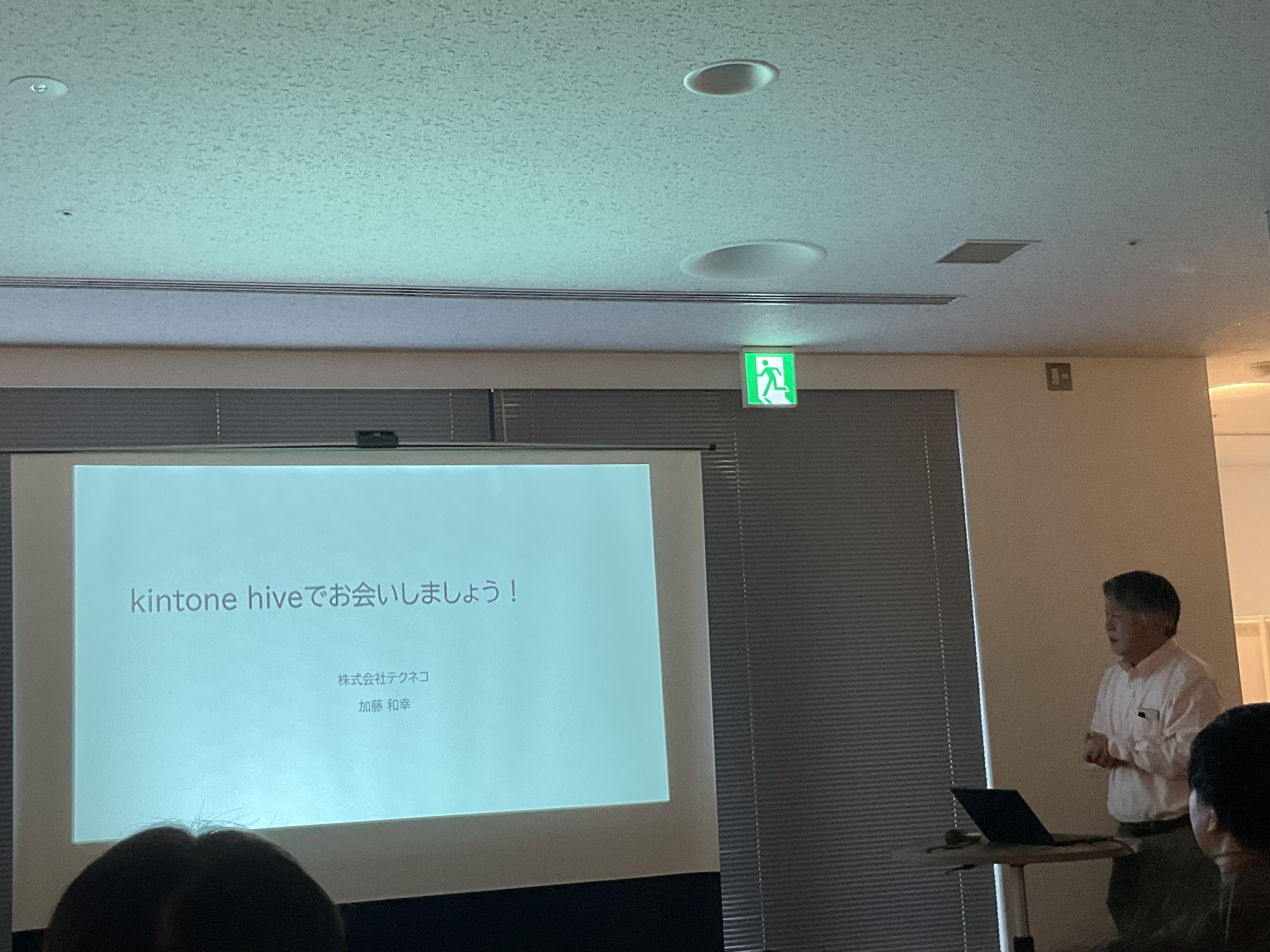 続いては加藤さん。
続いては加藤さん。昨年のkintone Café 山口でもご一緒した加藤さん。
今回もメグリバに来る前の駅の広場でばったり出会い、一緒にメグリバまでの道すがらを語りました。
kintone Café 神奈川を立ち上げた加藤さんは、今、kintone hiveを巡る活動にも力を入れておられるそうです。今回の登壇でも「kintone hiveでお会いしましょう!」と題して語ってくださいました。過日、広島でもkintone hive Hiroshimaが行われました。その紹介や三日後に福岡で開催されるkintone hive Fukuokaへのお誘いなども話されていました。
私もkintone hiveにはなかなか行けていません。今年も結局、kintone hive Tokyoに行くのがせいぜいです。
私ももう少し余裕ができたら、全国のkintone hiveを巡りたいと思っています。なぜなら、システム技術者の役割とは、ただ言われた仕様をコードやプログラムに実装することではなくなるからです。
ユーザーのニーズを的確に汲み取り、言われたことより上のシステム提案を行わねばならない時代はすでにきており、kintone hiveのような場から学べることも多いはずです。
私もkintone hiveにはなかなか行けていません。今年も結局、kintone hive Tokyoに行くのがせいぜいです。
私ももう少し余裕ができたら、全国のkintone hiveを巡りたいと思っています。なぜなら、システム技術者の役割とは、ただ言われた仕様をコードやプログラムに実装することではなくなるからです。
ユーザーのニーズを的確に汲み取り、言われたことより上のシステム提案を行わねばならない時代はすでにきており、kintone hiveのような場から学べることも多いはずです。
 続いては高知からの片岡幸人さんによる「kintoneでオープンデータの活用」です。
続いては高知からの片岡幸人さんによる「kintoneでオープンデータの活用」です。昨年、私と幸人さん、吉富さんの三人でMessengerで会話し、どういう登壇内容にするかを決めました。今年も同じ場で会話をし、私たち2人はLT登壇でという要請をいただきました。そこで私と幸人さんは地図やオープンデータの共通のテーマで登壇することにしました。
幸人さんの調べによると、山口県でもオープンデータは提供されており、使える可能性があるそうです。
上に挙げたIoT分科会でも、かつてRESASが取り上げられました。私もその存在を知りました。今、RESASはアップデートされましたが、私の中でまだ理解が進んでいません。
上に挙げたIoT分科会でも、かつてRESASが取り上げられました。私もその存在を知りました。今、RESASはアップデートされましたが、私の中でまだ理解が進んでいません。
幸人さんの登壇を聞きながら、IoT分科会に参加していた頃に、もう少し山口にコミットができていればとの後悔が脳裏をよぎりました。でも、今からでもまだ間に合う。kintoneを用いてそうした活動をしなければと感じました。
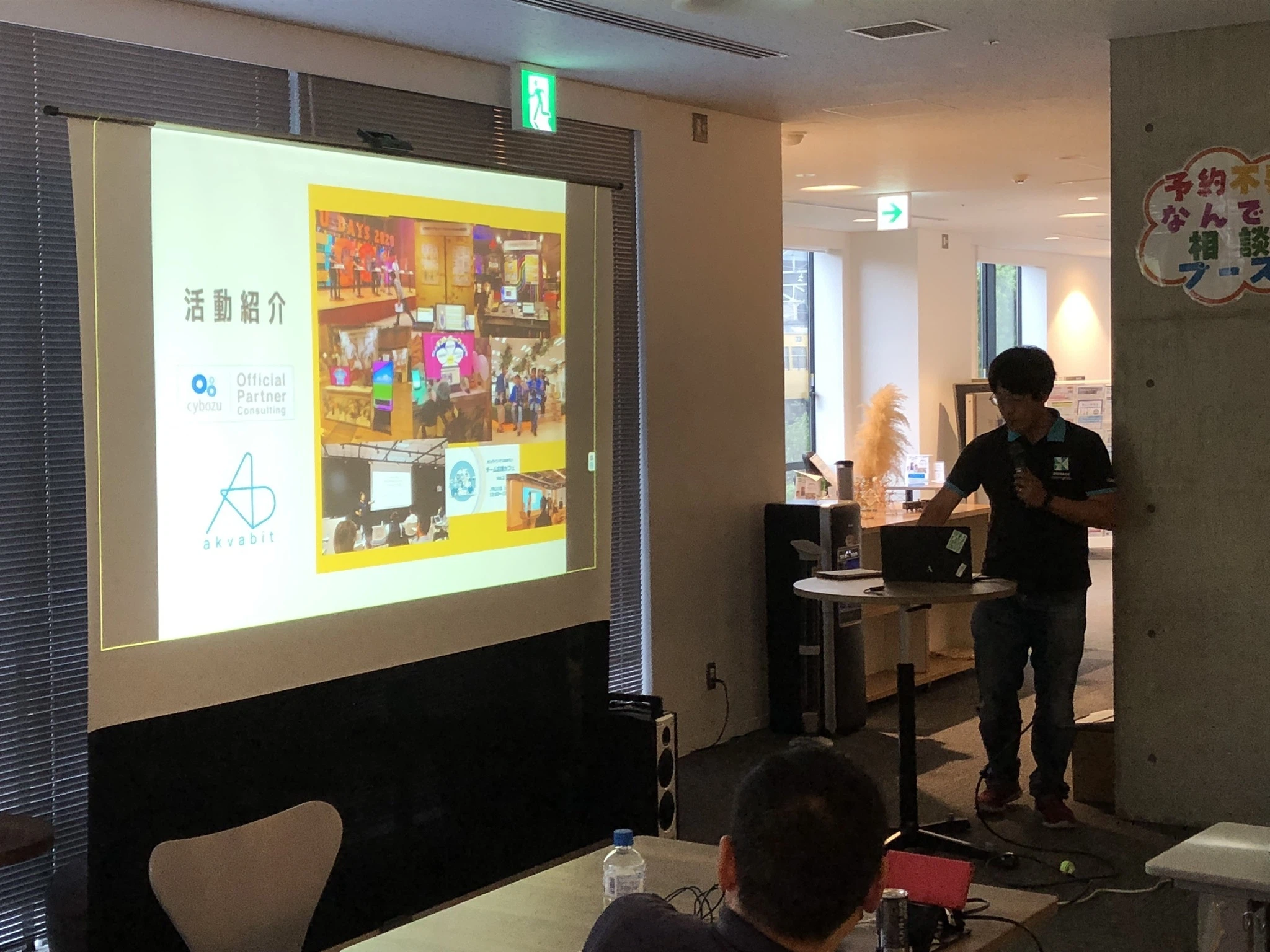 さて、LTの最後は私です。
さて、LTの最後は私です。私は先日のkintone Café 和歌山で登壇した内容の山口版ということで少し短くして話しました。
オープンデータの下りは全部カットし、山口用に農林水産省のポリゴンデータをダウンロードし、国土地理院のパネルデータも山口版に差し替え、ポリゴンデータを使えば無料でもここまで地図データをkintoneで可視化できるとお伝えしました。
実は私のポリゴンデータのネタは、檜谷さんが登壇の中で取り上げてくださいました。また、紀伊田辺で経験した奇跡の連鎖の再現かと驚きました。実際、私の登壇内容に興味を持ってくださった方もいたようで、良かったです。
今回も登壇内容を新たに考える余裕がなく、不本意ながら前回の登壇内容を流用してしまいましたが、一方で、この内容は各地の方に知ってほしいという思いもあります。また、別の地方に行った際、時間がなければこの題材をその他地域向けにアレンジして登壇しようと思います。
それにしても、Xで誰も実況ポストを投稿しておらず、私の登壇写真がまったく残っていません。
ということで吉富さんの作ってくださったレポートから写真を拝借しました。
実は私のポリゴンデータのネタは、檜谷さんが登壇の中で取り上げてくださいました。また、紀伊田辺で経験した奇跡の連鎖の再現かと驚きました。実際、私の登壇内容に興味を持ってくださった方もいたようで、良かったです。
今回も登壇内容を新たに考える余裕がなく、不本意ながら前回の登壇内容を流用してしまいましたが、一方で、この内容は各地の方に知ってほしいという思いもあります。また、別の地方に行った際、時間がなければこの題材をその他地域向けにアレンジして登壇しようと思います。
それにしても、Xで誰も実況ポストを投稿しておらず、私の登壇写真がまったく残っていません。
ということで吉富さんの作ってくださったレポートから写真を拝借しました。
 さて、皆で写真を撮り、懇親会へ。
さて、皆で写真を撮り、懇親会へ。懇親会場は近くの「黒船」でした。
皆さんでそれぞれの話題に花を咲かせました。私は原田さんや筒井さんとご一緒だったので、お二人が登壇でお話ししなかったようなこと、例えばこれまでの経歴など、深い内容を聞くことができました。
また、何人かが帰った後は、さらに二次会の「餃子のやっさん」に場所を移し、話の続きをしました。
ここでは、檜谷さん、藤井さん、筒井さんと私で一つのテーブルを囲んでの深い話ができました。
皆さん、これからの山口や中四国のkintone界隈を支えていってくれる人ばかりです。いや、中四国に限らず、他の地方にもこの熱を伝えていってくれる方々です。私もぜひそんな皆さんとご一緒に活動できればと思いました。
ここでは、檜谷さん、藤井さん、筒井さんと私で一つのテーブルを囲んでの深い話ができました。
皆さん、これからの山口や中四国のkintone界隈を支えていってくれる人ばかりです。いや、中四国に限らず、他の地方にもこの熱を伝えていってくれる方々です。私もぜひそんな皆さんとご一緒に活動できればと思いました。
惜しむべきは、同日にkintone Café 広島が開催されており、山口に参加したかった方が参加できなかったかもしれないことです。
今回のkintone Café 山口の内容は、ぜひ多くの方に聞いてほしかったなぁと思う内容でした。それが惜しい。
山口の運営の皆さんにはぜひXでの告知もお願いし、隣県同士での開催バッティングは防いでもらえると良いと思いました。
今回のkintone Café 山口の内容は、ぜひ多くの方に聞いてほしかったなぁと思う内容でした。それが惜しい。
山口の運営の皆さんにはぜひXでの告知もお願いし、隣県同士での開催バッティングは防いでもらえると良いと思いました。
次回も開催しようと盛り上がりを見せました。次回は萩で開催されるかもしれません。萩といえば松下村塾をはじめとした日本の維新の震源地の一つです。
私もお誘いいただいたので、また参加したいと思います。
そして、山口県のkintone活用の盛り上がりに一役買えたらと思います。
私もお誘いいただいたので、また参加したいと思います。
そして、山口県のkintone活用の盛り上がりに一役買えたらと思います。
今回の主催である吉富さん、奥様、藤井さん、中野さん、ありがとうございました。登壇された檜谷さん、筒井さん、原田さん、加藤さん、幸人さん、ありがとうございました。そして、参加者の皆さん、ありがとうございました!


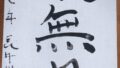
コメント