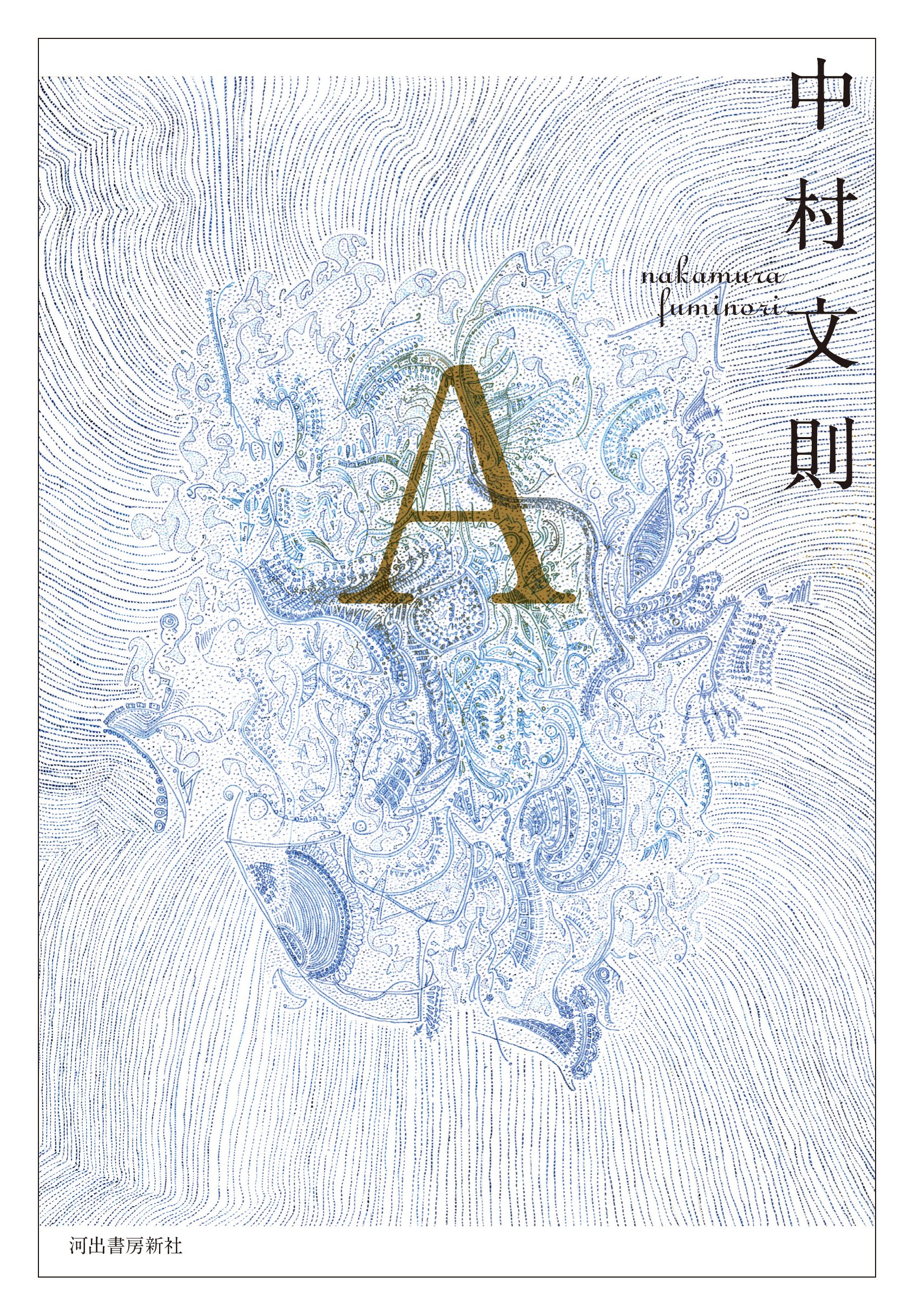
著者の長編は何冊か読んできた。だが、短編は初めて読む。
本書に収められた十三篇のそれぞれは、新たな著者の作風の一面を表していてとても面白く読めた。
十三編の全てに共通するテーマとは何だろう。
それは個々の人の生と社会の断絶ではないか。人が生きる上で思索する流れが、社会の流れとどれほど違っているか。
本書に収められた全ての短編の登場人物が、自らが抱える思いが世間の通念とほんの少しずれていることに気づいている。
気づきながら、その差を埋める術を知らず、ただ思考を垂れ流しながら日々を生きている。
それらのズレを著者はうまく言葉に表し、文章に紡いでゆく。
「糸杉」
ゴッホの「糸杉」の妙な禍々しさは、印象に残る。
渦巻き模様で描かれた糸杉や畑や三日月や雲や空。
本編はその糸杉に取りつかれてしまった男の、妄想に支配されそうになる思考の流れを追っている。
糸杉に惹かれるあまり、同じように美術館で糸杉に見入る女性に執着する男。執着のままに女性の後をつける。
その女性は風俗嬢。店に入って風俗嬢のサービスに己の性欲をうまく適合させようとする。だが、そうはならない。行き場をしなった欲望を苛立ちのあまり暴力として発現させてしまう。
欲望のリビドーが暴発するさまを現代の孤独なあり方と結びつけた、印象に残る一編だ。
「嘔吐」
コンビニの、おそらくはスーパーバイザーの仕事に従事している主人公。
結婚している。穏やかな外見をまとったまま、日々を送っている。
けれども、何か違和感を抱えながら生き続けている。
そんな日々を描き、社会の中、組織の中で生きる。だが、仕事の目的やあり方が自分の生き方とずれてしまっており、それが何かを追い求めている。
それは、生きるための実存と言う意味で良いだろう。ジャン=ポール・サルトルも同じ名前の小説をものにし、そこでも人間の実存とは何かについて追い求めている。
本編もまた、繰り返しの毎日の暮らしに人が何を求めようとしているのかを根本から考えている。著者の姿勢もそこにあるのだろう。
「三つの車両」
本編は、通勤に題材をとっている。通勤といえば日々の繰り返しの代表的な場面だ。その当たり前の日常が突如として変転し、異常に走っていく様子を描いている。
裸の男が横たわったまま少しずつ巨大化し、車内を満たしていく。そして電車は目的の駅にいつまでたっても着かない。
人々が通勤のすました仮面の下、隠していた欲求が、行動や言葉に漏れだす。そして現実を侵食する。
それを観察しながら、自らも良からぬ妄想に浸る作家。
その作家とはもちろん、著者自身でもあるはずだ。
著者自身の作家としての妄想を断片に表すとこのような作品になる、ということを表した短編だ。
「セールス・マン」
本編も、日々の雑多な出来事の断片を、妄想にからめている。作家の想像力を日常の中におけば、どういう作品ができるかを表している。
生活申請を待ち続ける列は無限に伸びていき、人々は、無意味な妄想に余念がない。
セールスの仕事にも実は全く意味がないのだ。そのことを言いたいかのように、人々は何かと何かを交換し続ける。
世界が終わりへと向かっているその瞬間にも。
「体操座り」
作家としての自分の実存がナンセンスであること。
著者自身も現実の生活に違和感を覚えながら生きているのだろう。
日常の愉快な出来事も真面目な仕事も、全てが現実に流れていく感覚。
そうした全ての違和感を、著者はナンセンスな言葉の流れでつないでいく。
何を目的にしているのか、一体われわれは何を目指しているのか。
つまるところ、そこに答えはない。著者はそう言いたいかのようだ。
「妖怪の村」
ヒッチコックの鳥のように、鳥に襲われた街。
住民は周囲から身を守りながら、奇妙に仕事のルーチンを守ろうとする。
合間には優美な行為に時間をつぶしながら、鳥の襲撃に対策を打つふりをする人々が描かれる。
そもそも、予定調和の世界はどこまでが予定なのか。何が何と調和しているのか。
見た目は平穏で安定しているように見える世界。その不安定な可能性を著者は鋭く短編として表している。
「三つのボール」
生きること。社会というもの。その法則はどこにあるのか。それを物理の法則に置き換えて単純にモデル化する。
妄想の一つとして誰もが考えることだと思う。
本編はそれを短編に表したものだ。
三つのボールの動きが作用し合う。お互いに対応し合う。
そこに思惑などという高尚なものはない。ただ反応の繰り返しに過ぎない。
著者の乾いた世界観の一端が見えているようだ。
「蛇」
画家の老人が、裸のモデルを描く。裸体を描きながら、言葉でモデルを責めようとする。
蛇は性的なモチーフとしてはよく使われる。そのイメージを登場させながら、言葉やイメージを援用することでしか女性を責められない老人の衰えと苛立ち。その苛立ちを、さまざまな言葉で表したのが本編だ。
これもまた、現実の認識と自分の中の認識に差異を自覚したものの末路を見越した一編だと言える。
「信者たち」
教会の壇上でセックスする男女。その背徳の行為を神の不在や宗教の空虚さに結びつけた一編だ。
信心は個人の問題であり、宗教の本質が組織による集団の同調圧力であることは確かだろう。
それを性のイメージで表し、統合しようとした冒険作だ。
「晩餐は続く」
本書の中では、もっとも分かりやすい。
政治家の二世の夫に嫁いだ女の視点から、無能で甲斐性のない夫の浮気への復讐を兼ねた晩餐。
追い詰める女の怖さが本編の中で鮮やかに描かれている。
本書の中でもっとも人に薦めやすい一編かもしれない。
「A」
第二次大戦中の日本軍。中国人の捕虜を首だけ残して生き埋めにし、斬首を強制する上官。その理不尽な命令に抗おうとするが、抗いきれない男が自我を崩壊させる様子を描く。
そもそも戦争とは、己が認識する世界と現実の世界の認識がもっとも乖離する場と言える。その中で人は残虐になり、われを忘れる。
戦争は人を殺させるとはよく言う言葉だが、それを短編として描き、イデオロギーの壁も乗り越えて描ききった著者に敬意を表したい。
「B」
本編もまた、第二次大戦中の日本軍が舞台だ。
軍医として従軍した主人公の視点から描かれる本編。慰安の名において連行された女性を正当化された名分のもと、性の慰み者として消費してゆく様子。その中で主人公が自己弁護する醜さを描いている。
「A」と「B」はナショナリズムなど、何するものぞという著者の政治的立場の一端を見せた問題作だろう。
「二年前のこと」
志賀直哉の名前が登場する本編。はるか昔に文壇を席巻した私小説の現代版と言えるかもしれない。
縁のあった女性との思い出を書きながら、その女性が亡くなったことを悼む。そして悼みつつも小説の題材として描ききってしまう作家としてのサガを書く。
志賀直哉を登場させるあたり、本編が私小説であることを著者は明確に意識しているに違いない。
‘2019/12/13-2019/12/16
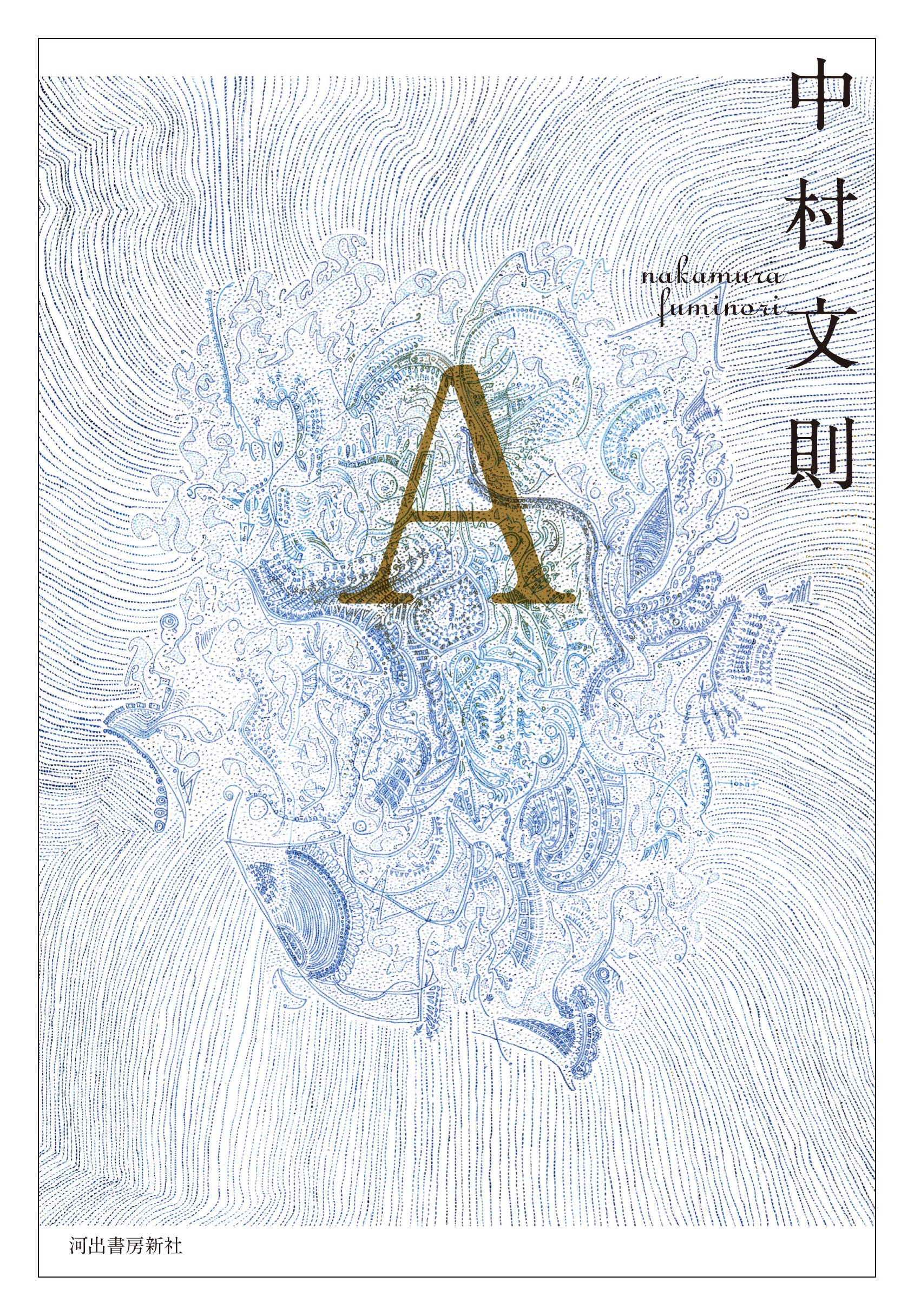
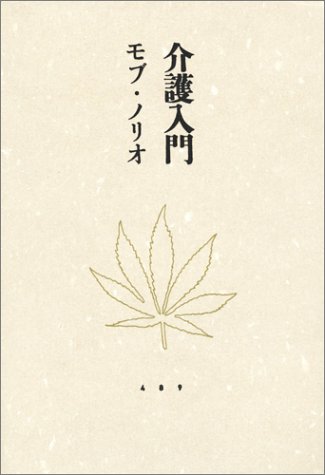

コメント