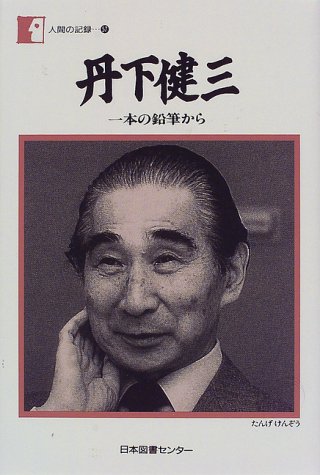
石井光太氏の『原爆 広島を復興させた人びと』を読んでから、本書の著者である丹下健三氏と建築家に興味を持ち、建築家が著した本、建築物を紹介する本などを読んできた。
『原爆 広島を復興させた人びと』は、広島の戦後復興を、原爆ドームと平和公園と広島平和記念資料館の建設過程とからめて描いていた。
その中では、著者が平和記念公園の都市設計を手掛けるようになった背景にも触れている。
昭和20年8月6日。
今治の実家の父が死すとの電報を受け取った著者が乗った列車が、突然尾道で止まってしまう。それは広島に新型爆弾が落とされたからだった。
ようやく故郷の今治にたどり着いた著者は、父が既に8/2に亡くなっていたことと、8/6の今治空襲によって母も世を去っていた事実を知る。
戦争が母を奪い、そして原爆が旧制高校時代に著者が学んだ広島を破壊した衝撃。
その衝撃が著者を広島平和公園の都市設計に駆り立てたことは容易に理解できる。
『原爆 広島を復興させた人びと』で紹介された8/6の著者の体験は、本書から引用されていた。
それ以来、一度は本書を読まねばと思っていた。
本書の表紙には著者の晩年の顔写真が掲載されている。とても福々しい容貌だ。上方の落語家、桂米朝師匠に似ている。
失礼ではあるが、建築家には思えない。ましてや世界のタンゲというキーワードは浮かんでこない。
だが、著者の名声は世界中に知れ渡っている。広島以外にも日本や世界のあちこちにシンボリックな建築物の設計を手掛けた実績。
本書の内容は、広島平和公園を手掛ける前半部までは自伝的な要素が強い。だが、それ以降は華麗なる世界の名士にふさわしい遍歴が続く。
某国の王室、某国の政府、さる国の首都の都市計画。会う人、会う人物が各国の首長であり、大統領である。もらう勲章、爵位、勲位。キリがない。とにかく華麗。とにかく豪華。功名を遂げた者にしか許されない高み。本書の後半は私ですら、鼻につくほどの栄誉の連続だ。
表紙に載せられた著者の福々しい風貌が中和していなかったら、本書の余韻は後半の印象に引きずられて悪くなっていたに違いない。
だが、本書は自分の経歴を誇らしげに語っているだけと見なしてよいのだろうか。そんな疑問も湧く。
本書で著者は、自らの活動を振り返っている。
他の本やWikipediaでも触れられていたが、著者は普段、そうした自分の経歴や業績をあまり語らなかったそうだ。Wikipediaの著者の項目にも、過去の業績に対して無頓着だったと書かれている。
それらを信じるならば、著者は普段、自らの実績や自らを誇るようなことは語らないし書かなかったようだ。つまり、本書は、一生に一度のつもりで、普段は振り返らなかった自らを詰め込んだのだろう。
著者をかばうわけではないが、著者がやり遂げたことのレベルは高すぎる。だからこそ、ありのままの姿を書いてもそれが自慢に感じられてしまうのだろう。
ましてや本書は日経新聞に連載された「私の履歴書」が元になっているという。ということは、限られた紙面しか与えられておらず、エッセンスを詰め込んだ。
それが後半の業績や華麗なる交流となって現れているのではないだろうか。
本書には、著者が設計を主導した建築物の写真や完成予想模型が豊富に載せられている。著書はそれらの建物にも言及している。その数たるや膨大。
その多くに私は足を踏み入れている。広島平和記念資料館。フジテレビ本社。代々木体育館。東京都庁。東京ドームホテル。兵庫県立人と自然の博物館。大阪万博お祭り広場。大津プリンスホテル。横浜美術館。
それぞれの建物の外観がすぐに思い出せる。それだけ著者の手掛けた作品が独創的であり印象に残ったのだろう。
建築の分野に限らず、名声を浴びる人は間違いなく何かを表現し、それを発表している。
著者の場合、表現の対象が建築物である。そのため、著者の実績も目立ち、長きにわたって人の目に触れている。批評にさらされ続けながら。
著者は本書の中で自らの建築家としての哲学や仕事のやり方にも触れている。
何度も一位を獲得した各種の設計コンペティションに臨むにあたり、泊まり込みも辞さなかったこと。何人ものチームで徹底的に議論し、少しでもよい提案を行うべく議論したこと。
著者の業績は、そのような不断の努力に裏打ちされていることはいうまでもない。もちろん、私が付け足すこともない。
では、そのような実績と栄誉が書き連ねられた本書から、読者は何を読み取ればよいのだろうか。
私は本書から三つの学びを読み取った。
一つ目は、著者が建築家を志したきっかけだろう。
星が好きで数学を得意とする少年が、多感な時期に芸術に心を動かされたこと。
文系に志望を変えようとしたが、建築は理系の頭脳を生かしながら芸術も表現できると思い至り、志望を建築に変えたこと。
そこからは、文系や理系といった枠にこだわらず、より広い視野で物事に取り組むことの大切さが学べる。
二つ目は、冒頭に書いた通り、父母の死去が原爆投下に重なった悲劇だ。それを著者は創造へのエネルギーに昇華させた。
そのエネルギーは、著者の広島への思いとあいまって平和記念公園の設計への熱意と変わった。
私たちは毎日の暮らしから、著者が体験し、昇華させたような体験をどこに見いだすべきだろうか。そして、その体験をどうとらえ、どのように自らの創造の力に変えればよいのだろうか。
それを見つけ出すのは私たちだ。
三つ目は、著者の仕事への姿勢だ。
本書が書かれたのは著者が70歳を超えた頃だと思う。が、まだ一日ぐらいの徹夜は平気と書かれている。本書の中では一ページほどしか割かれていないが、著者のバイタリティと集中力は、私たちも見習わなければなるまい。
本書に書かれた華麗な交流や栄誉や実績に目を奪われ、こうした著者の努力を見逃してはならない。
本書には、『私の履歴書』の連載に加えて、著者によるこれからの建築論が披歴されている。
著者はその中で、情報技術が進化する将来にあって、建築はどうあるべきかを述べている。建築物それ自体の機能ではなく、建築と建築をつなぐ空間の大切さ。その空間を情報が流れるための媒体として生かすべきだと。
技術が進歩し、建物の機能は充実してきた。だからこそ、建物に利用者や設計者の感情や美を含めるべきだし、そうした感情の情報が流れることを考え、空間設計をしなければならないと主張している。
本書には著者が手掛けた「東京計画――1960」も紹介されている。
「東京計画――1960」とは、川崎と木更津を太い線で結び、その線上に首都機能を配置する構想だ。
周知のとおり現代ではこの構想はアクアラインとして実現している。だが、海ほたるをのぞけばアクアラインの現状はただの連絡道路にすぎない。
また、著者が構想した時期に比べると、首都圏の集中の弊害ははるかに深刻になっている。地震や富士山噴火のリスクも無視できない。
今こそ、東京の都市計画が求められている。
著者のような人物が、遷都を含めた東京のマスタープランを構築しなければならない。
もちろん、そのためには、私たちも努力しなければならない。
著者の受けた無数の名誉や栄誉に嫉妬しているだけではだめなのだ。
‘2019/10/21-2019/10/21
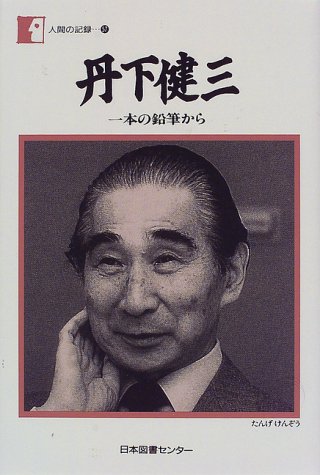
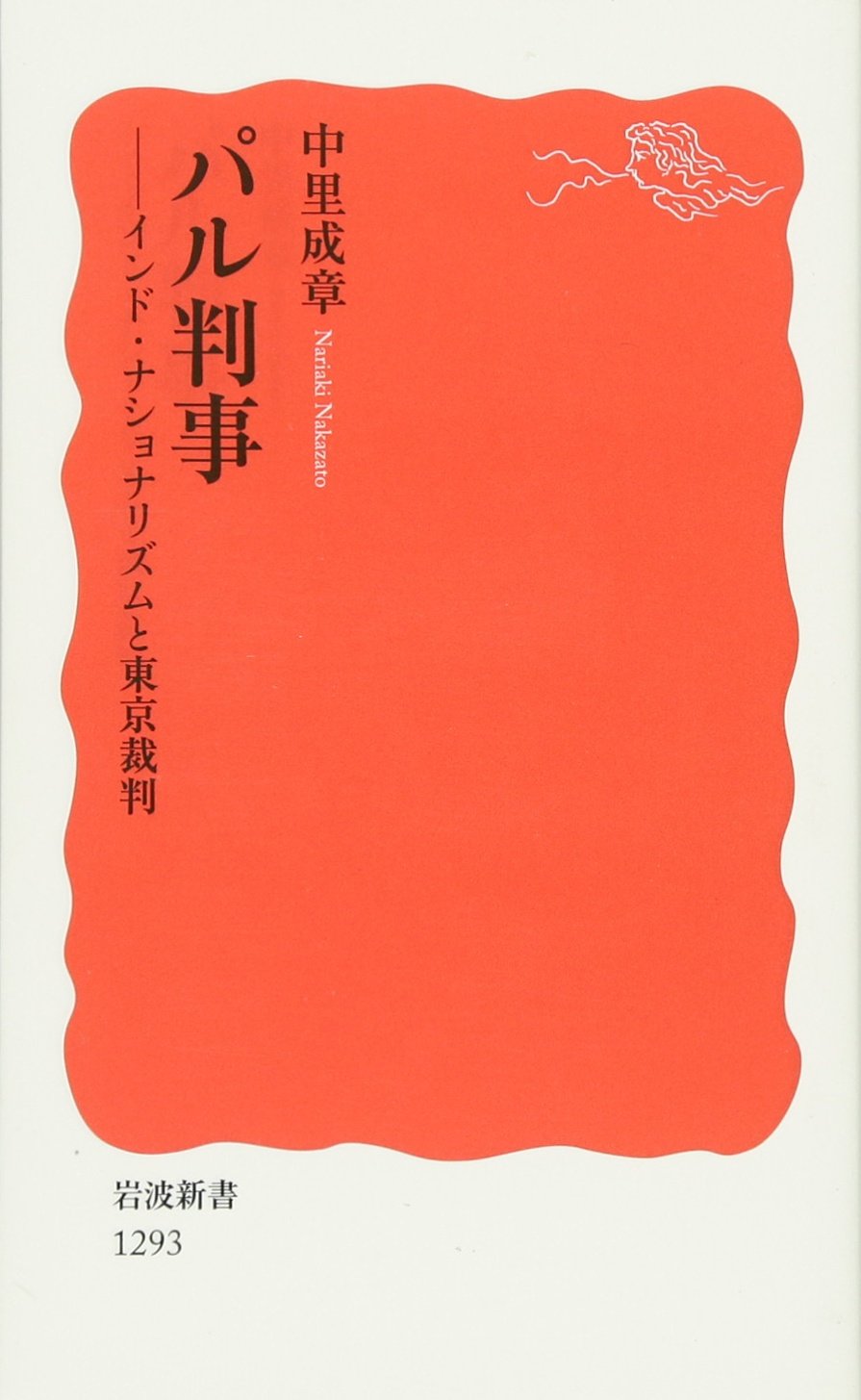
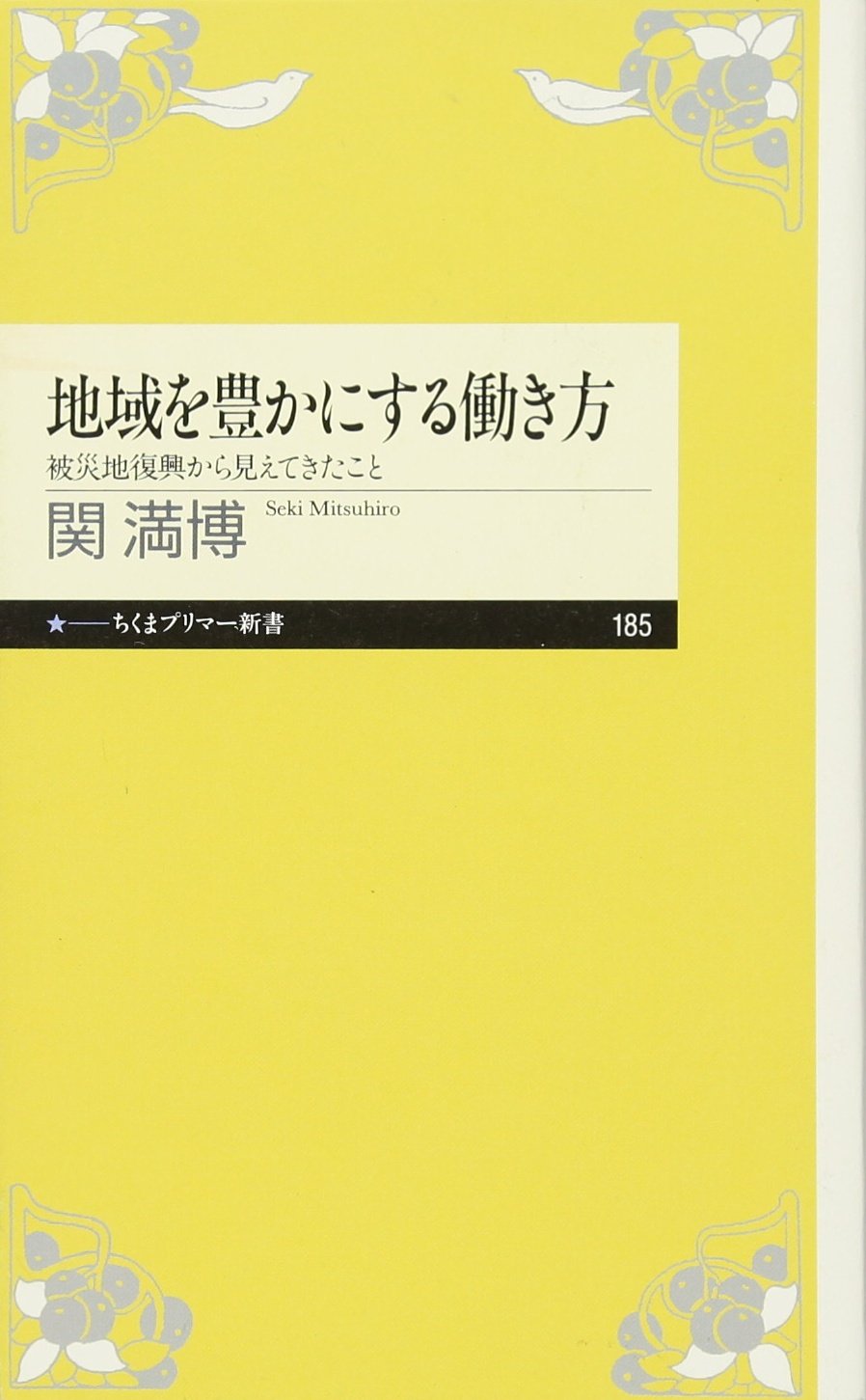
コメント