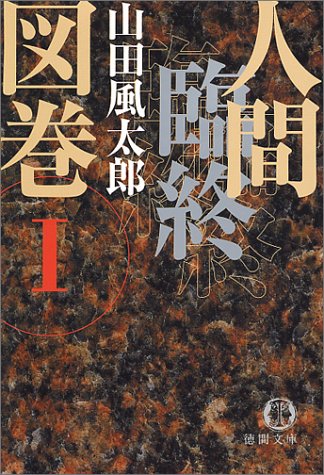
伝奇作家として知られる著者だが、有名な諸作品を読む前に著者の書いた伝記を読むことになってしまった。何を隠そう、私は著者の作品を今まで読んだことがなかったのだ。雑誌ではなく、書物で読むのは初めて。
本書は、古今東西の有名人の死に様を集めている。取り上げられているのは、享年が若い順だ。
冒頭をかざるのは、八百屋お七。想い人に逢いたいあまり放火をしでかした江戸の女性。享年十五歳。次は大石主税。忠臣蔵で知られる内蔵助の息子だ。父と共に吉良邸に討ち入りを果たし、切腹で生涯を終えた。享年十五歳。その次に登場するのは、ナチの強制収容所で命を落としたアンネ・フランク十六歳だ。
冒頭の若くして亡くなった三人は、どれも我が国では知られた存在だ。だが、人類の歴史を振り返れば享年十五歳未満で亡くなった人は他にもたくさんいるはずだ。だが、本書には登場しない。恐らくは本書に取り上げられるに足る業績がないためだろう。(放火を業績というのは憚られるが。)
なぜ、十五歳未満の人物が登場しないのか。それは、人生で成果を出し始める時期が十五歳以降であることを示す証拠だと思う。
本書は以降、十代から二十代、三十代と取り上げられる享年が上がってゆく。それに従い、紹介される死に様が変わっていくのが興味深い。
若いうちに亡くなる原因とは、不慮の事故であることがほとんどだ。もしくは若さ故の勇み足か。だが、将来を嘱望されながら、若くして病に世を去った方もいる。彼ら彼女らの無念も本書には取り上げられている。
三十代にもそれぞれの一生の締めくくりがあり、四十代にも死に至るまでの事情がある。著者がとりあげるのは、聖人君子だけではない。鬼畜な犯罪者だって革命家だって等しく取り上げる。いかに死んだのかを書く本書だが、何かを成し遂げないと本書には取り上げられないのだ。ただ死んだだけなら他にも該当者は沢山いる。諸外国にはその地で有名な若くして亡くなった人もいるだろうが、つまりは著者が取り上げるかどうかだ。やはり何をなしたか、が重要になるのかもしれない。
ただ、生前の業績が取り上げられる理由になるとはいえ、やはり本書は死に様を描く本だ。本書は享年五十五歳でなくなった大川橋蔵までが取り上げられている。人生五十年の信長の時代ならともかく、今から見ると五十代で死ぬのは若死にを意味する。
そのためだろうか、著者が書く若い人々の死に様には、どことなく哀惜の色が漂う。本書には32歳で暗殺された坂本竜馬も取り上げられているが、著者は以下のような言葉をはなむけに添えている。「もう少し生かしておきたかった、と思われる人間は史上そう多くないが、坂本竜馬はたしかにその一人である」。他に著者が本書内で同様に評価しているのは大杉栄、小栗虫太郎、島津斉彬などだ。
また、著者が作家なだけに、作家の訃報には紙数が割かれている。石川啄木や夏目漱石など。
本書は日本人の著者によって書かれただけに、日本人の割合が非常に高い。だからこそ、我々にとっては思い入れもあるし、日本人の死生観について興味深い例を教えてくれる。
自分がどうやって死ぬか。死ぬときには後世に恥じぬ死に様でありたい。そう思うのだが、まだまだそう思うには時間が掛かるのだろうな。
‘2016/07/06-2016/07/08
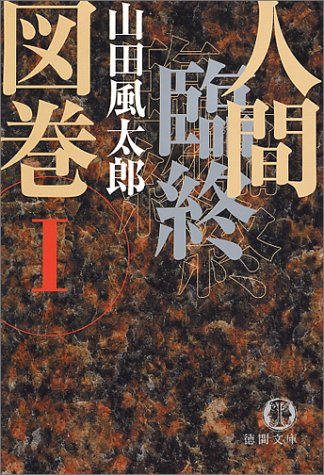

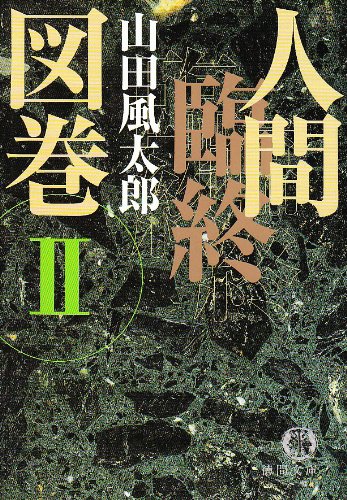
コメント