9月12日のkintone Café 和歌山 Vol.4に参加してきました。
告知ページ

今回、田辺に来たのは約3ヶ月半ぶりです。様々な場所を訪問する私にとってもこのインターバルは短い方かもしれません。
前回、5/24に紀伊田辺駅前のkintone Café 和歌山 Vol.3にお呼ばれし、会場のtanabe en+で登壇した私。再度の登壇のリクエストをいただき、再び田辺にやってきました。
登壇のリクエストがあったことは、前回の内容がご評価いただいたからでしょう。となれば、お応えしないわけにはいきません。
ましてや今回、会場をお借りする田辺市役所さんの皆さんからのリクエストとなればなおさらです。
もう一つ、私が再訪を躊躇しなかった理由があります。
それは、前回のkintone Caféの翌日に皆さんで田辺や白浜を散策したのですが、当初訪問予定に入っていたアドベンチャーワールドの訪問を諦めたことです。入場チケットも買っていたにもかかわらず、入場を諦めたのは、当時、アドベンチャーワールドにいた2頭のパンダが中国に返還される一ヶ月前であり、パンダを見納めようと来場客の混雑が連日報じられていたためです。
パンダがいなくなった今、アドベンチャーワールドを楽しめるゆとりがあるはず。今回のkintone Caféの日程にアドベンチャーワールドの訪問が組み込まれ、さらにそこにイルカが好きな私の妻も呼び、夫婦旅行も兼ねることにしました。それもあっての田辺再訪でした。
今回、登壇の依頼にあたり、私としてはガラッと趣向を変えるべきかどうか考えました。
登壇にあたってテーマが指定されていれば、私としてもそれに沿えば良いのです。ただ、前回の登壇内容がとても印象を与えたのか、私が話す内容であればなんでも学びになるから内容はお任せしたい、とのことでした。
そこまで言われれば、普通は前回とガラッと変えた内容を選ぶべきなのでしょう。
ところが私の今回の登壇のベースは地図連携です。つまり前回とテーマを変えずに臨みました。
これは私には珍しいパターンです。なぜなら、要望があろうとなかろうと、場所や運営の皆さんが変わろうと、私が同じ内容で登壇することはほとんどないからです。
私は性格的に同じことを繰り返すことが苦手です。
ではなぜ同じテーマで話したのでしょう。その理由は私に十分な時間がなかったことに加えてもう一つあります。
前回のkintone Café 和歌山で訪れた田辺の街。前日も当日の朝も翌日も街を巡りました。
その中で、私の印象に残った場所が何箇所もありました。それらの場所は、過去の歴史を踏まえた時間軸の中で考えると、より田辺の街のイメージを豊かにします。
その地とは、田辺城址であり、安政南海地震・昭和南海地震 津波潮位碑であり、南方熊楠翁が神社合祀に反対するパフォーマンスを行った南方熊楠山中裸像撮影場所であり、熊野本宮の大斎原の鳥居であります。
これらの地に共通するのは、水害や人災によって景色が変わり、または、時間の経過や天災によっても山河の織り成す光景は変わっていないことです。自然の強さとしなやかさを表す地なのです。
そうした記録を時間軸と空間軸でkintoneに残せれば、田辺市の皆さんや全国の自治体にとっても参考になるのではないか。また、前回のkintone Caféで、田辺市役所の田上さんと南さんがお話しされた取り組みに対するkintoneを用いた答えになるのではないかと考えたのです。
夏休みのお盆期間、うちの会社は休みにしていました。その時間を生かして私は実装に邁進しました。
kintone上に国土地理院マップを呼び出し、OpenLayersで重ね、ピンを立て、ピンをクリックすると詳細のポップアップを出す実装までは前回もお見せしました。今回はピンをクリックするとポップアップを出すだけでなく、そのポップアップ画面に画像を出す実装を組み込みました。さらにその画像もその場で更新できるようにし、さらには地図の任意の場所をクリックすると新たなレコードを画像も含めて追加する実装も組み込みました。
実装ができたことで、私は本業の作業に戻りました。実際の登壇スライドを作り始めたのは、登壇の約1週間前。ちょうど名古屋で行われたkintone Café 名古屋やdevkin meetupに参加する前の日でした。

さて当日。飛行機が怖くて避ける習性を持つ私は、新幹線とくろしおを乗り継いで田辺にやってきました。
今回の会場である田辺市役所は、田辺駅から15分ほど歩いた高台にあります。前回は来られなかった市庁舎をようやく訪れることができました。

つい1年3ヶ月前に移転したばかりのピカピカの市庁舎です。
この移転にあたっては、海沿いに立っていた旧庁舎が津波被害に遭うことへの対策として立案されたと伺っています。
会場は1階の多目的ホール3で、十分な広さがあります。
こうしたスペースも、災害時に多くの市民を保護することを想定されているとか。有事には避難スペース。平時にはコミュニティに活用。まさに市庁舎とはかくあるべし、とのお手本を見せてもらっています。

まずはキミコさんから開会の挨拶がありました。

続いては、田辺市役所の南さんから「田辺市の紹介& kintoneの利用状況」と題して。
南さんは前回のkintone Caféで、オープンデータを用いた田辺市の地図構築のご紹介をしてくださいました。ちょうどその後に控えていた私の登壇内容に近く、ご縁と内容に対する感銘とともに、私の登壇を後押しされました。
その際、kintoneについて田辺市ではこれから導入を進めるとおっしゃっていましたが、着実に進んでいるようでよかったです。

続いては、小牧岩倉衛生組合の水谷さんです。
水谷さんとは、つい数日前のkintone Café 名古屋でもお会いしたばかりです。
水谷さんの登壇内容は、その時に伺った内容に近しく、私としては回を重ねるごとに、水谷さんの登壇技術が向上していることを実感できました。
こうやって何度も何度も登壇を重ねることで、登壇に慣れていく。それがとても大事だと思います。
私は同じような内容で登壇することはありませんが、登壇を始めた頃も同じ内容を避けたいと毎回登壇内容を変えていました。
ところが、慣れないのに格好をつけて綱渡りの登壇をしていたため、自分でも不十分だと思うような内容もあったかと思います。
水谷さんのように、最初のうちは同じようなことを何度も話し、内容を徐々に自分のものにし、聴衆の反応も含めて取り入れるのがおすすめです。これから様々な場所で登壇をしようと志す方にアドバイスをするなら、同じような内容で何度もいろいろな場所で話し、慣れていくといいですよ、とお伝えしたいです。
水谷さんとは、これからもいろんな場所で登壇が重なるといいなぁと思います。

続いては、アドベンチャーワールドの北田さんと中谷さんからです。
前回のkintone Caféでは、北田さんは懇親会からの参加でした。そのため、少しはお話しできたものの、アドベンチャーワールドでのkintone活用についてはわずかにしか伺えていません。
今回は、実構築に携わっておられる中谷さんと組んでの登壇だったため、いろいろな活用事例が聞けました。

そもそも、私はkintoneに限らず、こういうアミューズメント施設でのシステム運営の内部をあまり知りません。
イベント・サービス業界にはkintoneで関わっているので、全く無縁ではないのですが、こういうパーク系の案件はほぼ無縁です。
そのため、どのような運用が必要なのか、kintoneをどう活用できるかについて、お二人からはとても有益な知識をいただきました。kintoneのようなツールがこうしたアミューズメント施設の運用に合うという確信を深めました。

アドベンチャーワールドは動物園と水族館と遊園地の3つの機能を兼ね備えています。中でも最初の二つは生物が相手です。人間が利用し、人間の関係をベースに発想するシステムとは前提が異なります。
人間の思い通りにならない生物相手だからこそ、より細かい調整が必要です。スタッフが自在に項目を追加し、スタッフ自身が現場で臨機応変に内製できるシステムが求められます。kintoneはまさにそうしたニーズを満たすシステムだと思います。
上に書いた通り、翌日、私たちはアドベンチャーワールドの中を楽しみました。中を巡って、動物たちと触れ合いました。私は園内で、様々なkintoneの活用場面が見られるかと期待してキョロキョロしていました。が、期待に反してkintoneを思わせるパソコンの画面は園内で見当たりませんでした。それもそのはずです。そうした情報が利用者に見えたら問題ですから。
でも、kintone Caféの中で運営の苦労やkintoneの果たす役割を伺っていたことで、kintoneが黒子として園内で活躍していることを容易に想像できました。

続いては石際さんです。
石際さんもまた数日前のkintone Café 名古屋と翌日のdevkin meetupでご一緒しました。また、前回のkintone Café 和歌山でも、私と石際さんはアベック登壇を果たしました。
前回は私が先で石際さんが後でしたが、今回は逆に石際さんが先に登壇します。
前回の石際さんは、田辺が産んだ偉人南方熊楠翁の研究した粘菌が、独自のアルゴリズムでネットワークを形成する様子をkintoneで再現し、地図の最短距離を編み出す様子を再現する離れ技で私の度肝を抜きました。
今回は、その南方熊楠翁が残した南方マンダラに加え、和歌山の誇る高野山の密教文化を取り入れた曼荼羅をkintone上に再現し、複雑なヒアリング要件を曼荼羅によって視覚化する離れ技を見せてくれました。まさに恐るべし石際さんです。

さて、続いては私の出番です。私の登壇内容は上に挙げた通りです。
主観的な印象では、前回の登壇よりも皆様からのダイレクトな笑いの反応は薄かったように思います。ただ、一部の方からは良い反応をもらえました。他の方からの反応も悪くなかったのかなと思います。
多分、前回の登壇と地図連携という骨子が似ていたため、新鮮味に欠けたのでしょう。
ただ、今回はきちんとkintoneとは多次元のデータを管理できるツールだよ、というメッセージを込めました。そこは伝わったのではないかと思います。

私の登壇に続いては、株式会社G-gen 片岩裕貴さんからです。「Google Workspaceについて」とのタイトルでGoogleについて話してくださいました。
kintoneの内容があまりなかったのですが、私はこれはこれでkintone Caféとして必要だと思っています。
なぜなら、kintoneは様々な場面でGoogleの諸サービスと連携する必要が生じるからです。
また、Googleと無縁でいられる現場の割合はそう多くありません。また、仮にkintoneとGoogleが対抗するサービスであったとしても、だからこそ私たちはGoogleのことをよく知っておくべきと思います。ユーザー側としても、開発側としても、何が最適なサービスかは常に考える必要があります。
今のGoogleには、私があまり触っていないサービスもまだあります。その意味でも参考になりました。
特にAI関連のサービスは今のトレンドでもありますし、頻繁に変わるため、興味深くお伺いできました。

さて、続いては飯塚さんです。
同じkintoneエバンジェリストとして長年一緒に活動している飯塚さんですが、私と飯塚さんが同じ場所でアベック登壇を果たすのは、私の記憶が定かなら、今回が初めてかもしれません。

ここで飯塚さんは、エバンジェリストとはかくあるべき、と思わせる見事な会場を巻き込んだ登壇を見せてくれました。
コアな浦和レッズファンとして知られる飯塚さんですが、そこでファンが声援を送る時に使われる「WE are REDS!」をkintoneにもじって「WE are kintone!」を皆に叫ばせる離れ技を。田辺市役所の南さんや、なぜかkintoneエバンジェリストの中尾さんまでで巻き込んで前に呼び、皆を盛り上げるこの破壊力!
かと思えば、きちんと和歌山や熊野での地方創生、地域活性化の事例などを紹介しつつ、kintoneのコミュニティーの本質をそこに絡めてきます。さすがです。
途中、トイレが我慢できずに少しだけ席を外してしまった私ですが、登壇の構成の仕方など、とても参考になりました。

さて、最後を締めて下さるのは宇都宮さんです。
前回のkintone Café 和歌山にもご参加いただき、ドローンや3Dモデリングを用いたkintone活用についての底知れぬ知見の一端を披露してくださいました。
今回は田辺市役所さんからもぜひということで、登壇を引き受けてくださったそうです。そして披瀝された知見の豊富さは素晴らしい。世界の広がりに圧倒されました。
前回のkintone Caféでも、田辺市役所の田上さんによるデジタルツインの活用例や3Dモデリングの可能性に私は強く感銘を受けました。宇都宮さんはそれを事業で展開しており、その事例の数々には圧倒される一方でした。
また、忘れてはならないのが、前職の神戸市役所での事例です。数千のkintoneアカウントを用いて、全庁展開を繰り広げ、全国でもkintone活用で有名な神戸市役所のDX推進のこれからに貢献されています。

私自身、デジタルツインもドローンも3Dモデリングも実装として行う機会がほとんどありません。
もっぱら利用者側としての利用にとどまっています。だからこそ、実装側でそれを展開されておられる宇都宮さんの事例には圧倒されました。言えるのは、この分野がこれからまだまだ莫大な可能性を秘めていることです。
そして、そこにkintoneを組み合わせれば、私が登壇して話したような多次元の広がりに加えて、視覚的に実感できる世界の中に、kintoneが活用できる余地が生まれます。
例えば、プロットしたデータの保管場所としてのkintoneの可能性などです。こういうワクワクさせてくれる登壇って、本当に嬉しいです。

さて、あっという間に盛りだくさんの時間が終わり、皆さんで集合写真を撮り、会場をお開きとしました。歩いて駅前まで移動し、闘鶏神社をご案内いただいた後は、「旬彩居酒屋 膳」さんへ。

ここでは皆さんと大いに語り合いました。二次会は、私が泊まっていたホステルの一階にあるラウンジで場所を変えて。
翌日は、先に書いた通り、アドベンチャーワールドや円月島、白良浜、とれとれ市場、うめ子、味小路などを皆さんと訪れました。妻も翌日から合流し、さらに1日宿泊し、天神崎、高山寺、秋津野ガルテン、奇絶峡、紀州備長炭記念公園など、田辺の街を歩きました。
来れば来るほど、田辺の街は面白いですね。
次にお呼ばれした時は、地図ではなく、違う可能性に着目してお話しできればと思います。まずは今回お会いした皆様、ありがとうございました!


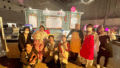
コメント