
パンフレットによると、本作の企画段階において、映画会社からは宗教をテーマから外すように言われたという。 その代わりに提示されたのが、ある中年男性の家に閉じ込められた2人の女性だけの状況設定だそうだ。 だが、本作のホラーの肝は宗教だと譲らなかった二人の監督の英断によって、本作は宗教をテーマに作られたという。
宗教を本筋のテーマに据えた判断は正しいと思う。 宗教の持つ闇の部分と、組織化した時にさらけ出される本質の恐ろしさは、ホラーの題材として十分成立しうる。
宗教。 その恐ろしさは、宗教についてメディアがなかなか触れたがらない理由でも想像できる。宗教を絡めた途端、どこからともなく火の粉が降りかかる。だから、映画会社として面倒なことは避けたいと判断するのもわかる。 宗教とは本来、迷える人々に神という名の光を与える仕組みだ。しかし、その光が強ければ強いほど、影も色濃く刻まれる。その濃さこそが、人の心の闇である。闇の生じるところは、ホラーの要素が好んで住まう場所でもある。
宗教は多種多様だ。教義もそれぞれ違えば、神や教祖にもいろいろな種類がある。本作の中でもいくつかの宗教がミスター・リードから言及される。饒舌なミスター・リードの高説を聞くのは二人のモルモン教の宣教師だ。 二人をにこやかに迎えながら、やがてモルモン教について揶揄し、当てこすりを始めるミスター・リード。
モルモン教の宣教師は、二人一組で自転車に乗り、歩いている私たちを呼び止めて宣教に勤しむ。その姿が本作にも描かれている。 わが国でもその活動の様子はかつてはよく見られた。今でもたまに教会というか、集会所は見かけるので、宗教としては健在のようだ。 私もかつてモルモン教の宣教師に呼び止められ、宣教されたことがある。それも何回も。
私も含めた大多数の日本人は、宣教師を避けるべき対象とみなしている。宗教勧誘に対してアレルギー反応が生じており、さまざまな宗教の勧誘に眉唾で臨むような態度が板についている。オウム真理教の一連の事件によってその態度に拍車がかかった。 私も大学時代、何度もさまざまな宗教から勧誘を受けた。モルモン教に呼び止められたのも、オウム真理教がサリン事件を起こした後だったように記憶している。
何度も勧誘を受けたことで、私の中に培われた宗教観は、信教は個人の自由だが、それは個人の心の中にとどまるべきというものだ。組織としての勧誘は宗教の本来のあり方と違うとさえ考えている。 若い頃に経験した幾度もの勧誘と、その後の社会人生活で育まれた組織への拒否感が、上のような宗教勧誘への対処として私の中に刷り込まれている。 私自身にとって、宗教とは哲学と同じような存在である。生き方の知恵を得るために学ぶ点は多い。だが、哲学は組織化しない。また、哲学者は自分の考えを人に強制しない。
ところが、教団はちがう。迷える子羊である教徒の信心を教化し、神の名の下に教団の一員として取り込む活動が教団の存在意義の一つだ。 ところが、教化という言葉には上から目線が透けて見える。まだ神の教えに触れていない無信心者に神の恩寵を与え、神の恵みを知らぬかわいそうな人を導いてあげなければ。 本来、宗教とは自分の中から湧き出たものであるはず。そうした考えを持つ仲間が自然に集まるのならまだわかる。だが、ある時点から、教団の目的が組織の維持のために変質していく。 その目的のために信教を言葉巧みに勧めるのが宣教だとしたら、私は抵抗する。
その対立軸で考えると、本作のシスターBとシスターPに対するミスター・リードの立場に私は近い。
もちろん、本作のミスター・リードは、ホラーを体現する悪役だ。 彼の本性が明らかになっていくにつれ、私の考えと乖離していく。
本作が面白いのは、本来なら宣教される側のミスター・リードが、逆に宣教師を罠にはめる点にある。
だが、彼の弄するあらゆる策略は、どんどん化けの皮が剥がれていく。 シスターBとシスターPがミスター・リードを怪しみ、それでもなおミスター・リードの策略に乗せられて地下へと誘導されるあたりの掛け合いが見事だ。
本作はホラー・サスペンスと銘打たれているが、この心理戦にこそ見どころがあると思う。 本作でミスター・リードを演じたヒュー・グラントは、ゴールデングローブ賞をはじめとした複数の主演男優賞にノミネートされた。
それもそのはず。二人を罠にかけようとする饒舌の中に、単なる知識の奔流だけにとどまらないたくさんのユーモラスな点があり、これが本作を面白くしている。単なる怖さだけでなく、そこはかとないユーモアを滲み出させた点が評価されたのだろう。 具体的には、モノポリーを例に挙げ、世の中の宗教とは、模倣と剽窃の繰り返しだと指摘するセリフがある。あるミュージシャンが曲をパクリ、さらにそのミュージシャンも別のミュージシャンに曲を真似される歴史がある。さまざまなファストフードを挙げさせ、宗教のファストフードを目指すといった意見表明がある。 こうした独特の宗教観は本作の面白さであり、ヒュー・グラントがそれを饒舌に演じる中、単なる組織の羅列だけでなく、その怪しさやボロが見え隠れすることによってますますその面白さが際立ったと言えよう。
もちろん、それだけではとどまらない。本作が終盤を迎えるにつれ、ミスター・リードの本性が徐々に明らかとなる。BGMも大仰になって怖さは増す。本作が宗教を取り入れた一番の恐ろしさとは、宗教の本質を暴く点にある。 これは、世の中の宗教関係者には、到底受け入れられない結論であり、実際、モルモン教から本作に対して抗議が表明されたそうだ。 だが、私にとっては、この本質こそ、先ほど書いたように、宗教のある種の真理であると思う。宗教よりも「教団のあり方」と言い換えた方が良いだろうか。 支配。 それこそが、教団や宗教のある種の側面であることは否定できない。
だが、それにも増して恐ろしいのは、人の心のあり方である。ミスター・リードの中で誰にも知られぬうちに培われた宗教観は、教団によるものではなく、あくまでも彼一人の中で育まれた考えである。 これは、先ほど書いた組織化された宗教こそが恐ろしいという仮説とは相反する。個人の中で煮詰まっていった宗教観は、誰にも止められない。この人間心理の恐ろしさ。
結局、本作が醸し出す恐ろしさとは、宗教に依存し、頼ってしまい、それを利用する人の心の恐ろしさに尽きるのだろう。
‘2025/5/11 イオンシネマ新百合ヶ丘


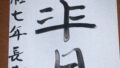
コメント