
諏訪の国とは、これほどまでに日本人の深層に訴えかけるのか、と考えさせられた。それが本作を見終わった感想だ。
今回、友人と共に観劇した。
この友人とは10年ほど前から諏訪大社やミシャグチを祀った神社、遺跡、洩矢神長官資料館や、諏訪湖周辺の山城、温泉などを何度も旅している。
その経緯もあって、私が諏訪大社関係のことであれば興味あると思い、誘ってくれたようだ。
本作は民俗学に題材を採ったドキュメンタリー形式の映像作品である。
私にとってそこまで見る機会がない形式であったためか、本稿を書くにあたって考えをまとめながら書いた。
諏訪はとても面白く、そして深い。一筋縄ではくくれない場所である。
中心に諏訪湖を擁し、城や山、そして温泉でにぎわっている。冬はスキーやリゾートが可能であり、中央道の諏訪湖サービスエリアからは、風光明媚な景色が堪能できる。
が、諏訪はそうした形式や一過性の体験だけではとらえ切れない魅力がある。その中心にあるのが上社と下社に分かれた諏訪大社である。神の御業を具現化したようなお御渡りがあり、湖の周辺には上社前宮と上社本宮、下社春宮と下社秋宮といった四つの大きな社が鎮座している。
表向きは観光地の顔をしながら、裏側には深く広大な精神世界が湛えられているのが諏訪である。
古代からさまざまな信仰が年月を経て何重にも積み重なり、混じり合っている。古代史や民俗学者にとっても諏訪の歴史や民俗、信仰や文化は理解しづらく、それが碩学を魅了してやまない。
また、日本史上でも諏訪地域は合戦をはじめとした数々の出来事の舞台になっている。古代から現在まで、史実と伝承が積み重なるこの地は興味が尽きない。
友人たちと何度も訪れる中、この地について惹かれている自分がいる。
本作の表向きのテーマは、諏訪大社の神事を今に再現することである。
ただ、あくまでもそれは表向きのテーマである。底には違うテーマが流れている。
私が受け止めた底のテーマとは、諏訪大社や諏訪の暮らしや日々を通じて、人の営みを見つめ直すこと。
まず、表のテーマから取り上げてみる。本作は一体諏訪の何を描いているのだろうか。
まず、表向きは、諏訪神社の歴史に埋もれた神事を現代に蘇らせるいきさつが描かれる。
古代中世芸能の専門家に協力を仰ぎ、さらに途絶えた伝承を神仏の垣根を越えて探求していく様子が描かれる。
諏訪地域は度重なる戦乱もあり、また、つい先年には、大祝一族の末裔が断絶したばかりである。途切れてしまった神事や伝承は多い。地元の諏訪地域文化・信仰の研究会スワニミズムの有志を集め、小学生高学年の少年たちにも神使(おこう)として登場してもらい、神事再現の試みが描かれる。その中で、地元諏訪の様々な風景や習わしや出来事が描写されていく。
そうした表のテーマが描かれながら、随所に挟まれる映像が、徐々に底のテーマを私たち観客に提示していく。それらは何気ない諏訪の日常の中から徐々にあぶり出されてくる。
それは古来から数限りなく受け継がれてきた人や生命の営みの尊さである。
鹿たちが森の中を自由に駆け回るシーンが描かれるかと思えば、鹿が猟によって仕留められる銃声が響く。諏訪大社の神事では鹿の頭部が数十個並べられ、神事にそぐわない生臭さがむき出しとなる。
また、稲が発芽して生育する様子を超高速で再現した描写が挟まれる。そして、諏訪で稲作農家を営む方の農作業の様子がつぶさに描かれる。また、地元の大木を祭る人々の拝礼の様子なども描かれる。
そうした狩猟と神事。農作と神事の何気ない描写がコラージュのように次々と現れる。
こうした描写から感じられるのは、地に足のついた暮らしの確かさだ。
一方、昨今は人の暮らしや営みがAIによって徐々に侵食されつつある。そうした時代の流れに対し、人の営みの意味に再び焦点を当て、人間としての原点に着目しよう。それが監督の狙いではないかと考えた。
本作には、デジタルやITを伺わせるものが一切登場しない。あえて言うと、蛇のミシャグチ様を表現するシーンにアニメーションが使われていることと、かつて唱導されていたという「諏訪講之式」を諏訪大社で読経するにあたり、僧侶たちが曲節をつけて復活させる取り組みの中で、音律を探り当てる助けに電子鍵盤が登場しているシーンぐらいだろうか。
それ以外はデジタルを思わせるシーンが出てこない。つまり、人の暮らしとは突き詰めていくとITとは無縁であることを示したいと受け取った。 都市化によってサービス業が盛んになり、人間の関係を円滑に進めるためにデジタル技術が幅を利かせる今。
だが、本来ならばそれらは社会の必要として求められた技術であり、自然と一体となって暮らす人々にとっては、デジタルは必要ない。
まずは、デジタルの影響を排し、人の暮らしの本質を求めようとしたのが本作ではないかと感じた。
私はITによる業務改善を生業としている。その視点からやるべきことは多い。
また、AIが劇的に進化し、人の暮らしとは関係のないレベルで業務最適化を進めていく進化も見ている。
だからこそ、これからはかえって人の暮らしのあり方が重要となっていく未来が予測できる。
つまり、社会生活で求められる手続きはAIなどが根本的に変え、省力化されていく未来だ。
一方で、人の暮らしの本質は、AIやITの影響とは乖離し、原点に回帰するのではないか。その二極化が進んでいくのではないか。
そう考えると、ここらで人の暮らしや営みのあり方を見つめ直し、自然と一体化した暮らしを志向する人も増えていくはずだ。
それこそが本作に込められた底のメッセージである気がする。
上映が終わった直後、監督の弘理子さんが壇上で我々に向けてコメントを述べてくださった。
その中で、この映画の撮影の意図を観客に伝えてくださった。
「鹿なくてハ御神事ハすべからず」
その言葉が古人からの警句として残されている。
なぜ鹿なのか。
という疑問を持った監督自身が考えている概要を示してくださった。
それは、鹿が生命の循環を象徴する存在だからではないかとおっしゃっておられた。
鹿の角は、冬になれば自然と取れ、また春になってくると生え変わって来る。メスは子を孕(はら)み、生命の営みとして繁殖活動のサイクルが続く。こうしたサイクルは、他の動物では人間の目には見えにくい。
その循環は人の暮らしに欠かせない。農業とは一年の中で種まきから植え付け、収穫の後は凍りつく田として次のサイクルへとつなげる営みである。その循環こそが人の暮らしを支える根本原理であり、人の営みとはその繰り返しに尽きる。
そうした循環の象徴として、角が生え変わる鹿が貴ばれたのであろう。
それが監督の考えだ。
私もその考えに同意するし、作中でも繰り返し鹿の生の営みが見事な映像で描かれていたことで、観劇中でもその意図は感じていた。
上に書いた通り、今の世の中はAIを代表するデジタル技術が幅を利かせている。そのため、そうした循環の考えが人の営みから感じられにくくなりつつある。死が生の現場から遠ざけられ、私たちが何に支えられて日々を営んでいるのかすら見えにくくなっている。
それを75頭の鹿の首を奉納することによって、自然に生かされた人の摂理を確認し、神に感謝することが諏訪大社の神事の本質でもあるのだろう。
私たちが人間であり、生物である以上、生命循環の摂理は変えられない。
遠い未来に技術の進化がそれらを制御できるようになるのかもしれないが、そうなった時、おそらく人類や私たちの暮らしはまったく違ったものになっていることだろう。
また、生死を含めた人としての在り方を追求する考えも見直される日が来るに違いない。
私達はそれをどう扱うのか。そして、我々はどこに向かおうとしているのか。
本作は未来の私たちに向けて、どう生きるべきかの問題提起になっていると思う。
最後に個人的な話を書く。
弊社は一昨年から京都のジビエを扱う会社様と取引がある。
また昨年あたりから、妻が別会社を通して山梨の甲州印伝を製作する会社様と取引を始めようと調整している。
そんな中、先日も釧路でジビエを研究する方とご縁ができた。その方は駆除が必要となった鹿肉の利用方法を模索している。
私自身、ジビエや鹿との関わり方について考えることが増えている。
また、弊社は某農協に対して何年にもわたって業務改善で協力している。つまり、仕事上で農業との関わりも増えてきている。
さらに甲府に妻が別会社で拠点を設け、私も山梨に訪問する頻度が増えている。春からは山梨で案件も始まる予定だ。
そうした私自身の環境の変化も鑑み、私自身、無邪気にデジタル技術を礼賛するだけでなく、自然との関わり方についても否応なしに意識する場面が増えてきた。
果たして人はどこまでデジタル技術に依存するべきなのか。
この先、デジタルに依存すべき範囲はどこまでで留めるべきなのか。人間としての本分や生活を守るべき臨界点はどこにあるのか。それらを見極めるためにも本作は良いヒントとなった。
劇場を出た後、監督がサイン会をして下さっていた。
その時点で私はガイドブックを買っておらず、一緒に行った友人はサインをしていただいていた。私はその直後に売店でガイドブックを買い求め、本稿を著すにあたり、一カ月たってようやくガイドブックを読んだ。その中には諏訪の文化や信仰、本作の背景についてより詳しいことが載っている。
本作を観劇し、本稿を著したことによって、諏訪にまた訪れたくなった。
私自身、最近は忙しさのあまり、諏訪にあまり行けていない。そろそろ自分の次のライフステージを見据えて動かねばならない。
また、諏訪に訪れた後に本作を観返したいと思う。
‘2025/3/1 横浜シネマリン

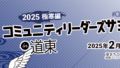

コメント
建御名方命と先住の洩矢神との間に確執があった」ことは、伝説としてよく知られています。そのため、「優位に立った建御名方命が洩矢神の血を引く千鹿頭神を追い出し、代わりに息子の内県神を据えた」という説が成り立つことから、千鹿頭神が妻の故郷のある松本のウラコ山に引っ越した先に松本千鹿頭神社が存在することを知り、行ってみたいと思ってます。
映画「信虎」を観て新作のイメージは固まったものの、なかなか筆が進みませんでしたが、最近になって、東出雲王家富家の伝承から、建御名方の父親が事代主であること、伊賀服部(麻績)氏の末裔の方のサイトから勝頼の母方の祖母が忍者の家系であるばかりでなく、ミシャグチよりも古層の頭である天白神に奉仕する氏族であること、忍者の組織のルーツが山窩であることなど次々に新しい発見がありました。
映画「鹿の国」は、小説の新たなステージへの良いきっかけになりました。諏訪や茅野にも行きたいところが山ほどありますので、お付き合いしていただければ嬉しいです。そもそも小説を書こうと思ったのは、長井さんが見つけた桑原城跡の看板から始まっているのも、何かのご縁と感じています。
おお!
それはまた諏訪や茅野へご一緒しましょう!
私もまたいかねばと思っています!
まずはこの度は映画のことを教えてくださってありがとうございました!