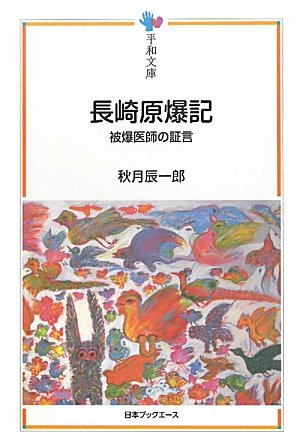
夏真っ盛りの時期に戦争や昭和について書かれた本を読む。それが私の恒例行事だ。今まで、さまざまな戦争や歴史に関する本を読んできた。被爆体験も含めて。戦争の悲惨さを反省するのに、被爆体験は欠かせない。何人もの体験が編まれ、そして出版されてきた。それらには被爆のさまざまな実相が告発されている。私は、まだそのうちのほとんどを読んでいない。
被爆体験とは、その瞬間の生々しい記憶を言葉に乗せる作業だ。酸鼻をきわめる街の地獄をどうやって言葉として絞り出すか。被爆者にとってつらい作業だと思う。だが、実際の映像が残っていない以上、後世の私たちは被爆体験から悲惨さを感じ取り、肝に刻むしかない。特に、戦争とは何たるかを知らない私たち戦後の世代にとっては、被爆された方々が身を削るようにして文章で残してくださった被爆の悲惨さを真摯に受け止める必要がある。ビジュアルの資料に慣れてしまった私たちは、文章から被爆の悲惨さを読み解かなければならない。熱風や放射線が人間の尊厳をどのように奪ったか。人が一瞬で変わり果てるにはどこまでの力が必要なのか。
著者は長崎で被爆し、医師として救護活動を行った。著者と同じように長崎の原爆で被爆し、救護活動に奔走した人物としては永井隆博士が有名だ。永井隆博士は有名であり、さらにクリスチャンであるが故に、発言も一般的な被爆者の感情からは超越し、それが逆に誤解を招いているきらいがある。さらに、クリスチャンとして正しくあらねばならないとのくびきが、永井博士の言葉から生々しい人間の感情を締め出したことも考慮せねばなるまい。
それに比べ、著者は被爆者であり医師でもあるが、クリスチャンではない。仏教徒であり、殉じる使命はない。本書での著者の書きっぷりからは、人間的で生々しい思いが見え隠れする。それが本書に被爆のリアルな現場の様子が感じられる理由だろう。そもそも、人類が体験しうる経験を超越した被爆の現実を前にして、聖人であり続けられる人など、そうそういない。おおかたの人々は、著者のように人間の限界に苦しみながら対応するに違いない。不条理な運命の中、精一杯のことをし、全てが日常から外れた現実に苛立ち、悪態もつく。それが実際のところだ。
本書を読んでいると、何も情報がない中で、限られた人員と乏しい物資を総動員し、医療活動に当たった著者の苦労が読み取れる。著者は、被爆者でありながら、一瞬で筆舌に尽くしがたい苦しみに置かれた人々を救う役目を背負わされた。その苦労は並大抵ではなく、むしろ愚痴の一つも言わない方がおかしい。著者が本書の中で本音を吐露すればするほど、本書の信ぴょう性は増す。いくら救いを求める患者が列をなしていようとも、三日三晩、不眠不休で診療し続けるには無理があるのだ。
長崎に玉音放送が流れようとも、著者の浦上第一病院に患者の列は絶えない。それどころか医療の経験からも不思議な症状が著者を悩ませる。放射能が原因の原爆症だ。著者は秋月式治療法と称し、食塩ミネラルの摂取を励行する。玄米とみそ汁。これは著者の独自の考えらしく、著者はその正しさに信念を持っていたようだ。永井博士も他の博士も、他の療法を考え、広めた。だが、著者は食塩ミネラル療法を愚直に信じ、実践する。特筆すべきは、糖が大敵という考えだ。ナガサキの地獄から70数年たった今、糖質オフという言葉が脚光をあびている。その考えに立つと、著者の考えにも一理あるどころか、むしろ先進的であったのかもしれない。
また、本書にはもう一点、興味深い描写がある。それは九月二日から三日にかけての雨と、その後の枕崎台風が放射能を洗い流したという下りだ。雨上がりの翌日の気分の爽やかさを、著者は万感の思いで書いている。著者が被爆し、それ以降医療活動を続けた浦上といえば爆心地。原爆がまき散らした放射能が最も立ち込めていたことだろう。著者の筆致でも放射能にさらされる疲労が限界に来ていた、という。私たちがヒロシマ・ナガサキの歴史を学ぶとき、直後に街を襲った枕崎台風が、被爆地をさらに痛めつけたという印象を受けやすい。だが、著者はこの台風を神風、とまでいう。それもまた、惨事を体験した方だからこそ書ける事実なのかもしれない。
本書には永井博士が登場する。そこで著者は、永井博士の直弟子であったこと、永井博士とは人生観に埋められない部分があることを告白する。
「私の仏教的人生観、浄土真宗の人生観、親鸞の人生観は、どこか私を虚無的・否定的な人格に形づくっているようだった。
永井先生の外向的なカトリック的人類愛と、私の内向的な仏教的人生観は、あまり合わなかったのである。
私は、ただ結核医として、放射線医学を勉強した。むしろ、永井先生の詩情と人類愛、隣人愛を白眼視する傾向さえあった。」(185-186ページ)
ナガサキを語るとき、永井博士の存在は欠かせない。そして、ナガサキを語る時、キリスト教が深く根付いた歴史の事情も忘れてはならない。それらが永井博士に対する評価を複雑なものにしていることはたしかだ。果たして原爆はクリスチャンにとって神の試練だったのか。他の宗徒にとっては断じて否、のはず。宗教を介した考え方の違いに限らず、被爆者の間でも立場が違うと誤解や諍いが生ずる。その内幕は、被爆体験の数々や、「はだしのゲン」でも描かれてきた。本書にもそうした被害者の間に生じた軋轢が描かれている。それが、本書に被爆体験だけでない複雑なアヤを与えている。
昭和25年当時の推計でも、死者と重軽症者を合わせて15万人弱もの人が被爆したナガサキ。それだけの被爆者がいれば、体験を通して得た思いや考えも人それぞれのはず。人々の考え方や信仰の差をあげつらうより、一瞬の間にそれだけ多くの人々に対して惨劇を強いた原爆の、人道に外れた本質を問い続けなければならない。本書を読むことで、私のその思いはさらに強まった。
‘2018/08/17-2018/08/17
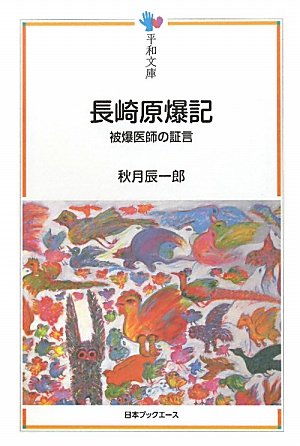


コメント