
一巻で逮捕された弓成記者。数週間の拘留を経た後に釈放される。一方、三木秘書はより長く拘留され、情報漏洩の罪が自分にあると全面的に供述する。そんな三木秘書に対し、弓成記者は一貫して罪を認めぬように、と強く伝える。しかし、拘留されたことが三木秘書には堪えたのか、もはや取り調べに抗うことすらしない。
なぜ、弓成記者が三木秘書に対してそんなことを言えるのか。西山事件を知らない読者は怪訝に思うだろう。それは、西山事件が、単に取材権の行使の自由を求めた事件ではないからだ。西山事件とは記者が秘書と肉体関係を結び、その関係を利用して情報を提供してもらったことが取材権の濫用にあたるとして非難された側面ももっている。
一巻ではほのめかされるだけで明確に書かれなかった二人の肉体関係が本書で明かされる。なぜ一巻では明かされなかったのか。一巻のレビューにも書いた通り、私にはわからない。小説的になにか顕著な効果があったとは思えない。だが想像するに、一巻の内容は取材の自由と政治の秘匿権のせめぎあいをより強調したかったのではないか。そこに著者の狙いがあったため、余計な関係を含めると対立関係が見えにくくなる。そのため肉体関係が描かれなかったのだと思う。
第二巻では、全マスコミによる弓成記者の擁護キャンペーンが張られる。マスコミにとっては取材の自由が危うくなった訳だから当然だ。しかし、三木秘書の告白によって肉体関係という俗な要素が白日の下にさらけだされてしまった。その報道を境として一転、弓成記者の境遇に逆風が吹くことになる。
本書の登場人物は、一巻のような政財界の華やかな人々はあまり出ず、逆風に翻弄される弓成記者と妻由美子、そして裁判にあたった弁護陣が主となる。
特に、弓成記者の妻由美子の厳しい日々が描かれる。夫に浮気された事実もさることながら、社会からの批難の声は厳しい。周囲からは離婚を勧められもする。しかし由美子は離婚を選ばず気丈に耐え抜く。
第四巻の巻末に取材協力者の氏名が列挙されている。その中の一人に西山記者の奥さまの名も見える。おそらく、本書で書かれた出来事の多くは妻から見た事実だったに違いない。
本書で描かれるのは、裁判準備と公判の様子が大半だ。弁護側は取材の自由や密約の違法性を論点とするが、検察は情報の入手過程に犯罪を構成する要素があると主張する。報道機関と政府による対立はあるが、その軸は双方で全くずれている。報道側は取材権の自由と政府による秘匿に。検察側は取材権の濫用と適正な取材のありかたに。
なぜ政府はここまで弓成記者の密約リークを目の敵にするのか。著者はその理由に密約のリークが沖縄返還の華やかなムードに水をさしたためだという。佐橋長期政権にとって沖縄返還は花道となるべき最後の事業。佐橋首相自身にとっても、平和裏に沖縄返還を実現したことでノーベル平和賞の候補に上がっていた。弓成記者のリークはそれら佐橋政権の花道に泥を塗る行為だった。そのため怒りを買った。おそらくは、そういう構図だったのだろう。いうまでもなく、佐橋首相、すなわち佐藤栄作首相は結果としてノーベル平和賞を受賞している。
本書では、権力の持つ腐臭が濃厚に漂う。そして弓成記者は、終わりなき謹慎の日々と法廷闘争の中で自分を見つめなおす。その時間は弓成記者に自らもまた、権力の腐臭に集まっては特ダネという褒美を漁る輩に過ぎなかったことを気づかせる。一巻では権力と報道機関の対立が描かれていたが、本書では筆調に変化が兆し始める。マスコミもまた政府の投ずるネタに群がる同じ穴の狢にすぎないのでは。そんな弓成記者の自省が浮かび上がる。だがそれは同時に弓成記者から生きがいを奪うことにもつながる。
取材する権利そのものは、優秀な弁護団が打ち出す訴えが効果を発揮し、判事に届き始める。しかしその成果がでればでるほど弓成記者から記者に復帰できる可能性は失われて行く。裁判の進展につれ、通常は権力に蹂躙された報道記者の権利は回復する。ところが一度取材行為に倫理上のケチが付けられた弓成記者を毎朝新聞は切り捨てにかかる。報道の在り方について、裁判の経過につれ、抜き差しならない危機が立ち上ってくる。
この辺りの展開のもっていきかたはうまいとしか言いようがない。
‘2016/10/05-2016/10/05


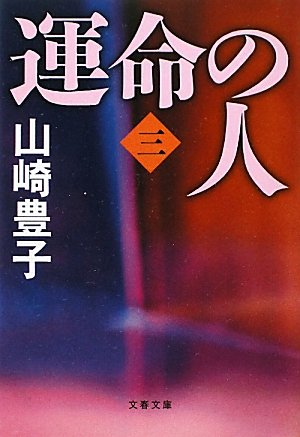
コメント