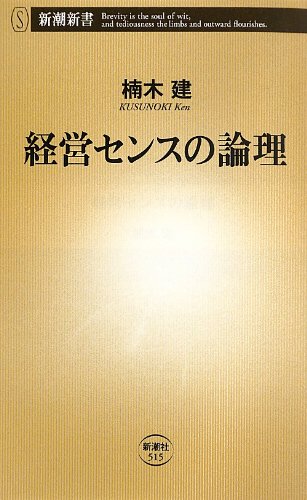
Cybozu社のイベントで何度か著者をお見かけした。そのイベントとは、Cybozu Days。その中にkintoneを活用したユーザーが事例発表を行うkintone hiveというコーナーがあり、著者はその審査委員長だ。
そんなわけで著者の名前は以前から知っていた。だが、著作を読むのは本書がはじめて。本書のタイトルが私を引きつける。経営センス。経営者の端くれにいる私に全く足りていない。
私は、自分に経営センスがあるとは思っていない。あればとっくに大勢の人を雇っている。私に経営センスがないのは、経営についての勉強を全くしていないからだ。全てが独学。ようやく法人化して四年目を迎え、さまざまな話をさまざまな方から伺い、自分なりに経営に試行錯誤してきた。
だからこそ、経営には「センス」と「スキル」があり、経営には両方とも必要なのだ、という著者の説には勇気づけられる。私の場合、圧倒的に足りないのは経営スキルであり、経営センスは多少なりとも身についているのでは、という勘違い。私に足りないのはむしろ経営センスではないだろうか。
財務諸表の読み方など、しょせんスキルの話だ。それらをいくら身につけてもそれだけでは優れた経営者とはいえない。せいぜいがスーパー担当者に過ぎない。そんな著者の言葉には頷けるところもあり、耳も痛い。私の場合は多分経営者ではなく、スーパー担当者に過ぎないのだろう。経営者でありながら、自分でプログラミングや設計やテストをこなしているうちは経営者とは言えない。
とはいえ、経営センスを身につけねばならないことは差し迫った課題だ。そもそも経営センスとは何なのか。で、どうやって身につけるのか。分かるはずがない。著者は「善し悪し」よりも「好き嫌い」で経営することが経営センスではないかという。そう聞くと、「好き嫌い」による経営は感情を論理より重んずる経営と同じ意味になり、あまりよろしくない気がする。ところが、センスある経営者をみていると好き嫌いで経営判断を下しているとしか思えないと著者はいう。確かに有名な経営者の言動、例えばスティーブ・ジョブズや松下幸之助の事績を見ると、論理よりも感情が見え隠れする。
経営者といえども人間だ。時間も有限にしか持たない。つまり、どこまでを自らの手で行い、どこまでを任せるのかについての線引きをきっちり行わねばならない。それがすなわち、本書でいうハンズオンとハンズオフの境界なのだろう。とくに、オフの線引きが重要なことは本書から読み取れる。私の場合もそう。コーディングはまだしも、テストまで手を染めることはやりたくないし、やってはならないと思っている。ところが、先日、某案件で私自身がテスターとなってしまった。忸怩たる思いに苛まれている。
著者は経営で重要なこととして「自由意志の原則」を挙げている。本来経営とは自由意志に基づくはず。ところが「⚪⚪せざるを得ない」という理由で経営の舵取りをする経営者がいかに多いか、と嘆く。これも耳が痛い。弊社の場合、さしずめ「人を増やさざるを得ない」「案件を請けざるを得ない」から経営しているといえよう。
第1章が、「経営者」の論理であるなら、第2章は、「戦略」の論理を取りあげている。ここで重要なのは、「連続性」と「非連続性」の観点だ。ここでいう連続性とはルーチン業務を指す。この連続性のラインに載っているかぎり、イノベーションは生まれない。同業他社から一歩抜け出すためには非連続性の中に踏み込まねばならない。著者がここで持ち出すのは、米国のサウスウエスト航空の事例だ。航空業界の中にありながら、あえてLLCという機軸を生み出す。そして業績を好転させる。一方で著者は、IT業界を技術革新の連続からなる非連続性の業界と解釈する。アマゾンは非連続性の中でユーザーの購買行動という連続性に着目し、業界のみならず、全産業の中でも巨人となった。新規の事業ではなく、従来からある事業の連続の中に商機を見いだしたからこそ、アマゾンはその地位を得た。
ちなみに著者は非連続性の業界の例としてIT業界をあげたが、連続性の部分もある。いわゆるSESだ。多重請負のもと、大手開発案件に技術者を派遣する業務だ。私も以前はこの業態の末端にいた。この業態には残念なことにイノベーションはない。私自身も未来を感じられずにいた。それなのに十年近くも在籍してしまった。それは私の後悔であると同時に、本書の記載に唯一疑問を抱いた点だ。
あと、この章では攻撃は最大の防御という戦略も描かれる。著者はご自身の頭髪を例に挙げ、ユーモアをたっぷり振りかけつつ戦略を語る。本書は全体的にこのような脱線が随所に挟まれ、心を和ませてくれる。「善し悪し」よりも「好き嫌い」で経営は語られるべき、を実践するかのように。
第3章は、「グローバル化」の論理だ。
この章にも重要な指摘がちりばめられている。そもそも著者は、グローバル化に当たっては、三つの壁があるという。それは英語の壁、多様性の壁、経営人材の希少の壁だ。それらはある意味では分かりやすい構造だ。しかし、著者の視点によると、この壁はかなりの誤解を生んでいるという。まず、英語の壁は英語の能力ではない。コミュニケーション能力の壁であること。多様性についても同じく誤解が生じている。それは、経営とはどこかで統合しなければならないことだ。各部門が好き勝手やっていたら会社は成り立たない。当然の指摘だと思う。「経営の優劣は多様性の多寡によってではなく、一義的には統合の質によって左右される」(119p)
三つ目に挙げられた経営人材の希少。経営人材とは、一章で挙げられた経営センスを持った人材を指す。スーパー担当者だけでは会社は回らない。センスを持った人材を育てなければならない。「非連続性を乗り越えていける経営人材の見極めは多くの日本企業にとって最重要課題である」(131p)
もちろん弊社にとっては、私自身が経営人材として舵取りをしていかねばならないわけで、肝に銘じねばならない。
第4章は「日本」の論理。ここも、日本にしがみつかざるを得ない(という自由意志を放棄したような)、弊社にとっては心強い内容に満ちている。いわゆる日本の終わりを予言する論調。それらの論調に反し、著者は日本の優位を説く。例えば日本が抱える問題で筆頭に挙がるのは少子高齢化だろう。だが、著者に言わせれば、それは逆を返せば問題が分かっていることと同じ。そして問題が事前に分かっていれば対策も採りやすい。一方、諸外国にも問題はある。日本と違い、諸外国の抱える問題は不確定の要因からなっている。たとえば宗教の対立、民族の対立などの問題はいつ何時どのように起こるか分からない。日本の場合はその問題が相対的に低いため優位な地位にあるというのが著者の分析だ。また、日本の企業は専業志向であるため、その分野では底力を発揮するというのも著者の見立てだ。諸外国の企業はポートフォリオ経営に特化し、採算が悪ければあっさりとその事業を売却する。日本でも大手の家電メーカーは、事業の切り売りをはじめているが、中堅どころの体力のあるメーカーは専業志向で頑張っていると著者はいう。
第5章は「よい会社」の論理。
この章で著者は、若者のブランド志向を指摘する。かつての私を思い返すと耳が痛い。顔から汗が噴き出る思いだ。就職活動の時、ろくに会社分析をせず、イメージだけで選んでいた私自身への痛烈な指摘が続く。私はこの時の経験から大企業への信仰がすっかりうせてしまった。今、零細企業の経営者として恥じるところはまったくない。ところが今の若者たちの多くはまだ企業をブランドイメージで捉えていると思う。消費者として眺めたときのイメージと、働く側で見据えたイメージの落差。先日もとある方としゃべっていたが、その方からはいわゆる大手企業にある官僚的な体質、社風について懇々と教えていただいた。
良い会社とは、いわゆる企業ランキングではわからない。そこで著者はGPTWインスティテュートによる働きがいのある会社ランキングを推奨する。このランキングは従来の指標とは一線を画し、働き甲斐に着目したランキングなのだそうだ。
第6章は「思考」の論理。
ここではもう少し経営センスのコアな部分に着目する。「抽象」と「具体」の往復。それこそが、地頭の良さを決めると著者はいう。その振れ幅の大きさこそが、行動や選択の幅や人間の器を大きくする。頭でっかちなだけでは駄目で、猪突猛進なだけでもだめ。両方が出来る人こそが器の大きい人物なのだろう。また、情報と注意をトレードオフするコツとして、巷に溢れる情報の渦の中で、どこまでを取捨選択すべきに帰ったについて、著者は語る。私の場合はSNSからの情報を絞ることにした。結局のところ、SNSから得られる情報量と時間の生産性を考えると、どうしても生産性は落ちる結論に達する。私はそう割りきってSNS投稿を行うように変えた。私の考えでは、自分のビジネスの広告効果より、生涯の収穫量に重点をおいている。
このように、本書はさまざまな視点から考えさせてくれる。
’2018-06/22-2018/06/30
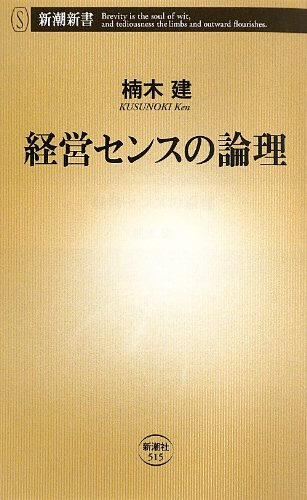


コメント