
本書は著者にとって絶筆となった作品だ。すでに病に体を蝕まれていた著者。本書は大手術の後、病み上がりの時期に書かれたという。そして本書を脱稿してすぐ、再度の発作で亡くなったという。そんな時期に発表された本書には回想の趣が強い。著者の人生を彩った出来事や体験の数々が、エッセイにも似た不思議な文章のあちこちで顔を出す。
著者の人生をさまざまに彩った出来事や体験。私たちは著者が著した膨大なエッセイから著者の体験を想像し、追っかける。だが、私たちには、著者が経験した体験は文章を通してしか伝わらない。体験とは、本人の記憶にしか残らないからだ。私たちはただ、文章からイメージを膨らませ、著者の体験を推測することしかできない。
著者の体験で有名なものは、釣り師としての冒険だろう。また、ベトナム戦争の前線に飛び込み、死を紙一重で逃れた経験もよく知られている。壽屋の社員として酒と食への造詣を養い、それを数々のエッセイとして発表したことも著者の名を高めた。そうした著者が過ごしてきた多方面の経験が本書には断片的に挟まれる。エッセイなのか、小説なのか判然としない、著者自身が主人公と思われる本書の中で。
著者は作家として名を成した。名を成したばかりか、己の生きた証しをエッセイや小説に刻み、後世に残すことができた。
ところが、本書からはそうした積み上げた名声や実績への誇らしさは微塵もない。むしろ、諦念やむなしさを感じるのは私だけだろうか。それは著者がすでに重い病を患っていたから、という状況にもよるのかもしれない。
本書に満ちているのは、人生そのものへの巨大な悲しみだ。著者ほどの体験を成した方であっても、死を目前にすると悲しみと絶望にくれる。なぜなら未来が残されていないから。全ては過去に属する。現在、病んでいる自分の肉体でさえも。本書からは未来が感じられない。全編に過去を追憶するしかない悲しみが漂っている。
死ぬ瞬間に走馬灯が、という月並みな言葉がある。未来がわずかしか残されていない時、人の心はそうした動きを示す。実際、未来が閉ざされたことを悟ると、人は何をして過ごすのだろう。多分、未来に楽しみがない場合、過去の記憶から楽しみを見いだすのではないか。それがストレスをためないために人の心が本能的に振舞う作用のような気がする。
著者は作家としての名声を持っている。だから、過去の記憶から楽しみを拾い上げる作業が文章に著す作業として置き換えることができた。おそらくは依頼されていた執筆の責任を果たしながら。
輝いていた過去の記憶を原稿に書きつけながら、著者は何を思っていたのだろうか。それを聞き出すことはもはやかなわぬ願いだが、これから死ぬ私としては、そのことが知りたい。かつて茅ケ崎市にある開高健記念館を訪れ、著者が使っていたままの状態で残された書斎を見たことがある。そこでみた空っぽの空間と本書に漂う悲しみのトーンは似通っている。私が死んだ後、絶対的な空虚が続くのだろうか。誰も知らない死後の無に恐れを抱くしかない。
本書は三編から成っている。それらに共通するのは、宝石がモチーフとなっていることだ。言うまでもなく、宝石は未来に残り続ける。人は有限だが、宝石は永遠。著者が宝石をモチーフとしたのもわかる気がする。まさに本書のタイトル「珠玉」である。病の悲しみに沈み、過去の思い出にすがるしかないからこそ、そうした日々を思い出しながら原稿に刻んでゆく営みは著者に救いをもたらしたのではないか。著者は自らの過去の体験が何物にも代えがたい珠玉だったのだ、と深く感じたに違いない。三編に登場する宝石のように。
「掌のなかの海」は、主人公が訪れたバーで知り合った船医との交流を描いた一編だ。世界の海や港の話に花を咲かせる。そこでは著者が培った旅の知識が縦横に披露される。そこで主人公が船医から託されたのがアクアマリン。船乗りにふさわしく青く光るその貴石には”文房清玩”という一人で楽しむための対象として紹介される。息子を亡くしたという船医が感情もあらわに寂しいと泣く姿は、著者の不安の表れに思える。
「玩物喪志」は、主人公が良く訪れる渋谷の裏道にある中華料理店の店主との物語だ。世界の珍味をあれこれと肴にして、食の奥深さを語り合う二人。その店主から受け取ったのがガーネット。深い赤が長方形のシェイプに閉じ込められた貴石だ。主人公の追想は今までの人生で見つめて紅や緋色に関するイメージであふれかえる。サイゴンでみた処刑の血の色、ワインのブドウから絞られた透き通る紅、はるばる海外のまで出かけてみた川を埋めるキング・サーモンの群れの紅。
追憶に満ちたこの一編は、著者の人生のエッセンスが詰め込まれているといえよう。ここに登場する店主の友人が無類のギャンブラーであることも、著者の思想の一端の表れに違いない。
「一滴の光」は、主人公が鉱物の店で手に入れたムーンストーンの白さから始まる。本編では新聞社に勤める記者の阿佐緒とのエロティックな性愛が描かれる。温泉につかり、山々を散策し、温泉宿で抱き合う。ムーンストーンの白さとは、エロスの象徴。著者の人生を通り過ぎて行った女性がどれだけいたのかは知らない。著者は家庭的にはあまり円満でなかったという。だからこうした関係にわが身の癒やしを得ていたのかもしれない。
三編のどこにも家庭の団欒を思わせる記述はない。そんな著者だが、本編には著者が生涯でたどり着いた女性についての感想を思わせる文が記されている。
(・・・女だったのか)(192P)
(女だった・・・)(193P)
後者は本書の締めの一文でもある。この一文を書き記した時、著者の胸中にはどのような思いが沸き上がっていたのだろうか。この一文が著者の絶筆であるとするならば、なおさら気になる。
‘2018/09/20-2018/09/22

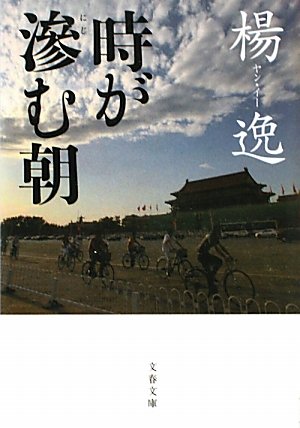

コメント