
著者の自在に変幻する叙述の技は、大勢いる推理作家のなかでも最高峰といってもよい存在だと思う。
くだけた口調の独り語りでスタートする本書。だが、その語りこそが曲者だ。それぞれの章ごとに鮮やかに視点が入れ替わってゆく。誰の視点で語られているのか常に追っておかねばならない。油断するとすぐ著者の仕掛けた罠に嵌ることになる。その技はお見事としか言いようがない。あまりにも切れ味の鋭いどんでん返しが次々と繰り出される。鮮やかにひっくり返されたあまり、そこで小説が終わったと勘違いしてしまうほどだ。特に前半のうちは、本書の全体ボリュームを知らずに読んでいたため、本書を中編小説だと勘違いしたほどだ。つまり小説が終わり、次の短編が続くのだ思わされたくらいに。そんな私の期待を裏切り、次のページからは何事もなかったかのように次の視点で本書の続きが紡がれてゆく。他の小説を読んでいてそう思わされた経験はあまりないが、本書では何回そうやって見事にしてやられたことか。著者の力量をあらためて思い知らされた思いだ。
本書では二人の中年男が主人公だ。芸能人とその付き人。彼らを中心として物語は進む。彼らの思いはスターにさせたいなりたいというスター志望と付き人志望のもの。彼らの思惑が入り乱れる。生き馬の目を抜くといわれる慌ただしい芸能界。よほど気の利いた売り込みを図らねばあっという間に埋もれて行ってしまう。そんな世界を頼りなく進んでいく中年男達はどこに進んでいくのか。本書の語りは世界観を再現するかのようにあくまでも軽快だ。芸能界の掟に生きる二人の男とその間にいる一人の女。三人の関係を語るには軽すぎるリズムで本書は進む。著者の語りは読者を惑わせ、結末を予測させない。したがってページを繰る手も止まらない。
芸名の名字がもう片方の本名の名字というややこしい関係。そのややこしい関係は言うまでもなく著者の仕掛けたトリックの一つだが、読者はよほど注意していないと誰の話しなのか分からなくなる。片方の男の話として読んでいたはずが、実は視点が反転していていつの間にもう片方についての話が進んでいた、ということもあるかもしれない。
誰が誰のために演技をし、誰が誰のためにマネージメントをするか。本書にあっては芸の肥やしとは演技の肥やしであり、演ずることと生きることの境界がぼやけ曖昧になってゆく。柔軟で枠にはまらぬ生き方が芸能界には求められるのかもしれないが、本書のそれはあまりにもトリッキーだ。
芸能界とはパフォーマーが脚光を浴びる場所。それゆえにスターの変幻自在な生き方を支える付き人にもトリッキーさが求められる。スターをいかにきらめかせ続けるか。細切れに時間が過ぎてゆく芸能界の中で、スターとは照らされる光をあまさず集め、観客へその光を反射させ続けなければならない。付き人に求められる能力とは、照らされる光の発信源を即座に捉え、その方向にスターを向かせること。つまり感度が人一倍高いことが求められる。大衆が求めるもの、つまり光の発信源を探す能力は一朝一夕には身につかない。それはもはや才能と呼んでよいかもしれない。せわしない芸能界にあってその能力を発揮し続けることは重責であり才能だ。あるいはその能力が付き人本人を芸能界で光り輝かせるほどに発揮されることだってあるはずだ。
だが、万が一失敗すると、もはや光を照らしてくれる相手はいない。光が照らされなくなったスターはもはや輝くことはない。それはスターと一心同体の付き人も同じ。光を喪ったスターと付き人は一市民として生きて行くしかない。そんな芸能界の移ろいやすさと次々に切り替わる人々の求めるスター像。本書では光と影が交錯する芸能界の現実も描かれる。
「お客さん、今の東京の夜空じゃもう一等星だって光らないですよ」
結末に近くなってタクシー運転手が発する台詞が象徴的だ。
‘2016/03/18-2016/03/22


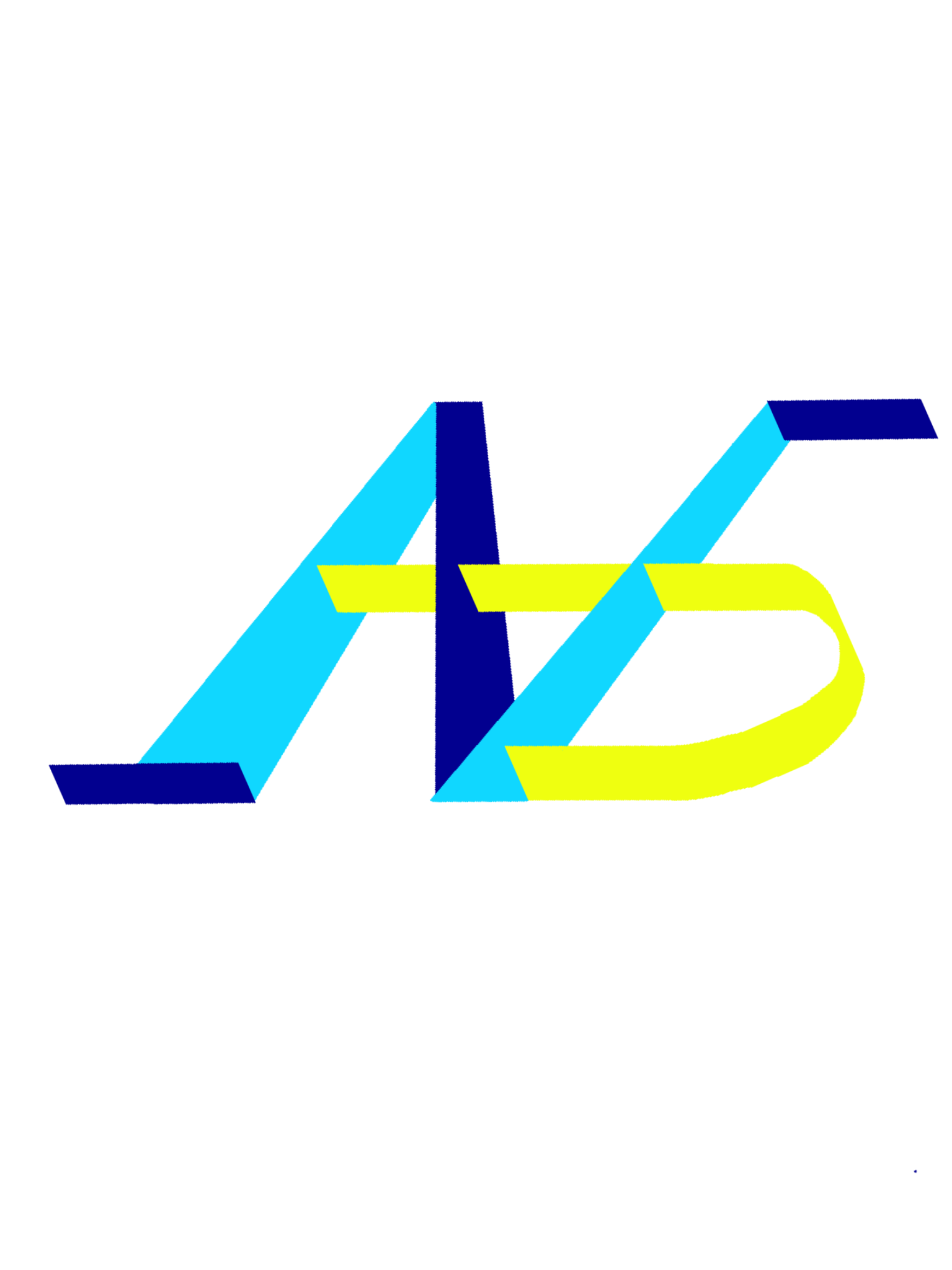
コメント