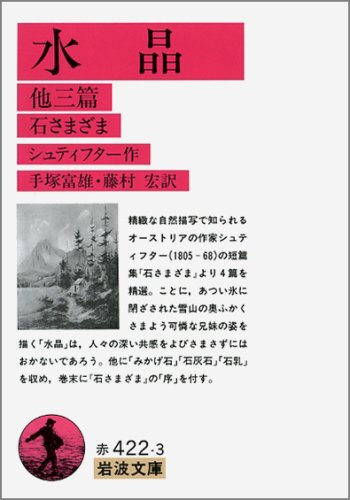
アーダルベルト・シュティフターという著者のことを、私は本書を読むまで知らずにいた。
著者は詩人や小説家としても名を残しているが、画家としてもよく知られているようだ。
19世紀の前半、1805-1868年を生きたこの作家は、当時オーストリアに属していたボヘミア地方に生を享けたという。
訳を担当した藤村宏氏が解説で記した内容によれば、当時のドイツ語圏の文学状況は過渡期にあったという。
ロマン派の芸術家たちが次々と世を去り、人々は現実に対して風刺をもって立ち向かう風潮が優勢になっていたという。
そうした中、ロマン主義の理想を守り続けようとした人々もいた。著者もまたその一人。
彼らの共通するのは、現実を素直に受け入れ、現実の中で与えられた人生をまっとうしようとする姿勢である。与えられた自然を賛美し、人生をあるがままに謳歌しようとする思いが作品にあふれ出ている。
そうした理想主義の色合いは、本書に収められた四編にも共通している。
私は四編のそれぞれから、古くからある教養主義の香りを嗅ぎ取った。
教養主義とは、人は学問によって導くことができるという立場を指す。要するに、人格は学問によって形成できるという考えだ。
その背景には人は本来、善の存在であるという性善説がある。本来、善である本性が学問によって開花するという前提だ。
私はもともと楽観的な考えの持ち主だと思う。
もちろん人は弱く流れやすい存在だ。
だが、それでも環境によって歪められない限り、大半の人間は善に違いないという考えで日々を過ごしている。
だから、私にとって本書の内容はとても心地よかった。
どれもが素朴であり、教訓を含みつつも、その根本には人の善が賛美されている。
本書は『石さまざま』という短編集に収めたられた六編の物語のうち、四編を収めているという。
原題が『石さまざま』というだけあり、各編は石をモチーフとしている。
「水晶」
山を越えた向こうの祖母のもとでクリスマス・イブを過ごした後、帰り道を歩んでいたはずの二人は、雪に降られてしまう。そして、雪に覆い隠された道を外れ、雪山に迷い込んでしまう。
二人が迷う山の姿はとても厳しい。けれども、厳しさの中に美しさがある。
水晶が露頭にその姿をのぞかせ、それが星明かりと雪に照らされた姿は、神々しくさえある。
幼い兄妹は雪明りに照らされ、持っていたコーヒーを啜り合いながら雪の中を眠らずに過ごす。
兄が妹を励ましながら、二人は冬の過酷な雪山を生き抜こうとする。
そのけなげな姿は、読みながら二人を応援したくなるほどだ。
そんな二人を支えるのは、今日がクリスマスイブであること。
普段、ふもとから見上げている冬の山が、一変して厳しい姿を見せる。その姿は本書では明らかに示されていないものの、父なる神の存在を思わせる。
自然に抱かれているはずの人は、自然を甘く見るとしっぺ返しを食う。
二人は頑張って朝まで眠らずに過ごし、ふもとから来た村の人々に救われる。
とても簡潔でありながら、山の描写の美しさと、けなげな二人の会話がとても深い余韻を誘う一編だ。
「みかげ石」
父の生家の前に置かれたサイコロのような四角い石。
本編は、この四角い石の来歴を語る。そして、人々の歴史がどのようにして伝えられていくかを教えてくれる。
車の差し油売りのいたずらにより、足に油を塗られてしまった若き日の主人公。母に足の油を見せたところ、家が汚れるからと叱られ、邪険に扱われてしまう。
そんな傷心の主人公のところに現れたおじいさんは、主人公を家に入れ、油を洗い落してくれる。
それをきっかけとして、おじいさんにかわいがってもらうようになった主人公は、おじいさんからこの地方に伝わる物語を教えてもらう。
おじいさんから教わったのは山の名前や生活の知恵だけではない。ペストがこの村や付近にたくさんの災厄を運んできた時の人々の工夫もそうだ。倒れているところを少年たちに救われ、ペストの災いから逃れることができた少女の物語もおじいさんによって語られた。
ペストといえば、一般的には14世紀にヨーロッパで猛威を奮ったパンデミックを連想する。だが、本書の時代はそれよりも大分下っているはずだ。
だが、14世紀の大流行の後も、数度にわたって局地的な発生があったというから、本書で伝わるペストもその一つなのだろう。
そして、ペストのような災厄を後世に伝えることができる人はもういない。
当時の事を後世に伝えられるのは、碑や書物や柵や施設だが、そうした物も長い年月のうちに忘れられ
、崩れてしまう。何も残らないのだ。こうしておじいさんが次の世代に語り伝えない限りは。
その象徴こそが、父の家の前のみかげ石なのだろう。
世の中には、本編のみかげ石のように路傍にありながら誰にも由来が知られていないものがどれだけあるだろう。
私が本編を読んですぐに思ったのが、東日本大震災の時に津波が到達した地点に古くから立てられていた石碑の存在だ。それらは過去の災害に遭った人々が、後世のために教訓として残しておいたものだったに違いない。他にも水害、土砂災害を後世に伝えるための地名が、近代化の名のもとに消えて行っているという。そうした現状が本編によって思い出された。
「石灰石」
本編は、測量士をやっている主人公と、主人公が仕事で訪れたある村で知り合った牧師の話だ。
牧師のつましい生活と禁欲的な生活に惹かれた主人公は、その地方での測量が長期にわたったため、牧師と親しくなる。ついには牧師に信頼されるようになった主人公は牧師から生い立ちを聞かされる。
牧師が語った生い立ちは、数奇なものであった。
曽祖父が起ち上げた革工業の家業を継いだ父が、牧師とその兄の二人を育てるにあたり、兄には跡継ぎとしての教育を施したこと。ところが、そうした実業には興味を示さなかった牧師には強制せず、牧師は興味の赴くままに学問に打ち込んだこと。
家業を継いだ兄は、商売の中で失敗し、家業を手放すことになった。そして兄は失意の中で亡くなり、自分は牧師としての仕事に進み、今ではつつましく暮らしていることなど。
本編は残念ながら、描写が冗長ですっきりまとまっているとはいえない。
だが、本書が言いたい教訓は明らかだ。
それは、自分の素質が向いている方向を見極め、その方向へと学んでいれば、何者にかは成れることだろう。そう、まさに教養小説のように。
そして牧師が残した遺言と遺産は、人々の善意を呼び起こす。
もう一つ、本編が語っているのは、人は生前でも、そして死後でさえも、社会のために何がしかの貢献が行うことで、必ず報われることだと思う。
「石乳」
本編は、オーストリアを舞台に戦われた戦闘が題材となっている。
その戦闘とは、ナポレオンが率いるフランスがヨーロッパ諸国を相手に仕掛けた一連の戦いの一つだろう。
フランス軍の斥候として村にやってきた兵士が村を接収する。
そして斥候の都合で村の人々に制限を掛ける。それに抵抗し、兵士を監禁しようとする大人たちに対し、子供たちが助けようとする姿が描かれる。
戦争が終わって数年し、兵士が村へとやってくる。そして、当時の非礼を村人に謝ろうとする。
その心根は人々の間を宥和の心で満たす。その結果、人々は幸せになる。そんな物語だ。
本編が説いているのは戦争の愚かさであることは言うまでもない。
もう一つは、戦争の現実は兵士を服従させ、その本性とは違う行動を強いてしまうことだろう。
だが本来、戦争中は服従の義務から戦争に手を染めるけれど、戦争がなくなれば人間性を取り戻し、幸せになれることだと思う。
‘2019/01/04-2019/01/12
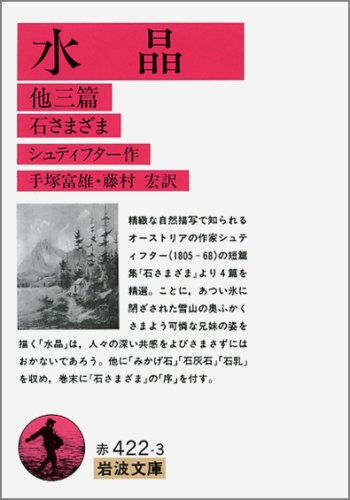
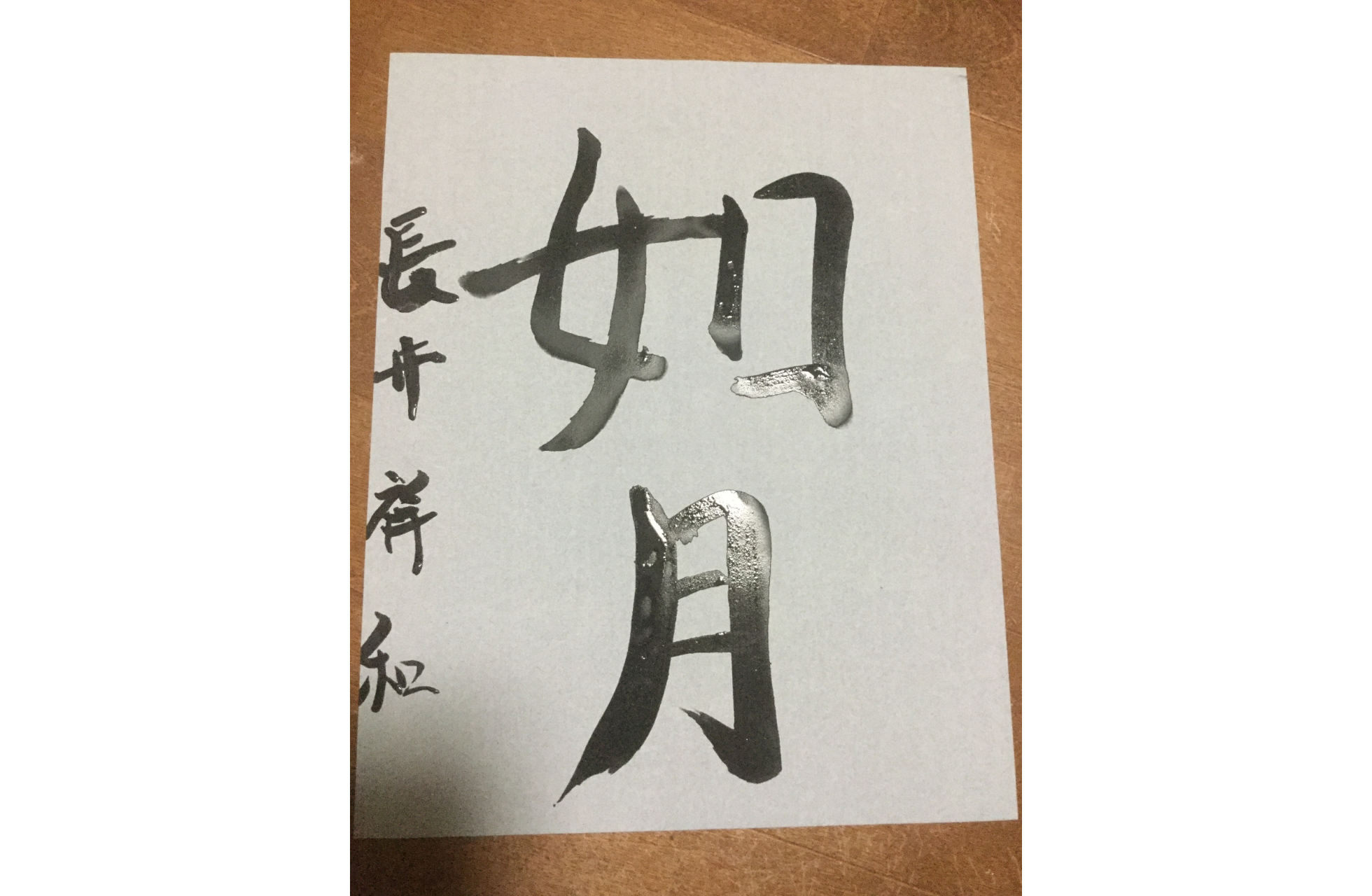

コメント