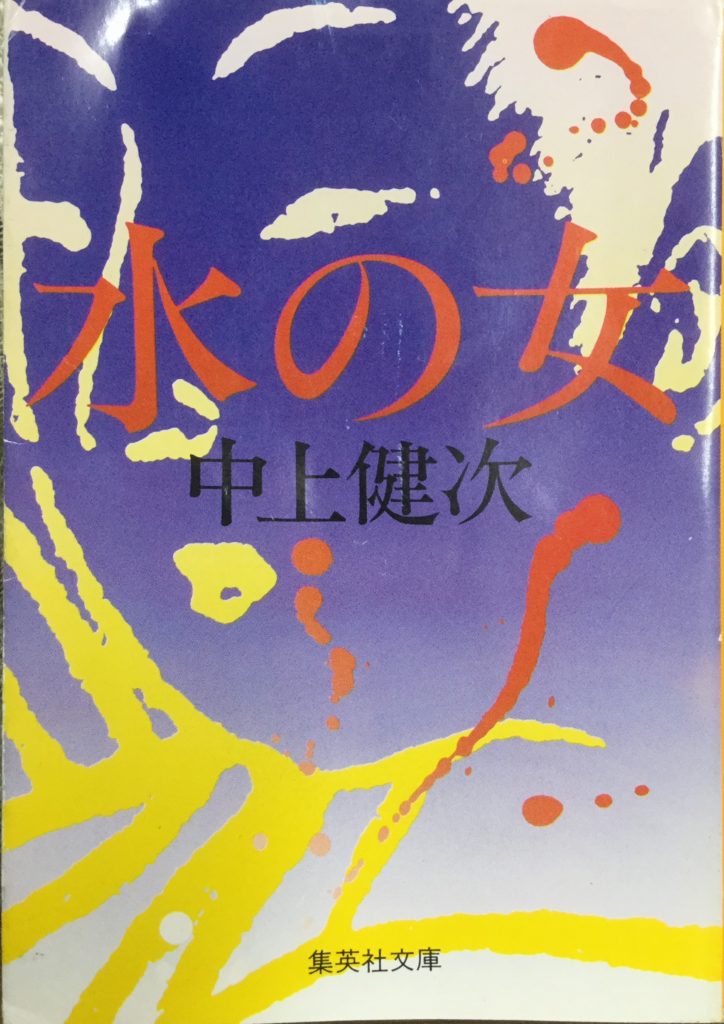
本書の著者である中上健次氏。その中上健次氏を取り上げたのが高山文彦氏の『エレクトラ』だ。中上健次氏の生い立ちから作家としてのデビュー、そして死ぬまでを濃密に描き切った傑作評伝だ。かつて私は、中上健次氏の『枯木灘』を読んだ。だが、それから20年以上、中上健次氏の作品を読むことはなかった。そんな私に『エレクトラ』は著者のすごさと深みをもう一度教えてくれた。(レビュー)
『エレクトラ』に触発され、久々に中上健次氏の作品を読んでみようと思った。だが、どれから手に取ればいいか全くわからない。古本屋に行っても中上健次氏の本は書棚で見かけない。『エレクトラ』の中で高山氏は、初期の重要な作品として『十九歳の地図』『火宅』『蛇淫』『岬』などを取り上げていた。私も本来、その順に読んでいきたかった。だが手に入らず、たまたまブックオフにあった本書を手に取った。
熊野。本州の南端にある交通の不便な地。そして著者が生まれ育った地。著者はそこを舞台に濃密な血縁と暴力、そして性を描いた。本書には全部で5編の物語が収録されている。5編とも熊野地方が舞台となっている。熊野は交通が不便であるため、開かれていない。閉じている。人と人の関係も。
5編に登場する男女も、閉じた熊野の地で限られた関係にからめ取られている。むしろ自ら進んでからめとられようとするかのようだ。男といることを当たり前のように考える女。女を常にそばにおきたがる男。そしてお互いが性で結びつきあい、依存しあっている。出口のない世界の中、愛欲と性の世界に浸っている男女。本書に流れているのはそうした世界観だ。
仕事がなければ、家に二人がいれば、四六時中、乳繰り合い、まぐあって性交にふける。他にやることがないのだろうか、と思いたくもなるほど2人の男女は始終セックスをしている。まるでそれが、2人を結びつける唯一の絆であるかのように。そこには、男が女に、女が男に対する優劣はない。むしろ、依存し、依存しあう男女の平等な関係が見えてくる。
相手に依存するためには、何かを差し出さなければならない。女にとってはそれが自分の体であり、男は自分の体で女を悦ばせる。相手を体で喜ばせることで、依存させてもらっている相手へ無意識に償っている。お互いが性を介して依存しあう。そんな関係が濃密にあらゆる角度で描かれる。
これが都会であればそうはならない。人と人との関係には違う何かが入り込んでくる。例えばビジネス。文化や享楽もある。それらが身の回りにあふれているので、誰かに依存しなくても生きてゆける。それが都会であり、現代の情報の氾濫だ。だが、本書が書かれた当時の熊野には文化や享楽は乏しく、ビジネスも規模が小さい。なので、人が依存する対象は男と女に絞られてゆく。そんな間柄にあって、何を媒介にするか。それは相手を喜ばせることだ。そのような暗黙の了解が男と女にできあがる。それがすなわち性。愛欲。
そんな閉じた関係が濃密に息づいているのが熊野。そして『エレクトラ』にも書かれていたとおり、著者は被差別部落の出身である。そういう土地柄であるため、そうした持ちつ持たれつの関係はさらに濃縮され、しがらみをさらに強固に縛ってゆく。
本書に出てくる5編はその関係性において大きく二つに分けられる。最初の「赫髪」「水の女」「かげろう」の男女はいずれも似たような関係だ。女には名がなく「女」として登場する。一方、男には名前が付けられている。これは男女の関係の重心が男性側にあることを示しているのだろう。男が支配し、女が支配される関係。
ところが「鷹を飼う家」「鬼」の女性にはそれぞれ「シノ」と「キヨ」という名前が付けられている。実際、「シノ」と「キヨ」は、男をあしらい、うまく利用するしたたかさを持つ女として描かれている。男に支配されるどころか、逆に利用するだけの強さをもつ女として。
だが、女たちのあり方に変化があるのに比べると、5編に出てくる男はどれも似たような武骨で不器用な性格の持ち主だ。ところが、あまり変わりばえしない男と違い、女は「女」であっても、登場人物によって個性が描き分けられている。例えば、自らの未来を考えず、ただ、男といる今を生きる女がいる。意思を放棄したようにただ男について行く主体性のない女がいる。自分の行き先に迷い、今の状態をいとう女がいる。かと思えば、男と夫婦となって子をなし、したたかにお互いを抜き差しならない関係に持ちこみながら、他の男にも母性を任せる「シノ」もいる。かと思えば、独立心を持ち、性にすら理由をつけ、自分の性に頼る理由に意味を持たせようとする「キヨ」もいる。
個性を持った女性がいる一方で、本書に出てくる男性がどれも似たように描かれているのは、著者が自分自身を投影したからだろうか。執拗に同じような男を描く。それは、著者が熊野を憎む度合いの強さであり、もしくは地縁に縛られたしがらみの重さの表れなのかもしれない。そして、女に依存しなければならなかった過去から逃れ、東京で小説家になった著者は、あえて過去の自分を投影させた男を執拗に描き、それによって、故郷から決別を図りたいかに思える。
そう考えてみると、著者が各編の女性に個性を与え、男性をステレオタイプに描いたのにも理由があるように思える。
また、著者は5編で男女の違いを際立たせる試みに挑んだのかもしれない。性とは、男女によって受け取り方が違う心理をつかみ取るために。
ただ単に相手を孕ませるため、子孫を作るための本能につき動かされている男性と、それを、生きるための手段であり、自分の中に生命を宿らせる母性から生まれた本能で性をとらえる女性。つまり女性の方がより確信を持ち、しかも性がもたらす結果を本能の奥底で予期しつつ性を受け止めているのかもしれない。
著者がそういう試みをしているのでは、と思うのは、本書の5編には血縁のややこしさがあまり出てこないからだ。あくまでも5編で描かれるのは縁あった男女が性という営みで結びあった姿だ。それは、血縁やしがらみと性を完全に分けようとした著者の意図から出ているのではないだろうか。都会では、男女は性で結びつく。だが、血縁と言う面では結びつきは弱い。それが、逆に有機的で多様な男女の関係を作り出している。都会での作家生活を通してそのことに気づいた著者が、短編として著したのが本書ではないだろうか。
ただ『エレクトラ』でも高山氏が歩いて感じた通り、著者が育った新宮の街は、かつてとは違っている。もう本書に描かれたような閉じた関係はそれほど見られないはずだ。著者は後年、再び熊野の地縁をもとめ、熊野を歩いてルポを著している。それもまた、このような濃密な男女の関係を探し求めていたのかもしれない。
本書の解説は映画「赫い髪の女」を監督した神代辰巳氏が担当している。この映画は本書の第一編「赫髪」を基にしているそうだ。そこで神代氏は「赫髪」では「女」と呼ばれた女性をモチーフに映画を撮ったが、第五編の「鬼」のキヨのしたたかで複雑な描かれ方も踏まえて、映画の脚本に取り入れたかったと言う意味のことを書いている。
本書の内容を基に神代氏はどのような映画に表現したのだろう。とても興味がある。全編がからみ合う日活ロマンポルノとはいえ、お互いを頼るしか生きていけない男女の性の機微を繊細に描いたとすれば、それは立派な映画だ。だが、神代氏が、女性の個性を他の編も踏まえて描くべきだったと反省しているとはいえ、「赫髪」から生まれた作品であるとの基準に考えれば傑作であるはず。機会があれば観てみよう。
‘2018/09/10-2018/09/16
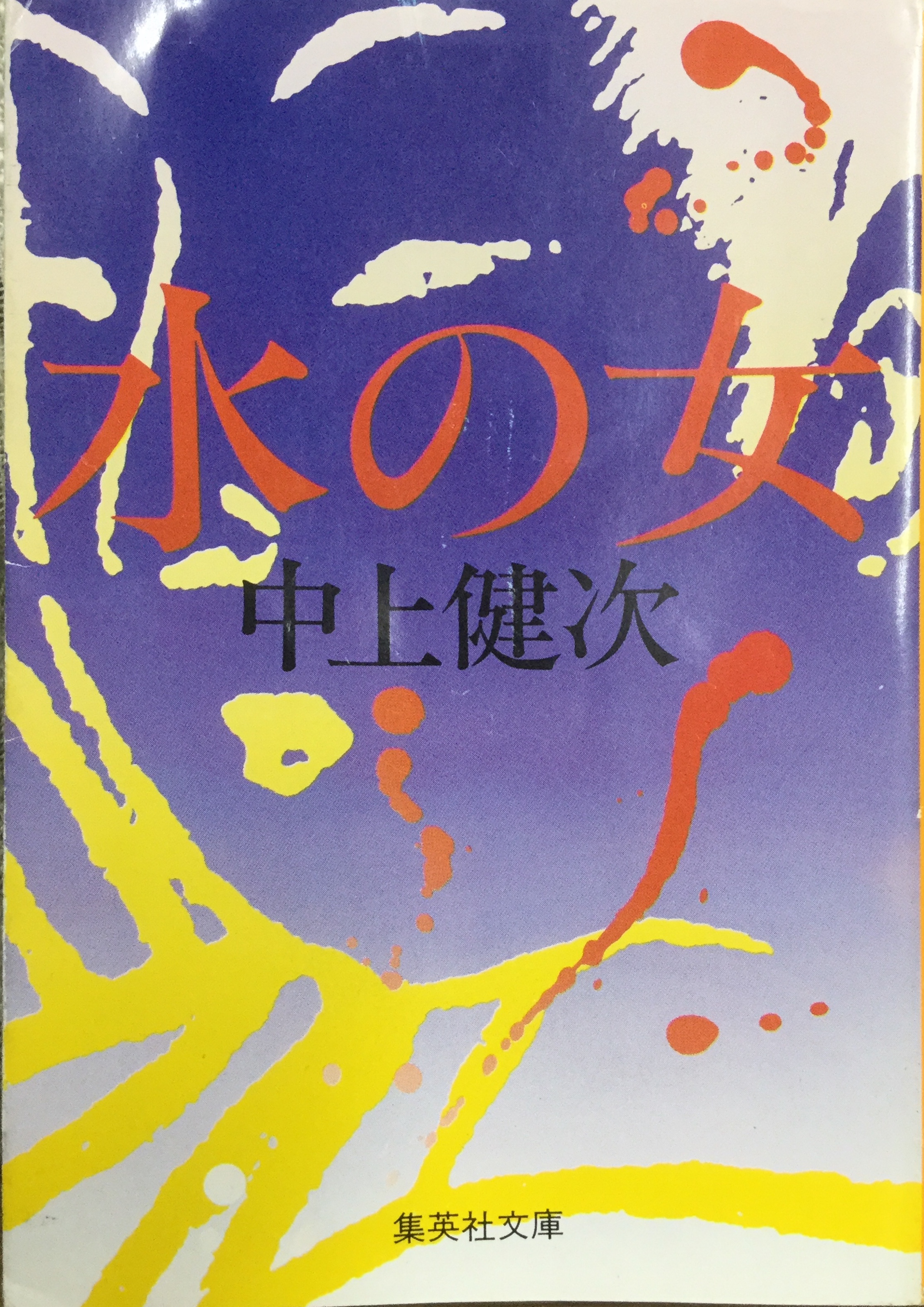
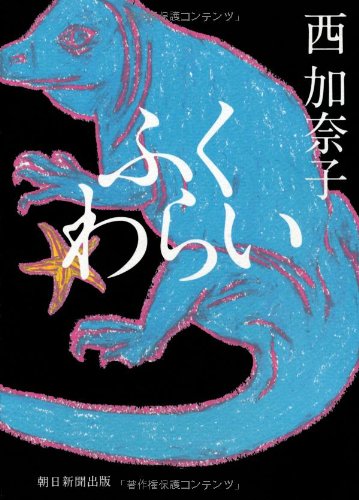
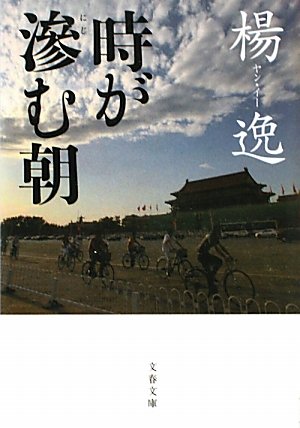
コメント