
本書は、世田谷文学館で開催されていた「小松左京展-D計画」で購入した。
同展の中で本書は著者の膨大な作品群の中でも一つの到達点であると紹介されていた。
それにもかかわらず、私はまだ本書を読んでいなかった。これは読まなければ、とミュージアムショップで購入した。
本書はタイトルからも想像できる通り、時間の壮大な流れをテーマとしている。
普通に生活していては決して感じられない悠久の時間の流れ。
その気の遠くなるような時間の尺度の中で、人間とは刹那の時間、生まれては死んでゆく存在にすぎない。
人間とは果てしない時間の流れの中において何のために存在しているのだろうか。無限に近い時間の流れの中、人の生に意味はあるのか。
人間にとって根源となる問い。著者はその問いの答えを本書に描いている。複数の時代を区切る時間の断層を自在に飛び移る壮大な物語に仕立てて。
21世紀末の太陽フレアの異常で滅亡した人類。
太陽が暴発する直前に宇宙から飛来した異星人の船団によって救われた人類。その中で異星人によって選別され、人類の次の階梯に進むことを許された何人かの人類。
太陽系に人類が住む場所はなくなっても、2473年にまで生き延びた人類。
人類の次の階梯に進むことを許された松浦ことマツウラ、そしてマツラ。彼は時間機を操り、時間軸を狂わせようとたくらむルキッフの一味を追う。
ルキッフの一味は、人類の黎明期から機械文明を持ち込み、人類の歴史を根底から変えてしまおうともくろむ。それによって人類の歴史とあり方を根底から改善してしまおうとするのが狙いだ。
今までに発展してきた文明の中で無数の試行錯誤を重ね、あたら多くの命を散らしてきた人類。その愚かな歴史の初期から高度な科学文明の成果を持ち込むことで根本から改善し、人類の壮大な歴史の無駄を清算し、より良い未来に変える。それが彼らの考えだ。
しかし、人類よりさらに進んだ高次の生命体は、過去を変えることを決して許さない。その指示に従いマツラはルキッフたちの一味を追う。
各時代のあちこちに潜む工作員。そして、人類の歴史を変えるために各時代に拉致された人々。中生代から弥生時代、戦国時代。本書の舞台はあちこちへと飛ぶ。
本書には著者の作品としてあまりにも高名な『日本沈没』のその後を思わせる記述も出てくる(289-290ページ)。そこで日本民族の末裔は、喪われた日本の精神を残したまま、αCⅣ星へと移住することを熱望している。
本書は、人類の意識に次の段階があるのか。それは何かを描こうとしている。
今の段階での人類の意識は、時間や生命の営みの裏側にある意味を理解するには及ばない。
ようやく、民族や地域ごとの紛争を卒業できるかどうか、という段階だ。
その低次元の争いから次へ進むにあたって、人類は何が必要か。そもそも人類はどこに進むべきか。外的な要因がない限り、人類が新たな段階に進めないのでは。
著者の青春時代の敗戦体験や、そこで培った人のあり方への深刻な悩みは、本書のテーマとして結実している。
また、人類の歴史のあちこちに刻まれている謎めいた痕跡や伝説や神話。それらはただの進化の痕跡と考えるにはあまりにも不可解だ。
人類の進化の歴史には、何らかの知的生命体による操作が加わっているのではないかとの疑い。
著者の博識はそうしたエピソードを丹念に拾う。そして本書の中にちりばめる。
実は人類の歴史とは私たちが思っている以上の裏の意味をはらんでいるのかもしれない。
著者は本書にそれらの思いを詰め込んでいる。
人類の歴史や生の意味についての著者の考え。それらは本書の中でも開陳されている。
「モラルというやつは──要するに、配分の公正さ、ということで、その公正、適正は、時代と社会によってケース・バイ・ケースだ。社会を成立させる、最低の条件としてのルールやタブーもあるだろう。だけど、こいつは、大したことじゃない。モラルというやつは、もともと人間主義とは、何の関係もないんだ。おそろしく冷厳で、現実的なものだから、その社会のモラルにしたがって、人間はいくらでも、犠牲にできる。──だが、人間の”認識する能力”というものは、大変なものだな、ホアン。人間の認識能力は、人間の現実的状態の幸不幸に関係なく、とてつもなく、深遠で巨大なことを認識できる。しかし、その到達し得た認識は、その時の人間の状態を、ちっとも変えやしない。かろうじて、現実自体のルールで動いている人間的現実に、一刻休戦を勧告し、その闘争の過酷さを、いくぶんとも緩和させるように、はたらきかけるだけだ。それも、有効範囲は、人間の相互関係の中でうみ出される人間的現実にかぎられていて、人間の、存在状態の方には、指一本ふれられやしないのだ」
「だがその認識によって、人類全体は理想状態に、一歩一歩、ちかづいていくのじゃないのかね?」
「そして、ついに、状態は認識に追いつけない」野々村は、乾いた声で言った。「理想状態って、何だ! ホアン! 幸不幸は、全然別の問題だ。それは実際にその時生きている具体的な、個々の人間の問題だ。飽食していて不幸なやつもいれば、飢えて、幸福な奴もいる。みずから求めて苦痛を追い、その中で恍惚を味わうやつもいる。先史時代から、宇宙時代までの間に、何千億というあわれな連中が、けだものみたいに死んでいったが、そいつらは、後世の連中が考えるほど、不幸じゃなかったかも知らない。けだものには、けだものの充実した生活──飢餓と敵との闘争の日々があるからな。”種”としての人間は、まさに特殊化した哺乳類、二足獣にすぎない。──だが、こいつは、ただ生きるための知恵と工夫を行う獣とは、すこしちがうものをもっている。そいつは……」
「ものを知る力、か……」ホアンは、こめかみをもんだ。「宇宙のひろさと、テコの原理を、そして、人間が頭でっかちのケダモノであることを認識する能力か」(364-365ページ)
この部分だけでも、本書の追い求めている考察の深みが感じられる。
SF作家とは、科学者と哲学者の素質をともに備え、さらにそれを面白く読者に教えられる教師なのかもしれない。
今さらながら、小松左京展で著者のすごさを知った。
著者の作品は、残さずに読むつもりだ。
‘2019/11/1-2019/11/4


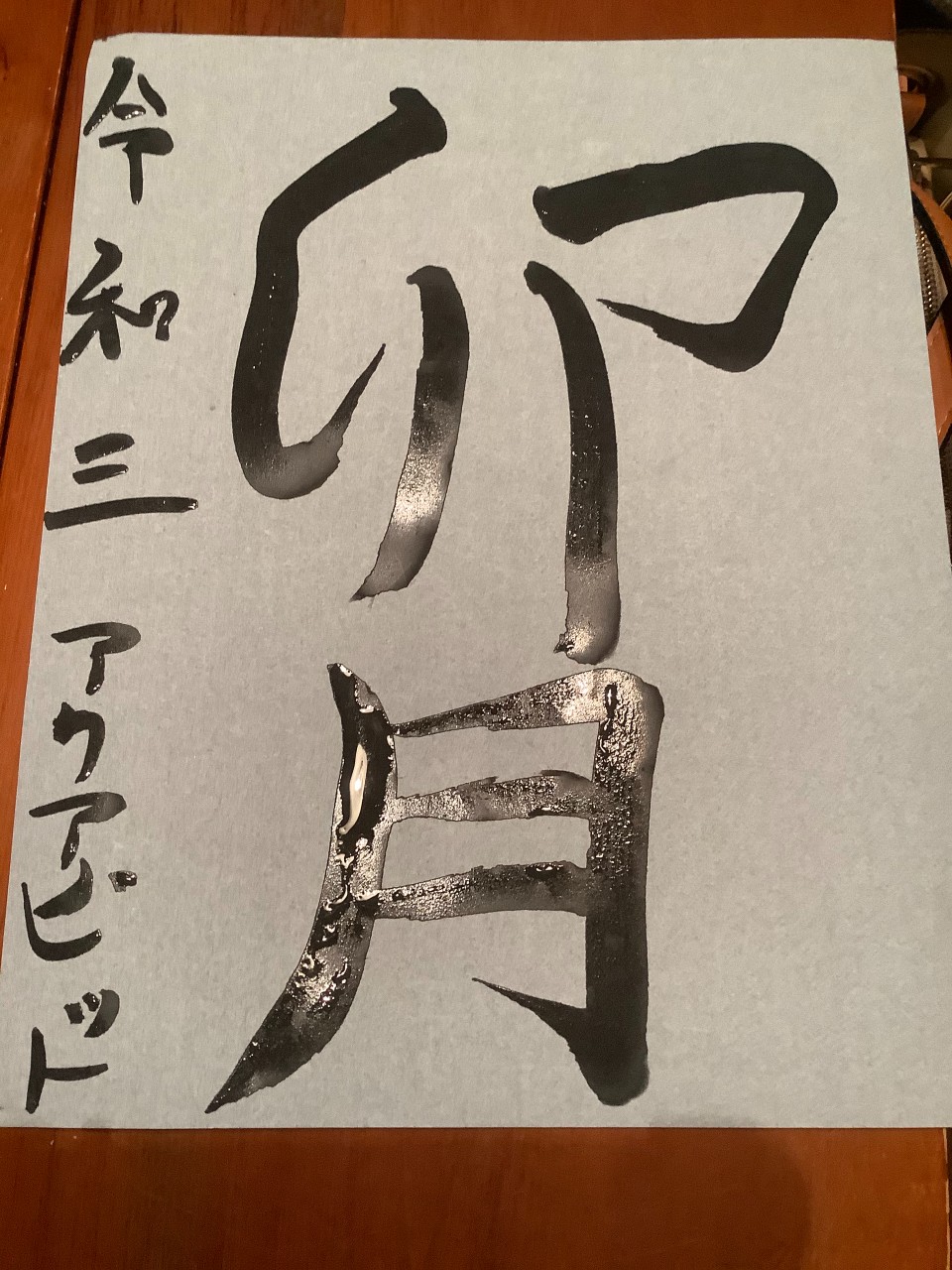
コメント