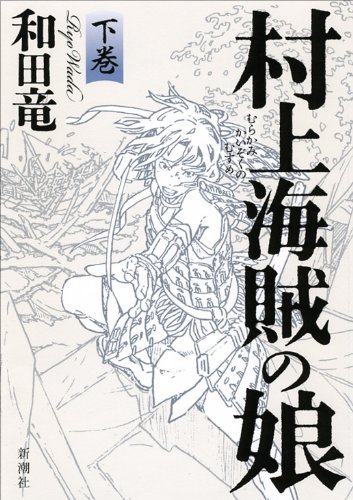
木津川砦をめぐる戦いにおいて、本願寺が門徒たちに示した旗。そこに書かれていたのが「極楽往生を遂げたければ、敵に背を見せるなかれ」。
その旗を見て逆上した”景”。
はるばる大坂本願寺まで信心の篤い信徒たちを送り届ける船旅の中で、漁民たちの一途な思いに触れ、今まで軽んじていた信仰心を見直した”景”。
なのに、その信心を利用し、使い捨てのように使う本願寺のやり方が許せない。
戦いの中で斃れた源爺の亡骸を担ぎ、本願寺の軍を指揮する下間頼龍の元に向かった”景”。そこで”景”は、源爺が確かに極楽浄土に行ったことを証明せよ、下間頼竜に迫る。
そんなことができるはずもなく、けんもほろろに扱われる”景”。
傷ついた”景”は、自らに好意を寄せてくれていたはずの眞鍋海賊の長、七五三兵衛にまでおもろないやつ、と見放されてしまう。
苛烈な戦国の世にあって、何よりも必要なこと。
それは御家を、一族とそれを支える人々を生き延びさせることにある。
一向宗の漁民たちを道具として扱う本願寺への”景”の憤りは、あくまでも私憤でしかない。つまり、小局だ。
己の感情に縛られ、大局を見ずに私憤だけで行動する”景”は、ようやく世の中の動かしがたい現実を知る。
人々の抱く信念と己のそれの決定的な違い。
それを突きつけられた”景”は傷心のまま、能島に戻る。戻ってきた娘を父の村上武吉は何も言わずにただ労わる。
父には最初からお見通しだったのだ。
だからこそ、ひたむきな気持で漁民たちを送るために飛び出していった景をあえて追わなかった。それが”景”に戦国の世の冷徹な現実を悟らせるなら、良い機会と見定めていた。
まさに娘には旅をさせよ、だ。
そんな村上武吉は、村上家を今後どうすべきか思考を巡らせていた。
そもそも、事の発端は、織田家に包囲され兵糧が乏しくなってきた大坂本願寺が毛利家に援助を乞うたことにある。
毛利家も単独では食料を輸送することは難しい立場。能島を本拠にする村上水軍に協力を依頼しなければどうにもならず、苦慮していた。
だが毛利家を支える小早川隆景は、北国の上杉謙信が立たぬ以上、本願寺だけで織田家に向かうのは勝ち目がないと判断していた。
その状態で毛利家が本願寺に援助を行うことは、織田家に敵対する意思を表明するのと同じ。
村上武吉はそんな毛利家の思惑を読み切っていた。だからこそ、時間を稼ぐために”景”の嫁ぎ先を毛利水軍の児玉就英にと条件を吹っ掛けたり、大山祇神社での連歌奉納に悠々と参加したりしていた。
そして、兵糧を積んだ船を大坂に向けて出帆させた後も、村上武吉は上杉謙信の出陣はないことを見切っていた。そして、途中で戦局を見守ったまま、いたずらに戦いを仕掛けず様子を見るように指示していた。
それはすなわち、兵糧攻めを受けている本願寺の人々を見殺しにすることに等しい。
能島に帰ってからというもの、すっかり人が変わり、おしとやかになっていた”景”。ところが、父から出帆した船が本願寺に行くことはない、と打ち明けられる。それに逆上した”景”は、単身大坂へと向かう。
大坂本願寺の人々からは、明石の浦から淡路の岩屋城へ続々と集まる軍船が見えている。淡輪にいる眞鍋水軍にも。
だが、いったん集結した船が動くことはない。いくら待てども。それらの船が動く気配はないことを知った人々に絶望の気運が高まる。
業を煮やした”景”は、単身で織田軍の味方である眞鍋水軍へ乗り込む。そして、兵糧を本願寺に運びたいから包囲を解くよう七五三兵衛に談判する。
だが、毛利軍と村上水軍の多数の軍船が控えている中でも、七五三兵衛は退かない。眞鍋水軍は村上水軍に受けて立つと吼える。
ここで引くことは、大局を見た場合には利があるのだろうが、それを行うことは海賊としての誇りが許さない、と。
交渉が決裂する。
上杉謙信の出陣の報も見込めず、万策が尽きた毛利水軍と村上水軍の連合軍は、再び本拠地へ向かって一戦も交えぬまま撤退する。
だが、”景”はその中の五十隻を率い、単身眞鍋水軍へ戦いを挑む。
大局に唯々諾々と従うのではなく、己が奉ずる信念のために。
そんな”景”を迎え撃つのは、大局よりも海賊としての己の本能に従った、七五三兵衛の率いる眞鍋水軍。
かくして歴史に残る第一次木津川口の戦いは始まった。
今まで私が読んできた多くの歴史小説でも海の上の戦いは初めだ。
著者も海戦に目をつけて本書の構想を練ったのだろう。だから熱の入り方が違う。
下巻の後半のほとんどは、この海戦の描写に費やされている。
最初は五十隻で挑んだため、多勢に無勢の不利があって追い詰められる”景”と村上水軍。
だが、その事実を”景”の弟、景親が大声で自陣に告げる。
村上水軍の軍紀として、女が海戦に参加してはならぬ。この掟は、実は村上水軍にとって鬼手とされる秘策だった。そのような掟に縛られていたからこそ、”景”は無頼を気取って好き放題に生きてきた。
だが、”景”の影に隠れ、弱弱しい弟だった景親が放った大声が、村上水軍の全軍に響きわたる。”景”が自ら鬼手である秘策を実行したのであれば、村上水軍に勝機は見えた。
そこで村上水軍の残りが明石の浦に再び現れ、大坂湾へと戻ってくる。
眞鍋水軍に傾きつつあった戦局は、村上水軍がそろったことで逆転する。そればかりか、村上水軍の秘策である焙烙弾によって壊滅的な被った眞鍋水軍は不利となる。
海賊としての誇りをかけて、それぞれの水軍の将が思うがままに暴れまわる。
ここに大局を見る、といったささいな心は捨てられ、ただ己の奉じる信念と戦いのために磨いてきた能力だけ。それが生き残りの武器となる。
“景”と七五三兵衛の因縁にもケリがつけられる。
己を指しておもろないやつ、と見限った相手に対し、再び価値を認めさせる戦い。
実に読み応えのある海戦のシーンが続く。
戦国の世を描いた物語は、大局を見据えた人物が最後は勝つのが定石だ。
だが、敗れた側が大局を見る目を持っていなかったのではなく、己の信念に殉じただけにすぎないのだろう。
七五三兵衛もそうなら、かろうじて勝利を収めた”景”もそう。
本書の末尾では、主要な登場人物のその後に触れている。が、”景”のその後の消息はわずかにしか伝わっていないと述べる。
“景”もまた、非情の戦国の世に翻弄され、己の信念を全うできずに歴史の中に消えていったのかもしれない。または、彼女なりに己の信念を貫いたのかもしれない。
大局と小局の対比。そのことを考えさせられた小説だった。
それこそ、海賊の言葉が標準語に近いことなどささいなことと思えるぐらいに。
‘2019/10/10-2019/10/10
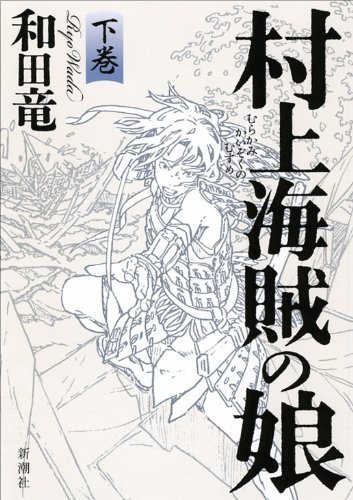


コメント