
NHK朝の連続ドラマ「マッサン」は、私のようなウイスキー愛好家に大きな影響を与えた。ウイスキーがブームとなり、酒屋の店頭からウイスキーが売り切れていった。原酒は不足し、製品のラインアップは変わった。それを差し置いても、ウイスキーが人々の身近な酒となったことはとても素晴らしいことだ。何よりも素晴らしいのは、我が国で造られたウイスキーの品質の優秀さを日本人自身に知らしめたことだ。そこには「マッサン」のモデルとなった竹鶴政孝氏の努力と情熱もさることながら、妻として支え続けたリタさんの献身が欠かせなかったと思う。竹鶴リタこそは、日本のウイスキーを語る際に欠かせない人物であり、「マッサン」によってその生涯に脚光が当たったことはとてもうれしい。20年ほど前に初めて訪れた余市蒸留所。そこには夫妻の自宅を再現したリタハウスが建っていた。そこで飲んだアールグレイの味は忘れてしまったが、おいしかったことと、リタハウスの落ち着いた雰囲気はとても印象に残っている。
私は夫妻に関する関連書籍は何冊か読んできた。そのうちの2冊「竹鶴政孝とウイスキー」と「マッサンとリタ ジャパニーズ・ウイスキーの誕生」は当ブログでレビューにも書いた。しかし、それらの本は二人のロマンスよりもウイスキー造りやニッカウヰスキーの歩みを記すことに焦点が当てられていたように思う。
しかも、上に書いたその二冊はノンフィクションに属する内容だ。「 竹鶴政孝とウイスキー 」はウイスキー評論家として著名な土屋守氏によるもので、「 マッサンとリタ ジャパニーズ・ウイスキーの誕生」は、日英関係を研究する英国女性の著者の視点から書かれている。前者はウイスキー作りを学ぶ政孝の努力や当時のウイスキー作りの比較や分析に力が置かれているし、後者においては、異邦の日本で住まう英国女性の苦労を描くことに重心が置かれている。 後者には、リタと故郷のカウン家で交わされた往復書簡もたくさん紹介されている。英国に残されたリタの手紙には、日本にいては言いづらいリタの望郷の思いや、異国にきて竹鶴政孝の妻として最善を尽くそうとするリタの意地もにじみ出ていたようだ。リタは政孝の妻として精一杯生きたが、そこには異郷に住む女性として、後悔や弱音を吐きたくない矜持があったはずだ、と著者は英国女性の立場からリタの肩を持っていた。
私は「マッサン」はいまだに見ていない。なので、二人のスコットランドでのロマンチックな出会いやその後の苦労は知識としてしか知らない。ウイスキーを日本で造ることに情熱を燃やす竹鶴青年とスコットランドのおとなしい少女であったリタが出会い、結婚するまでにどのようなことがあったのか。特にリタは、おとなしい少女だったという描写が多い。だが、日本の青年について異国へ向かう度胸を見せるリタの心をおとなしい、だけで片付けるのは物足りなさを感じていた。政孝と出会う前のリタに何があったのか。リタの心のうちに焦点を当て、リタを日本に赴かせた背景に何があったのか。 日本人にとって国際結婚がとても珍しい当時の事情にも興味があるが、リタの心の動きにはとても興味があった。リタの心を描く作業は小説家の独擅場だ。 そして私は、リタの生涯を取り上げ、蘇らせた本書の存在をつい最近まで知らなかった。
本書は森瑤子氏による作品だが、女性的な視点でどこまでリタの内面に踏み込んでいるかを期待しながら読み進めた。じつは著者の作品を読むのは本書が初めて。だから、小説家としての技巧はよく知らなかった。しかし、本書で書かれるリタは丁寧に描写されており、同じ女性からの感性で書かれた感情の揺れには説得力があった。リタの生涯がまざまざと読者の前に蘇るようだ。
本書は、リタのスコットランド、カーカンテロフでの少女時代を丹念に書いている。今までの夫妻の出会いを描いた文章はどちらかといえば政孝の視点で描かれることが多い。政孝に出会う前のリタの少女時代は省かれているように思う。でも本書はその部分を重点的に書いている。なぜなら本書の主人公はリタだから。リタの少女時代について、われわれはあまり知ることがない。たとえばリタが政孝と出会う前、婚約者を第一次世界大戦で亡くしていたことや、リタに妹や弟がいたことなど。それは、政孝のウイスキー修行とニッカウヰスキーの歩みにとってはあまり重要なことではないのだろう。でも、リタがなぜ政孝からのプロポーズを受け入れ、遠い日本へ渡る決断を下したか。それを推し量る上で婚約者ジョンの戦死とその後に続いた父サミュエル・カウンの死は忘れるわけにはいかないのだ。また、日本に渡った後のリタは、一度だけ政孝のスコットランド視察に付き添って母国に帰ったものの、それ以外はとうとう64歳で亡くなるまで日本を離れることはなかった。その理由は、リタが夫に従い夫の夢を支えようと決意したことだけでない。スコットランドを離れる際にカウン家の妹エラや弟ラムゼイとこじれてしまったことも原因としてあったのだろう。
リタを主人公とした本書は、リタがイギリスを離れるまでの日々に全体の半分以上を費やしている。ページ数にして252ページ。リタが日本で異邦人として生き、日本婦人以上に日本を大切にした背景を描くためにはそれだけの紙数が必要だったのだ。婚約者ジョン、父サミュエル・カウン、母アイダ・カウン、妹エラ、ルーシー、弟ラムゼイ。彼らとの満ち足りた日々。出会った当初は反発しあう仲だったジョンとの恋愛、そして婚約。引っ込み思案な少女に訪れた幸せは、シリアの戦場から届いたジョンの戦死の知らせによって打ち砕かれる。ジョンの命はイギリスに捧げられ、同時にリタの心もイギリスから、日常から、そして神からも離れてしまう。
そんなところにやってきたのが竹鶴政孝だった。快活な青年タケツルは、カウン家にやって来たリビングルームで、ラムゼイに語る。「男が命をかける場所は戦場じゃないよ」「男が命をかけるのは、自分の夢に対してなのだ、と思うな。夢を実現させるために、命がけで闘うのさ」(142ページ)。鮮烈な出会い。タケツルの存在はカウン家に新風を吹き込む。しかし、父サミュエルも老い、タケツルとの出会いを警告するかのように娘たちに告げる。「良かった。それで安心したよ。人間というものはな、自分の国の言葉が通じるところで生き続けるのが一番幸せなことなのだ。いいかね、人間の感情の中で何よりもつらいのは、望郷の念なのだ」(149ページ)。
自分の余命を知った上で警句のように言葉を掛ける父サミュエル。しかし、若い二人が惹かれることは最初から定められていたかのように、二人の距離は迫る。そしてサミュエルは世を去ってしまう。政孝の夢を支えようと決意したリタは、婚姻届を出す。幸せをふっと掴んでは行ってしまうリタに、ジョンの時もマサタカのときもそうだったと憎しみをぶつける妹エラ。妹ルーシー以外の誰にも理解されぬまま、スコットランドをたつリタの姿は決意に満ちている。ルーシー以外の家族の誰にも見送られなかったにもかかわらず。
日本に着いてからも、夫婦の前途は多難だ。摂津酒造は不景気でウイスキー作りどころではなくなり、自らの志と違った状態に退社を決意する政孝。そして桃山中学での教師時代と雌伏の時を過ごす。後日、鳥井 信治郎から誘われ壽屋に入社し、山崎蒸留所の建設に取り組む政孝。政孝のウイスキー造りの仕事に従ってリタの生活も変化する。だが、リタも必死に日本に溶け込もうとする。そんな日々を著者は丹念に追う。そして、不慮の事故からの流産や孤児院から養子沙羅を貰い受ける経緯など、本書はあくまでもリタの視点から物語をつむいでゆく。
そんなリタの懸命の努力にもかかわらず、日本には戦時の空気が満ち、敵性外人であるリタへの風当たりは厳しさをまして行く。さらに、完璧な日本人であろうとするリタの姿勢は娘沙羅にも疎まれ、出奔される。父サミュエル・カウンから言われた警句である望郷の念がリタをさいなむ。だが、リタの真面目さは日本婦人になり切らないと、と自分を甘えさせない。そしてそんな日々はリタの身体を知らぬ間にむしばんで行くことになる。
だが、竹鶴夫妻が新たに広島の竹鶴本家から迎えた威が、リタの心のこわばりをほぐす。リタが威の胸で泣き崩れ、神が自分から奪って行った人々を威という形で返してくれたことに感謝するシーンは感動的だ。本書はリタの死の前年、仲たがいしていた妹エラからの手紙で幕を閉じる。望郷の念を忘れ去ろうとするあまり、リタが自分で凍り付かせていた故郷とのつながりが現れた瞬間だ。エラとの確執と和解こそが、本書のテーマなのだと思う。本書はウイスキー作りの物語ではない。 望郷の思いを押し殺 した一人の女性の物語なのだから。ならばこそ、故郷からの和解の手紙はリタだけでなくわれわれをも感動させるのだ。
残念なことにリタは、夫政孝が一生を掛けて作り上げたウイスキーが本場スコットランドから高い評価を受けることを知らずに死んだ。だが、望郷の念に打ちのめされたまま死なず、最後にエラとの和解がなったことは彼女のためにも祝福したいと思う。それにしても「マッサンとリタ ジャパニーズ・ウイスキーの誕生」ではこの和解の手紙には触れていなかった。この和解は事実なのだろうか、それとも著者による脚色なのだろうか。とても気になる。
私が最後に余市を訪れてからもはや12年以上の日々が過ぎてしまった。そして私はまだお二人の眠る墓地を訪れたことがない。「マッサンとリタ ジャパニーズ・ウイスキーの誕生」のレビューにも書いたが、竹鶴家による墓参り自粛のお願いがあったという。そのお願いは解けたのだろうか。そろそろマッサンブームも落ち着いたころだと思うので、余市を訪れた際は墓参したいと思う。そして、リタという一人の女性が過ごした数奇な一生に思いをはせたいと思う。
‘2016/09/05-2016/09/06
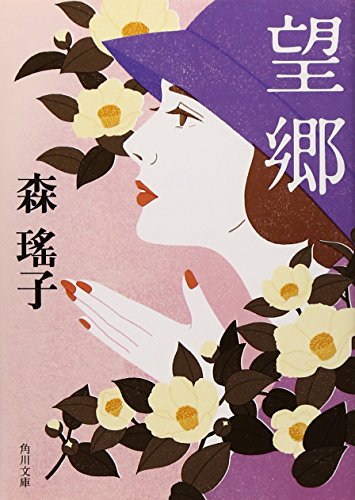


コメント