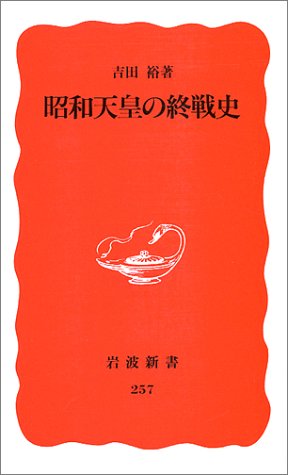
岩波書店は、注意深く覆い隠しているが、どちらかと言えば左寄りの論座を持っている。もちろんそれは悪いことではない。
本書のタイトルから推測するに、昭和天皇の戦争責任についてある程度は言及し、認めているであろうことは予想していた。
昭和天皇が崩御して間もない時期に発見された昭和天皇独白録。敗戦後すぐの時期に内々で語られたというこの独白録が発見された時、新聞で一面に取り上げられたことを私は見た覚えがある。
本書はこの独白録の成立までの過程や、その内容などを取り上げている。著者は、この独白録が「平和のために苦悩する天皇」という先入観につながることを危ぶんでいる。著者は軍国とリベラルの二元で終戦史を捉えることに反対する立場だ。
私は、昭和天皇は一点の過ちも曇りもない、いわゆる聖人君子だとは思っていない。結局、すべての歴史上の人物と同じ、歴史の波に翻弄された方だと思っている。巨大な歴史の渦に抗おうと、懸命に努力し、あわや最後の天皇として名を残すところまで追い詰められた方だと。
判断を誤った局面もあった。逆に日本をそれ以上の破滅から救った英断もあった。
終戦の際、御前会議で聖断を下したことも昭和天皇の本心だったと思う。勝者として進駐してきたGHQのマッカーサー司令官に会った際、私がすべての責任を取るといった言葉も紛れもなく本心からの言葉だったと思う。緒戦の戦果に喜んだのも事実だろうし、開戦が決断される御前会議において明治天皇御製の句を詠んで深い憂慮を示したのも事実だろう。
一人の人間が担うにはあまりにも大きな重荷を背負ったのが昭和天皇。その逆境に耐え、日本の戦後の復興に導いたのも昭和天皇。実に英明な人だったと思う。昭和天皇がこの時、日本の天皇でよかったとすら思っている。
理想主義に燃え、軍国主義に対抗する天皇だったら、軍部の若手将校に退位させられていただろう。悪くすれば幽閉や暗殺さえあったかもしれない。
逆に愚昧な方だったとしたら、聖断もくだせなかっただろうし、GHQの協力も得られぬまま日本は共産主義に赤く染まっていたかもしれない。日本はもっと破滅的な未来を迎えていた可能性だってあった。
賢明でバランスのとれた方であったため、自らの置かれた政治的な立場やよって立つ体制の仕組みや限界もわかっていたはずだ。また、帝王学を学んでいたので、国際関係や地政学もある程度は身につけていたと思う。その上で世論の右傾化や軍の強硬な態度も把握していたことだろう。
その一方、ひと時の衝動で千数百年と続いた王朝を自らの代で終わらせられないとの危機感も強く抱いていたはずだ。
著者が描く昭和天皇のイメージとは以下の文に表される。
「天皇自身は、国家神道的国体観念をふりかざす「精神右翼」や「観念右翼」を一貫して忌避し、そうした勢力の政治的代弁者とみなされていた平沼騏一郎や「皇道派」系の将軍に対しては、終始批判的な姿勢をくずさなかった。
しかしそのことは、天皇が国体至上主義から少しでも自由であったことを意味しない。むしろ天皇は、「皇祖皇宗」に対する強烈な使命感に支えられながら、「国体護持」を至上の課題として一貫して行動した」(219 ページ)
つまり著者は、昭和天皇独白録を奉るつもりもなければ、戦争を主導した戦犯だと昭和天皇を糾弾するつもりもない。その一方で、昭和初期の日本が戦争主導グループとリベラルなグループに分かれ、昭和天皇が終始リベラルな側にいて戦争に反対を唱えていたと言う論調が定着し、それがこの昭和天皇独白録によってさらに助長されるのではないかと言う懸念を表明している。
本書は、独白録の内容や、成立までの過程を丁寧に追っている。
著者のスタンスは上に書いた通り。その上で著者は、本書において宮中派と呼ばれるグループに焦点を当てている。宮中派とはつまり牧野伸顕から木戸幸一に至る天皇の側近グループであり、穏健派とも呼ばれるグループだ。
「この「穏健派」の評価いかんによって、日本の近代史はまったく異なった像をむすぶが、私見によれば、当初、対米英協調路線と政党内閣制を支持していたこのグループは、十五年戦争の経過のなかで次第にそのスタンスを変化させ、軍部の路線との間の距離を縮めていった」(228ページ)
東京裁判において裁判に協力的な姿勢を示し、軍部に戦争責任を押し付ける形で国体の護持、すなわち天皇の戦争責任を免責に持ち込んだ事は、穏健派としては上々の成果だろう。この独白録の作成も対策の一つであることは当然の話だ。むしろ、国難にあたってこうした弁明書がないことの方が不思議に思える。
私は、穏健派と昭和天皇が成し遂げた今の日本の基盤をよしとし、感謝している。
戦前の皇国主義が今も続いていたら私のような自由を尊び、多様性を重んずる人間には生きづらい世の中だったと思うし、日本が悪平等を旨とした共産主義になっていたら、もっと生きづらかったはずだ。
私は昭和天皇には戦争責任はあったと考えている。だが、それは昭和天皇をおとしめることにはならないはずだ。一人の人間として懸命に努力し、知恵を絞り、立場や体制のバランスを考え、いざというときには毅然とした態度で事に当たった昭和天皇に私心はなかったちろう。その苦悩や責任の重さは私には到底想像もつかない。
だが、それでもどうにもならないのが歴史の当事者の宿命だ。
その過程では後世から見れば誤りと判断できる言動もあった。戦局にも一喜一憂した。ときには首相を叱責し、反乱軍に対してつよい口調で意思を示したこともあった。作戦に口を出したこともあった。
それらだけを取り上げれば、昭和天皇の戦争責任は重く、東京裁判ではA級戦犯並みの判決を受けた可能性だってあっただろう。少なくとも退位は避けられなかったはずだ。たが、昭和天皇は退位論にも与せず、あえて困難な道を選び続けた。
国民から畏れ敬われる立場から、親しまれる象徴の立場へ。国内を行幸し、四十数年の間をかけて新たな天皇像と戦後の日本を作り上げた。それは、普通の人にはとうてい成し得ないことだと思う。
聖人君子としての固定のイメージで語ることは、決して昭和天皇も喜ばないと思う。むしろ、バランスのとれた方だからこそ、自分の戦時中の過ちも含めて、バランスを取るために本書を良しとしたはずだ。むしろ喜ばれたのではないだろうか。天皇機関説をその通りだと認めた方だけに。
2020/10/14-2020/10/18


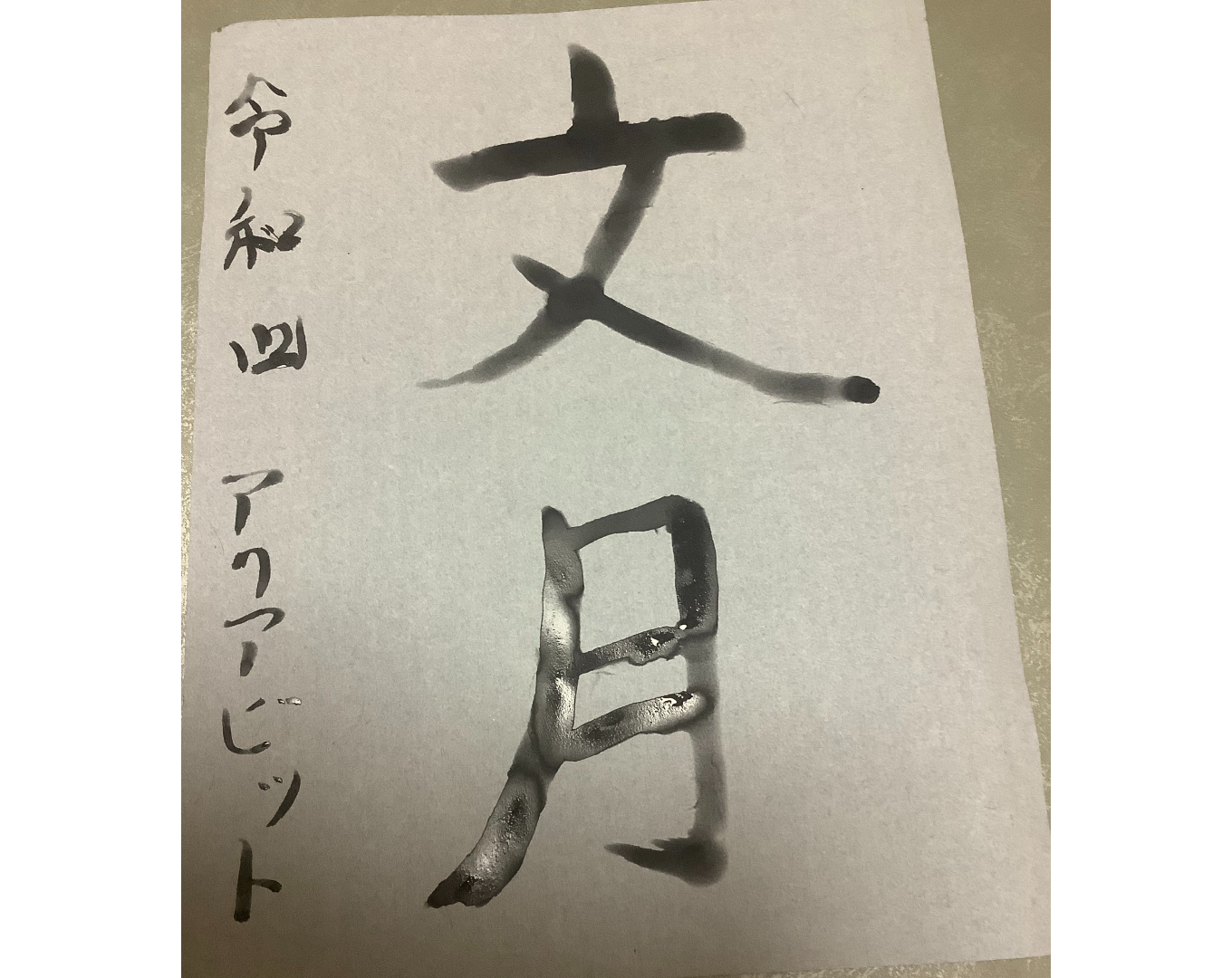
コメント