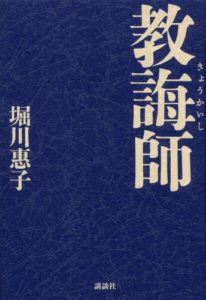
本書にはとても考えさせられた。
教誨師。私は今までの人生で教誨師を名乗る方に会ったことがない。教誨師と知り合いの人にすら会ったことがない。それもそのはず。教誨師が活躍するのは一般人にあまり縁のない場所だ。つまり刑務所や拘置所。そのような施設に収監された方々の話し相手として宗教的救いを与える。そういった職業の方を教誨師と呼んでいるようだ。と、一般的にはそういうことになっている。私も本書を読むまでそのように思っていた。
昭和史、とくに太平洋戦争に関する本を読むと、巣鴨でのA級戦犯の方々の挿話をよく目にする。その中で登場するのが花岡信勝教誨師。A級戦犯が死刑に行く際に外界へのメッセージを受け取る役としてよく登場する。私にとっての教誨師のイメージとはこの方によるものが多い。しかし、そういった巣鴨での挿話からは教誨師の実像は掴みにくい。教誨師からの目線では書かれていないからだ。本書は、囚人に影のように付き添う存在である教誨師の目線から書かれた一冊だ。教誨師についてより深く知ることができる。
本書は、教誨師として活動されていた渡邉普相氏へのインタビューを元に構成されている。本来ならば教誨師の仕事はこのような形で公開されない。権利と職掌という網の目のように張り巡らされた糸。それは、獄中で教誨師が見聞きしたエピソードを漏らすことを許さない。教誨師として知りえたことは、決してわれわれが知ることはない。教誨師の胸の中に仕舞われたまま秘密のベールに隠され、報道されることも公言されることもない。
本書の主人公である渡邉師もまた、本書は自身の死後に出版してほしいと著者に言い残し、教誨師として僧侶としての生涯を全うした。しかし渡邉師は、死ぬ前に教誨師の仕事を言い残したいと思ったのだろう。死刑囚が直面する生死のはざまとは、教誨師にしか明かされない死刑囚の想いとは。それは教誨師が伝えなくては、どこにも残らない。それを言い残さぬままでは成仏することができないと思ったのか。本書はまさに遺言である。教誨師として半世紀以上も勤めた人間による率直な反省の弁であり、そこで掴み取った人生の視線といえる書だ。
渡邉師の遺言どおり、著者は渡邉師の死後に本書を出している。教誨師と呼ばれる仕事の本質を渡邉師のインタビューを元に組み立てたのが本書だ。
本書の内容は、教誨師の仕事を知る上で興味深い。それだけではなく、教誨師の仕事の中でいや応なしに突きつけられる現実に焦点を当てている。生死とは、教育とは、矯正施設の持つ意義とは。私たちの知らない世界がそこにはある。
本書のページ数は250Pほど。さほど多くない。しかし、内容はとても充実している。本書は渡邉師の生いたちから筆を起こす。だが、単に順に生い立ちを追うわけではない。そうするには、渡邉師の生きざまはあまりにも波乱に満ちているからだ。
なので本書はなぜ渡邉師が教誨師としての道を選んだか、のいきさつから筆を起こす。篠田隆雄師から教誨師としての後継者と目されたからだ。そこに至るには、さらに渡邉師の生い立ちをさかのぼる必要がある。 渡邉師は人間が直面させられる極限な試練を受けている。広島原爆で九死に一生を得た 渡邉師 は、横にいた友人たちが一瞬で焼かれた刹那を経験している。炎と煙渦巻くキノコ雲の下、生きたいと必死に逃げた自分との直面。水を乞う人々を見捨てて生き延びた罪悪感。
二度と逃げ出すようなことはしたくない、との思い。それが渡邉師を半世紀にわたって教誨師の地位に留めたともいえる。
しかし、渡邉師は心の強靭な聖人君子ではない。教誨師も罪人と同じく弱い人間であるということ。それをきちんと描いていること。そのことが本書をたんなる伝記や宗教書と一線を画した大きな点だ。そもそも聖人君子には教誨師は勤まらない。渡邉師も著者に対して根がいい加減だから勤まったと述懐する。
本書には渡邉師が教誨師として向き合った幾多もの囚人との挿話が収められている。存命関係者に迷惑を掛けぬようその多くは仮名で登場している。仮名なのに死刑執行が昭和40年代以前の人しか語らない。
教誨師は囚人を宗教的に救う人。しかし、その作業がそんなに生易しい作業ではないことを読者は知る。沙婆と違い、刺激のない単調な獄中の日々。そんな囚人にとって、教誨師とは唯一外界の空気を持ち込む存在となる。普通に生活を営む人々が思う以上に、囚人は相対する人物の一挙手一投足に敏感だ。一瞬たりとも態度に馴れは出せない。事務的な定型の対応はもってのほか。一度そういう対応してしまうと囚人との信頼関係は壊れてしまう。教誨師の仕事とは、全てが真剣勝負。気を抜く間もない。
本書には、数多くの囚人との挿話を通じて渡邉師が得た苦しみや挫折が赤裸々に告白される。本書を読み終えると、死刑囚とはこれほどまでに孤独な存在で、教誨師とはこれほどまで過酷な仕事であることがわかる。そして、いくら死刑に価するだけの犯罪を犯したとはいえ、死刑が確定した途端に死刑囚に代表される画一の枠に収めて済ませようとするわれわれへの警句も読み取れる。
また、渡邉師は、死刑囚の多くがやむを得ず犯罪に走ったのであり、あるいは彼や彼女を親身になって支えてくれる人がいたら、こうはならなかったと残念がる。
関心や愛情を注がれれば、それを受け止めるだけの素養は人間みな持ち合わせているのに本当に惜しい、と渡邉は思った。(226p)
との記述がある。これこそまさに渡邉師が教誨師の仕事で会得した実感なのだろう。
ここで「いや、どんな境涯にあっても踏みとどまれた人だっている」とか、「同じような環境でも誘惑に屈しなかった人もいる」と思ったとすれば、渡邉師の思いを全く汲み取っていないことになる。死期を察した師がなぜ著者に対して一切を告白しようと思ったか。
渡邉師は、大勢の死刑囚との日々の中で、救いを与えるという自分の考えすら思い上がっていたのではないかと気づく。教誨師に出来ることとは、ただ聴く。囚人の発する思いを不安をただ聴く。これに尽きるのではないか。そんな境地に至る。
だが、そんな悟りくらいでは渡邉師が被った心の痛手はいやされるはずもない。 渡邉 師はアルコールが手放せなくなってしまう。そして断酒の為、入院。しかし、そのアル中の入院経験は、かえって囚人の心を開くのだから面白い。それがもとで教誨師の仕事に一つ山を相談を受けるようになる。
このくだりは印象深い。教誨師と囚人の一方的な関係では何も変わらないことを示している。結局、教誨師とは一方的に上から救いを与えるだけの存在ではないか。全国教誨師組合長を務めた渡邉師が得たこの悟りは深い。それは教誨師が善人、囚人は悪人、そんな二元論で済ませてはいないか、という反省である。親鸞は問うた。悪人とは、自らの悪を自覚した者。善人とは、自らの悪を未だ自覚していない者。
苦闘の末、アル中という聖職者にあるまじき病に身をおとし、初めて師は自らが悪人なのだ、との事に思い至る。罪を悔い改めよと説く人もまた罪人。そんな結論は、あらゆる宗教が喪ってしまった原点を思わせる。
本書は聖職者である渡邉師の悟りの軌跡を描いた書。とても考えさせられる一冊だ。
‘2016/09/28-2016/10/02
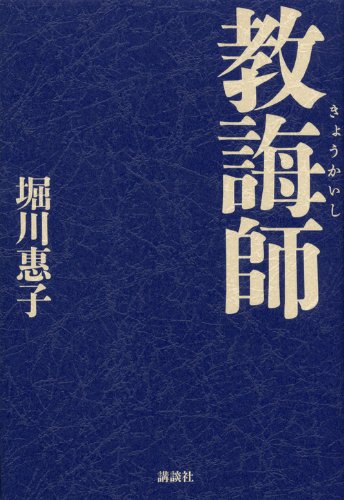
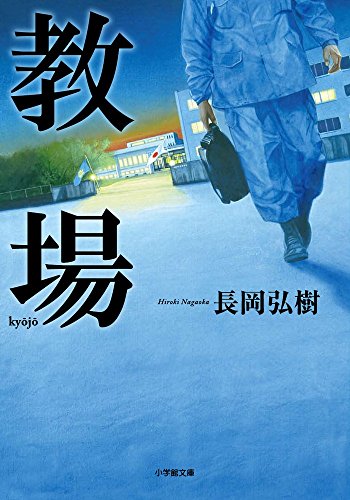

コメント