
この作品には衝撃を受けた。
文学史上、名作と語り継がれる作品には語り継がれる名場面がある。
読者の感情を揺さぶり、読者が抱いている世界と人生の概念を大きく書き換える場面が。
本書で名場面を挙げるとすれば、教祖が世界の様相と人生の意味を語りかける場面だ。本書の中では前半に登場する。
この場面は圧倒的だ。
私たちはどういう存在なのか。生を享け、意思を持ち、欲に駆り立てられるのはなにゆえか。
私たちの自我と世界の間にある見えない壁は絶対に破れないのか。
そもそも私たちの思惟とは、死んだら”無”に消えゆくしかない定めなのか。死ねば世界は消えてしまうのか。
時間と空間に限りはあるのか。その無限の範囲の中で私たちの生は何ほどの意味を与えられているのか。
古来、こうした話題は哲学者が考え抜いてきた。そして幾多の優れた文学作品の中で登場人物の悩みの対象となってきた。
例えば「カラマーゾフの兄弟」の大審問官の章でイワンとアリョーシャが論を戦わせたように。
だが、大半の人にとって、世界の中で自分がどのような意味があるのか、と言った問いは高尚にすぎた。人がそのような高邁な意思を語るなど恐れ多いと、考えること自体を避けてきた。
その方が悩まずに済むからだ。
人生の意味に答えなどたやすく見当たらない。だから、神の意思に預けてしまう。
人類の存在する意義とは、神の意思によるものでしかない。だから 気楽に生き、自然に苦しめられたらそれまで、というのが大衆の処世術だった。
神が預言者に託した生き方の意味。それを伝える場。それこそが宗教の役割だ。
そして、教祖が説いた生き方の意味を人々にあまねく広め、皆で考えるための装置として教団が結成された。
信者は信教の名の下に集い、神の代弁者に従う。教祖が語った生きる意味をありがたく崇めながら。
ところが、時代が経過するとともに、教祖が語った生き方が時代に合わなくなってきた。
それは科学技術が進展した事が大きい。
例えば天動説から地動説へと天体の動きは変わり、例えば生命の起源は神による創造から果てしなき淘汰の連続の結果である進化論へ。
ありとあらゆる科学的な事実が、教義に書かれた内容と次第に乖離してゆく。
信者の間に疑念が湧く中、教団はひたすらに抗ってきた。
ルネサンスがイタリアを中心に科学の発展を進めてきたが、そのお膝元であるカトリックが科学の事実に最も抗ってきたのは皮肉な話だ。
教皇が科学の事実の正しさを認めたのはようやくここ数十年のこと。
今や、教義に科学の知見を取り入れなければ、信者をつなぎ止められない。そんな時代がすでにやってきている。
ニーチェが神に死を宣告したように、神の絶対が科学技術の前に薄らぎつつある。果たして神と科学はともに並び立つものだろうか。
いや、今の時代こそ、宗教が科学の最新の成果を取り入れつつ、人としての生き方を示すべき時期だと思う。
科学を啓蒙する書は数多く出版されている。だが、そうした書の多くは、科学の知識の紹介に終始しがちだ。
科学が日々の暮らしにどう絡んでくるのか、人としてどう生きるべきかを考える際に科学がどう役に立つのか。そうした深い論点にまで立ち入り、分かりやすく説いてくれる書にはなかなか出会えない。
だが、本書の価値はそこにこそある。
教祖が穏やかな語り口で語る思索。意識や生の根源にまで迫らんとする思索の切っ先は鋭い。それでいながら難解に陥らず、とても分かりやすい。
最新の科学技術の成果も惜しげなく盛り込みながら生命の実存とその進化の成果である人間の意志のあり方に迫っている。
本書の前半で著される教義の深さと広がりは、わたしが今まで読んできたわずかな宗教書や哲学書、啓蒙書の中では群を抜いていると思う。
最新の科学の知見を吸収し、本書のような形で著すまでには、並大抵でない著者の苦労があったことと察せられる。
だが往々にして宗教が組織になると、教義そのものよりも組織の維持が目的と化してしまう。それが組織の宿命だ。
そして宗教とは、人の弱さを救うことに重きが置かれている。
つまり、人の弱さと宗教は不可分なのだ。だからこそ、人々の切実な思いが渦巻く教団にはそうした弱さやそこから生まれた醜さが沈殿してゆく。
本書には、そうした教団の宿命である醜さがことさらに描かれる。
欲にまみれ、欲に耽溺しながら、欲から逃れようとあがく人々。
むしろ、欲とは抑圧することが救いではなく、解放することが救いにつながるのだろうか。
本書で描かれる性の狂宴は、ポルノよりも赤裸々ではるかにどぎつい。
欲が人間にとって避けられず、人間の存在の影となって分かり難いことは必定。
それ故、著者は欲をベールに一切包まず、斟酌もしない。たださらけ出す。煽情的に挑むようにありのままを描く。
欲をありのままに描くには性欲を描くことが最も伝わりやすい。
欲に身を任せ、欲に溺れる自分を認めてこそ、弱い人間であり、宗教こそがそのような弱い存在を救いうる。
自らの醜さに気づけば気付くほど、教祖が語る教義の説得力は増す。
著者が力を入れたのは、本書で描いた教義をどれだけ真に迫った内容に研ぎ澄ませるか、だったと思う。
そのため、本書の筋運びに意外性を持たせる必要はなかったはずだ。
本書で描かれるカルト教団。その姿から思い起こせるのはオウム真理教だ。まだ、記憶に新しい一連の事件と教祖の逮捕劇。
果たしてあの凶行によって、カルト教団がはびこる芽は全て摘まれたのだろうか。
私はそうは思わない。
人が生きる意味や目的はどこにあるのか。人は何を目指せば良いのか。
おそらくその真理はどこにもなく、誰にも教えられないはずだ。
結局、その意味は一人一人が探し求めるしかない。
その道は一生を賭けてもどこにも見当たらない可能性が濃い。道を探すことに疲れ諦めた人々が宗教に救いを求める。その図式が存在する限り、宗教はこれからもあり続けるだろう。そしてカルト教団も跳梁することだろう。
もし文学が、少しでも宗教のかわりになる存在であるとすれば、本書もその中の一つに加えられるべきだと思う。
‘2019/02/21-2019/02/26

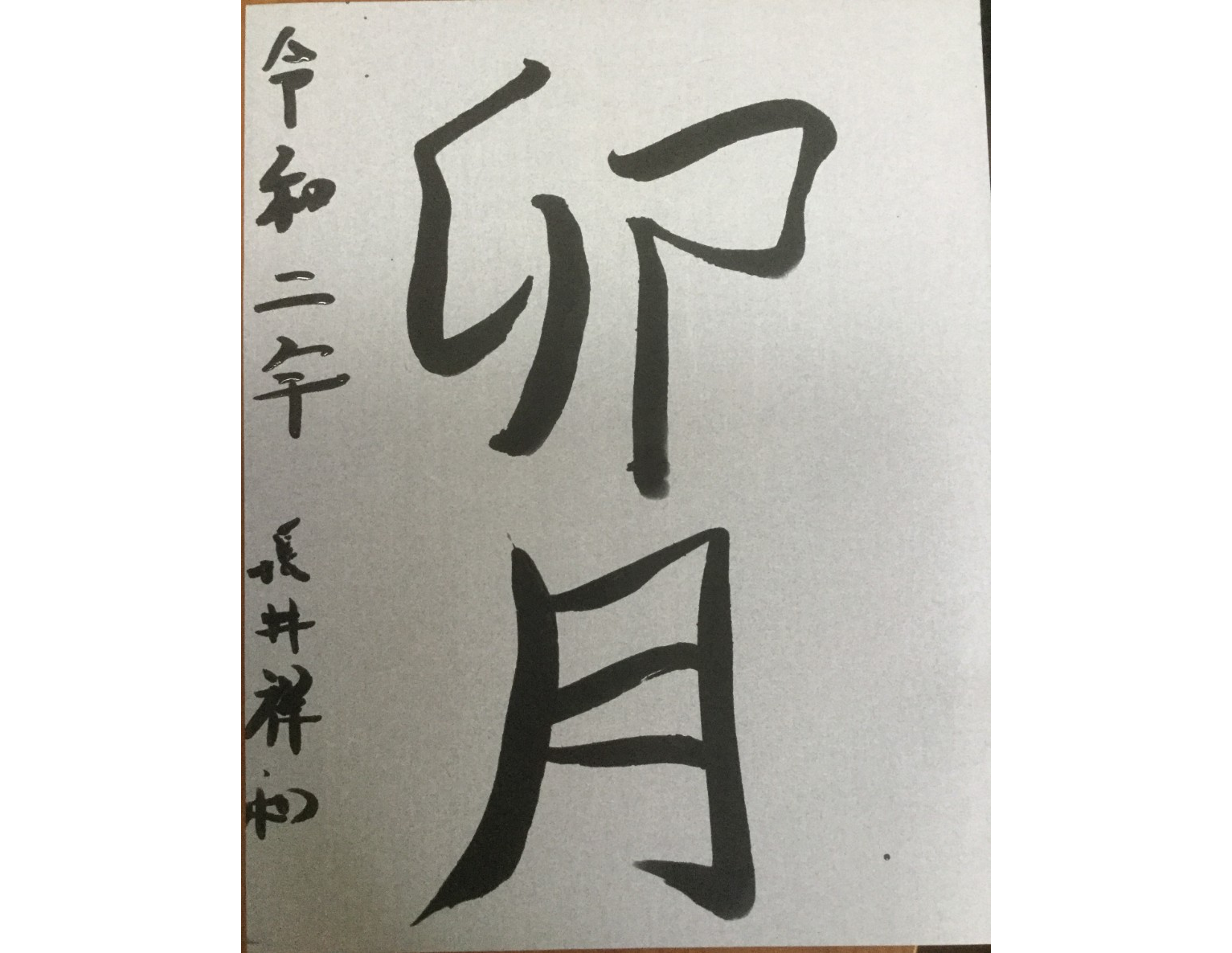

コメント