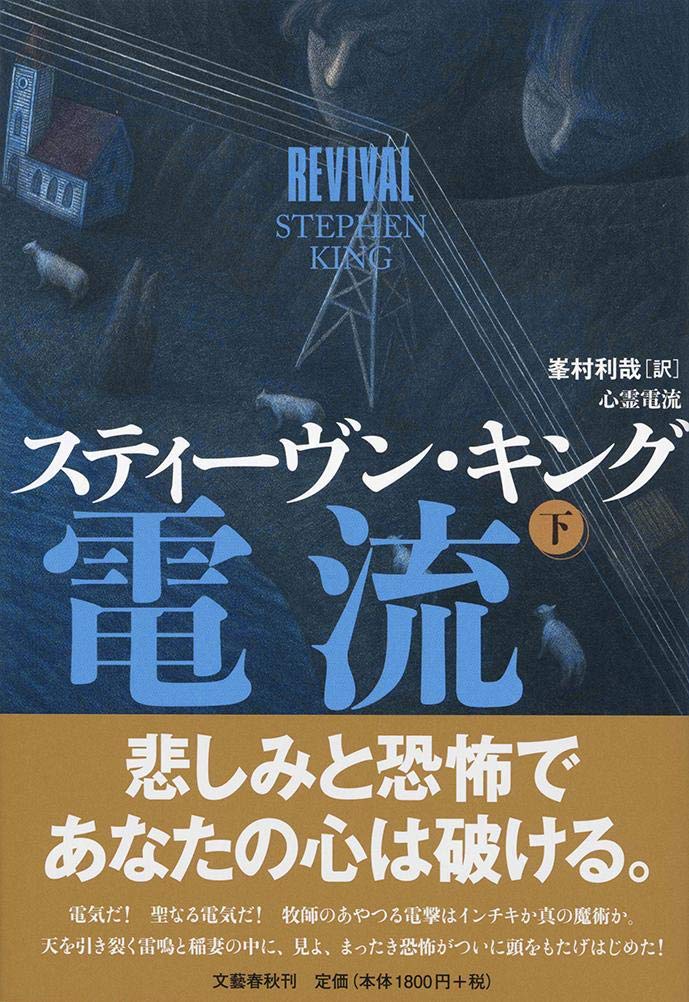
二人のなれ初めから、約二十年の間、離ればなれになっていたジェイミーとジェイコブズ師の数奇な縁。
一度は身を持ち崩しかけていたジェイミーは、再会したジェイコブズ師から手を差し伸べられる事で身を持ち直す。そして、それを機に二人の縁は再び離れる。
ジェイミーは、ジェイコブズ師から紹介を受けた音楽業界の重鎮のもとで職を得て、真っ当な生活を歩み始める。そして数年が経過する。
ジェイミーが次にジェイコブズ師の名を目にした時、ジェイコブズ師の肩書は、見せ物師から新興宗教の教祖へと変わっていた。電気を使った奇跡を売り物にした人物として。
かつて信仰に裏切られたジェイコブズ師が、今度は自ら信仰の創造主となる。その動機には何やら不穏なものを感じさせる。
それどころか、ジェイコブス師の弁舌に魅せられたコミュニティまでできている。太陽教団やマンソンが率いた教団のような。
ジェイミーは、ジェイコブズ師との数十年にもわたる因縁に決着をつけるため、再び会いにゆく。
老いたジェイコブズ師は、自らの研究の集大成として、ジェイミーをとある場所へと誘う。
そこは、彼らが最初に出会った街の近くにある、雷を集める自然の避雷針スカイトップ。
ひっきりなしに雷が落ちるこの場所を舞台に、ジェイコブズ師は最後の忌まわしい実験に乗り出す。
それはまさに、神も恐れぬ冒涜。おぞましく不吉な結末が予感できる。
この結末は、著者が今までの傑作の中で描いてきたカタストロフィーと比べても遜色ないっq。
ただ、今までのカタストロフィーは、壮健な人々によって演じられてきた。
それに比べて、本書では老いてゆくジェイコブズ師によって成されてゆく。そのため、演者としての迫力は弱い。
ただ、本書で展開される世界の秘密のおぞましさ。そこにホラーの帝王である著者の本領が発揮されている。
ジェイコブズが呼び出したおぞましき世界。そこでは、神の冒涜を主題とした本書のテーマを如実に体現した、究極の終末とも言える世界だ。
神の救い、神の恩寵、神の御手。それはどこにもない。ひたすらに救いようのない世界。
私たちが信ずる来世のおぞましさ。
今まで、神の名において未来への希望を掲げていた教団は、神の名を借りて、人々をたぶらかしてきた。
われわれは何のために生き、そして何のために死んでいくのか。
本書の結末は、そのような問いをはねつけ、絶望に満ちている。
果たして、ジェイコブズ師が一生をかけて神に背き続けた復讐は、この世界を呼び出す事によって成就したのだろうか。
なぜ、私の妻子は無残に死ななければならなかったのか。なぜ私はそれほどまでの仕打ちをくだされなければならないのか。私が神に何をしたというのか。
絶望と呪いに満ちたジェイコブズ師による実験。
その目的が残酷な現実とは違う、理想の世界を見ることにあったとすれば、神の虚飾の裏にあるおぞましい世界を呼び出した事は、牧師の人生にとって最後のとどめとなったはずだ。
本書は、あくまでも神の不在と神への冒涜が主題となっている。
もちろん、本書で描かれた世界が真実とは限らない。来世は誰にも見えない。
だが、神なき世界の真実とは、案外、このようなものなのかもしれない。
本書のカタストロフィーは、それを主宰するジェイコブ師が老いているため、迫力に欠ける事は否めない。
だが、現れた世界の圧倒的な欠乏感。そこに、今までの著者の作品にはない恐ろしさを感じる。
それは、上巻のレビューにも書いた通り、ホラー作家として突き抜けた極みだ。
神の徹底的な否定。そして、私たちが真実と信じているはずの科学技術、つまり電気が引き起こす奇跡の先に何が待っているのか。
本書は著者による不気味な予言ではないだろうか。
あわれなジェイコブズ師がまだ敬虔な牧師だった頃、ジェイミーたちに示した電気じかけのキリスト。
それはまさに、今の世の中に氾濫する価値観の象徴である。
私たちは一体、何を頼りにこれからの世界を生きていれば良いのだろうか。
宗教もだめ、科学技術もだめ。では何が。
そんな戸惑いを尻目に、時間は私たちを等しく老いへと追いやる。
下巻では、上巻でジェイミーの初体験の相手となったアストリッドが老いて死に瀕した姿で登場する。
その残酷な現実は、まさに本書のテーマそのものだ。
人は誰もが老い、そして誰もが取り返しのつかない人生を悔やむ。誰もその生と時間を取り戻すことは不可能だ。
結局、人間にとって唯一の真理とは、時間が人を死に追いやってゆく事に尽きるのかもしれない。
だが、人はその事実を認めようとせず、欲望や見栄や見かけの栄華を追い求める。ある人は神や宗教を奉じ、自ら信じたものを信じて時間を費やす。
そのような人生観にあっては、死さえも救いとなりうる。本書には何度か、このような文句が登場する。
「永遠に横たわっていられるなら、それは死者ではない。異様に長い時の中では、死でさえも死を迎えうる」(263ページ)
それに比べ、ジェイコブス姿が呼び出した世界の寒々としたあり様。それはまさに無限の生。無限に苦しみの続く生なのだ。死してのちも続く無残な生。
おそらく著者は、老境に入った自らの人生を顧み、本書のような福音のない世界を著したのだろう。
そして、その事実に気づくのはたいていが老年に入ってからだ。
私はまたその年齢に達しておらず、自分の人生を充実したものにしようと、一生懸命、日々をジタバタと生きている。
私の考えが正しいのか、それとも間違っているのか。それは死んでからの裁きによって決まるはずだ。そもそも永遠の無が待っているだけかもしれないし。
本書に唯一の救いがあるとすれば、救われない未来が待っていたとしても、本書によってある程度は免疫が得られる事だろうか。
でも、著者は神の背後に覆い隠されていた言いにくいことをズバリと書いた。本書は、ホラー作家としての著者の畢生の作品だと思う。
著者にとって、もはや思い残すところがない。そう思う。
‘2019/5/19-2019/5/20
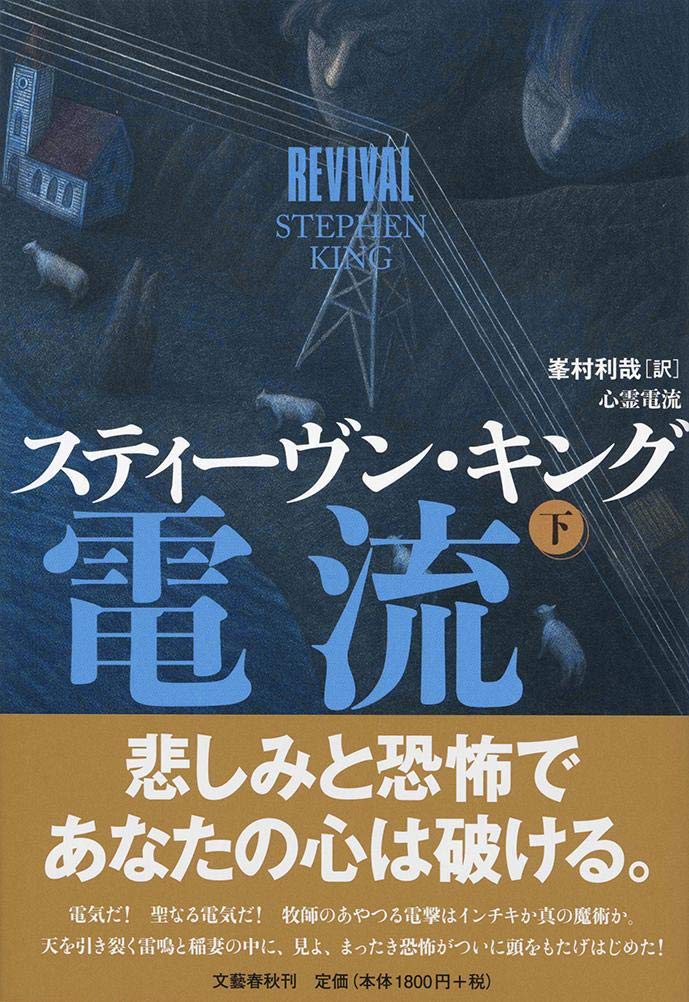
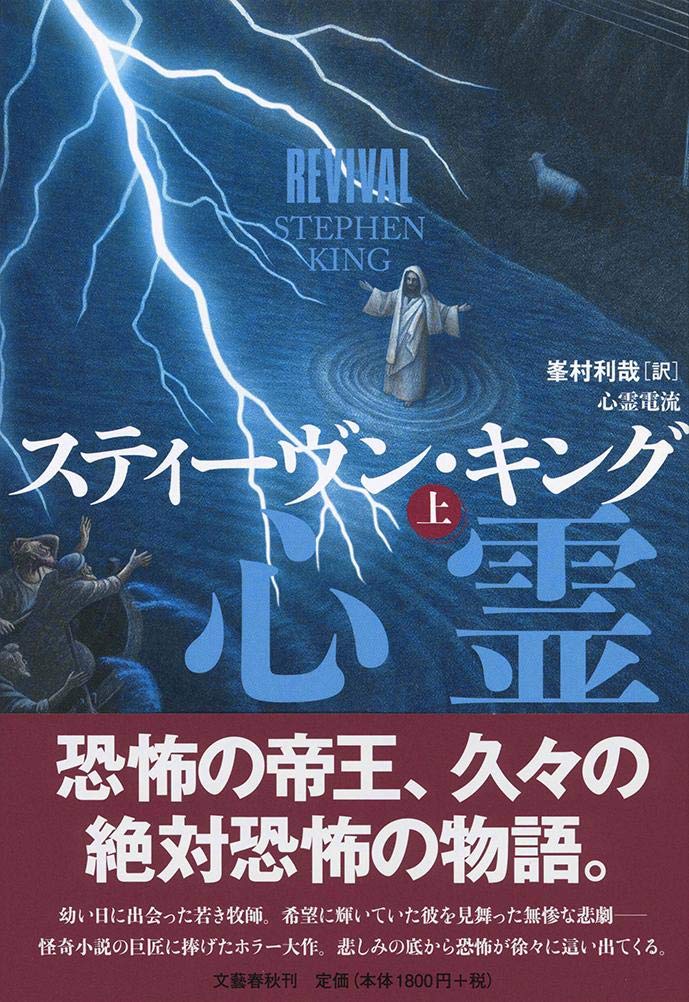
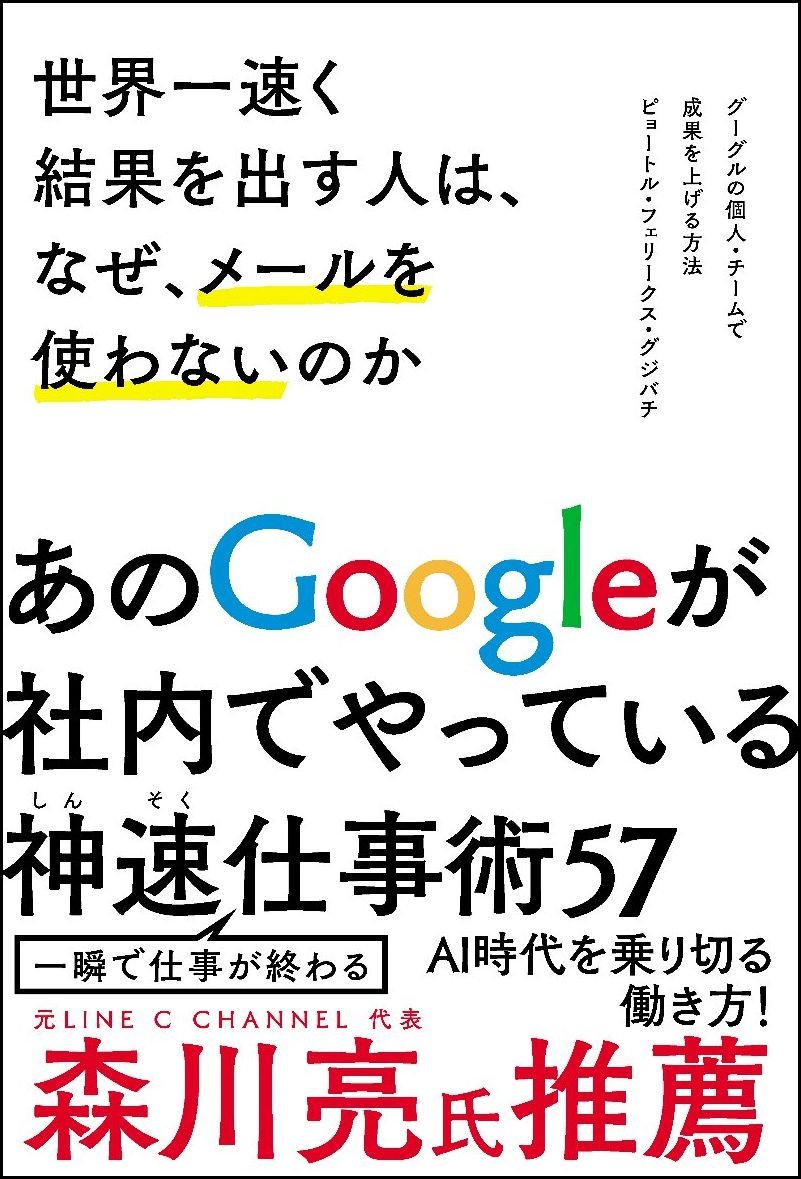
コメント