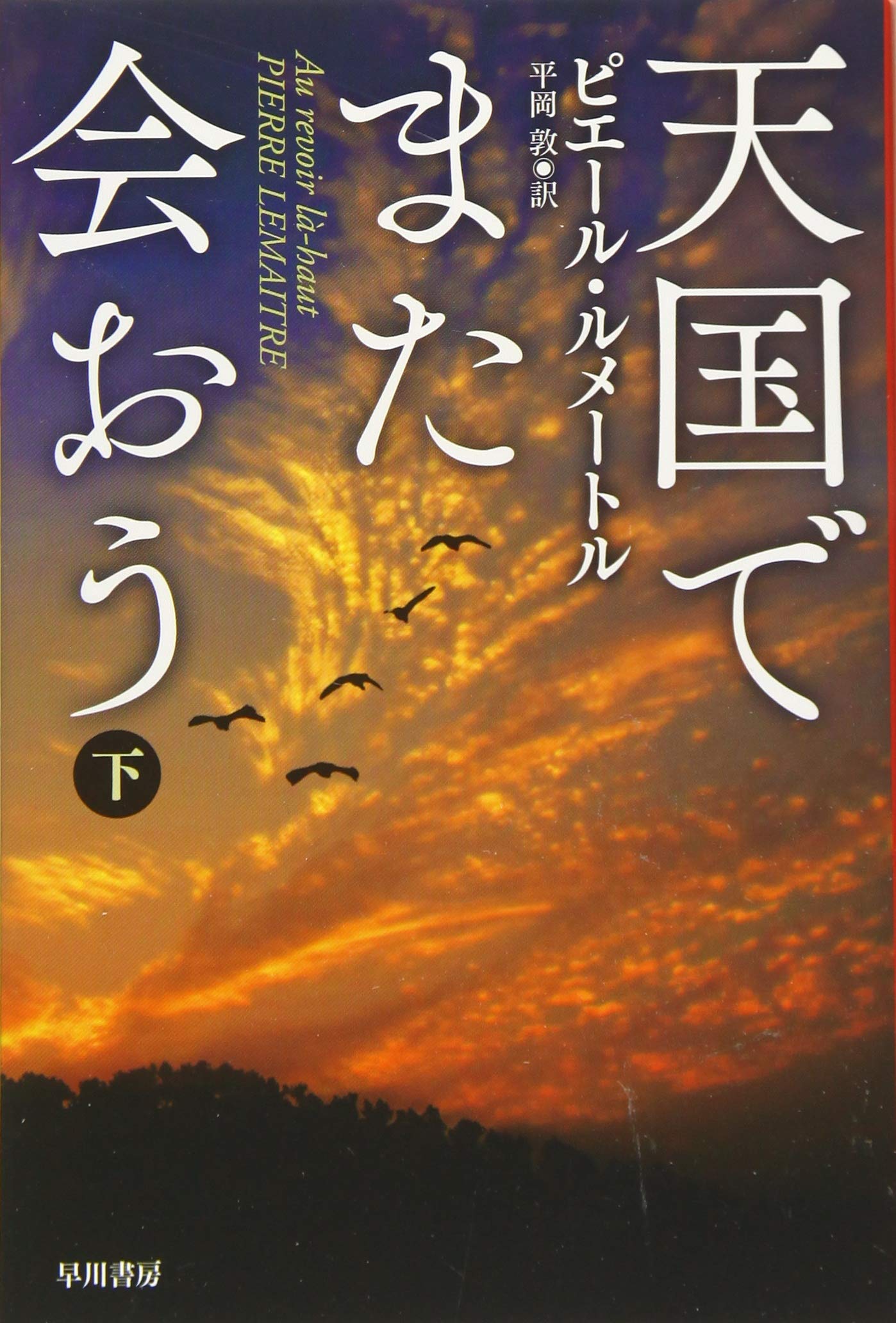
上巻では、戦争の悲惨さとその後の困難を描いていた。
その混乱の影響をもっとも被った人物こそ、エドゥアールだ。
戦争で負った重い傷は、エドゥアールから言葉と体の動きを奪った。さらに破壊された顔は、社交の機会も失わせた。
そのような境遇に置かれれば、誰でも気が塞ぐだろう。エドゥアールも半ば世捨て人のようにアルベールの家にこもっていた。
ところが、顔を隠すマスクを手に入れたことによって、エドゥアールの生活に変化が生じる。
そしてエドゥアールは良からぬことをたくらみ始める。それに巻き込まれるアルベール。
本作においてアルベールは、気弱でおよそ戦いの似合わない青年である。常に他人の意志に巻き込まれ、振り回され続ける。
そのような人物すらも兵士として徴兵する戦争。
戦争の愚かさが本書のモチーフとなっている事は明らかだ。
上巻のレビューに書いた通り、戦争は大量の戦死者を生む。そして、戦死者を丁重に葬るための墓地も必要となった。戦死した兵士たちの亡骸を前線の仮の墓地から埋葬し直す事業。それらはプラデルのような小悪党によっては利権のおいしい蜜に過ぎない。
プラデルによって安い作業員が雇われ、彼らによっていい加減な作業が横行する。おざなりな調査のまま、遺体と名簿が曖昧になったままに埋葬される。
国のために戦った兵士たちの尊厳はどこへ。
国のために戦った兵士も、小悪党の前には利潤をうむモノでしかない。
そんな混乱の中、国によって兵士の追悼事業を催す計画まで持ち上がる。
そこに目を付けたのがエドゥアールだ。
その企画に乗じ、架空の芸術家をでっち上げ、全国の自治体に追悼記念碑<愛国の記念>なる像を提供すると称し、金を集める。
そんなエドゥアールの意図は、プラデルの悪事と似たり寄ったりだ。
だが、大きく違う事がある。それはエドゥアールには動機があったことだ。
戦争をタネに一儲けしようとするエドゥアールの姿勢は、戦争への復讐でもある。戦争によってふた目とは見られない姿に変えられたエドゥアールには、戦争へ復讐する資格がある。
そして、戦争の愚かさをもっとも声高に非難できるのもエドゥアールのような傷痍軍人だ。
ただし、本書の語り手はエドゥアールではないため、エドゥアールの真意は誰にも分からない。不明瞭な発音はエドゥアールの真意を覆い隠す。
そもそも、おびただしい数の傷痍軍人はどのように戦後を生きたのだろう。
戦後を描いた小説には、しばしば傷痍軍人が登場する。彼らは四肢のどれかをなくしたり、隻眼であったりする。彼らは、戦争の影を引きずった人物として描かれることはあったし、そうした人物が戦争を経験したことによって、性格や行動の動機にも影響はあったことだろう。だが、彼らの行動は戦争そのものを対象とはしない。なぜなら戦争は既に終わった事だからだ。
本書は、エドゥアールのような傷痍軍人に終わった戦争への復讐を行わせる。その設定こそが、本書を成功に導いたといってもよい。
エドゥアールのたくらみとは、まさに痛快な戦争へのしっぺ返しに他ならない。
エドゥアールの意図には金や報復だけではなく、別のもくろみもあった。
それは、エドゥアールの芸術的な欲求を存分に活かすことだ。芸術家として自分のデッサンを羽ばたかせ、それを評価してもらう喜び。
親が富裕な実業家であるエドゥアールにとって、自分の芸術への想いは理解されないままだった。それが戦争によって新たなる自分に生まれ変わるきっかけを得た。
エドゥアールにとって、戦争は単なる憎しみの対象ではない。憎むべき対象であると同時に、恩恵も与えてくれた。それが彼の動機と本書の内容に深みを与えている。
そのようなエドゥアールを引き留めようとしていたはずのアルベールは、いつのまにかエドゥアールのペースに巻き込まれ、後戻りが出来ないところまで加担してしまう。
一方、後戻りができないのはプラデルも同じだ。
戦争中の悪事は露見せずに済み、戦後も軍事物資の横流しによって成り上がることができたプラデル。
だが、彼の馬脚は徐々に現れ、危機に陥る。
エドゥアールとプラデルの悪事の行方はどこへ向かうのか。
そしてエドゥアールの生存を実業家の父が知る時は来るのか。
そうした興味だけで本書は読み進められる。
こうして読んでみると、第一次大戦から第二次大戦への三十年とは、欧州にとって本当に激動の時代だったことが実感できる。
社会の価値観も大きく揺れ動き、新たな対立軸として共産主義も出現した。疲弊した欧州に替わってアメリカが世界の動向を左右する存在として躍り出た。
国の立場や主義が国々を戦争に駆り立てたことは、政府へある自覚を促した。それは、政府に国民の存在を意識させ、国民を国につなぎとめ、団結させる必要を迫った。
政府による国民への働きかけは、それまでの欧州ではあまり見られなかった動きではないだろうか。
だが、働きかけは、かえって国民の間に政府への反発心を生む。
それを見越した政府は、戦争という犠牲を慰撫するために催しを企画し、はしこい国民は政府への対抗心とともに政府を利用する事を考えた。
そのせめぎ合いは、政府と国民の間に新たな緊張を呼び、その不満を逸らすために政府はさらに戦争を利用するようになった。
それこそが二十世紀以降の戦争の本質ではないかと思う。
本書をそうやって読みといてみると、エドゥアールやプラデルの悪巧みにも新たな視点が見えてくる。
そうした世相を描きながら、巧みな語りとしっかりした展開を軸としている本書。さまざまな視点から読み解くことができる。
まさに、称賛されるにふさわしい一冊だ。
‘2019/6/29-2019/7/2



コメント