
著者がこれまたすごい本を出した。出版界をぶった切りまくっている。
その迫力は凄まじいの一言に尽きる。
本書は、筒井康隆氏の「大いなる助走」を思い出させる。
「大いなる助走」は、文学賞をめぐる内幕を暴露して読書人に衝撃を与えた。
選考委員を殺しまわる筋書き、殺される選考委員のモデルが誰かを想像させる描きかた。どれもが記憶に残る一冊だ。
ただし「大いなる助走」は、まだ出版業界が元気だった頃の作品だ。
その頃は、これほどまでに出版業界が衰退するとは、誰にも想像さえしなかったはず。というのも当時、インターネットとは軍や研究者によってほそぼそと使われるに過ぎない存在だったからだ。インターネットがここまで出版業界を脅かす存在になるなど、どこの誰が予想できただろう。
本書は今の不況にあえぐ出版業界に鋭くメスを入れている。
著者も出版業界には利害関係を持っているはず。だが、そこに遠慮の色は全くない。
ネット上には消費者の欲求を満たすコンテンツがあふれ、人々の中で読書の趣味は少数派になりつつある。
さしずめ、読んだ本のレビューを記す当ブログなど、絶滅危惧種の代表だろう。
再販制度に保護というぬるま湯に浸ったまま、抜本的な改革を怠り今に至った出版業界。
売り上げの減少を多種多様な出版点数で補おうとした結果、おおかたの本はすぐに売り場から撤去され、年をまたいで売れ続ける本はいまやごく一部になってしまった。
売れぬ作家の体たらくといったらどうだろう。作家専業で稼げる作家など、見渡しても今やほんの一握り。
原稿を集めるため、出版社は文芸雑誌を出し続けているが、その売れ行きは散々たるもの。赤字を積み上げるために出していると言っても過言ではない状態だ。
なにせ、私のような本好きの好事家ですら、文芸雑誌を読む暇がない。
読みたい本、読むべき本が多すぎて、とても雑誌まで手が回らないから。
本書に書かれていたが、世界に発信されるブログの中で日本語で書かれたものが最も多いそうだ。
それはつまり、日本人は誰もが発信したがり、自己表現をしたがる民族である事を意味する。なまじ豊かさがあり、発信する環境が整っている国、日本。
衣食住が満たされた民族が次に目を向けるのは、承認欲求なのだろう。
当ブログなど、まさに承認欲求の成れの果てなのかもしれない。
それを分かっていながら、読書ブログを一生懸命に書く私も、著者には自己表現をしたがる輩と同列に見られているに違いない。
著者の振りかざす刃、つまり本書の切っ先におびえるべきは私。いや、今の私ではない。著者の舌鋒に打ちのめされるべきは、若い頃の私であるに違いない。
本書の帯にはこう書かれている。「注意!作家志望者は読んではいけない!」と。
本書を読み、それでもなお印税生活への憧れを保ち続けられる人は果たしてどれほどいるだろう。
それほどまでに、本書が描く出版業界の夢や希望の底は闇に塗りつぶされている。
その闇は本屋の店頭に並ぶ平積みの本と印税生活という甘い言葉に覆われ、隠されている。
本書を出版した太田出版は、これまでも問題となる書籍を出版してきたことでよく知られている。その太田出版がこうした本を出した事こそ、切迫した危機感の表れだと思う。
本書の主人公は牛河原。元夏波書店の敏腕編集者だ。今は自費出版を請け負う丸栄社の部長として辣腕をふるっている。
丸栄者のビジネスモデルは、読者ではなく、作家志望者から出版費用を徴収することで成り立っている。自分を表現したい志望者の夢を叶えます、というわけだ。
印税生活への憧れと、自らの言説こそが認められるべき、という強烈なプライド。その自我を牛河原は絶妙にくすぐり、作家の卵に金を出させる。
その口八丁手八丁のやり口が本書にはこれでもか、と描かれる。そして牛河原が前職の夏波書店を辞めた理由こそ、作家や取次、出版者、書店がひしめき合う出版業界への絶望だ。
上に書いた出版業界の状況は、牛河原が本書の中で発するセリフの中で言い尽くしている。
文学賞の現状、文庫のビジネスモデル、出版の広告、わがままな作家たちの末路。
それほどまでに牛河原は絶望している。出版業界に。おそらくそれは著者も同じであるはずだ。
「「出版社にいる連中は、口では文化的な仕事などと偉そうなことを言っているが、所詮はその程度の世界だ。結局は─金なんだ」」(186p)
本書はしかし、一方的に出版業界をこき下ろすだけの作品ではない。
このセリフをはいた牛河原を著者はこう描写する。「牛河原は初めて少し寂しそうな顔をした。」(186p)
牛河原がここまで出版業界に冷笑的になったのには理由がある。
そこに至るまでは、多くの作家の上にあぐらをかき続けた出版業界と、それにも関わらず次々に生まれ出づる作家の群れに閉口した牛河原の絶望がある。
ただし、この絶望は、希望や理想の裏返しでもある。牛河原にも文学や出版業界への希望や理想があった事は見逃してはならない。むしろ、抱いていた希望や理想が裏切られたからこそ、牛河原はシニカルな態度を取るようになったのだといえる。
そして、牛河原の怒りとは、当然、著者の怒りでもあるはずだ。
もっとも、著者は本書の中で自らをも客観視してみせる。
「元テレビ屋の百田何某みたいに」(206p)
「まあ、直に消える作家だ」(206p)
著者は自身もだらしない出版界に身を置いている現状をわきまえつつ、なんとかしてこの業界を変えたいと願っているのだろう。
そのためには何をすべきか。
本書の後半は、牛河原の属する丸栄社のビジネスモデルをよりアコギにした商法を駆使した狼煙舎が攻勢をかける。
対する牛河原は、それを詐欺だと世に告発する。そこには牛河原なりの正義感が顔をのぞかせる。
もちろんそれは著者の思いでもあるはずだ。
そして著者は、本書のラストで出版界も捨てたものじゃないというエピソードまで登場させる。
このエピソードを読むと、著者が嫌いなのは本書で散々罵倒してきた出版業界であり、本や文芸そのものはむしろ愛しているのだと確信できる。
著者のその思いが本書の余韻を清々しくしている。そして、本好きにとっては救いのある結末となっている。
‘2019/01/29-2019/01/29


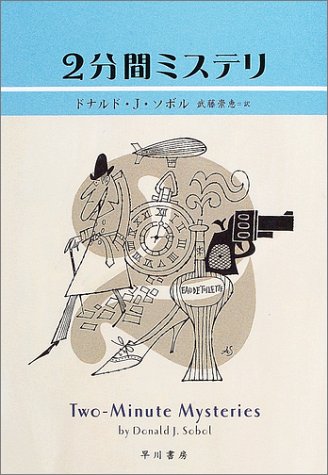
コメント