
私がまだ読んでいない「加賀恭一郎」シリーズは数冊ある。本書もその一つ。本作は連作短編集だ。五編が収められている。
本書の全体に共通しているテーマは女性のうそについて。女性がつくうそにはさまざまな目的がある。その多くは自らの過失や犯した罪を隠すため。そんなうそはその場しのぎであり、入念な計画もなく、狡知をこらしてもない。全ては急ごしらえなうそ。だから聡い人物にかかるとばれてしまう。それが加賀恭一郎であればなおさら。
どの謎も、あとから分かればいかにもその場しのぎの偽装だ。ところが、偶然が重なったり、部外者が後からみた程度ではすぐには見当がつかない。しかし、わずかなほころびが加賀恭一郎には矛盾と映る。そしてそれを見越した巧妙なカマをかけると、背後の犯罪が暴かれる。すべてが推理小説の、捜査の常道に沿っている。五編ともお見事だ。ただし、この後に発表される『赤い指』に比べると、少し物足りなさは感じた。本書は「加賀恭一郎」シリーズでも中期に位置する。『赤い指』は冷徹な頭脳を持つ加賀恭一郎を豊かな人情を秘めた魅力的な人物として書かれた傑作だ。「加賀恭一郎」シリーズはここで確立したともいえる。それからすると、本書は短編集だ。どちらかといえば優れた頭脳の持ち主としての加賀恭一郎が前面に出ていた。キャラクターの魅力が確立される直前の作品といえる。
だが、加賀恭一郎が持つ別の魅力は、五編においてきっちり書かれていた。それは謙虚さだ。聞き込みのセリフの一言一言に、加賀恭一郎の謙虚さがにじみ出ている。そういえば、このシリーズ全体に通ずるのが、物的証拠より聞き込みによって事実に迫ることを重んじていることだ。物的証拠とは聞き込みで得た結果を補強するものでしかない。聞き込みによって事件の全貌を見いだしてゆく加賀恭一郎の特徴が、本書ですでに確立しているのがわかる。
「嘘をもうひとつだけ」
「冷たい灼熱」
「第二の希望」
「狂った計算」
「友の助言」
とある五編のそれぞれのタイトルは、それぞれを読み終えてから見てみると、言いえて妙なタイトルになっている。その中でも「冷たい灼熱」という反語的なタイトルをもつこちらは、一番ひねりが効いているように思った。内容も「冷たい灼熱」は、他の四編と一線を画している。本編のキーとなるのはとある悪癖だ。だが、最期までその悪癖の固有名詞は明かされないままだ。多分業界への配慮なんだろう。けれど、それがかえって印象に残った。
うそとは多くの場合、自分にとっての利益が他人にとってのそれと相反する場合に生まれる。自分の願う利益が他人にとって不都合な場合、それを押し通すためには事実を隠したりうそを言ったりしなければならない。それは本来、許されることではない。だが、人はうそをついてしまう。もしばれた場合には社会から制裁が科される。だが、それを覚悟してまでうそをつく。人をそうまでさせる理由は人によってそれぞれだ。そこをいかに現実にありそうな理由として書くか。そして、うそを付くほか選択肢がなくなった、追い詰められた人間の弱さをどうかくのか。それもまた、推理小説にリアルさを与える。しかも短編の場合は、うその原因を簡潔に記さなければならない。推理小説の作家の腕前が試される点はここにもある。そこがしっかりと説得力を備えて書かれているのが、本書の魅力だ。
そもそも推理小説とはうそを出発点としなければ成り立たない。動機よりもアリバイよりもトリックよりも、まずはうそが優れた短編を生む。どうやってうそにリアルさを持たせるか。どのようにうそに説得力を持たせるか。そして、いかにして簡単にばれないうそを仕込むのか。優れたうそをひねり出すのは、簡単なようでとても難しいはず。あえて言ってしまうと、推理小説を書く作家とは、とびきりのウソツキでなければならないのだ。多分、著者はそれを十分に理解していたはず。だからこそ本書が生まれたのだろう。うそに目を付けたのはさすがだ。
冒頭に書いた通り、本書は推理小説の短編はこう書くべき、の見本だ。「加賀恭一郎」シリーズというより、すぐれた推理小説の短編として読むのがオススメだ。
‘2017/08/11-2017/08/12

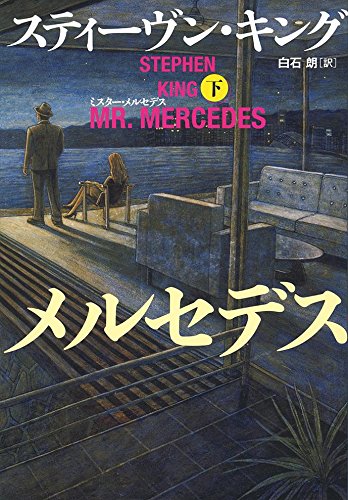

コメント