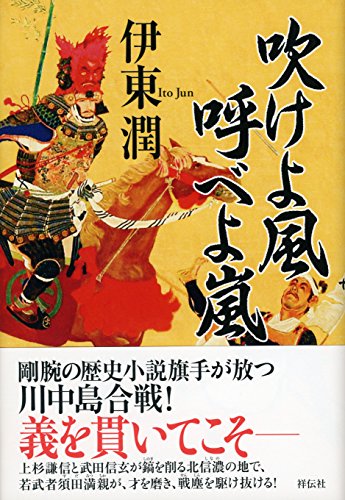
川中島にいまだ訪れたことがない私。それなのに、川中島の戦いを描いた小説を読む経験だけは徐々に積んでいる。そして合戦シーンに血をたぎらせては、早く訪問したいと気をはやらせている。そんな最近だ。友人が貸してくれた本書もまた、私の心を川中島に向かわせようとする。
だが本書の中において、川中島の戦いが描かれるシーンはほんのわずかしかない。386ページある本書の終盤、多めに数えてもせいぜい60ぺージほど。では、あとのページは何の描写に費やしているのか。それは、村上義清軍の戦いを追うことで費やしている。本書は上田原の戦いから始まる。上田原の戦いといえば、村上義清と武田晴信によってなされた信濃の覇権をめぐる一連の戦いでも初期に行われた合戦だ。上田原の戦いで武田軍の侵攻を退けた村上軍は、続けて武田軍に後世、砥石崩れと称される程の痛手を負わせる。北信濃に村上義清あり、と高らかに謳うかのような戦い。本書の主人公である須田満親は、従兄でかつ刎頸の友である信正とそれらの戦いを間近にみていた。
だが、村上義清がいくら北信濃で武名を高めようとも、勢力としては信濃の一地域を治めるだけの存在にすぎない。そもそも、信濃とは諸豪族が割拠する地。戦後史においては、信濃における二大勢力として小笠原長時と村上義清の両雄が並び称されていた。だがそれぞれは勢力として小粒。それゆえ、甲斐から侵略を進める武田軍に徐々に突き崩されてゆく。しかも武田軍は武で成果がなければ調略を試すなど、柔軟かつ老練な攻め手を繰り出してくる。硬軟取り混ぜた武田軍の攻撃に徐々に勢力を削られてゆく村上軍。その調略の先は、信正の親である須田信頼にも伸びる。その結果、須田信頼と信正親子は武田軍にくみする。つまり、須田満親と信正は敵味方となってしまうのだ。満親を襲った凶報は、満親と信正を互いにとっての仇敵に仕立て上げることになる。上田原の合戦見物の際は、弥一郎、甚八郎と呼び合っていた二人。それが憎み合い戦場で剣を交えるまでに堕ちてしまう。戦国の世の習いの無残さを思わせる展開だ。
仲の良かった従兄が敵味方に分かれる。そんなことは下克上のまかり通る戦国時代にあって特に珍しくもなかったはず。そして豪族が相打ち乱れ、合従連衡を繰り返す信濃にあってはより顕著だったに違いない。つまり戦国期最大の合戦として後の世に伝わる川中島の戦いとは、ついにまとまる事を知らぬまま、乱れに乱れた信濃が堕ちるべき必然だったのだ。信濃の地で戦われた合戦でありながら、甲斐の武田と越後の上杉の戦場となった川中島とは、つまるところ信濃の豪族たちのふがいなさが凝縮した地だったともいえる。
だが、その事実をもとに須田満親を責めるのは酷な話。彼は村上家にあって生き延びるため、そして須田家を存続させるため、懸命に働く。満親の働きは、村上家がいよいよ武田軍の攻勢を防ぎきれず上杉家を頼る際に彼自身の運命を切り開く。村上義清によって上杉家への使者に命じられることで。それまでに使者として上杉景虎の知己を得ていたことが上杉家への使者として適任だったのだ。それは、須田満親を次なる運命へと導く。つまり、川中島の戦いへと。満親の嫁初乃はもともと信正の妹として満親に嫁いできた。だが、武田軍の調略が須田家を引き裂いたため、兄信正と初乃は敵対することになる。そんな運命に翻弄されながら、彼女は世をはかなむことなく満親へ付き従い越後へと落ち延びる。本書で描かれる彼女の運命は戦国の時代の過酷さ、そして確固たる権力に恵まれなかった信濃に生まれた女子の運命を如実に書き出している。
親しさの余りに、憎さが百倍したような満親と信正の関係。それは、幾度もの運命の交錯をへてより複雑さを増してゆく。そしてついには川中島の戦いでは上杉軍と武田軍として相まみえ、剣を交えさせることになるのだ。
残された記録による史実によれば須田満親は1598年まで存命だったようだ。つまり満親は川中島を生き残ったのだ。では信正はどうだったか。史実によれば武田家滅亡後に上杉家に属したと伝わっている。だが、本書では川中島以降の両者には触れていない。あるいは、上杉家で旧交を温め直したのか、それともかつての反目を引きずりながら余生を過ごしたのか。本書には、上杉家での二人の邂逅がどうだったかについては触れておらず、読者の想像に委ねている。
そのかわりに著者は、川中島の戦いで満親と信正に剣を打ち合わせることで、二人のその後に著者なりの解釈を示している。満親に勝たせることで。そして満親にとどめを刺させないことで。その瞬間、二人の間には弥一郎と甚八郎の昔が戻ったのだ。「禍根を断っては、武士は鈍ります。禍根あってこそ、武士はよき働きができます」とは川中島の戦いの後、謙信と語らった際の満親のセリフだ。それを受けて謙信もこう返す。「もう一太刀か二太刀見舞えば、わしは信玄を殺せた」「だがな、馬を返して四太刀目を浴びせようとしたところで気づいたのだ。欲が勝つか義が勝つかは、力で決めるものではなく、天が決めるものだとな」「そうだ。欲に囚われた者は欲に滅ぼされる。最後に勝つのは義を貫く者だ。つまり禍根を断たずとも悪しき者は自ずと立ち枯れる」
ここでいう欲とは武田信玄の領土拡張欲であり、義とは毘沙門天を戴く上杉謙信の信念を表わしている。この二つの概念は、両者を比較する際によく見かける。だが、有名な一騎打ちをこういう解釈で描いた事に、本書の真骨頂がある。川中島の合戦で敵味方に相まみえる事になった須田満親と信正の従兄同士。二人の運命に小豪族の置かれた運命の悲哀を表しただけでなく、義と欲の争いを禍根を断つ形で決着させず、人の生き方として歴史の判断にゆだねた著者の解釈。これもまた、一つの見識といえる。
おそらく、川中島の戦場には、幾多の入り組んだ、長年に渡って織りなされた運命の交錯があったはずだ。満親と信正。信玄と謙信。信繁と景家。川中島には彼らの生きた証が息づいている。人の一生とは何を成し遂げ、何に争わねばならないのか。そんな宿命の数々がしみ込んでいるのだ。そのことを新たに感じ、人の一生について感慨を抱くためにも、私は川中島には行かねばならないのだ。
‘2016/12/24-2016/12/28


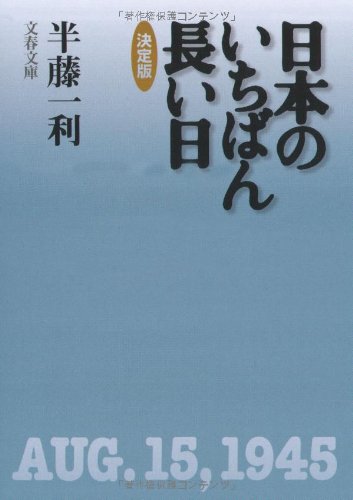
コメント