
意外なことに、本書は著者にとって初めてのミステリーらしい。
考えてみれば、今までに読んだ著者の本は、SFか歴史小説だった。
つまり、現代を描いた小説はまだ著していなかったのだ。
だが、それを忘れさせるほど本書は素晴らしかった。
まず、ネット上で呼びかけられた自殺志願の若者が集まる、という設定が今の世相をじかに示している。
今も、若者への自殺を教唆する事件がたまにニュースを賑わす。
今の世に絶望して死を選ぶ若者のいかに多いことか。
私たちが自殺を望む若者にしてやれることは何なのか。
おためごかしに人生を肯定してみせても何も変わらない。何の救いにもならない。
人はいつか、必ず死ぬ。
その時期を少しだけ早めることの何が悪いのか。
死に急ぐ若者たちの切実な問いに対し、真剣に答えようとする時、その人の人生への考えや死生観はあらわになる。
死に至る動機は人の数だけあり、それを止めることは本人だけができる。
周りができるのは、本人に気づいてもらうための働きかけぐらい。根本からの気づきは本人に委ねられる。
私があえて言うとするなら、生とは主体的に生きる喜びだろうか。
自分で自分の生き方をコントロールできると思えた時、死は誘惑にすらならない。
死の空虚さこそは、自分の人生を無に委ねることであり、耐えがたい。
だが、私がそのように思えるようになったのも、ようやく40を超えてから。
それまでは幾度も死の誘惑が脳裏にちらついた。鬱も経験したし、仕事にがんじがらめに縛られるつらさも経験してきた。怒鳴られ、詰められ、追い込まれ。出口もなく、光も見えない毎日。
だから、安楽死を求める若者たちの意思もわかる。そして、死ぬ以上は後の憂いをなくしてから死にたいと言う彼らの気持ちも理解できる。
そこまで死を決意した人に対して、できることは、あなたがいなくなると寂しいから死なないでくれ、と呼びかけるぐらいだ。
だが、それとて生者の側からの都合にすぎない。
本書は、死を望む十二人の若い男女がとある廃病院に集まる。それぞれがネット上での管理者の呼びかけに応じて集まったが、お互いに面識はない。
それぞれの若者が真剣にこの世から去りたいという切実な思いを抱えている。
ルールは一つ。実行にあたっては全員の意思が一致すること。
ところが、十二人が集まった時、そこには十二人に先んじて横たわる少年がいた。
彼は誰なのか。果たして誰によって手をかけられたのか。
謎が憶測を呼び、憶測が疑心につながる。
死ぬという全員の意思がゆらぎ、少しずつ事態が混迷へと向かってゆく。
初対面の者同士。ある者は反目し、ある者は協力し合う。
本書が面白いのは、全員が死を恐れないことだ。
死を前提として集まっているので、恐れはない。だが、死に当たってはきれいさっぱり、何の憂いもなく死にたい。
だから、ミステリーにありがちな防衛本能から来る思惑のさぐり合いは本書にない。私欲や物欲も。
それがとても新鮮だ。
人間とは死を恐れなくなった悟りの境地に達してもなお、自らの置かれた現実を自らの心で納得したい生き物なのかもしれない。
だから、仮想現実が用意されればそこに逃げ込む。
現実が自分の力でも他人の力を借りてもどうしようもなくなると、死を選ぶ。死をもって矛盾にピリオドを打とうとする。
それぞれが抱える思惑や奉じた理想でぶつかる様子を、著者は十二人のそれぞれを書き分けることで鮮やかに描き出す。
死を選ぶ理由はさまざまだ。
若い身空で死を望む若者の理由の深刻さを考えたことはあるだろうか。
私も本書を読んで、なるほど、こう言う理由でも死にたがるのか、と蒙を啓かれた思いだ。
本書の後半で、若者たちがそれぞれの素性を明かし、なぜ死にたいのか、お互いに告白し合うシーンがある。
そこで気づくのが、普段の慌ただしい日々で、そうした会話を交わす機会がどれほどあるのかについての疑問だ。
若い頃には思い通りにならない人生に悲観し、中年に差し掛かれば日々の責任の重さとそれをこなす忙しさに苦しむ。
老いてからは、いずれ訪れる死を悟ろうとジタバタする。
人生を通して死を考えずに過ごす人もいるだろう。だが、それでも晩年になれば死の現実は否が応でも死の現実は迫ってくる。
なのに人は死を語らない。死を考えない。それは日本の宗教的な欠点なのだろうか、とすら思う。
もっとそういう腹を割った議論が日常で行われれば、死を選ぶ人は減るだろうし、世の中から軋轢や諍いはもっと減るのではないだろうか。
そう思いたくなるほど、死をめぐる会話は世の中から排除されている。
それは、考える習慣が貧しいからなのだろうか。
考える機会の少なさは、本書を読んでいると明らかだ。
本書はその考える機会を与えてくれる本だ。
十二人の誰がみなを欺いているのか。それぞれの視点から事細かに行動が描写されてゆく。そのどこに矛盾が潜んでいるのか。
本書には考えるべき内容が含まれている。
本書は読者の洞察力を養い、それとともに死への思索を深めさせてくれる。
結局、生きていくとはどういうことか。
何が人生なのか、どこがゴールなのか。死ぬまでの時間、生の意味を考えさせるゲームにすぎないともいえる。
もちろん、本書にはミステリーとしての王道も踏まえている。
いくつもの伏線が敷かれ、最後には思わぬ謎が明かされる。
そうした楽しみも含みつつ、考える習慣へと読者を誘っている。
そこが素晴らしい。
‘2019/12/17-2019/12/19


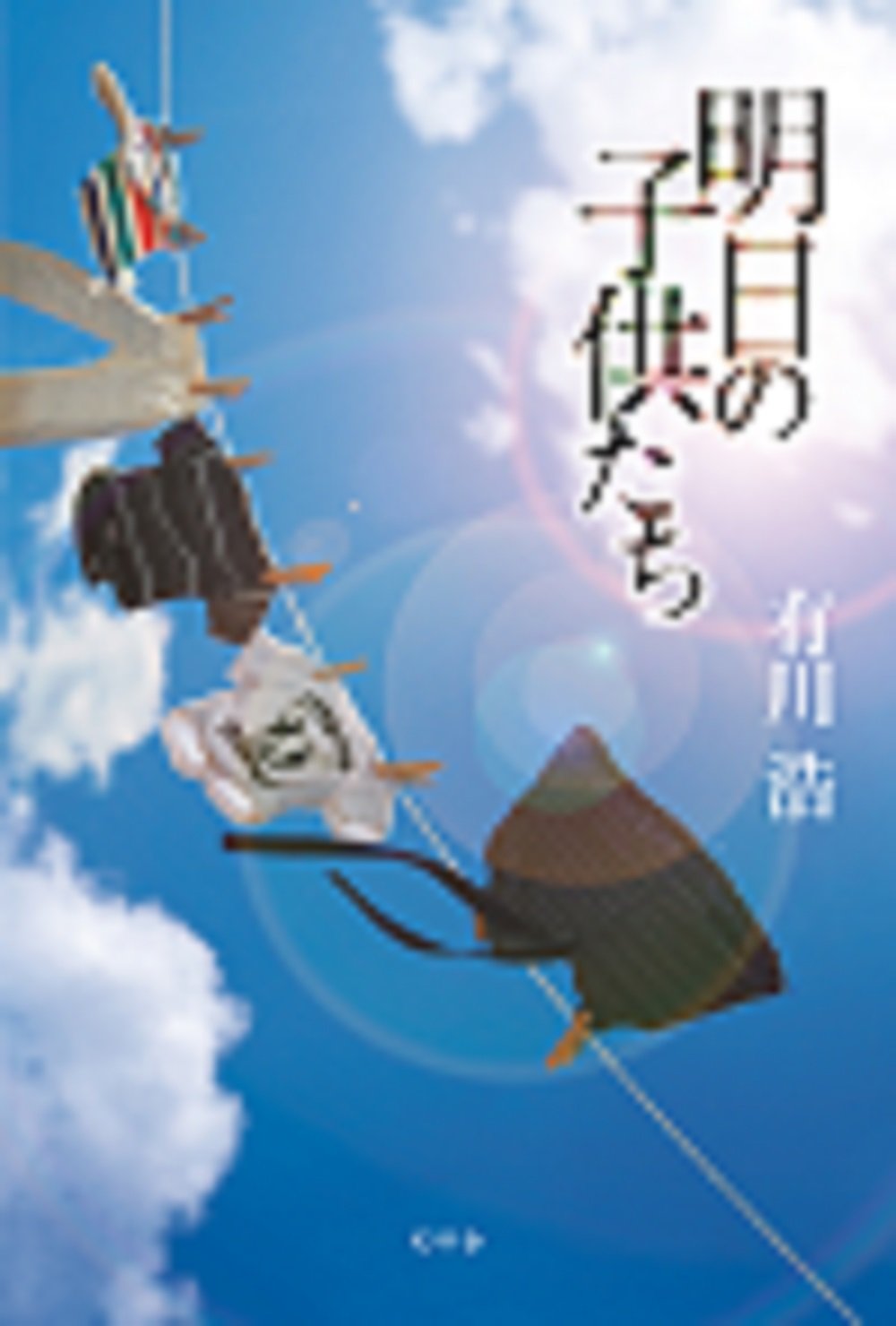
コメント