
フィクションのエルドラードと銘打たれたこのシリーズに収められた作品は結構読んでいる。ラテンアメリカ文学の愛好者としては当然抑えるべきシリーズだと思う。加えて本書の訳者は寺尾隆吉氏。とあらば読むに決まっている。氏の著した『魔術的リアリズム』は、2016年の私にとって重要な一冊となったからだ。
本書は三編からなっている。それぞれが味わい深く、優れた短編の雰囲気を醸し出している。
「別れ」
表題作である。訳者の解説によると、著者は本編を偏愛していたらしい。著者にとって自信作だったのだろう。
海外の小説を読んでいると、描かれる距離感に戸惑うことがある。小説に置かれた視点と人や建物との距離感がつかみにくくなるのだ。日本を舞台にした小説なら生活感がつかめ、違和感なく読めるのだが。その訳は、読者である私が他国の生活にうとく、生活感を体で理解できていないからだろう。だから、生活どころか訪れたことのない地が舞台になると描かれた距離への違和感はさらに増す。それがラテンアメリカのような文化的にも日本と隔たった地を舞台としていればなおさらだ。ラテンアメリカを舞台とした本書も例に漏れず、読んでいて距離がつかみづらかった。描かれた距離の違和感が私の中でずっとついて回り、後に残った。その印象は若干とっつきにくかった一編として私に残り続けている。
本編の舞台はペルー。謎めいた男の元に届く意味ありげな封筒。それを男に届ける主人公はホテルマン。次第に泊まっている男の正体がバスケットボールの元ペルー代表であることが明かされる。そして、男を診断した医師の話によると、男は不治の病にかかっているとか。次第に明らかになってゆく男の素性。だが、男は町の人々と打ち解けようとしない。それどころか部屋に閉じこもるばかり。
ある日、男のもとにサングラスをかけた女が訪れる。すると男はそれまでとは一転、朗らかで明るい人物へと変貌する。そして、女の訪問とともにそれまで定期的に届いていた二種類の封筒が来なくなる。数週間、男の元に逗留した女が去ると、再び二種類の封筒は定期的に届き始める。さらに、男の態度も世捨て人のような以前の姿に戻る。
夏のクリスマスが終わる頃、男の元には別の若い娘がやって来る。男は山のホテルで、若い娘との時間を過ごす。口さがないホテルの人々の好奇の目は強まる。娘が去ってしばらくすると、再びサングラスの女が来る。今度は子供を連れて。さらには若い娘も再び姿をあらわす。男のもとで2組の客人は鉢合わせる。一触即発となるかと思いきや、二組は友情を結ぶかにも見える。
そうした客人の動きを主人公はメッセンジャーとなって観察する。一体この男と二組の訪問者はどういう関係なのか。町の人々の不審は消えない。彼らのそばを送迎者となって動き回る主人公までもが、町の人々の容赦ない好奇の目にさらされる。男が死病によって世を去る直前、主人公は男に渡しそびれていた二通の封筒を見つける。そして中を開いて読む。そこには男と若い娘、そして母子との関係が記されていた。そして自分だけでなく、ホテルの人々がひどい誤解をしていたことに気付くのだ。主人公の胸にはただ苦い思いだけがのこり、物語は幕をとじる。
本編は男と二組の関係が最後まで謎として描かれていたために、あいまいさが際立っていた。そのあいまいさは、それぞれの関係どころか、小説の他の距離感までもぼやけさせていたように思う。本編で距離感をつかめなかった点はいくつかある。例えばホテルと山の家との距離。そして、登場人物たちをつなぐ距離感だ。例え閑散期であっても、一人の男の動向がうわさの的になるほどホテルは暇なものだろうか、という疑問。それほどまでに暇なホテルとはどういう状況なのか。その疑問がついて回る。それほどまでに他人に排他的でいながら、ホテルが営めるほどの需要がある街。そして、繁忙期は逆に人が増えることで男の行方がわからなくなる1950年代のペルー。一体どのような人口密度で、人々のつながりはどこまで密なのか。本編を読みこむにはその距離感が肝心なはずだが、私にはそのあたりの感覚がとうとうつかめずに終わった。
なぜ距離感が求められるのか。それは本編が別れをテーマとするからだ。別れとは人と人とが離れることをいう。つまり距離感が本書を読み解く上で重要になるのだ。それなのに本書で描かれる距離感からは、男と女性たちの、男と町の人々の距離感が測りにくかった。当時のラテンアメリカの街並みを思い浮かべられない私にとって、これはもどかしかった。かつて女にもて、栄誉につつまれた男が、あらゆるものとの別れを余儀なくされる。男の栄光と落魄の日々の落差は、距離感がともなってこそ実感となって読者に迫るはずなのだ。それが私に実感できなかったのは残念でならない。男と女の悲哀。そこに人生の縮図を当てはめるのが著者の狙いだとすればこそ、なおさらそう思う。男は女たちだけでなく、人生からも別れを告げようとするのだから。
本編が人々の口に交わされるうわさとその根源となる男女の関係を描き、その中から別れの姿をあぶりだそうとしていたのなら、そこに生じる微妙な距離感は伝わらねばならない。それなのに本書が描く距離感を想像できないのは残念だった。なお、念のために書くと、著者にも訳者にも非がないのはもちろんだ。
続いての一編「この恐ろしい地獄」は、若い尻軽女を妻に持つ、さえない中年男リッソが主人公だ。リッソが妻グラシア・セサルの所業にやきもきしながら、自暴自棄になってゆく様子が書かれている。訳者によると、本編は実話をもとにしているという。それも、三行ほどの埋め草記事。それを元にここまでの短編に仕立てたらしい。
女優である妻グラシアを愛しつつ、彼女の気まぐれに振り回されるリッソ。みずからに放埒な妻を受け止められるだけの度量があると信じ、辛抱と忍耐でグラシアの気ままを受けいれようとするリッソ。だが、悲しいかな、器を広げようとすればするほど、器はいびつになって行く。浮名を流し、自らの発情した裸の写真を街にばらまくグラシア。リッソが幾たびもの別居の末、グラシアを、そして人生を諦めて行く様子が物悲しい。リッソの諦めは、すべての責任をグラシアではなく自分自身に負わせることでさらに悲劇的なものになる。そしてグラシアの破廉恥さすら、非難のまとにするどころか悲しみの中に包んでいくように。生真面目な新聞の競馬欄を担当するリッソ。真面目に実直であろうとした男が、女の振る舞いを負うてその重みに押しつぶされて行く様子。その様を男の視点だけに一貫して書いているため、とても説得力に満ちている。
「別れ」では距離感の把握に難儀した。逆に本編は、男からの視点で描かれているため距離感がつかみやすい。男と女の関係は、日本だろうとラテンアメリカだろうと変わらないということなのだろう。
最後の一編は「失われた花嫁」だ。
結婚するため、ウェディングドレスを着てヨーロッパに向かった若い娘モンチャ・インサウラルデが、結婚相手から裏切られる。その揚げ句サンタ・マリアへと戻ってくる。そして街の家に閉じこもり、庭を徘徊してすごすようになる。
街にある薬局には薬剤師バルテーが住みついていたが、助手のフンタに経営権を奪われ、店は廃墟へと化してゆく。いつのまにか店に住み着いたモンチャとともに。
本編を彩るのはただ滅び。本編の全体に滅び行くものへの哀惜が強く感じられる。ウェディングドレスを狂った老婦人が着流し、町を彷徨う姿に、美しきもののたどる末路の残酷さを著している。著者はその姿を滅びの象徴とし、本編のもの寂しい狂気を読者に印象付ける。それは、美女が骨に変わり果ててゆく様子を克明に描いた我が国の九相図にも、そして仏教の死生観にもつながっている。
モンチャの死を確認した医師ディアス・グレイは、街ぐるみでモンチャを見て見ぬ振りし続けた芝居、つまりモンチャの狂気を狂気として直視しない振る舞いの理由を理解する。
「彼に与えられた世界、彼が容認し続けている世界は、甘い罠やうそに根差しているわけではないのだ。」154ページ
私にとって著者は初体験だが、後者二つは短編としてとても優れていると思う。ただ、訳者あとがきで寺尾氏が述べているように、なかなかに訳者泣かせの作家のようだ。多分「別れ」にしても距離感をうまく訳出しきれなかったのだろう。だが、他の作品も読んでみたいと思う。
‘2017/12/01-2017/12/07
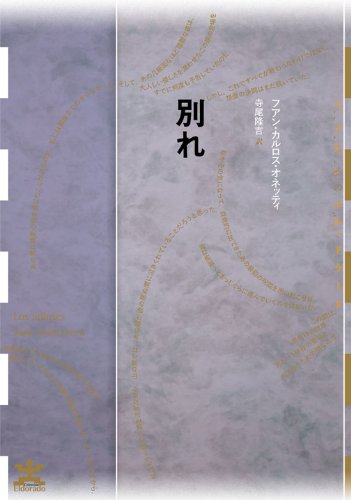
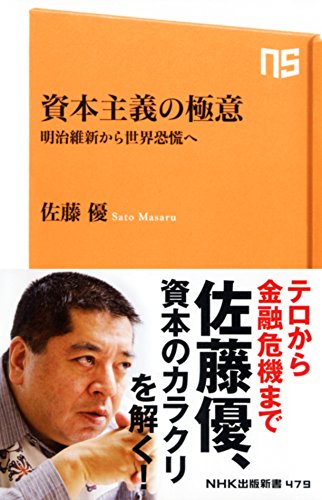

コメント