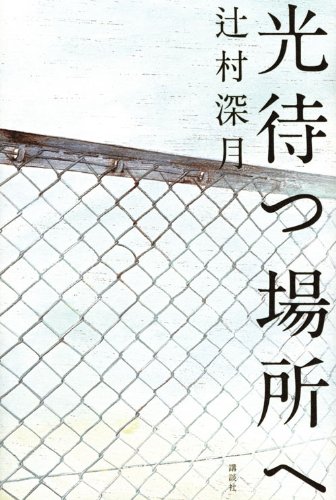
著者の作品を読むのは本書が初めてだ。
だが、著者の名前は今までもよく目にしていた。
何の予備知識もないままに読んだ本書だが、まず文体に惹かれた。
その理由は、頻繁に改行を繰り返す著者の文体のスタイルが、私とは違っていたからだ。
私には文体の癖がある。パラグラフごとに複数の文を連ねて書く。
その一方で、一文ごとはそう長くならないように、数年前に変えた。
だが、私の文でもまだ長いのだろう。短い文であっても複数の文がまとまっていれば、読者にとっては重く感じられるのかも仕方がない。
著者の文体は改行が一文ごとに行われる。それがテンポを生んでいるように思える。
私も著者のテンポのある文体をまねしてみようと思った。
そのような文体から書き連ねられる物語。
本書は三つの物語からなっている。
どの主人公も、自己の意識が強く、周囲とうまく折り合おうと苦しんでいる。
それゆえ、周りの人たちとの関係に疲れている。自らの思いの強さと周囲のバランスのずれに無意識に苦しんでいる。
自己意識とは、なかなか厄介だ。
自分が正しいと思っているが故に、その行動を改めることは難しい。
感情でも理屈でも自分が正しい思うので、その行動は改めにくい。
人間とは誰しも誤っており、自分も含めて間違っている。そうは分かっていても、振る舞いを変えるまでには踏み切れないものだ。
自らの心をあえて曲げ、周りの人とうまくやっていく術を練り上げてきたのが日本の和の心だ。
ただし、和の心とは、村や社会、会社といった組織の中だからこそ効果を発揮する。
ところが、目指すべき目標が芸術の場合は違う。個人の世界に閉じている場合、和の心はかえって足かせとなる。
芸術を究めようとする中で、いかにして自分の振る舞いを周囲と折り合わせるか。
本書に収められた三編とも、芸術が取り上げられており、自己と周囲の対立をテーマとしている。
「しあわせのこみち」
絵を描く営みは、1人の世界だ。1人でキャンバスに向き合い、自分の心情のイメージを絵筆に伝える。
その一部始終に、他人を寄せ付ける余地はない。
だからこそ、その状態に心地よさを感じる人もいる。
そして、努力して周囲と合わせる努力が不要であれば、それが高じて周りとの心の垣根を自分で張り巡らしてしまうこともある。
本編の主人公、清水あやめはそうした心の持ち主だ。
自らの美的センスに絶対的な自信を持っている。
そんなあやめが、大学の授業で提出した課題で初めて人に負ける。
しかも負けた相手から、自らの芸術に潜む独りよがりな点を的確に指摘される。
ショックのあまり震えるあやめ。自らの負けをわずかな余地もないほどに自覚した瞬間である。
それをきっかけに、あやめが自らの狷介な心の狭さとその限界に気づき、少しずつ周囲との関わりを変えていこうとする。そんな物語だ。
自らの心の持ちようは、他人と比べて違っている。
そうした心の動きは、自らの心と他人の心の間に境目を作る。
境目とは、すなわち壁のこと。心の持ちようによって他人との間に壁まで作ってしまう。
それは自らの心の可能性に枠をはめる。
芸術を目指し、自分の技に没頭しようとすることで、自らの心に枠をはめ、将来の可能性を大きく損ないかねない。
だからあやめは、一度は出展しようとした自らの作品をいちどあきらめ、白紙に戻す。
そして、新たな自分を表現するため、新たなモチーフに挑戦する。
それは異性でもあり、尊敬できる相手でもあり、自らが何年も秘めてきた思いの対象に対し、向き合ってみようとした瞬間でもある。
その対象が見えてきた時、あやめは新たな自分の可能性に向け、大きな一歩を踏み出す。
「チハラトーコの物語」
千原桃子は、幼い頃からステージママに振り回されてきた。
少女の頃から意識を常に急き立てられ、見えを張って自らを飾りつけることに長けて成長してきた。
自らを虚飾で飾り立て、しかも見破られないようなテクニックを駆使する。誰も傷つけず、自分も傷つけない嘘。
そうした嘘を重ね続ける中、誰にも自分の素顔はさらさずに違う自分を演じてきた。
ところがある日、自らの経歴があるファンに見破られそうになってしまう。
その出来事がきっかけでトーコは、嘘にまみれた自らの半生を振り返る。
そもそも、いったい自分は何になりたいのだろうか。
芸能事務所に所属するも、自らの感性に合った作品しか出ようとしない。
嘘に嘘を塗り付けて30歳を目前にした今、俳優としての未来に広がりはあるのか。
千原桃子は路上パフォーマンスで活動する後輩との交わりにも感化され、パフォーマンスとはいったい 何なのかについて深く思いを深める。
俳優とは、嘘と色にまみれた職業だ。演ずる営みこそが、そもそも素の自分とは違う他人に化けることだから。
とはいうものの、そこで自分の本質を見誤ってはならない。自分の芯を持たずして演じたところで、何者にもなれないし、自分自身にすらなれない。
そうした切実な気づきが得られる瞬間。トーコにとってとても大きな気づきだ。
それを大人への入り口と呼ぶ人もいるだろう。
親の束縛から逃れた瞬間だ。
「樹氷の街」
本編は、過剰な自意識が組織の中に飲み込まれて苦しむ物語だ。
クラスの合唱コンクール。そのピアノ伴奏者は、花形の役割だ。
ところが、少ししか演奏スキルがないのに立候補してしまった倉田。
その伴奏は、クラスのみんなから酷評される。そして倉田は立場をなくす。
もともと、クラスに別の伴奏者がいるのに、あえて立候補した倉田への風あたりはきつい。
とうとう、練習にも参加しなくなった倉田。それを見かね、クラスのリーダーの何人かが対策に動く。
彼らのクラスには、音楽大学に進学を考えるほどのピアノの神童がいた。松永。松永の圧倒的な演奏は、伴奏者のレベルをとうに超えていた。
松永が倉田に対して伴奏を教えることにより、クラスで目立たないようにしていた松永も、そのきっかけにクラスに気持ちを開いていく。
本編は、誰もが中高の頃に経験する合唱イベントを通し、自意識の成長する瞬間をたくみに捉えている。
この瞬間こそ、大人への成長と同じ意味だ。まさに青春小説と呼ぶにふさわしい。
‘2019/10/3-2019/10/6
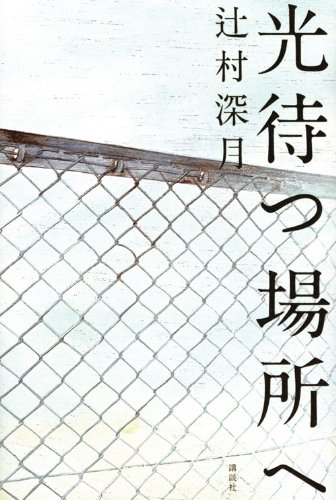


コメント