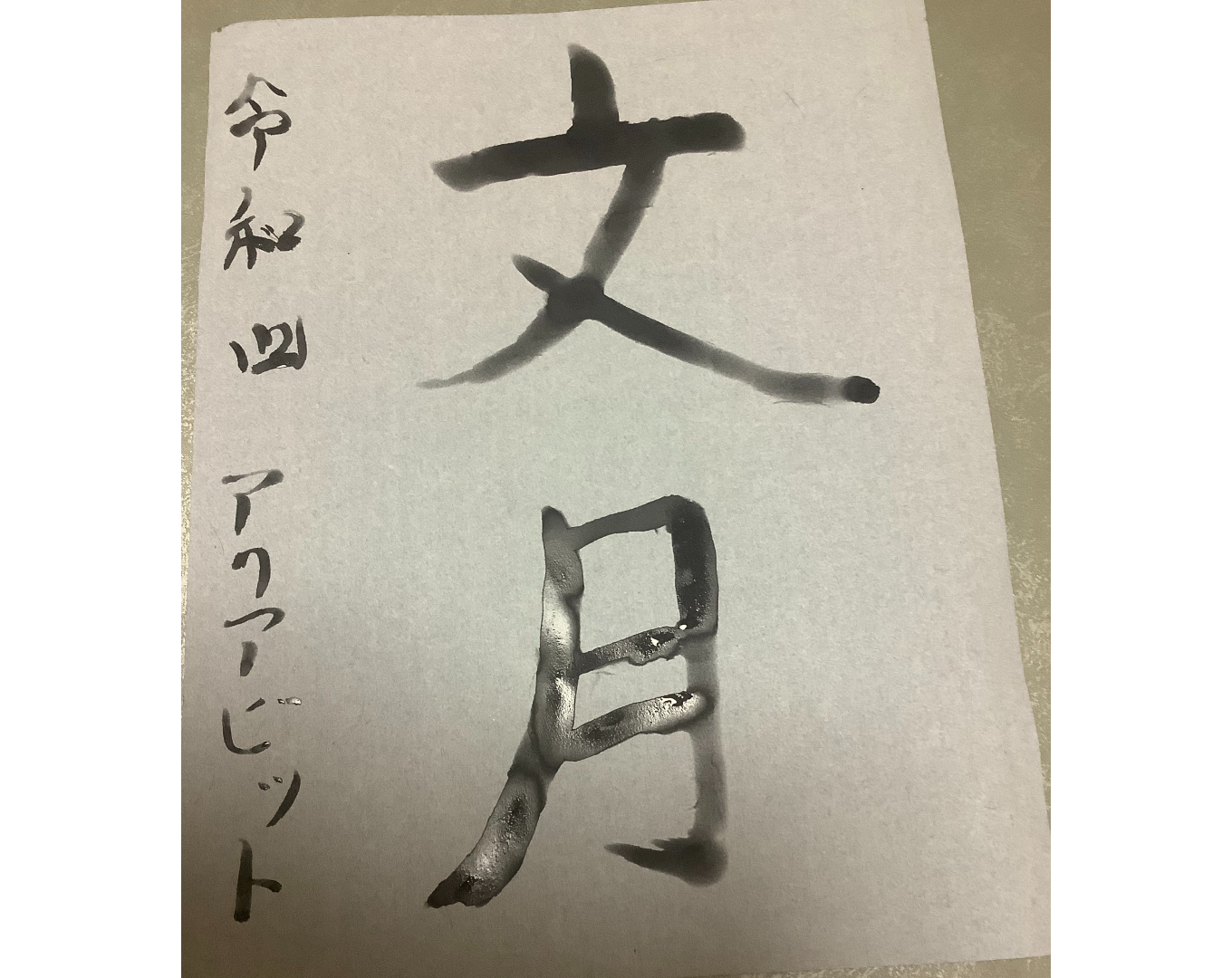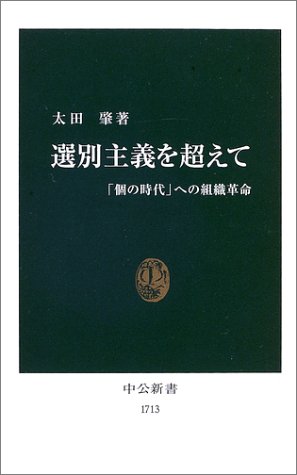かつて私は、某大手銀行の本店に勤務していた。全国の行員が使う内部のシステム構築の担当として。
開発センターではなく本店の中での勤務だったので、いわゆるシステム開発の現場とは違った雰囲気の中での仕事だった。朝は早く、帰りも残業ができず、強制的に帰らされることが多かった。他の開発現場に比べて納期に直接追われない現場だったのはありがたかった。受けるストレスといえば、朝夕に都心まで通うラッシュアワーだけだった事を覚えている。
今までの私の社会人経験を振り返ると、カスタマーセンターや中小企業や開発現場が多い。
個人事業主としてエージェントに仲立ちしてもらい、常駐先に通うように初めの現場は某上に挙げた大手銀行とは別の銀行の開発センターであり、かなりストレスを受けた現場だった。
その次に入った本店が開発センターと違い、現場と本店ではこうまで違うのかという経験を積ませてくれた。
この時の本店の個人個人の行員の皆さまは私によくしてくださった。私が離任するとき、行員の皆さんが10名弱集まって私のために慰労の飲み会を開いていただいたことも思い出す。
とはいえ、私は今までのさまざまな経験から組織と言うものをあまり信頼していない。
個人としては人間味が豊かに感じられる方であっても、組織の中では組織の論理に従い、非情な振る舞いに徹する。それが組織の中に生きる現実であることは分かっている。
本書は、そのような組織の中の人の振る舞いを教えてくれる。
かつての銀行勤務経験が私に本書を手に取らせた。そして本書は、それ以上の気付きを私に与えてくれた。
私は本店にいたとは言え、しょせんは外部から来た協力会社の人間に過ぎない。もちろん、内部のグループウエアにアクセスできたので、普通の人が知り得ない情報に触れられた。が、それすらもきちんとリスクマネジメント部署による統制が効いており、私が触れられることができた情報などはほんの一握りだったはずだ。
本書は、当時部長だった著者がイトマン事件に揺れる住友銀行の内情を赤裸々に語っている。文字通りの事件の渦中にありながら、著者は当時のことを克明にメモに取っていたそうだ。本書はそのメモをもとに構成されている。
本書で取り上げられるイトマン事件は、戦後最大の経済事件と呼ばれる。
大阪の中堅商社である伊藤萬の経営が傾いた。住友銀行から送り込まれた河村社長の経営責任が問われる。当時、住友銀行の天皇の異名をとった磯田会長は子飼いの河村氏を伊藤萬に送り込んだ以上、尻ぬぐいのために動かざるを得ない。道理を無理が押し通し、磯田氏の家族を巻き込んだ不透明な金が伊藤萬に投入される。そこにつけこんだ闇のフィクサーとしての異名を持つ許永中氏や伊藤寿永光氏の名前が連日のように報道され、何人もの逮捕者を生み出した。
事件によって、数千億の資金が住友銀行から伊藤萬を通してのみ社会に消えていったとされている。
そうした一連の事件を指して、バブルに踊る当時の日本の虚しさを指摘する事はたやすい。
本書に登場する人物のほとんどは当時の部長以上の役職だ。ほとんどが取締役や副頭取・頭取・会長といった経営陣ばかり。一般の行員は本書にはめったに出てこない。つまりそうした高い地位の人々だけが自らの裁量で金を自由に動かせる。銀行の些末な業務など一般の行員にまかせておけばよい。そのような論理が透けて見える。
さしずめ、本書に登場するような人々から見ると、システムを作るだけの私など一顧だにされなかったはずだ。銀行の内部にいた私も、銀行の抱える闇も深みも何も見ていなかったに違いない。
そんな私が本書から感じたこと。それは、資本家のグループと労働者の価値基準の違いだ。資本家とはつまり、会長や頭取、執行役員などを示している。そして労働者とは部長以下の一般の行員をさしている。
あえて資本家と言う手垢のついた言葉を使ったのは、本書に登場する人物たちの言動が世の価値基準から浮いてしまっているからだ。本書には高位の役職の人しか出てこない。
かろうじて労働者に属する著者が、資本家の毒に染まらずに義憤を感じて内部告発に踏み切った。そういう構図が読み取れる。
本書を読んでいると、取り扱われる額の大きさにも時代を感じる。わが国が空前のバブル景気に湧いていた時代。銀行が、バブル景気の演出者として最も羽振りの良かった時代だ。
少しくらい審査が甘くても乱発される融資。財務や経理データの語る事実よりも人と人のつながりやしがらみが重んじられる取引。それは本書の記述のあちこちに記されている通りだ。
最もリスクに敏感だったとされる当時の住友銀行にしてこの有り様。つまり、ほとんどの銀行が同じような状況だったと理解して差し支えないだろう。
後の世にさんざん批判され、大手銀行を苦しめることになる不良債権の種。それが旺盛に世の中にまかれてゆくいきさつ。それこそが本書だ。
著者のメモも、誰それと会ったとか密談したとかばかり。帳簿とにらめっこして頭を絞る担当者の姿や窓口で預金者と対話するテラーの姿は全く登場しない。それは著者が部長という役職だから当たり前なのかもしれない。
本書は、著者が訴えたいバンカーとしての自らの存在価値を越え、好景気に浮かれた当時の銀行がわが国の失われた30年を作り出したことをはからずも告白している。
私が大学に入学する少し前に弾けたバブル。それは私の人生の漂流に少なからぬ影響を与えた。
幸いにして、私は銀行内に勤務する経験も含めて、さまざまな経験を積んできた。そして、今も経営者の端くれとして活動している。
私が本書から学ぶとすれば、自分が金を操るだけの人間に堕さないようにという戒めだろう。資本家としてただ単に金を操るだけの人間には。
経営者であってもその戒めは常に持ち続けたい。
2020/10/19-2020/10/20