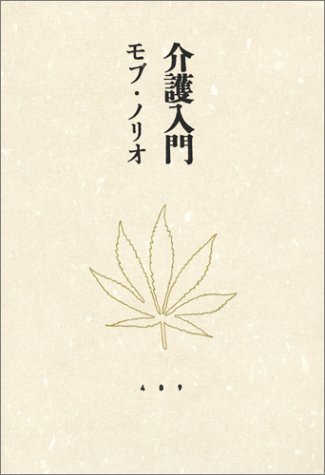
本書のタイトルの硬さに騙されてはいけない。タイトルと違い、本書はとても”パンク”な内容になっている。
29歳独身の男性が、祖母の介護に携わりながら、音楽に自らの人生を賭ける。音楽の夢に自らを委ね、”パンキッシュ”な文体を操りながら、介護のあり方を饒舌に語る。本書を要約するならこんな感じだろうか。
パンクと介護。この二つの言葉はすぐに結びつきにくい。無理に結び付けようとしても何か引っ掛かりを覚える関係だ。
だが、パンクを世の中の既成の体制に対する反抗とみなせば、この二つの概念にはつながりが見つかる。
介護はしんどい、介護はきつい、介護が汚いという常識に公然と反旗を翻すことも、またパンクなのだ。なるほど、と思う。
そもそも、かつての若者たちがパンク・ロックに熱狂したのはどういうきっかけだったのだろう。
体制への反抗とは、長じた者がえらく、若者はそれに従わねばならない、という若者からは無意味に思えるしきたりへの苛立ちから来ていたように思う。
年齢が上の者が支配し、統制し、運営する体制において、若者が反抗しない方がおかしい。
パンクが生まれたのは、イギリス。その当時のイギリスの社会体制は、貴族制が形式的にでも存続し、王室が君臨すれども統治せずの伝統を持ち続けていた。
また、そうした伝統にしがみつきながら、世界のリーダーとしての大英帝国の栄華を引きずっていた。伝統のしばりがある上に、経済も奮わず、社会が停滞していた。その影響を多く受けていたのが若者であり、若者がその状態にいらだっていたことがパンクを発生させた。
だが、そうした社会的な状況は直接のきっかけでしかなかったように思う。停滞した社会は、人のつながりを希薄にさせていた。人の関係が感じられない無力感。それがいっそう若者の苛立ちを募らせたはずだ。
「London Calling」「Anarchy in the UK」のようなパンク・アンセムには、そうした若者の苛立ちが現れている。
イギリスは世界的なムーヴメントとなった学生運動がそれほど盛り上がらなかったという。おそらく、そのエネルギーがパンクに向かったことは間違いないだろう。
転じて日本だ。日本はすでに60年代に学生運動の敗北を経験した。さらに、学生運動の挫折を受け、先鋭化した一部の学生がテロに走った。それがさらに若者の間に嫌気と空虚を生み出した。
だからイギリスを起点に広がったパンクは、日本ではそれほど受け入れられなかった。
その一つの理由は、わが国が高度経済成長の渦中にあり、生活の向上が実感できていたことだろう。それが若者の不満をやわらげていたことは十分に考えられる。
だが、もう一つの理由も考えられる。それは当時の日本にはイエの風習が残っていたからとはいえないだろうか。
つまり、古い家の結びつきや地縁社会がぎりぎり機能していたため。若者の暴発を抑えていたといえないだろうか。
でも今や、そうした結びつきの多くが失われてしまった。
では若者は何に寂しさを紛らわせればいいのか。
本書で、俺がおばあちゃんに対して示すのは、介護こそが人の結びつきであり、人間の手触りを感じさせるからだ。
現実が感じられず、あらゆる事物が不確かでつかみどころがなく、手がかりも行き先もないまま、生きている毎日。
ところが、おばあちゃんの介護は、生きている実感をもたらしてくれる。下の世話や、幼児に返ったようなおばあちゃんの姿は、生きる営みの本質を隠さずに見せてくれる。
そして、介護される側となった年上からほ、威厳や抑圧もない。老いて幼児に返る時、若者に対する威厳はどこかへ消えてなくなっている。そこにあるのは一人の生き物としての本質のみ。
その姿は、パンクの怒りの行き場を吸収する。そして、老いた姿は、生きていることへの本質とは何か、という考えに若者を導く。
パンクとは、すなわち生きること。であれば、介護とはすなわちパンク。
介護の世話をする現場においては、あらゆるくだらないしがらみや約束事や秩序やルールは消え去る。ただ生きること。
何という崇高な営みだろうか。
上辺だけの関係は一掃され、取り繕った態度も全く必要がない。
そして、パンク青年がこの後、数十年を生きれば同じような老後に直面する現実。その悟りこそ、パンクの行き着く先。
とりすましたやつ、悟ったやつ、エライセンセイ、統治する連中。皆、死ぬ時は一緒。衰えるだけ。この現実の哀れさ。
この小気味よさこそがパンクなのだ。
現実の哀れさに向けて必死で努力する奴らを嘲笑いながら、必死でパンクを歌い、必死で”パンク”な介護の現実に入門する。
生きていることが何なのか。それが何になるのか。
それを求め若者は暴れる。絶叫する。苦しむ。のたうちまわる。
この世の全てはしょせん暇つぶし。あらゆる営みなど時の流れがきれいに消し去っていく。意味のあることなど何一つない。
だから、若者はその無慈悲な未来に向けて全力で呪い、全霊でパンクを演じる。
そして、身近で突き付けられた老いの現実に、パンクの精神の全てをぶつける。
その現実に向き合い、世の常に全力で反抗し、己の生を証明する営み。これこそが、パンクの本質なのだと思う。
俺はいつも、《オバアチャン、オバアチャン、オバアチャン》で、この家にいて祖母に向き合う時にだけ、辛うじてこの世に存在しているみたいだ。(104p)
それ以外の時間、俺は疲弊した俺の抜け殻を持て余して死んでいる。(104p)
文体とタイトルに惑わされずに読んでほしいと思う一冊。
‘2019/12/12-2019/12/12
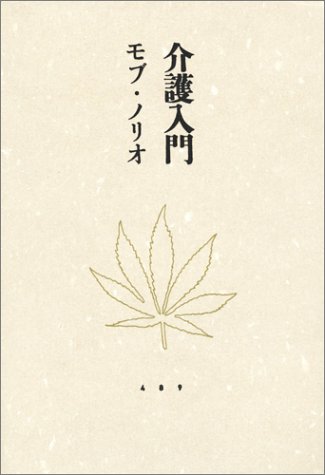

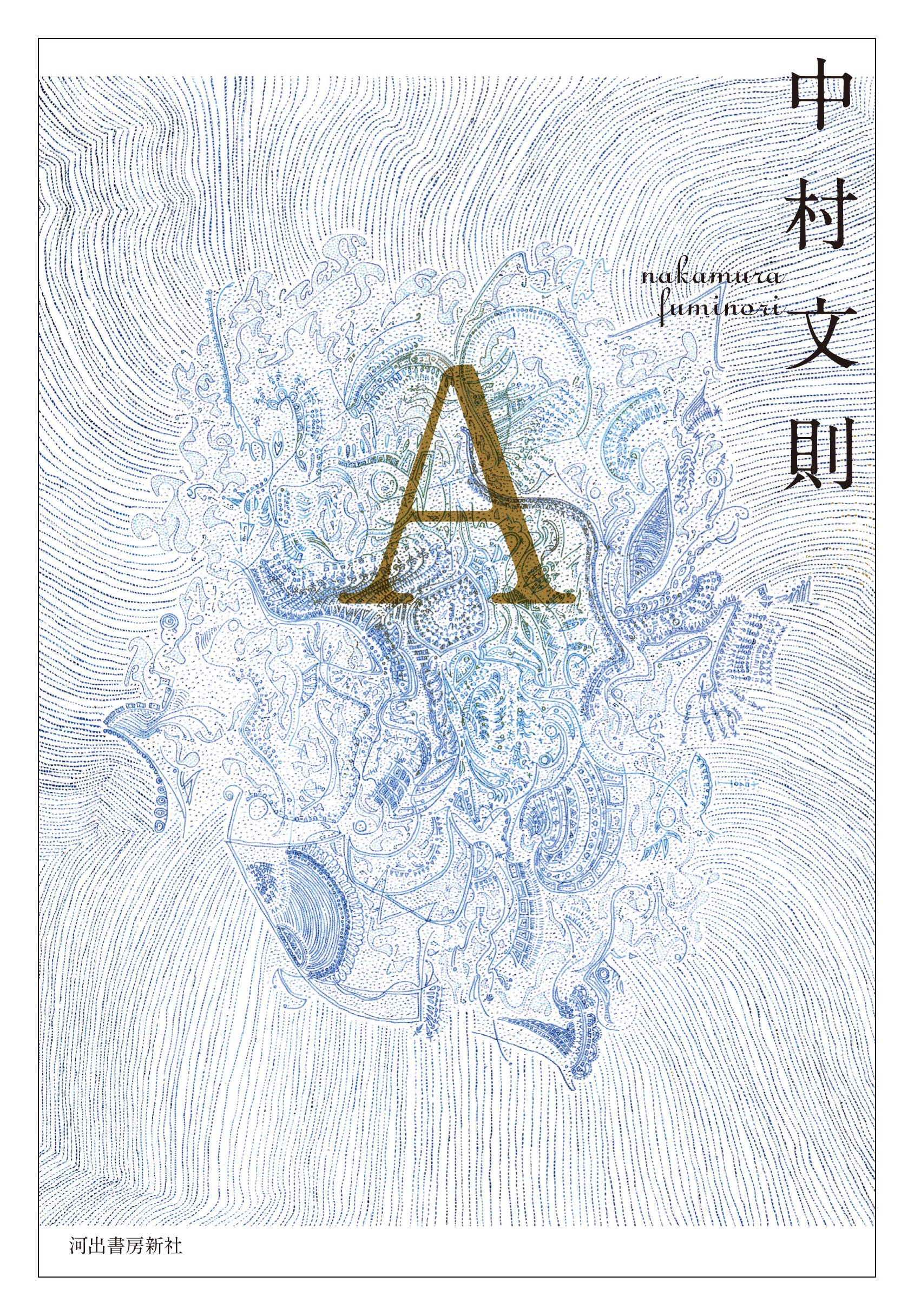
コメント