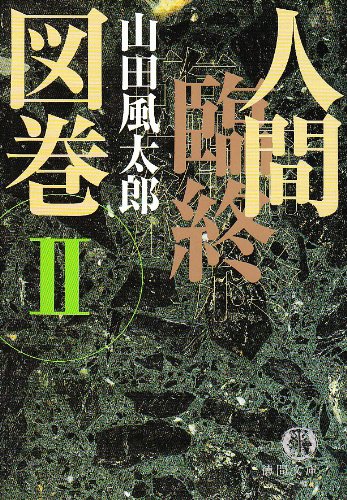
本書では享年五十六歳から七十二歳までの間に亡くなった人々の死にざまが並べられる。五十六歳から七十二歳まで生きたとなれば、織田信長の時代であれば長生きの部類だ。当時にあっては長寿を全うしたともいえる。
人生の黄昏を意識し始めた人々は、死に際して諦めがいい。とはかぎらない。
本書に収められている以上は、それぞれがその世界で名を成した人々だ。努力に研鑽を重ね、なにがしかの実績を重ねて来た人々でもある。が、そういった人々こそ、まだまだ道なかば、と思いながら日々を生きているのではないか。死を前にして、自分はまだ若いと考えたことだろう。
人の死にざまを描くことで、その人の一生を総括できるのか。著者がこの図巻で試みようとするのは難儀な試みだ。その人の一生を知りたければ葬儀の参列者を観察すればいい。誰が言ったかは知らないが、一面の真理をついている。では、その人の死に方を観察すれば、その人の一生は理解できるのか。悟ったように従容と死に臨むことができれば、その人は生涯を悔いなく過ごせたといえるのか。これまた難しい問いだ。
私自身、齢四十三を数えた自らの人生を振り返ると、道半ばどころか、ひよっこもいいところだと思っている。まだまだ知りたいことやりたいことが無数に残っている。仮に今、死期を知らされたところで、きっと未練で取り乱すに違いない。
産まれた瞬間に死刑宣告を受けるのが生きとし生けるものの定め。それは頭ではわかっていても、悟りを開くにはやるべきことがまだまだ残っている。そう思っている。もちろん、一生を悟りの中に生きることもありだろう。だが、そこに諦めは持ち込みたくない。死に臨むなら、諦めの中でなく、やり切った満足の中に臨みたい。最後に一念発起し、盛大に花火を打ち上げるのも良いが、生半可な花火ではかえって悔いが残るかもしれない。それであれば体力のある今のうちにやりたいことをやっておきたい。
本書を読むと、否応なしに死に方について思いを致したくなる。日々を生きるのに精一杯な状態では、死に方について考える暇もないだろう。であれば、せめて他人が死に臨んでどのように納得したのか。どのように折り合いをつけたのか。その様を知り、自らの死生観を養うのがよい。いまだかつて、死で自らの生を終わらせなかった人間はいない。これを書いている私にもやがて死は訪れる。これを読んでくださっているあなたにも。死は等しくやってくる。
そして、死ぬ事を、頭のなかでわかったような気になっているのも私も含めて皆一緒だ。それであれば、少しでも自分の死に際して、慌てず騒がず、悔いなくその時を迎えるにはどうすればいいか。本書は、やがて訪れる死を前に、読んでおくべき一冊だと思う。
’2016/07/08-2016/07/10
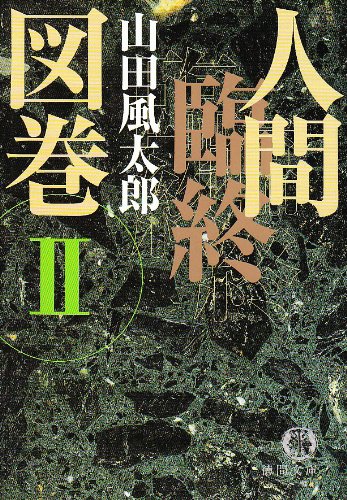
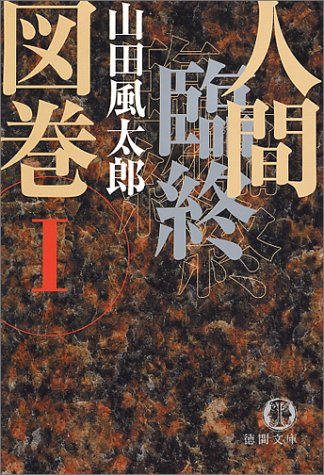
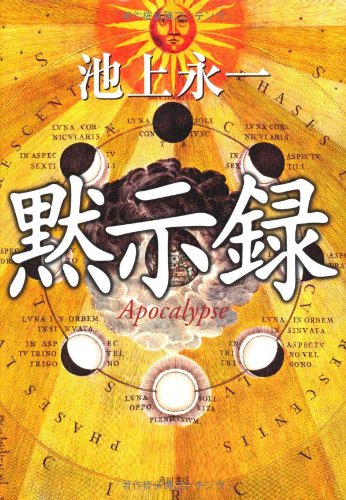
コメント