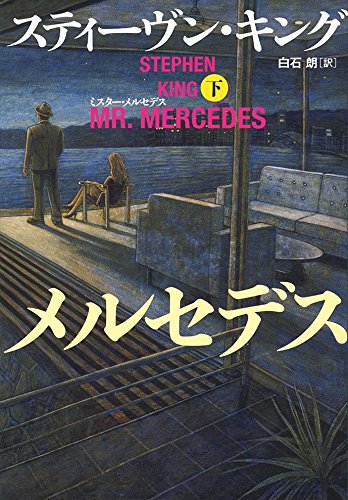
下巻は上巻からの承前で「毒餌」の章で始まる。ホッジズの友人ロビンスンの捜査を妨害しようと、ブレイディはロビンスン家の犬を毒殺しようとくわだてる。ところがその毒餌を、ブレイディの同居する母アンが誤って口にしてしまう。泡を吹いて死んでゆく母。これをみた時、ブレイディからタガが外れる。善良な市民という名のタガが。
ただでさえ、ホッジズとの息迫るやりとりでささくれ立ち高ぶっているブレイディの精神。すでに暴走し始めていた彼の心の崩壊は、母の死によってますます拍車がかかる。身から出た錆、という言葉はブレイディはこれっぽっちも届かない。「青いデビーの傘の下」のメッセージにホッジズを殺すと宣言し、ホッジズの車に爆弾を仕掛ける。ところが車が爆発した時、ホッジズの車を運転していたのはジャネル・パタースン。ホッジズがメルセデスを調査する中で知り合い、恋仲になったミセス・トレローニーの妹だ。恋人を殺されたホッジズの怒りは頂点に達し、二人の戦いは誰にも止められない段階に突入する。この戦いは「死者への電話」の章で著者の培ってきたスキルのすべてを費やして描かれる。
本書には登場人物がそれほど多くない。少なくとも著者の今までの大作よりは控えめだ。そして、ホッジズとブレイディの対決が大きな構成となっている。なので物語の視点は二人の行動に合わせて動く。二人のすぐ上から見下ろす神の視点だ。視点も限定され、視野も広くない。ホッジズとブレイディの戦いに迫った描写が主になる。だから読者は存分に二人の戦いを堪能できる。
ホッジズは、メルセデス・キラーがどうやってミセス・トレローニーのメルセデスのキーを開けたかを突き止める。そしてメルセデス・キラーがブレイディ・ハーツフィールドであることも突き止めてしまう。
荒ぶるブレイディの次なるたくらみ。それをホッジズがどう食い止めるのか。一気に物語はクライマックスに向かう。「キス・オン・ザ・ミットウェイ」で描かれるクラスマックスへの流れは著者が得意とするところだ。著者の熟練のストーリーテリングを読者は存分に堪能できる。この章は、著者が今までに発表して来たホラーの骨法をいかし、従来の筆さばきのまま、のびのびと書ける。この章の流れは、過去に著者が出してきた幾多の名作を思い出させる。そしてミステリーである以上、超常現象も不要だ。
それどころか、著者はスタイルを変える必要もない。なぜならここまで本書を読んで来た読者は、すでに本書がミステリーであると了解しているからだ。だからこの章が今までの著者の作品を思い出させたとしても、ミステリーとして違和感なく読める。追い詰められ、自暴自棄になった犯罪者と、猟犬のような探偵の知恵比べ。そこには善と悪の対立が明確に描かれている。
断章として置かれた「公式声明」は本書のミステリーとしての締めだ。ここで著者はミステリーとしての作法にのっとっている。いったん本書をミステリーとして終わらせた後、著者は本書の結末を読者が予想する方向から少しずらす。カタルシスでもカタストロフィでもない結末へと。その結末は本書の続編を予感させる。そして実際、本書には続編が用意されている。本書の結末も、続編以降と密接につながるはずだ。
そこで著者は、ほんの少しだけ著者の得意とするジャンルに読者を誘い込む。もちろん、ミステリーの枠組みを大きく外れない程度に。ミステリーとしての本書が締められた後、エピローグで描かれるのが「ブルー・メルセデス」だ。
本書は見事なまでにミステリーとして完結している。そればかりか、続編としての色っ気を放ちつつ、著者の従来のホラー路線のファンにもサービス精神を発揮している。「ミステリーを書いたけど、ホラーもまだまだ書くよ」と。だが、そのようなサービス精神を断章に挟み、続編に色気を出すにせよ、ミステリーとしての結構が素晴らしいことが第一だ。そこがきちんと描かれていること。ロジックやプロットがかっちりしており、読者のイマジネーションをホッジズとブレイディの対決に向かせたこと。それが本書をミステリーとして成り立たせている。
だからこそ、本書はエドガー賞を受賞できたのではないか。
本書はすでに続編とさらに続々編まで出ているという。近いうちに読もうと思う。
‘2017/08/10-2017/08/11
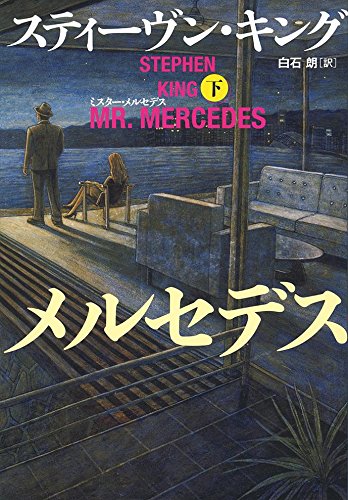
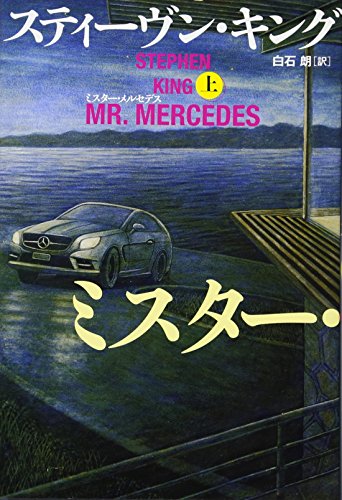

コメント