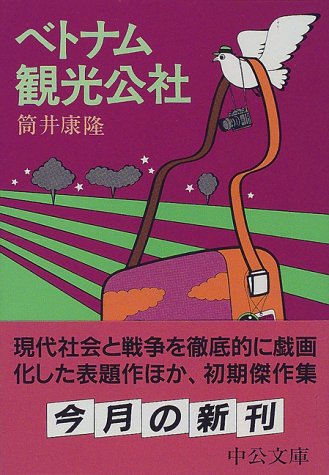
本書を読むのはおそらく三度目くらいだろうか。ふと手にとってしまった。
何度も読み返してしまう中毒性。それが著者の作品だ。
本書は、著者の短編集の中でも初期の頃に出版されたものだ。
だが、この時点ですでに著者の毒は存分に吐かれている。
今、読んでも強い印象に残る短編の数々。本書にはそうした短編が含まれている。
「火星のツァラトゥストラ」
メディアの持つ狂った一過性。著者はこのテーマを何度も短編の題材にしている。
本編もその一つだ。
火星で地球から来ただけでもてはやされ、スターになってしまったツァラトゥストラ。
元は火星の某教授が仕立て上げた流言の中の存在。だったはずが、あっという間に人々はその流言に乗せられ、ツァラトゥストラはスターに祭り上げられる。
ありとあらゆるメディアに登場し、火星中にツァラトゥストラの肖像が氾濫する。便乗商品やタイアップ商品が火星を埋め尽くす。
だが、流行はすぐにやむ。あっという間に大衆とメディアに見放され、捨てられたツァラトゥストラ。その様子を描いた本編は、メディアのあり方を鋭く風刺している。
ましてや、本編が描かれた当時は、テレビの黎明期。本編の末尾にはかの「スーダラ節」を思わせる音頭が登場する。
そうした早い時期からメディアの本質を見抜き、本編として発表していた著者の慧眼には驚くばかりだ。
「トラブル」
人間の肉体を乗っ取り、自由に操る「ゼン」という意識体。
脳を乗っ取るため、乗っ取られた人間は、痛みや意識を覚える間もなくゼンに好きなように操られる。
平和な日中の公園で、多数のゼンの間にいさかいが発生し、人間の身体を好きに使って血が飛び、脳が飛び散り、体をもぎ取り合う白昼戦を繰り広げる。
著者のお得意のスプラッタ描写がさく裂する一編だ。
「最高級有機質肥料」
本編は著者の数ある傑作短編の中でも上位に挙げられるのではないだろうか。
本編も著者が得意な爆笑短編の一つだ。
異文化との遭遇。
ある星の植物から由来の人間は、使節としてやってきた人間の排せつ物を好む。そして、その色や香り、形や中身にいたるまで微に入り細を穿ってその排せつ者に説明するのを礼儀とする。
スカトロジーの極致ともいえる一編だ。
どこかのエッセイに載っていたが、著者は本編を書くにあたり、自分の排せつ物を机の上でつつきながら描いたという。
まさに、著者の毒が存分に吐かれ、魅力にあふれた真骨頂といってもよい一編だ。
「マグロマル」
星間連盟の会議で扱われるマグロマルという議題。その意味を知らずに参加した地球人の大使。
さまざまな文化と習慣を持つあらゆる星の大使たちが集う会議はめちゃくちゃで、だれもがマグロマルの意味を理解せずに、めいめいが自分たちの文化を披露し好き勝手にふるまっている。
だれもが本質をつかんでいないのに躍る会議。その本質をつかんでいる。
異文化の遭遇ものとして、著者の得意とするスラップ・スティックが堪能できる一編。
「時越半四郎」
時代小説の体裁をとりながら、実はSFのタイムリープものである一編。
違うように見える二つのジャンルをいとも簡単に接続してしまうところに、著者のすごさがあるわけだが、私の中ではそれほど印象に残っていない。
「カメロイド文部省」
全く小説の文化がない星から、小説を書くために移住してほしいと頼まれた主人公。
移住してみたら、その星の大臣は聞きかじった地球の作家や出版事情の知識から無理難題を主人公に押し付けようとする。
毎月、主人公が執筆する10編の短編からなる雑誌を出し、長編も毎月出版しなければいけない。
それなのに主人公が提案したあらすじに文句をつけ、倫理観が高く、倫理に反するような小説は一切出せないと言い張る大臣。
激怒した主人公が脱出しようとするいきさつが面白い。
当時の出版と作家の置かれた状況に対する痛烈な皮肉を込めた一編だ。
こうした文壇や出版社を敵に回すような作品は、著者も数多く発表してきた。
著者は作家活動の初期の頃から、そうした権威に対する反抗心が出していた。読んで面白い。
「血と肉の愛情」
食人。それは人類の文化でも最大級のタブー。それをテーマとし、追い求めた一編だ。
愛情と食欲の極致が、愛する人を食べる行為に落ち着いたとしてもおかしくない。
著者の自由な思想の広がりがにじみ出ている一編だ。
「お玉熱演」
本編は、時代の切り取り方を著者なりの方法で追求した一編だ。
風俗や文化を表現するには、どういう演出が望ましいのか。
著者は舞台人でもあるので、演出方法にも関心が高いと思われる。
テレビなど、メディアで自分を認めさせたいとのお玉の熱意。これはお玉だけではなく、今の私たちの多くも願っていることではないか。
その意識を逆手にとり、認められたいとの意識の過剰をある時代の切り口として描いた一編だ。
「ベトナム観光公社」
本編が書かれた当時は、ベトナム戦争が真っ盛りの時期。
そんな時期に戦争を劇場の中の舞台として揶揄し、茶化す本編。すごいと思う。
遠い将来、もし時間旅行が商業として成り立っていたとしたら、戦場を観光する楽しみだって商売になるはず。
戦争など、当事者の悲劇や必死さを除くと、部外者からは劇場でみる映画のようなものにすぎない。
そのような戦争の本質をスラップ・スティックに包んでみたら、本編のような作品になった。そんな一編だ。
‘2020/01/03-2020/01/04
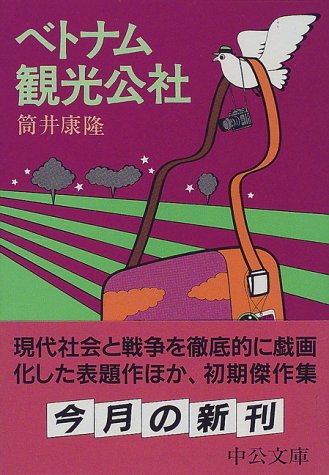
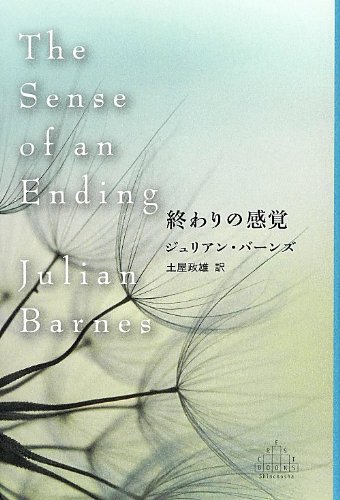

コメント