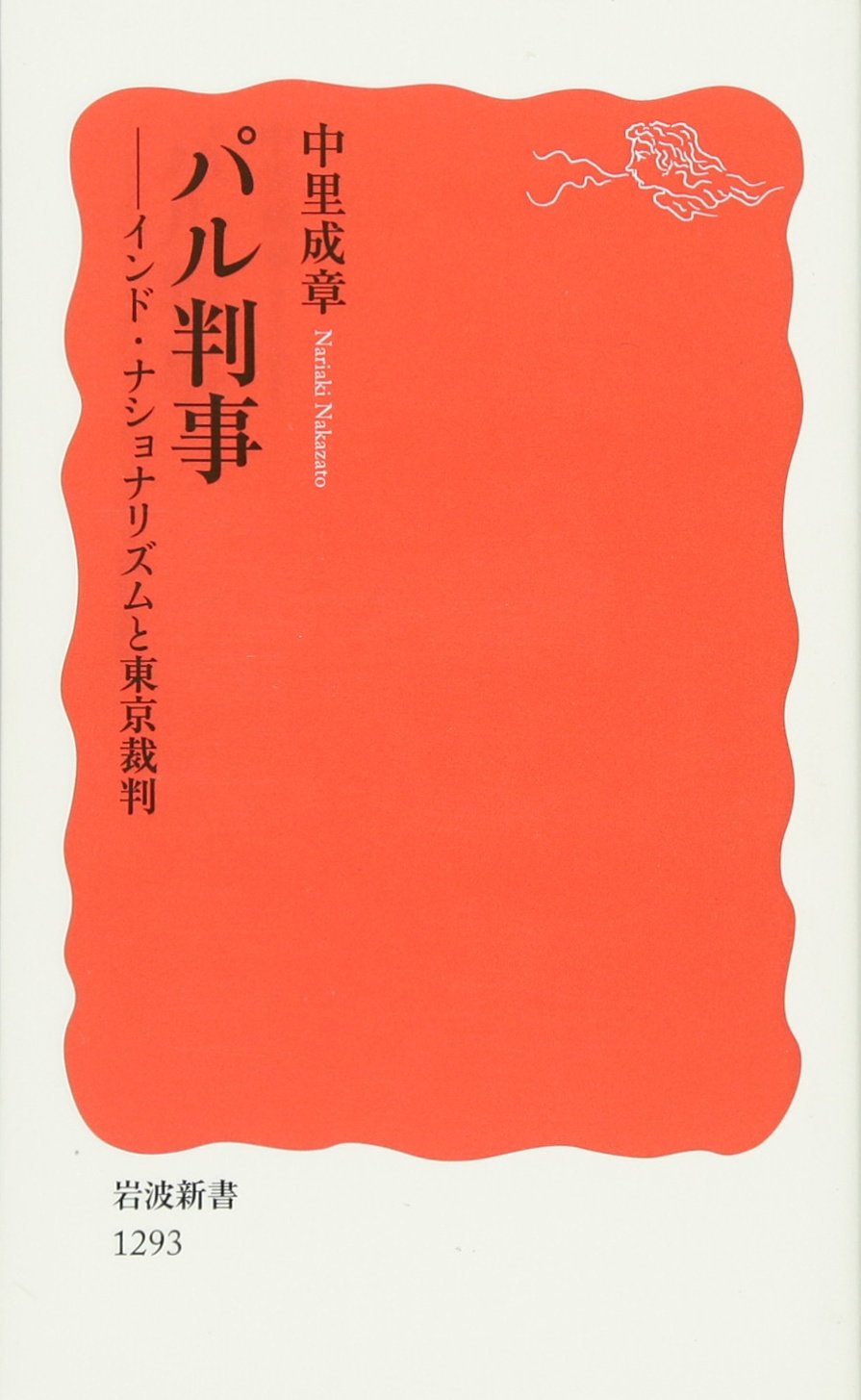
靖国神社。
わが国の戦死者の多くを英霊として祀る神社としてあまりにも著名だ。
神社の境内の一角には遊就館と名付けられた建物が設えられている。わが国の礎となって命を散らした戦死者を顕彰する施設である。
遊就館の脇には、いくつもの顕彰碑が建てられている。
その中の一つが、本社で取り上げられているパル判事を顕彰する碑だ。私も首を垂れたことがあるが、立派なものだ。
私は同じ顕彰碑を京都の霊山護国神社の境内でも見かけた。
二つの場所に共通しているのは、日本のために命を捧げた英霊を祀った神社であること。
極東国際軍事裁判において判事に任命されたパル氏は、被告となったすべての戦犯を無罪とする意見書を出したことで知られている。極東国際軍事裁判とは、第二次世界大戦の後、連合国が枢軸国の一員だった日本に対して戦争犯罪を告発し、求刑した裁判を示す。
普通、そうした裁判は勝者が敗者を一方的に裁く。
ところがパル判事の意見書では、戦勝国側の判事の立場でありながら、敗戦国である日本の犯した戦争犯罪の罪をなかったものとした。
平和に関する罪、人道に関する罪とは事後法であり、裁判の開始前に行われた日本の戦争犯罪には適用されないこと。罪刑法定主義の立場からも、戦争犯罪があらかじめ決められた罪刑ではないことなど。
法学の専門家の立場から日本の戦争犯罪がそもそも成立しないという解釈は、日本の多くが否定された極東国際軍事裁判において異質だった。
その異質さは、戦前の日本を良しとする立場からは歓迎されるはず。
だからこそ、靖国神社や遊就館のような極東国際軍事裁判と対立する施設において、パル判事の顕彰碑が建てられているのだ。
私はパル判事についてはいくつかの書物や小林よしのり氏の本で知っていた。
ただ、そうした顕彰碑の存在は、かえって私を身構えさせる。それを鵜呑みにしてはならじ、という戒めとともに。
本書を図書館で見かけ、パル判事のことを知る良い機会だと思い手に取ってみた。
顕彰碑だけを見ていると、パル判事の経歴や人格、そして東京国際軍事裁判の判事としての立場には一点の曇りもないと思える。完全無欠な人物で、なおかつ日本の立場を裁く人物からのお墨付き。
著者は冷静な立場からそうした見方に釘をさすような指摘を行う。
常に思うことだが、こうした歴史問題にはイデオロギーの存在がつきものだ。
イデオロギーの罠から逃れるには、資料を一つだけ読んでそれを盲信するのではなく多角的に見る必要がある。
本書はどちらかといえば、パル判事を賛美する従来の立場からは距離を置いている。そして、パル判事の認識や判断にそもそもの誤りがあったことをいくつも指摘している。
パル判事を本書のような視点で分析し、批判的に描いた書物を読んでおくのは良いと思う。
著者は法学の専門家でもなければ、日本史の専門家でもない。著者はインドの、中でもベンガルの歴史を主に専攻した方だという。
その立場からパル判事の生い立ちや経歴を綿密に調査する。どういう形でパル判事が東京国際軍事裁判の判事に選ばれ、どういう思想から日本の戦争犯罪が成立しないという判断に至ったのか。それを著者は分析していく。
まず本書は、パル判事の生まれた実家の当時の状況と、その当時のベンガル地方の歴史について触れる。
インドといえばカースト制が有名だ。カースト制が今なお幅を利かせるインドでカルカッタ大学の副学長にまで登り詰めたパル判事はどういうカーストの下に生まれたのか。
ラダ・ビノード・パル判事が生まれた一族は、陶器をこね、それを商う陶工をなりわいとしていたようだ。陶工とはいえ商売の手を広げ、商業カーストとして中級の地位にいたそうだ。
そこからパル判事は懸命な努力も行っただろうし、周りに引き立てられた運もあって、学徒として学ぶことに集中できた。まず数学を修め、ついて成績が優秀だったので法学の分野に進んだ。
そうした記述からは、パル判事が持って生まれた素質や向学心が一流のものだったことが理解できる。
次いで著者は、一介の法学士としてパル判事がたどった道のりや、カルカッタ大学の副学長に推挙されたいきさつを分析していく。副学長とは、学長が名誉職だとすれば現場の最高責任者ともみなせるだろう。
だが、著者の調べによると、就任までのいきさつにはやはり一悶着があったという。
だが、ここまでの経歴に関しては、パル判事が提出した意見書にはそれほど関係がない。
ここで著者が指摘するのは、極東国際軍事裁判においてパル判事が提出した意見書には、パル判事が持つ政治的な意図があったことだ。
その意図には、法学の立場を逸脱する要因があったという。
その要因とはインドがイギリスの植民地であった歴史だ。インドが植民地にされていた事実について、パル判事が植民地政策に対する怒りを持っていたということも。
つまり極東国際軍事裁判とは、パル判事の目にはこう映っていた。西洋の勝者が極東の敗者を一方的に裁く、不公平な裁判だと。
その考えは私たちも戦後ずっと抱き続けている。そもそも東京裁判とは何だったのかという問いとして、いまだにしこりを残し続けている。歴史修正主義者であろうとなかろうと。
遊就館や霊山護国神社が、太平洋戦争で日本の事績にも良い点はあったとする施設であることを考えると、パル判事を顕彰するのも当たり前のことだ。
著者は、極東国際軍事裁判でのパル判事の行動にも疑問はあると説く。就任早々に公判を欠席し、いったんカルカッタに帰ったこと。判事の辞任を申し出ていること。
また、着任早々に意見書によって自身の立場を明確にし、早くも極東国際軍事裁判のあり方そのものに一石を投じている。
著者とて、極東国際軍事裁判が全く汚れのない完全な裁判とは考えてはいない。
だが、著者の立場は、極東国際軍事裁判の結果が、そ後の人類の平和にいくばくか貢献するというものだ。
勝者が敗者を一方的に裁くだけでなく、どこかで人類の平和に貢献しているのであれば、裁判にも一定の評価を与えるべきとの立場だ。
その立場が影響しているのか、本書では東京でのパル判事の振る舞いには批判的な描写が多い。
また、最終章として著者は、なぜ。パル判事が戦後のわが国で顕彰されたのか。日本でパル神話と呼ぶべき現象が形成されていったのは、どの人物のどのような意図によるものかということを詳しく描いていく。そこにはやはり戦犯の罪を免じ、戦前の日本に対する復権を1とする一団の存在があった。旧軍人であったり、旧国粋主義者であったりといった人物がパル判事の顕彰を推進したようだ。具体的には平凡社社主の下中氏などが。
本書を読んでなお、私にはパル判事への感謝の念は残っている。
それは、一方的になってしまう裁判に別の見方を示し、それを後世に残してくれたことだ。
その一方で無条件にパル判事を賛美する風潮には背を向けたいと思う。
私は、極東国際軍事裁判を以下の通りにとらえている。
A級戦犯の判決にも、外交官の広田首相の絞首刑だけはどうかと思うが、おおかたの部分では賛成だ。
その一方で、極東国際軍事裁判が勝者による敗者への判決に過ぎない、との主張にも賛成する。結局、日本は負けたことのみにおいて罰せられたのだと思っている。
さらに、共同謀議の問題について、私はなかったと思っている。また、特定の人物が主導した戦争でないとも思っている。
だが、確固たる見込みもないままわが国を戦争に突入させ、破滅へ導いた責任は重いと思う。A級戦犯として裁かれたのも致し方ないと思っている。
つまり、極東国際軍事裁判とは、判決で終わりなのではない。
その裁判自体の正当性も含め、日本人がなぜ戦争に突き進んでしまったのか、戦時中の高揚する精神のあり方も含め、考え続けいかなければならない。
その意味でも、パル判事の示した立場は裁判を考える格好の機会になるはずだ。
‘2019/10/20-2019/10/21
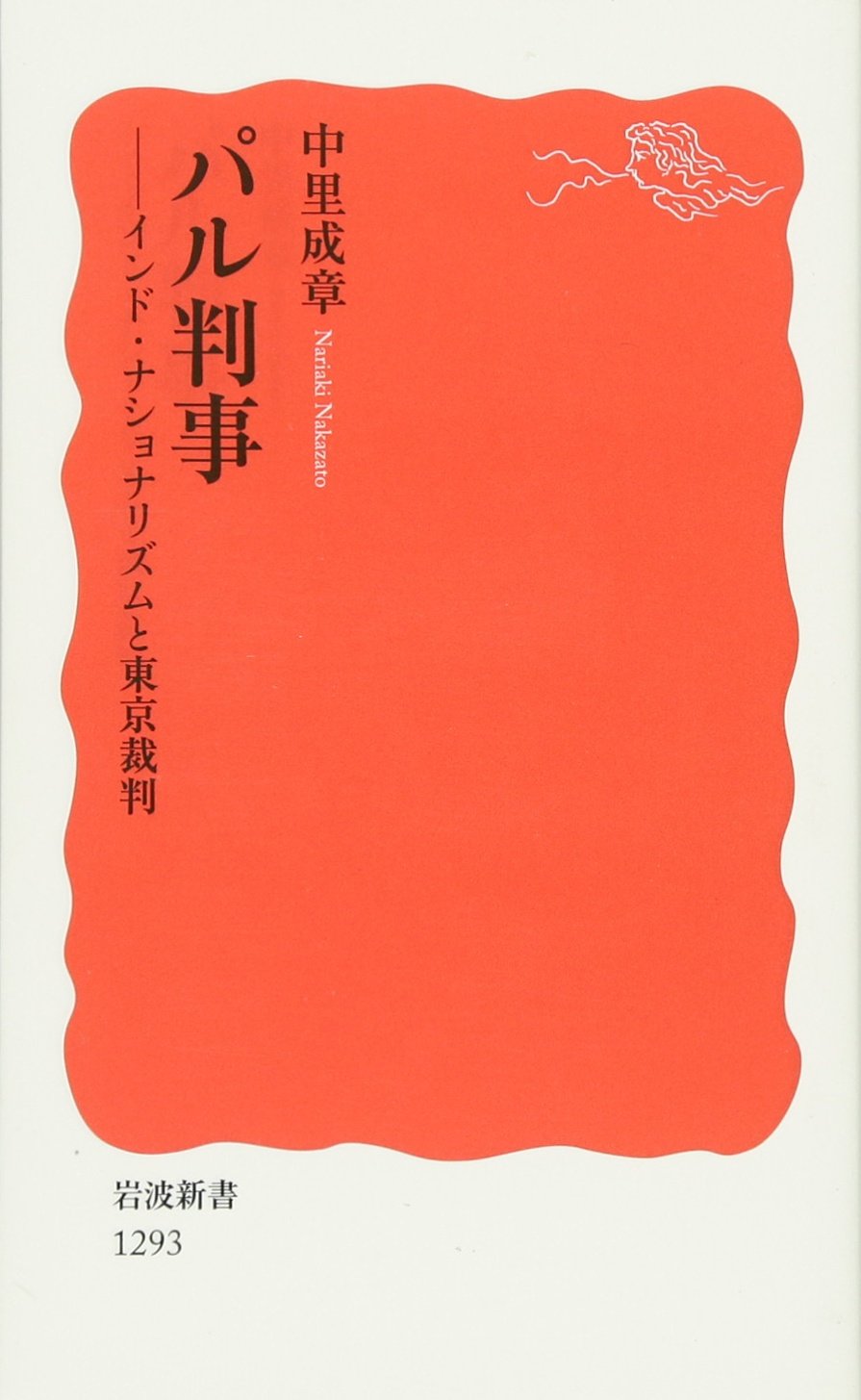

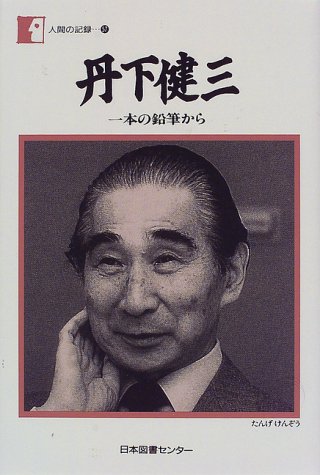
コメント