
本書も、開高健記念館に行った後、著者の作品を読み通そうと思って読んだ一冊だ。
著者に芥川賞を授けた出世作でありながら、私はおそらく本書を読むのは初めてだと思う。
どの作品も、人の営みとその巨大な徒労が書かれていてとても興味深い。
「パニック」
動物の旺盛な繁殖のたくましさとそれによって動揺する人間の浅さを風刺する一編だ。
ネズミの大発生の兆しを笹の大繁殖から予測した俊介は、笹の事前駆除を具申するが、役所仕事の例にもれず、却下される。
笹が120年ぶりに繁茂したことにより、それを餌にしたネズミが大繁殖。それが制御しきれぬほどの大集団となったネズミのエネルギーとして街を被っていく様子。
その不気味な予兆に警鐘を鳴らす俊介だが、すでに、組織の硬直した判断が覆ることはなく、街はネズミだらけになっていく。
そうした役所仕事の硬直性と、突発事に弱いわが国の組織機構の問題を、本書は乾いた筆致で描いてゆく。
責任を回避しようと策を巡らせる上司。事が起こってから俊介の慧眼をあらためて媚びるように褒めようとする上司。組織の中で生きるための手管を駆使する人々。
そうした人間の滑稽さにもかかわらず、ネズミは繁殖する。
人間がいくら駆除の手立てを凝らそうとも、自然の猛威は人間の作り上げたシステムを齧り取っていく。
「やっぱり人間の群れにもどるよりしかたないじゃないか」(78ページ)
これは、ネズミが湖へ集団で飛び込み、ネズミ騒動が終わった後に俊介がつぶやいた一言だ。人間の群れとネズミの群れのどこが違うのか。そんな著者の皮肉が炸裂する逸品だ。
「巨人と玩具」
著者が壽屋(現サントリー)の社員として、トリス・ウヰスキーなどの有名なコピーを手がけたことはよく知られている。
本編はそのサラリーマン時代の経験が十分に生かされている。
キャラメル・メーカーでの仕事が本編ではさまざまに描かれる。販売・製造・宣伝・総務・経理。組織を挙げ、マーケティング手法を駆使し、宣伝のためにあらゆる努力を惜しまない企業活動。どのようにして消費者にアピールするかについての試行錯誤に余念のない毎日。
ライバル会社のキャンペーンと比較しては一喜一憂し、ライバル社を凌駕するためにありとあらゆる策を練る。
その繰り返しは、高度経済成長期にあった当時のわが国にとっては正義だった。
だが、どっちその時期に描かれた本編の中で著者は、その虚しさを早くも予期している。本編は、現代に読むとより実感として迫ってくる。満足を知らない成長の追求が何をもたらすか、何をもたらしてきたかを知っているからだ。
価格競争の末に倒産する企業、消費者は加速するばかりのキャンペーンに飽きている。地球はそうした際限のない拡大の論理によって汚されつつある。
広告や宣伝のもたらす本質的な虚無を、著者は現場にいた人間として見事に描いている。
最後のページでは、主人公の心中が描かれる。そこで彼は、今まで自分で自分の力で成し遂げたことなどなく、自殺しか残されていないかのような心境に陥る。
その心のあり方など、当時の高度経済成長に乗っていた日本人の空虚を描いていて見事だ。
「裸の王様」
本書は芥川賞受賞作品だ。
先の二編と違い、本書はまた違う趣がある。
子供の描く絵の世界を通じ、大人が大人の論理で子供の絵を解釈することの愚かさ。批評が権威や金によって簡単に覆される軽薄さ。
大人の愚かさは、子供の純真さにも影響を与える。大人の顔色を見ることに長け、本来の感受性を失ってしまった太郎。太郎に対し、もっと自由に絵を描くよう、大人の顔を見ずに過ごすことのに力を入れて教える主人公。その取り組みにより、太郎は徐々に子供らしさを取り戻す。
その取り組みが実を結び、太郎の絵と表情が個性を放ち始める。だが、その絵は既存の児童画の概念を逸脱し、コンクールの審査員に酷評される。だが、実はそのコンクールの主催者が太郎の父であることを知った途端、審査員は批評を恥じ、審査員を降りていく。
子供の可能性を真摯に描き、大人の醜さや滑稽さを描いた本編は、芥川賞にふさわしい余韻を感じさせる。
私たち大人は、なんというところまで来てしまったのだろう。
かつての輝かしい子供時代に比べ、打算と計算と見栄と虚栄の今はどうなのか。自分を自省したくなる一編だ。
「流亡記」
中国の奥地にある砂漠の中の街を描いた本編。歴史の流れの中で権力や軍隊に蹂躙され、陵辱されるだけの存在。
大きな時間の流れの中で、人の営みのいかに小さく健気なさまであるか。
人は群れ、組織を作り、何かしら階層を作っていこうとする。
官僚による組織が作られ、それが権力を集め、皇帝の誕生につながる。人々はまるで運命に導かれるように階層や差別を自らの手で作り上げていく。
それが、悲しくも人間の習性であること。
著者の突き放したような筆は、人の営みなどに大した価値を認めないとでもいうように、淡々と時の流れと営みを描く。
本書は、中国の始皇帝を描いている。
焚書坑儒や万里の長城の建築など、世界史上でも有数の業績を残した始皇帝。だが、その始皇帝は自らの治世の結果を見るまでもなく倒され、後継者に取って代わられた。
始皇帝の生涯とは、その強大な権力とは裏腹に、単に人間の営みが作り上げた権力の役割を体現しただけのように見える。
権力や政治、人の作り上げた世界のあり方。それを端的に描いた本編は、著者の考えを反映していてとても興味深い。
‘2019/12/6-2019/12/8
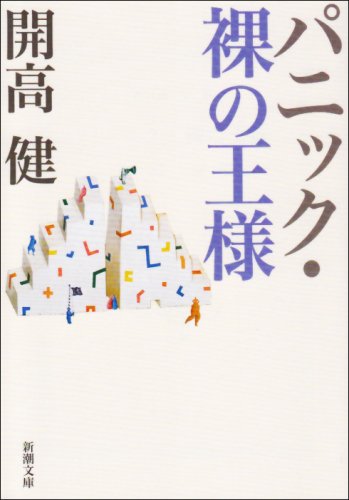
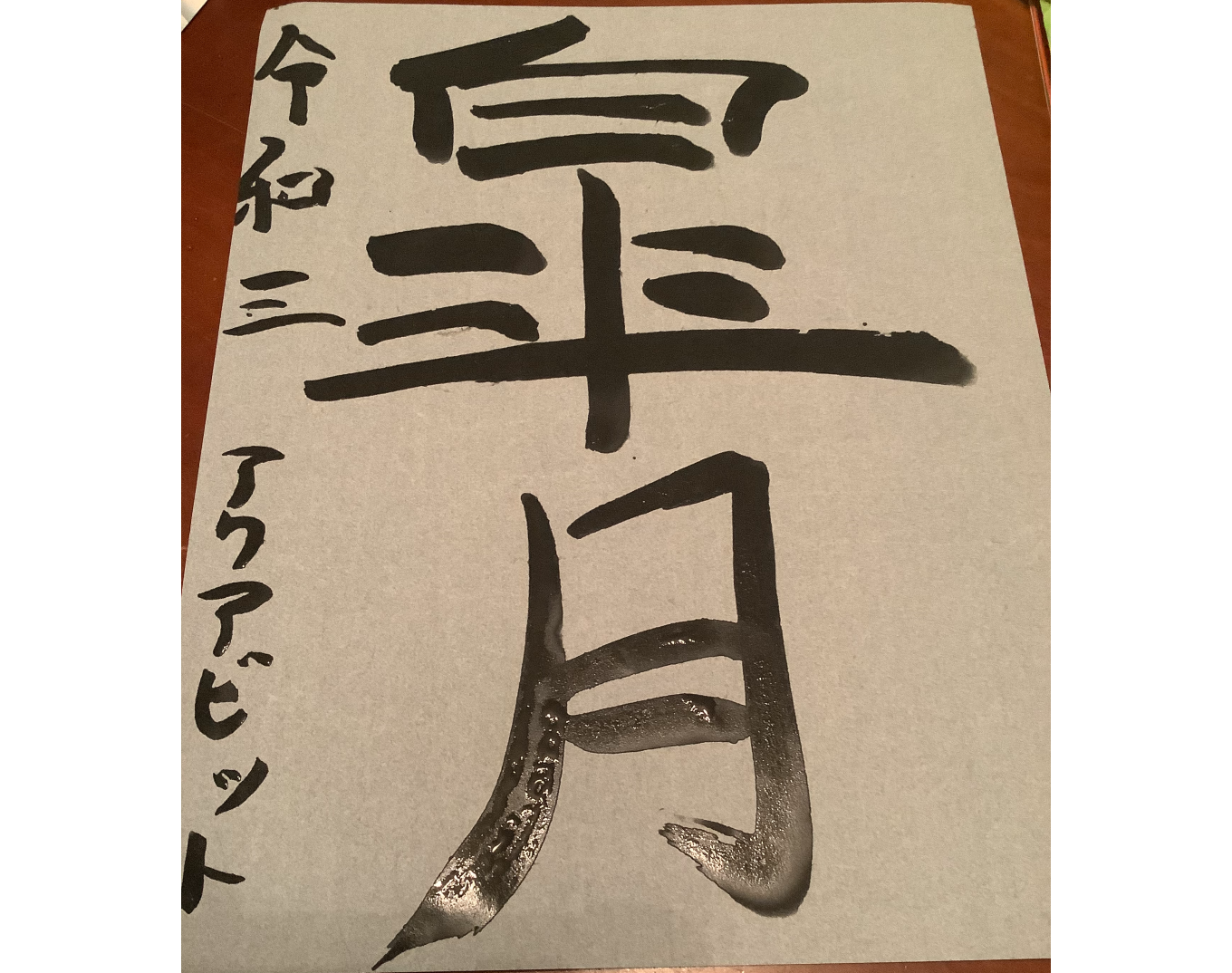
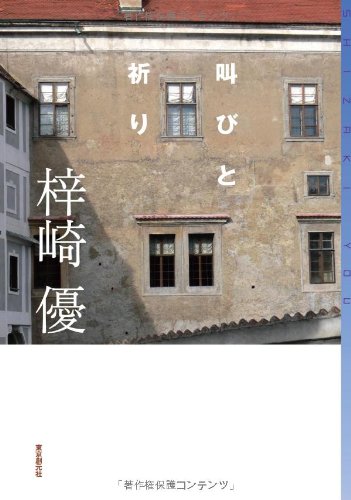
コメント