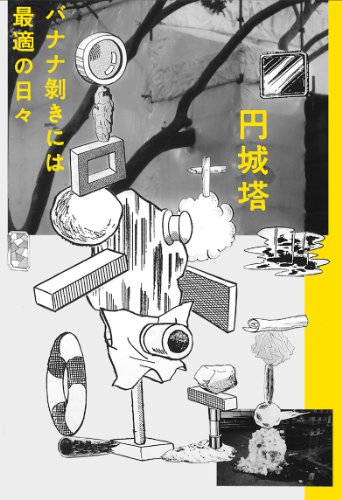
本書の帯には著者の作品中でもわかりやすい部類とうたわれている。だが、やはりとっつきにくさは変わらない。なぜなら全てのお話が観念で占められているから。小説にストーリー性を期待する向きには、本書は相変わらずとっつきにくいはずだ。
著者の作品を初めて読む人には、本書はどう取られるのだろうか。エッセイでなければ哲学の考察でもない。やはり小説だと受け取られるのだろうか。私の感覚では、本書は確かに小説だ。
本書は観念で占められている。観念とは、作家と読者の間に取り交わされる小説の約束事を指す。それは形を取らない。通常、それはわかりやすい小説の形を取る。例えば時間の流れ方だ。全体や各章ごとに時間の流れ方は違ったとしても、それぞれの描写の中で時間は過去から未来に流れる。それもまた約束事だ。他にもある。作家と読者の間には、同じ人間として思惟の基準が成り立っているとの約束事だ。その約束事が成立していることは、通常は作家から読者に向かって事前に了解を取らない。なぜなら、ものの考え方が共通なことは了解が不要だから。読む側と書く側で多少は違えども同じ思考様式を使うとの了解は、人類共通のもの。だから小説の作家と読者の間には了解を取る必要がない
。ところが、本書にはその了解が欠かせない。本書に必要なのは、作家の観念が小説として著されているとの了解だ。
そこを理解しないと、本書はいつまでたっても読者の理解を超えていってしまう。
本書に収められた九編のどれもが、約束事を理解しなければ読み通すのに難儀するだろう。
「パラダイス行」
約束事の一つに、基準がある。作家と読者の間に共通する基準が。それをわかりやすく表すのが単位だ。172cm。cmは長さの単位だ。172という数値がcmという単位に結びつくことで、そのサイズがお互いの共通の尺度になる。これは作家と読者の間で小説が成り立つためには重要だ。
ところが本編はその基準を無視する。基準を無視したところに考えは成り立つのだろうか、という観念。それを著者はあらゆる角度から検証する。
「バナナ剥きには最適の日々」
おおかたの小説には目的がある。それは生きがいであったり、自己実現であったり、社会貢献だったり、世界の平和だったり、世界征服だったりする。表現が何らかの形で発表される時、そこには作家と読者の間に買わされる約束事があるのだ。
話が面白い、という約束事もそう。どこかで話のオチがある、というのもそう。ところが本編は目的を放棄する。目的のない宇宙の深淵に向かって進む探査球。本編の主体である思惟はだ。そもそも宇宙の深淵に向かって進むだけの存在なので、追いつこうにも追いつけない。だから思惟の結果は誰にも読まれない。そして語られない。完璧なる孤独。しかも目的を持たない。そこに何か意味はあるのか、という作家の実験。読者が理解するべき約束事とは、孤独と無目的を追求する著者の問題意識だ。
「祖母の記憶」
本編に登場する約束事は、物語には意識する主体があるということだ。植物状態になった祖父を夜な夜な外に連れ出し、物言わぬビデオの主役に据える兄弟。物言わぬ祖父のさまざまな活躍を日々ビデオに収めては観賞する。そんな闇を抱えた行いは、いったい何を生み出すのか。
著者の実験にもかかわらず、本書に登場する主体はあくまでも兄弟だ。祖父は単なる対象物でしかない。祖父の代わりにマネキン人形でも良いことになる。そして、兄弟の活動に興味を持った娘と同じように物言わぬ祖母が現れると、本書の罪深さは一層濃厚になる。
祖父や祖母のような意思のない物体は、マネキン人形のコマ割りとどう違うのか。それが本編で著者が投げかけた観念だ。祖父を齣撮りする兄弟が、祖母を齣撮りする少女に出会う。そんな話だけなのに、そこには意思に対する問題意識の共有が必要だ。
「AUTOMATICA」
本編が示すのは文章の意味そのものだ。自動生成された文章が成り立つ要件とはそもそも何か。著者の観念が本編では論文体の文章で書き連ねられる。そもそも作家として、何を文章につづるべきなのか。そんなゲシュタルト崩壊したような、作家の存在自体への疑問が本編にはある。
そして、その情報が作家から読者に投げかけられる過程には、たしかに約束事がある。それは語彙のつながりであり、文法であり、情報の伝達である。その約束事を著者はいったん解体し、再構築しようと試みる。そこには作家とはいかなる存在か、という危機感もある。読者は普段おのれが仕事や学校で生み出している文章やウォールやツイートが何のために生み出されているのかも自問しなければならない。無論、私自身もその一人。
「equal」
本編は18の断章からなる。本書の中で唯一横書きで書かれている。内容は取り止めのないイメージだ。本編は小説というより、長編の詩と呼べるのかもしれない。
本編で押さえるべき約束事。それは小説にはストーリーや展開が必要との前提だ。それを著者は本編で軽やかに破り捨てる。だからこそ本編は長編詩なのだ。
詩とは本来、もっと自由なもののはず。詩人はイメージを提示し、読者はそのイメージを好きなように受け取る。そこには約束事など何もない。そもそも文学とはそういう自由な表現だったはず。なぜストーリーがなければならないのか。読者もまた、ストーリーを追い求めすぎてはいなかったか。そこに固定観念はなかったか。
「捧ぐ緑」
人間の生涯とは、つまるところなんの意味があるのか。ゾウリムシの生態を語る本編は、そんな疑問を携えて読者の観念を揺さぶりにかかる。生きるとはゾウリムシの活動となんら変わることはない。思弁する存在が高尚。それは誰が決めたのだろうか。著者の展開する文の内容はかなり辛辣なのに、語り口はあくまでもソフト。
だが、その裏側に潜む命題は、辛辣を通り押して虚無にまで至る。企業や仕事、全ての経済活動を突き放した地平。もしかすると人が生きていくための動機とは本編に書かれたような何も実利を生まない物事への探究心ではないだろうか。そんな気がしてくる。
「Jail Over」
本編は、倫理観の観念を料理する。かつて生命を宿していた肉体を解体する。それが生きていようと死んでいようと。人間だろうと動物だろうと。自分だろうと他人だろうと。果たしてそこに罪はあるのか。幾多の小説で語られてきた主題だ。
本編ではさらにその問いを推し進める。肉体を解体する作業からは何が生み出されるのか。そこにはもはや罪を通り越した境地がある。意識のあるものだから肉体を解体してはならないのか。
jailを超えて、語り手は肉片となった牢屋の中の自分に一瞥をくれる。肉体を破壊するとは、意志する主体が自分の入れ物を分解しただけの話。そうなるとそこには罪どころか意味さえも見いだせなくなる。遠未来の人類のありようすら透けて見える一編だ。
「墓石に、と彼女は言う」
無限と量子力学。この宇宙はひとつだけではない。泡宇宙や並行宇宙といった概念。その観念が作家と読者の間に共有されていなければ本編は理解できない。宇宙の存在をその仕組みや理論で理解する必要はない。あくまでイメージとしての観念を理解することが本編には求められる。
無限の中で、意識とはどういう存在なのか。己と並列する存在が無限にある中、ひとつひとつの存在に意味は持てるのか。その思考を突き詰めていくと強烈な虚無感に捕らえられる。虚無と無限は対の関係なのだから。
「エデン逆行」
本編が提示する観念は時間だ。どうやってわれわれは時間を意識するのか。それは先祖と子孫を頭に思い浮かべれば良い。親がいてその親がいる。それぞれの親はそれぞれの時代を生きる。そこに時間の遡りを実感できる。子孫もそうだ。自分の子があり、その孫や孫。彼らは未来を生きるはずだ。
命が絶たれるのは、未来の時間が絶たれること。だからこそ罪があるのだ。なぜなら時間だけが平等に与えられているから。過去もそう。だから人を殺すことは悪なのだ。なぜ今を生きる人が尊重されなければならないか。それは先祖の先祖から積み重ねられた無限の時間の結果だからだ。あらゆる先祖の記憶。それは今を生きている人だけが受け継いでいる。時間のかけがえのなさを描いた本編。本編が提示する観念は、本書の中でも最もわかりやすい概念ではないか。
本書の9編には、さまざまな約束事がちりばめられている。それぞれの約束事は作家によって選ばれ、読者に提示されている。それをどう受け取るかは読者の自由だ。本来ならば約束事とは、もっと自由だったはず。ところが今の文学もそうだが、ある約束事が作家と読者の間で固定されているように思う。今までも文学の閉塞については論者がさんざん言い募ってきた。そしてその都度、壁をぶち破る作家が読者との間に新たな約束事を作り出してきた。おそらく著者は、私の知る限り、今の文壇にあって新たな約束事を作り上げつつある第一人者ではないだろうか。
‘2017/08/12-2017/08/16


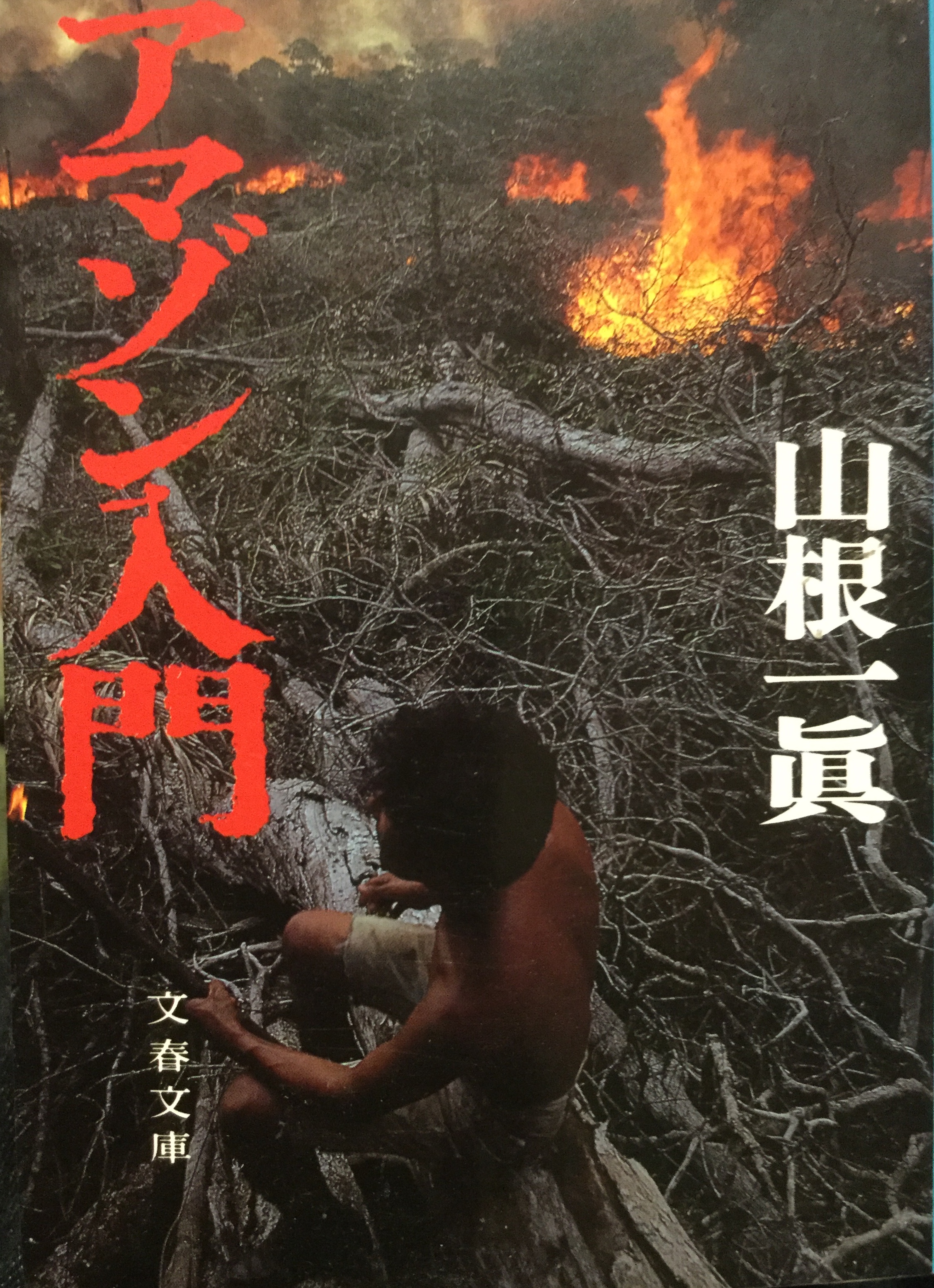
コメント