
夢を追う楽しみ。夢に向かって進む喜び。
本書はウイスキー造りの夢を追う人々の物語だ。
ここ10数年ほど、世界的にウイスキーが盛り上がりを見せている。だが、20年ほど前はウイスキーの消費が落ち込み、スコットランドのあちこちで蒸溜所が閉鎖を余儀なくされた。本書の舞台であるBruichladdichもそう。
スコットランド 、アイラ島。そこはモルト好きにとって憧れの地だ。大西洋に面し、荒々しく陰鬱な天気にも翻弄されるこの地は、ウイスキー作りに最適とされている。アイラ島のウイスキーといえば、地の利を生かした個性的な味が世界のウイスキーの中でも異彩を放っている。ボウモア、ラフロイグ、ラガヴーリン、アードベッグ、ブナハーヴン、キルホーマン、カリラなど、世界的に有名なブランドも擁している。Bruichladdichもその一つ。
ウイスキーの製造工程の中で麦を糖化させるため麦芽にする作業がある。麦の発芽を促すことで、でんぷんを糖に変える作業だ。しかしそこから芽が出てしまうと、今度は逆に麦芽の中の糖分が減ってしまう。そのため、ピートを焚いて麦芽をいぶし、発芽を止める。その時に使うピートとは、ヘザー(ヒース)が枯れて堆積し、長い年月をへて泥炭となったものだ。ピートをいぶすことで麦芽にピートの香りがつく。そしてピート自体が、長年大西洋の潮の香りを吸い込んでいる。そのため、ピート自体が独特な香味をウイスキーに与えるのだ。アイラ島のウイスキーにはそのヨード臭とも呼ばれる薬品のような香りが特徴だ。(あえてピートを焚かない蒸留所もあるが。)
80年代のウイスキー不況によって、Bruichladdichは閉じられてしまい、操業再開のめどもないまま大資本の間を転々としていた。それに目をつけたのがロンドンでワインを商っていたMark Reynier。彼はワインで培ったノウハウはウイスキーでも生かせるはずと買収に乗り出す。そしてBruichladdichの所有者に何年ものあいだ働きかけ続ける。難航していた資金調達も劇的なほどに土壇場でめどがつき、蒸留所の買取に成功する。まさに夢を追い、それを努力によって成就させた幸せな人だ。
夢とは単に願うだけでは叶わない。本書は夢を実現するにあたって、全ての人が覚悟しておかねばならない苦難と苦労がつづられた本だ。そして実現したら何物にも勝る喜びが待っていることも記されている。
アイラ島の様子はGoogle マップやストリートビューを使えば、日本にいながら確認できる。私も何度もディスプレイ上で憧れの地を探索している。そこでわかるのはアイラ島が純然たる田舎であることだ。だがMarkはそこも含めて惚れ込んだのだろう。ロンドンの渋滞や都会生活に心底辟易していたMarkが何度も漏らす言葉が本書には紹介されている。その言葉はMarkと同じく都会に疲れている私には同感できるものだ。
本書を読んでいると、人生を何かに賭けることの意味やその尊さが理解できる。都会でしか得られないものは確かにある。だが、都会で失うものの多さもかなりのダメージを人生に与える。
Bruichladdichの場合、幸運もあった。それはJim McEwanをボウモア蒸留所から迎えたことだ。伝説のブレンダーとして知られるJimは15才からボウモア蒸留所で経験を積んでいた。ボウモア蒸留所はサントリーが所有している。Jimはサントリーの下で世界中をマーケティング活動で回る役目もこなさねばならず疲れを感じていた。そんなJimとMarkの夢が交わりあい、JimはBruichladdichでウイスキー造りの陣頭指揮を取る立場に就く。閉鎖前に蒸留所長だった人物や他のメンバーも参加し、蒸留を再開することになる。
本書には、Bruichladdichで蒸留が始まる様子や、最初のテスト蒸留の苦心などウイスキーが好きな読者には感動できる所が多い。Bruichladdichの蒸留工程で使われる施設にはビクトリア時代から使われているというマッシュタン(糖化槽)やウォッシュバック(発酵槽)など。それを使いながら、人力で蒸留してゆくのがウイスキー作りのだいご味。それらの描写はウイスキー党にとっては耐えがたいまでに魅力的だ。
本書で面白いのは、本場のウイスキー造りの野卑な側面も臆せず書いていることだ。日本の蒸留所を訪れるとウイスキー造りに洗練され統制された印象を受ける。だが、ひと昔前のスコットランドのウイスキーの現場は本書で書かれるように荒削りだったのだろう。これは日本の蒸溜所を描いた書籍には見られない。また、何度も日本の蒸留所を訪れた私にもわからない雰囲気だ。本書からは本場のウイスキー造りのライブ感が伺えるのがとてもうれしい。
ここまで苦心して作られたウイスキー。それがアクアマリン色の目立つボトルでバーに置かれれば、呑助にとって飲まずにはいられない。あえてアクアマリン色のボトルにするなどの、マーケティング面の努力が功を奏し、Bruichladdich三年目ぐらいで黒字を達成する。
Markの想いは尽きない。彼の想いは全ての原料をアイラ島で供給したウイスキー造りにも向く。その製品は私も以前バーで見かけたことがある。まだ飲んだことはないが、こだわりの逸品と呼んでよいだろう。さらにはフェノール値(ピートを燻して得られる煙香の成分)が200PPMを超えたというOCTOMOREへの挑戦も本書にかかれている。また、Bruichladdichの近所にありながら1983年に閉鎖されたままとなっているポート・エレン蒸溜所の復活にまでMarkの想いは向かう。さらにはジンの蒸留に乗り出したりと、その展開は留まるところを知らない。
本書はポート・エレン蒸溜所を復活させる夢に向けて奔走する描写で本書はおわる。
だが、本書が刊行された後のBruichladdichにはいくつか状況の変化があったようだ。それは大手資本の導入。Markとその仲間による買収は全くの自己資本によるものだった。それは彼らの理想が大手資本の論理から独立した真のウイスキー造りにこだわることにあったからだ。その熱き想いは本書のあちこちに引用される。だが、これを書いている今、Bruichladdichの所有者はフランスのレミー・コアントローだ。本書には、彼らの理想に反し、レミー社の資本を受け入れるに至った経緯は書かれていない。それはぜひ知りたかったのだが。それともう一つの出来事はポート・エレン蒸溜所の復活を断念したニュースだ。これもまた残念なニュースだ。ポート・エレン蒸留所については、本書を読んで半年ほどたった頃、ウイスキー業界の大手であるディアジオ社が復活させるニュースが飛び込んできた。それはそれで喜ばしいニュースだが、私としては個人の力の限界を思い知らされるようで複雑な気分だ。
だが、Bruichladdichのウイスキー造りの夢は潰えたわけではない。それを確かめるために本書を読んだ数日後、新宿のバーhermitを訪れた。そこで飲んだのがアクアマリン色のボトルでおなじみのBruichladdich12年と、OCTOMOREだ。実は両者を飲むのは私にとっては初めてかもしれない。特にOCTOMOREは全くの初めて。ともにおいしかったのはもちろんだがOCTOMOREには強烈な衝撃を受けた。これは癖になりそう。そして、これだからウイスキー飲みはやめられないのだ。
20年ほど前、私は本場でウイスキーを知りたいとMcCallan蒸溜所に手紙を送ったことがある。雇ってほしいと。また、私が大阪の梅田でよく訪れるBar Harbour Innのオーナーさんや常連客の皆さんで催すボウモア蒸溜所訪問ツアーに誘われたこともある。しかし、私はともに実現できていない。本書を読み、Bruichladdichを味わった事でますます行きたくなった。それは今や私の夢となって膨らんでいる。
もちろん、私の夢など本書で紹介された夢よりはずいぶんと小粒だ。だが、まずは夢を願うだけでなく、実現させなければ。スコットランドに行きたいという思い、アイラ島やスカイ島の蒸留所を巡りたいとの思いが、本書を読んで燃え盛っている。かならずや実現させる。
‘2017/02/18-2017/02/20

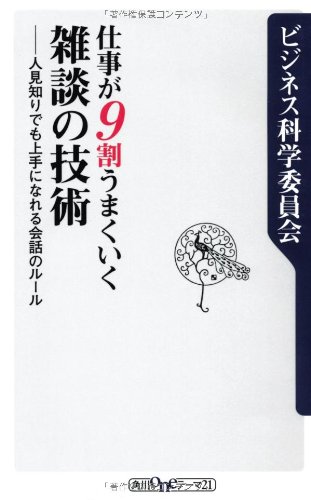

コメント