
本書は見慣れない形式で記されている。
小説のような散文形式でもなく、詩のような断片的な断章でもない。
詩のようでありながら、物語としての展開を備えている。
つまり、物語性を備えた長編の詩。つまりは叙事詩とでも言うべきなのが本書である。
よく、詩を朗読すると言う。ここでいう詩とは、カラオケのディスプレイに流れる歌詞のことではない。
詩人が書き連ねる詩を指している。
詩人によって研ぎ澄まされ、選ばれた言葉の連なり。
その美しく、時には韻を踏む言葉をいつくしみ、声に出して朗読する。
黙読して本を読む私には、なじみのない習慣だ。
少し前に、「声に出して読みたい日本語」と言う本がベストセラーになった。声に出して読むことで、内容が頭に入る。なおかつ、日本語の語感に対する感性が養われる。
今もYouTubeには詩の朗読の様子がアップロードされている。
実は私が知らないだけで、朗読の習慣はまだ廃れていないのだろう。
実は、一昔前の人々は、朗読や朗誦の習慣を普段の暮らしで持っていたのではないか。
今や私たちが詩を朗読する機会など、学校の国語の授業ぐらいだというのに。
ところが、人々は本書のような詩を朗読することで、読解力を鍛えた節がある。俳句や短歌もその一つだろう。
本書のような形をとる文学は、まさに朗読にふさわしい。本書を実際に読んでみると、格調も高くつづられた日本語が頭にしみ込むような気がする。
もちろん、本書はもともとイギリスの詩人テニスンによって生み出された。つまり、原文は言うまでもなく英語で書かれている。
それを美しい日本語に翻訳してくれたのが、訳者の入江直祐氏だ。
入江氏の訳した文も格調が高く、もともとの作品を思い描かせてくれる。
だが、翻訳の見事さを差し置いても、本書は本来は英語で読むべきなのだろう。その方が味わいが深まる気がする。
なぜなら、本書は過去を舞台としているからだ。そして、遠い国へと向かう船乗りの物語だからだ。
日本語で読むと、どうしても読み手の心の奥底に、日本の情景が浮かんできてしまう。
昔の日本では、ここまで長期間、故郷へ帰って来られない航海はなされていなかったはずだ。遣唐使や遣隋使ならまだしも。せいぜいが近海に漁に出てそのまま流されたような中濱万次郎か大黒屋光太夫の事例がある程度。
つまり、最初から困難が予想される遠洋への航海は、日本の歴史ではあまりイメージしにくい。
だから、本書には長期にわたる航海が行われていた19世紀イギリスの感覚が深く根を下ろしており、その感覚を描写するには英語が似つかわしいと思える。
19世紀のイギリスといえば、世界の七つの海を支配すると言われた大国である。世界中に植民地を持ち、イギリス人にとっては航海がそれほど珍しい営みではなかったはずだ。
だからこそ、本書でイノック・アーデンが、妻アニイや子供を置いて、家族のために航海で一稼ぎしようとする動機は理解できる。
また、難破し、はての島で長年を過ごした事も、苦労して故国に戻ろうとした執念にも、空想やおとぎ話の世界と片付けられない現実味がある。
本書は叙事詩とはいえ、荒唐無稽ではなく現実に即した物語なのだ。
さらに、地に足がついていながら、当日の人々がかろうじて想像ができる長大な旅路が描かれており、それがある種のロマンをかき立ててくれる。
本書で描かれているのは、愛にもさまざまな種類があることだ。
本書は三人の幼なじみ、イノック・アーデンとアニイ、そしてフィリップの物語だ。
アニイは二人から思いを寄せられる。だが、ストレートに思いを打ち明けるイノック・アーデンを好ましく思っており、イノック・アーデンの思いを受け入れて二人は結婚する。
だが、生活に苦しみ、イノック・アーデンは家族を養うため、一か八かを目指して航海に出る。そして遭難し、家族のもとへ戻れなくなる。
悲しみに暮れるアニイ。
フィリップは、アニイを慰め、そして秘めていたアニイへの思いを打ち明ける。数年ののち、二人は結婚する。
ここでは、若気のストレートな愛と、じっくりと見守る愛が描かれる。ともに美しい。
一方で、遭難の凄絶な苦労によってすっかり面貌が変わってしまったイノック・アーデンは、苦労して故国へと戻ってくる。そして彼が目にしたのは、幸せに暮らすアニイとフィリップと子供たち。
彼はそれを見て、自ら名乗り出ることをやめ、孤独のうちに生涯を終える。
彼の凛とした姿勢もまた美しい。
もう一つ、本書がテーマとしているのは、人にとって普遍的な問題である、冒険か安定かの選択が描かれていることだ。
イノック・アーデンのとった行動は冒険的な生き方の典型であり、安定の幸せを求めたアニイとフィリップとの生き方が対比されている。
どちらに優劣があるというのではない。それはどちらも人生のありうる姿であり、どちらも可能性として受け入れてこそ、人生を謳歌する姿勢であると思う。
本書を浅く読み、冒険を否定してはならないし、安定の家庭を築いた2人を非難してもならない。
本書のそうしたテーマから学びとれるのは、19世紀のイギリス社会が、人間に多様な生き方を許容できるように変わりつつあったことだ。
縛られ、固定された一生ではなく、冒険もできるし、安定もえらべる。そのどちらも人としての一生であり、どちらを選択するかを個人の意思に委ねられるようになったこと。
この時代の変化をテニスンは敏感に感じ取り、本書にしたためたのに違いない。
そうした自由な生き方をえらべるようになったとはいえ、冒険の果てにはイノック・アーデンが被ったような悲劇の可能性もある。
その時、イノック・アーデンのように自らの選択にきちんとけじめをつけ、見苦しいまねはしないでいられるだろうか。
本書からはそのような覚悟のあり方が示されていると思う。
その覚悟こそは、世界に冠たる国家になるつつある、イギリスの男子のあり方なのだ、とテニスンはほのめかしているように思える。
そんなテニスンの思いが伝わったからこそ、一旗をあげようと決めた人々が自らを鼓舞し、奮い立たせるために本書を朗唱したのではないだろうか。
‘2019/01/03-2019/01/03

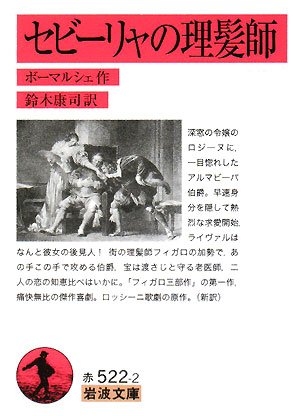
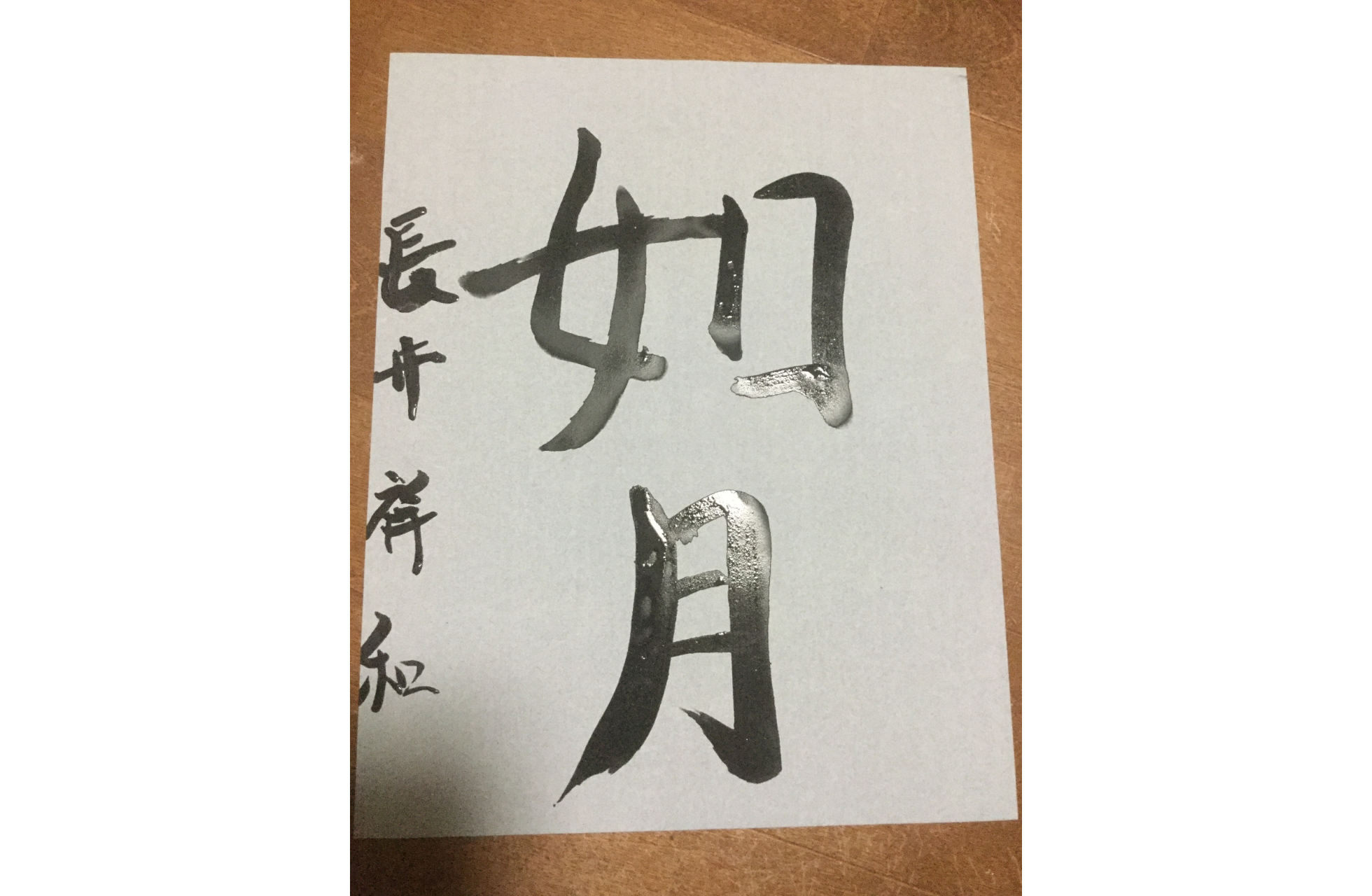
コメント