
本書は、著者の名をノーベル文学賞受賞者にまで高めた一作だ。
トルコにルーツを持つ著者の文化的なバックボーン。それはイスラム教であり、イスラム文化である。
今でこそ、世界は長らく西洋のキリスト教が優位に立ってきた。だが、歴史を紐解くと、かつてはイスラムこそが世界を引っ張っていた。強大なオスマン・トルコが西欧と対等な強国として栄えていた時期。さらに、ルネサンス勃興期までは、西洋文化は完全にイスラム文化の影響下に置かれていた。
その一方で、1453年までは東ローマ帝国の首都が今のイスタンブールに置かれていた。つまり、トルコとは、西洋文化をルーツとした土壌と文化的な誇りを持った国なのだ。
蒸留技術、数学に化学。イスラム文化が世界の文明に貢献した業績は多い。
美しいゴブラン織、ペルシャ絨毯、曼荼羅のような幾何学模様のタイル。これらもイスラム文化からうまれた。イスラム文化は間違いなく、世界の文明をリードしていた。
本書は、イスラム文化が、オスマン・トルコによって最盛期を迎えていた時期を舞台にしている。
最盛期を迎えたオスマン・トルコ。だがその時、西洋ではルネサンスがその文化的な先進性によってイスラム文化の脅威となりつつあった。
例えばルネサンスが成した文化的な改革の一つに絵画がある。
それまでの絵画とは、中世の宗教画に見られるような平板な背景が描かれ、奥行きがなかった。
それが、遠近法によって革命と言っても良い変化を遂げた。
それまでの遠近法を知らない絵画は、奥にいる人物は絵の上側に描かれ、手前の事物は絵画の下側に描かれた。本書のカバーを彩っている絵画のように。
本書のカバーを彩るのは『祝祭の書』(1582)から引用された、珈琲店同業者のパレードの様子が描かれている。だが、遠近法になじんでいるわたしたちから見て、絵画としてあか抜けていない。
ルネサンス期で有名な絵画と言えば『ヴィーナスの誕生』だ。サンドロ・ボッティチェッリによるこの作品はあまりにも有名。そこではすでにきちんと奥行きが描かれており、当時のイスラムでは最先端の絵画だったであろう「祝祭の書」とは明らかな差がある。
本書は、細密画師の葛藤を描いている。
敬虔なイスラム信仰が既存の絵画技法への疑問を許さず、偶像崇拝をよしとしないイスラム教の伝統も相まって、イスラム絵画は進歩から真逆の停滞に甘んじている。
にもかかわらず、ルネサンスによって長足の進歩を遂げた異教徒の絵画技法の革新性は、イスラムの細密画師たちを困惑させていた。
そうした中、細密画師の一人が無残に殺される。彼はなぜ殺されたのか。誰が殺したのか。
本書はそうした謎解きの要素もはらむ。それでいながら、本書は読者をつかんで離さない仕掛けに満ちている。
まず、本書のアプローチはとても面白い。
33章に分かれた上巻において、それぞれの語り手は自在に入れ替わる。その語り手に沿って章の題は設定される。最初の十章を挙げてみると、
「わたしは屍」
「わたしの名はカラ」
「わたくしめは犬にござい」
「わたしは人殺しと呼ばれるだろう」
「わたしは諸君のおじ上」
「僕、オルハン」
「わたしの名はカラ」
「あたしはエステル」
「わたしはシェキュレ」
「わたしは一本の木」
といった具合だ。
語り手の視点によって物語が変幻自在に変わる。性や職業、立場の違いに応じて自在に。生きていようが死んでいようが。人であろうがものであろうが悪魔であろうが関係ない。奔放だ。ある章では本書の題名の通り、赤が語り手となる。色の赤だ。
語り手の視点が自在に角度を変えることによって、物語の奥行きは深まる。平面的な絵画から遠近法を駆使した絵画へと進化したように。
語り手を章によって自在に変える手法。それは、丸山健司氏の『千日の瑠璃』で読んだことがある。
本書で著者は、語り手を変化させつつ、着実に物語を進める。そして、誰が〈優美〉と呼ばれる細密画師を殺したのか、の謎で読者を引っ張りつつ、当時のイスラム文化のあり方と、西洋文明が少しずつ浸透するイスラム文化の矛盾や苦悩を描いている。
複数の視点が自在に交錯することが、それらの描写に陰影を与え、抑揚をつけており、それが深みを本書に与えていることは言うまでもない。
本書にはそうした深いテーマだけではなく、読者が物語に入り込むための魅力的なテーマも忘れない。人の生き方や、悩み、そして人類が共通で持つ感情、つまり恋。
シェキュレに対するカラの熱情こそ、本書を貫くもう一つの糸だ。
イスラム文化の伝統とは、女性が自由に恋ができない環境でもある。ましてや封建的な時代。
幼いころからシェキュレに思いこがれていたカラは、シェキュレの父である、おじ上の許可を得ることに失敗する。そこから失意の12年にわたる流浪を余儀なくされていたカラ。その間にシェキュレは結婚し、オルハンとシェヴケトの二人の息子を設けた。だが、夫は対ペルシャの戦いに出たまま、すでに四年も消息が不明。
それを知ったカラはおじ上から結婚の許可を得るため、おじ上が皇帝から命じられた細密画の完成に協力する。
イスラムの因習と戦いながら、恋い焦がれるカラの熱情。その一方で家に縛られ、現実的な判断を優先させるシェキュレの冷静。
もちろん、シェキュレは、カラから想いを寄せられることに悪い気はしない。
この二人の駆け引きに、〈優美〉を殺したのは誰かという謎。そして宗教的な葛藤の中で進められる細密画の変革、そして細密画に求められる需要。
本書はこの三本の筋で綴られていく。
‘2019/11/10-2019/11/24

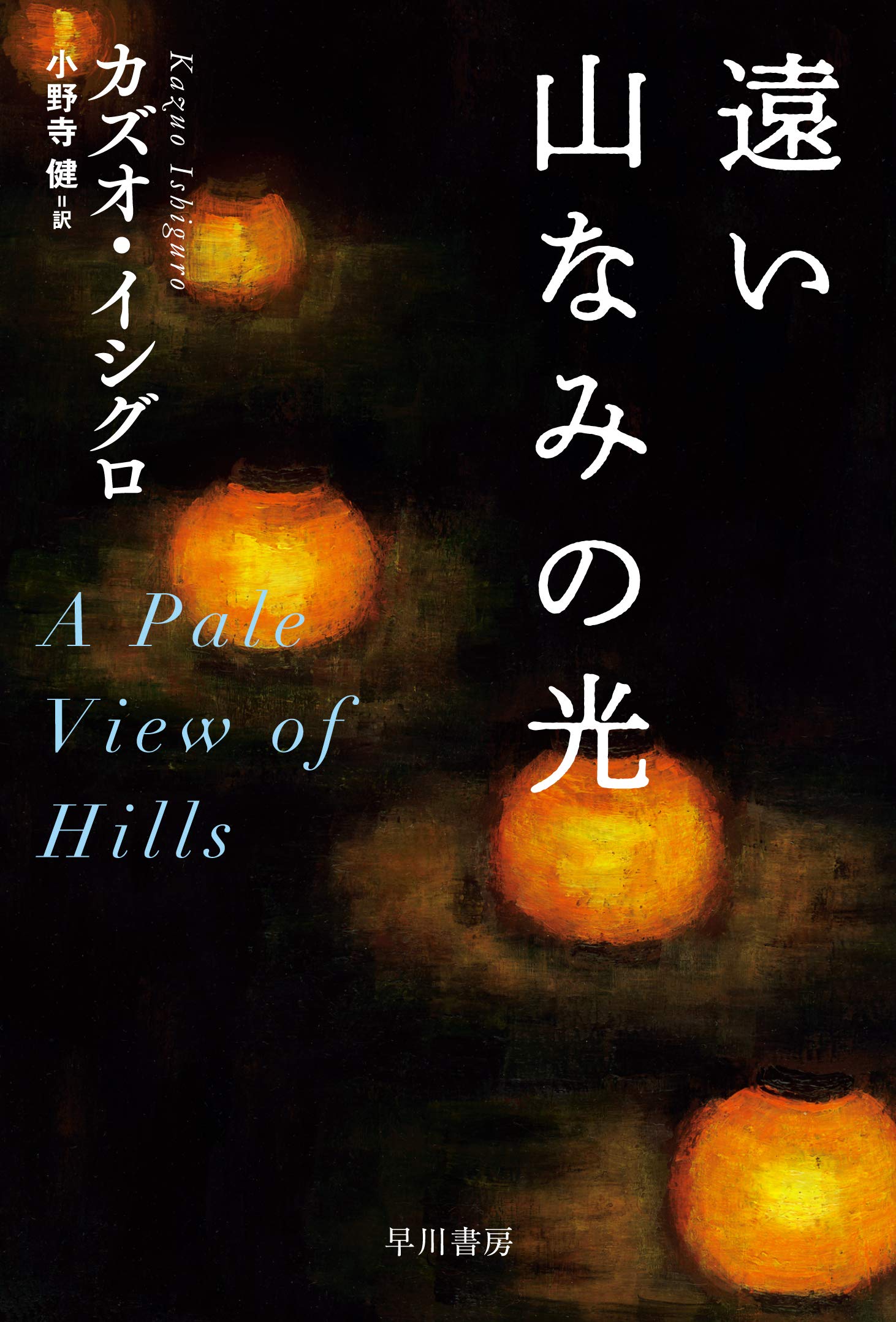

コメント