
著者がノーベル文学賞を受賞したこと。それは、以前から著者の作品に親しんでいた私にも喜ばしいニュースだった。なぜなら著者の作品が邦訳される機会が増すから。本書は著者が文学賞を受賞してから最初の作品だそうだ。すぐに翻訳され、このように読めることがうれしくてしょうがない。
ノーベル文学賞といえば高尚なイメージがついて回る。それを意識したからだろうか、本書は読みやすく仕立て上げられている。たぶん受賞作家について回る難解なイメージを覆すためにも本書ぐらい分かりやすい方がいいのだろう。そのため、私が読んだ著者の作品の中では本書は楽に読める部類だ。
もちろん、著者の独特の癖は本書でも健在だ。文中の展開を無視するかのようにいきなり会話が挟み込まれる。その会話は地の文で展開されているのとは関係ない、他の時間、別の場所でやりとりされたものだ。だが、唐突に現れる登場人物のセリフがその箇所の展開を補足し、読者が本筋を理解する助けとなる。著者のその癖は慣れていない読者だと面食らうだろう。が、慣れてくると本筋の理解に欠かせないことに気づいてくる。
でも著者の作品を読んだことがない方にとって戸惑うことがあるとすればその点くらいだ。他の点はとても読みやすいはずだ。
本書では二つの話が並行して語られる。
一つはフェリシト・ヤナケの物語だ。彼はペルーの北西部に位置するピウラでナリアウラ運送会社を経営している。ある日、マフィアらしき組織からみかじめ料を要求される。だが彼はその要求をきっぱりとはね付ける。彼が父から教わったこと。それは、男はこの世で誰にも踏みつけにされてはならないこと。彼は父から教わった遺訓に従い、マフィアからの踏みつけをきっぱりと断ったのだ。
フェリシトはミゲルとティブルシオという二人の息子に会社の後継者としての教育を施しながら、妻のヘルトゥルディスとは愛のない結婚生活を続けており、愛人のマベルと過ごす一時の情事に慰めを見いだす人物だ。
フェリシトはマフィアからの脅しに対し、真っ先にピウラの警察署に相談に行く。そこでフェリシトを応対したのがリトゥーマ軍曹。著者の作品に頻繁に登場する人物だ。これは著者のファンへの贈り物なのだろう。
そして本書で語られるもう一つの話。そこでも著者のファンへのサービスが惜しげなく振る舞われる。こちらの主役はドン・リゴベルト。そしてリゴベルトの傍には妻のルクレシアと息子のフォンチートがいる。この三人は「継母礼賛」「ドン・リゴベルトの手帖」でお馴染みの家族だ。その二作品では彼らはエロチシズムとフェティシズムの怪しくも艶やかな世界を見せてくれた。だが本書ではそのような精神性やスノビズムとは無縁の登場人物として描かれる。
それどころか、本書のドン・リゴベルトは世俗のあれこれに振り回される普通の人物だ。ドン・リゴベルトは長い間勤めた保険会社を退職する決意を固める。保険会社のオーナー、イスマエルとは上司と部下の関係を超えた友情で結ばれている。だが、かねてからの憧れていた芸術と精神性に満ちた世界の中で余生を過ごそうと決めたのだ。そんなリゴベルトに老齢のイスマエルは再婚の意思を告げる。前妻をなくしてから長らくやもめ暮らしを過ごしていたイスマエルだが、前妻の間に作った二人の息子が道楽息子に堕ちてしまい、彼らの露骨な遺産狙いに辟易した対応として、老いらくの恋として屋敷のメイドを妻に迎えたのだ。そしてそのままハネムーンと称してヨーロッパに旅立ってしまう。後始末を腹心のリゴベルトに託して。
その仕打ちに激高した息子たちは、会社の後を託されたリゴベルトに向かって父の結婚の無効を訴え、遺産を譲渡させるためのあらゆる嫌がらせを仕掛ける。もはやリゴベルトの望む精神性はかけらもないままの俗にまみれた下世話な話が飛び交う。しかもそれに追い打ちを掛けるように息子フォンチートに異変が生じる。フォンチートの周りに夢かうつつかは分からず、フォンチートの心が生み出したのかはわからないが謎の人物が見え隠れする。フォンチートの言動に振り回された夫妻は、息子の正気を信じられなくなり、それがリゴベルトをさらに弱らせる。
本書ではこの二つのエピソードが交互に描かれる。ところが、リゴベルトの表われるエピソードは全てペルーの首都リマでの話だ。一方、フェリシトのエピソードはペルーの北西部ピウラの話だ。二つの場所は距離にして約千キロ離れている。つまり全く接点がない話が交互に続くのだ。
果たして、お互いの話はどのように関わっていくのだろうか、という興味が読者を引っ張る。果たしてどうなってゆくのか。それを思わせるヒントが本書の扉に記されている。
「人間のすばらしき本分は、迷宮と一筋の糸があると想像することである。」
これはホルヘ・ルイス・ボルヘスの「寓話の糸」の一文だ。それを頼りに本書を読み直し、お互いの話を結び付ける一筋の糸を探してみると面白いかもしれない。
本書に描かれた二つの話が、どう絡み合っているか。それは訳者が解説を加えていてくれている。そこで知ったのだがマフィアに脅されて屈しないフェリシトには実在のモデルがいるらしい。著者が本書について語った言葉によると、フェリシトの姿を通して社会とは彼のような「つつましい英雄」によって支えられていることを書きたかったそうだ。では、リゴベルトは本書で何を象徴しているのだろうか。おそらくは、彼が志向する精神性や芸術性に満ちた生活もフェリシトのような「つつましい英雄」たちが作り上げる社会の上にあること。彼らのような無名の英雄が動かす土台があってこそ、を意図しているのではないだろうか。それは、ノーベル文学賞を受賞した著者が自らを戒める意図もあるはずだ。著者の謙虚な姿勢をよしとしなければならないだろう。
それと併せて、本書は今のペルーを知る上で興味深い一冊だと思う。
‘2017/03/18-2017/03/29

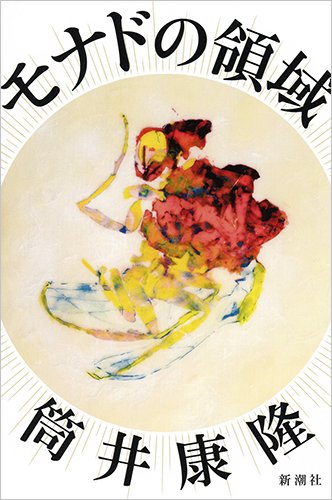
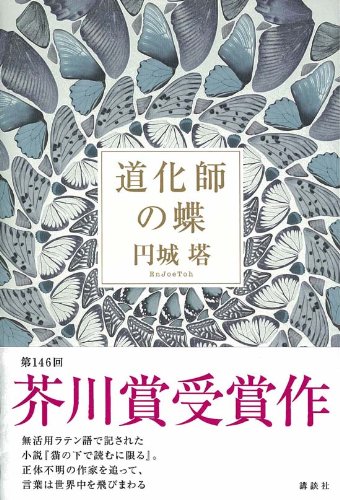
コメント