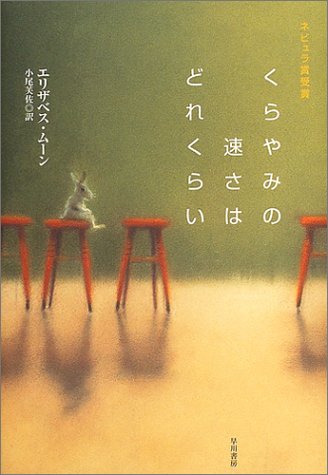
本書の帯にはこう書かれていた。
「21世紀版 『アルジャーノンに花束を』」
確かにそうとれなくもない。だが、本書を単なるリニューアルした『アルジャーノンに花束を』と思わないでほしい。なぜなら、本書は全く別の観点、別の展開、別の時点で描かれた物語なのだから。
似ているのは、主人公が精神に問題を抱えていると言うこと、そして、精神の問題を改善するための手術に主人公がどう対処するかという点だけだ。
『アルジャーノンに花束を』は、かつて三回読んだが、私にとって本書は断じて『アルジャーノンに花束を』の二番煎じではない。本書は別の物語であり、傑作と言って間違いない作品だ。本書が投じる新たな視点は、全く独自の世界観を築いている。『アルジャーノンに花束を』とは多少の設定が似ているが、それがどうした。以下、両者の似ているところと、それぞれがどう違うかについて挙げてみたい。
『アルジャーノンに花束を』の中で主人公のチャーリィは最初から知恵遅れの人物として登場する。しかし、本書の主人公ルウ・アレンデイルは自閉症を患ってはいるものの、訓練によって普通の人とあまり変わらない生活を送っている。
また、『アルジャーノンに花束を』は、手術を受けた後のチャーリィが感じた実社会の矛盾を描いている。本書のルウは、手術を受ける前から健常者と障害者の間の世界の違いに葛藤を感じている。そもそも、無邪気に頭が良くなりたいと願ったチャーリィと、最初から手術の是非を判断する知能を持ったルウの間には前提から違っている。
ルウは、自閉症患者が持つ特殊な能力を生かした部署で働いている。その部署は集中力を要する作業を行う自閉症患者のため、潤沢な設備を備えている。それが、新任の管理部長ミスター・クレンショウには気に入らない。障害者を雇用しているからこそ、法人税率が優遇されている事実や企業の備えるべき社会的な責任。それらはミスター・クレンショウの視野には入らない。それらをないがしろにしてまで経費を圧縮しようとするのがミスター・クレンショウだ。ルウの直接の上司であるミスター・オルドリンはルウたちの立場を守ろうとするが、会社にあってはより上位のミスター・クレンショウの判断が優先される。
ミスター・クレンショウの圧力は巧妙だ。本書の設定では、自閉症はすでに出生前に遺伝子治療で治ることになっている。つまり、ルウ達は最後の自閉症患者。そして今や、自閉症を患っていても新たに開発された手術によって治る可能性があるという。ミスター・クレンショウはその実験を受けないかとルウたちに迫る。その手術を受けて健常者になるか、引き続き自閉症でいるかをルウたちに選ばせ、健常者になれば健常者たちとと同じ待遇になることを示し、手術を受けず自閉症のままでいるなら退職を勧告するという。二者択一。強制的ではないが、実質は陰険な圧力。ルウの他にも同じ自閉症を持つ仲間がいる。彼らにはそれぞれの思いがある。自分の意思で健常者に戻るのが正しいのか。そもそも、自閉症とは健常者よりも劣っているのか。自閉症は一つの精神のあり方ではないか。社会にとって本当に異質な存在なのか。ルウの知能は、手術を受けないかと誘われる自分の立場をよく理解している。だから自らのあり方を矛盾ととらえ、どうすればよいのか懸命に考える。
著書が本書で問うているのは、自閉症を人間の持つ多様性の一つとして取り扱えないのか、という視点だ。健常者と自閉症患者は何が違うのか。自閉症の症状とは、人の感情を読み取るのが不得手で、社会的な振る舞いが極度に苦手であること。いわゆるコミュニケーション障害だ。だが、健常者にもコミュニケーションが不得手な人はいる。人はみな、何かしらの障害や不得手な部分を持っている。コミュニケーションが不得手だからといって、特殊だ異常だとくくってしまうことが果たして正しいのか。
著者はルウの内面を通して、その問いを読者に投げかける。ルウは自らの存在や思考のあり方が正常かそれとも異常なのか、という問いかけを作中で何度も自分に対して行う。彼の仕事は、空間のパターンを創造し、そのパターンを元に新たな価値を製品に付与することだ。障害がある分、ほかの健常者にない能力が備わっている。それは社会に十分役立っている。だからといってルウのような自閉症患者を社会の異物としてはじき出すべきなのか。
本書にもドン・ポワトウのような健常者の立場から自閉症のルウにつらくあたり、妨害しようとする人物がいる。でもドンは自閉症でない。健常者の一員として扱われている。ルウの素朴な心はドンを決して悪く言わない。ルウが決してドンを異常だと言わないこと。その観点は重要だ。ルウはドンを異常だと思わないのに、ドンはルウを異常だと迫害する。著者はその点を注意して書いている。
それでいて、ルウの高度に発達した状況判断能力は、フェンシングの技量においてドンを圧倒する。そしてルウは一緒にフェンシング・クラブで学ぶマージョリ・ショウに恋する。フェンシング・クラブを主催するトム・ルシアはルウの人物やフェンシングの技量を高く買い、ルウに援助を惜しまない。ルウの日常はルウにとって不都合ではなく、ルウは日常に満足している。ところが社会の区分けはルウを異常者と分類しにかかる。手術をすれば健常者になれるのか。その時、手術を受ける前の記憶はどこに行くのか。性格は変わらないのか。なにも保証されない。マージョリを愛する気持ちは消え失せないのか。何より今の自分はどこにいってしまうのか。自我の連続性が問われる。果たして、ルウは手術を選ぶのだろうか。読者にとって気になる。
ルウの選択は本書を読んで確認していただきたい。読者によって受け取る感想はまちまちだと思う。自閉症は性格の一つの特徴なのか。それとも異常なのだろうか。ルウの葛藤は、読者にとってもひとごとではない。読者の心を激しく揺さぶるはずだ。
もう一度書くが、本書は傑作だ。多様性やダイバーシティがだいぶ市民権を得てきた今だからこそ読んでほしい一冊だ。
’2018/05/22-2018/06/01
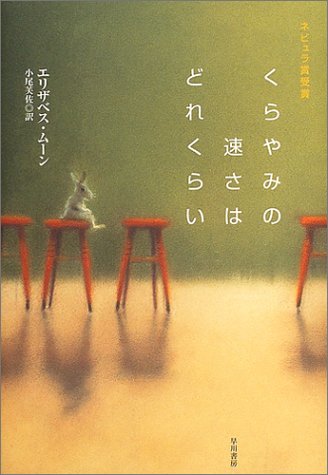


コメント